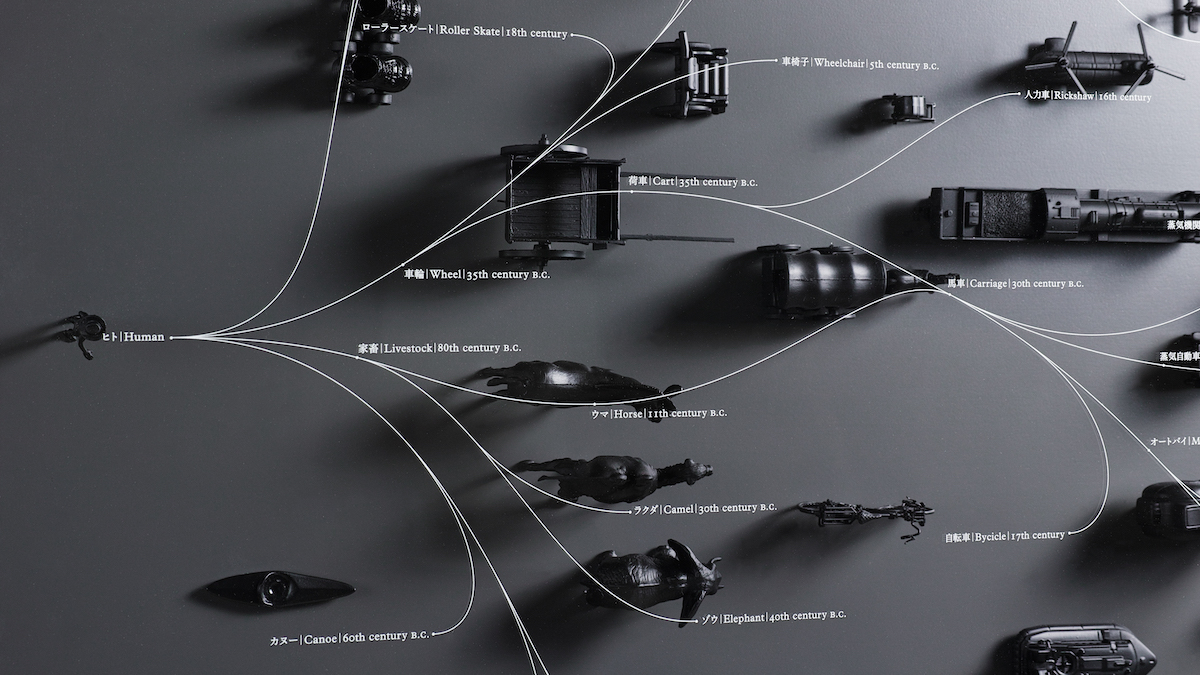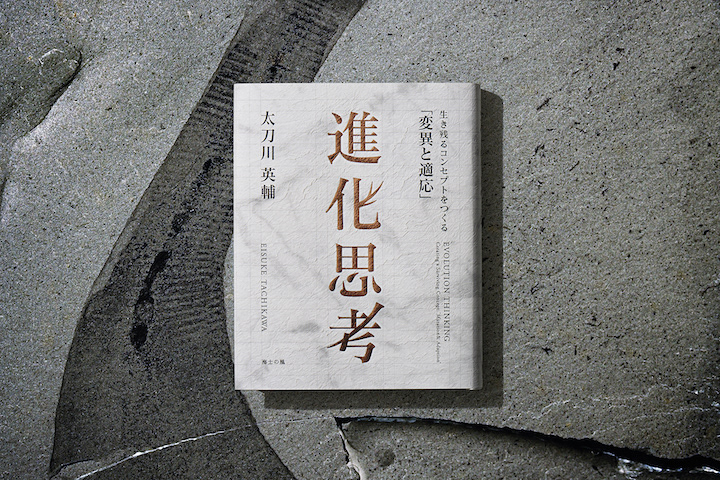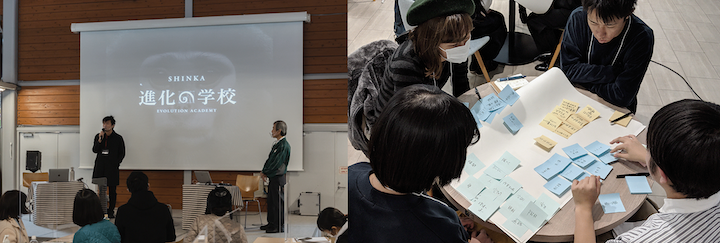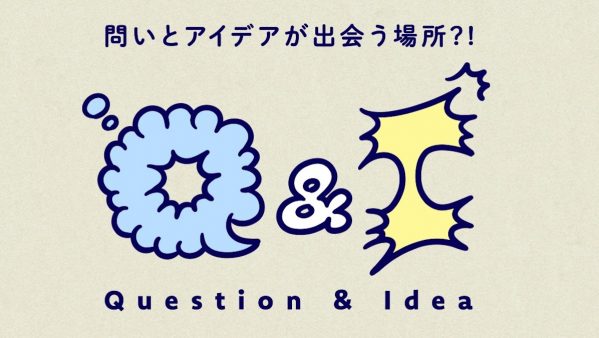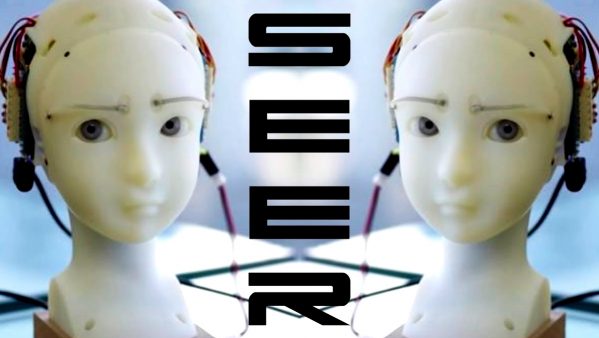音を光と振動で伝えることに焦点を絞って開発された「Ontenna」。学生時代から開発を続け、現在は富士通株式会社に所属、Ontennaプロジェクトリーダーを務めている本多達也氏。プロダクトが完成したことで、新たな挑戦をはじめようとしていると言う。開発当初から親交のある編集長、杉原行里がそんな本多氏を直撃。新たな挑戦について話を聞いた。
杉原:紆余曲折を経て富士通に籍を置いてOntennaが発売されたと伺いましたが、一般の方もすでに手にすることができるとか。
本多:はい。Amazonでも販売されています。本体は25,000円、コントローラーは30,000円です。最初に行里さんに着目いただいた充電器、聾学校の先生たちからも簡単にできるようにしてほしいという意見があったのでこだわりました。1個の充電器で本体もコントローラーも充電できるようにしたんです。クリップ型のプロダクトと発信機をマグネット式かつ、1つの充電器でチャージできるもので特許も取っています。
杉原:これ、カッコイイし、よく考えられているなと思いました。

本多:ありがとうございます。クリップ式なので、髪の毛につける人もいます。いろいろなところにつけられるのですが、耳に直接付けるのがいいと言われる方もいて、使い方は人それぞれです。世界中の人にこの「Ontenna」を届けたいと思って、富士通に入社しました。
プロのデザイナーやエンジニアの方、聾者の方にも実際にプロジェクトに入ってもらったおかげでプロダクトを進化させることができました。最初はもっと大きいものだったのですが、企業に入ったことでブラッシュアップされて使いやすく、サイズも小さくすることができました。新しくコントローラーも作りまして、こちらは複数の「Ontenna」を同時に制御できる機械になっています。これがあることでダンスをするときや太鼓をたたくときに複数の生徒たちに同時にリズムを伝えることができます。
マグネット式の充電は聾学校の先生から「休み時間が短いのでなるべく簡単に充電できるようにしてほしい」と言われて、もともとmicro SDを抜き差しする必要がありましたが、置くだけで、さらにコントローラーと一緒に充電できるデザインを取り入れました。
杉原:なるほどね。
本多:全国に聾学校が118か所あるんですが、全国聾学校長会を通じて希望するところには「Ontenna」の体験版を無償で提供しています。
杉原:「Ontenna」が販売開始されたとき、ネットに「待ってました!」というコメントがすごくて、プロダクト冥利に尽きるなと。「待ってた!」と言われるプロダクトって、なかなかないんですよ。
本多:ありがとうございます。今、いろいろなエンターテインメントのほうでも使われ始めていて、まずはタップダンスの映像をお見せいたします。これはタップダンスのタップ音だけに反応するようにチューニングして使ってもらってます。
「Ontenna」だから実現できた
ボーダレスなエンターテイメント
本多:この時は聴覚障がい者の方もたくさんいらっしゃっていたのですが、健常者の方も同じくらい来てくださいました。振動や音を複数で制御できるプロダクトって他になくて、「Ontenna」を健聴者の方もつけると「臨場感が増した」とか、「光で一体感が生まれて面白い」と言ってくださいます。障がい者の方とデザインしたインターフェイスが僕たちにも使えるものだったっていうのがとても嬉しかったです。
杉原:実は僕らがRDSチームで開発しているものと全く同じことで、特定の人を助けたい、もしくは選択肢を拡張したいという思いがあるプロダクトって、ある1つのところに陥りやすくて、その人たちの少ないマスだけで勝負してしまうから、シュリンクしちゃう。「Ontenna」は “多くの人が使えるんだよ” “聾者の方たちにも楽しめるんだよ” っていう入り口にすれば、あらゆる人にとって一気に当たり前のコンテンツになっていく。単純にこれ見ても楽しそうだなーと思うし、プロダクトとしてももちろん、流行るのではないかな。
本多:RDSの松葉杖 (参考:http://hero-x.jp/article/2202/) もそうですけど、パッと見て何となくかっこいいとか、軽くて使いやすいとか、なおかつ僕らも使いたいと思うし、そういうのってすごく大事だなと思います。「Ontenna」プロジェクトをやっていて感じることは、スペシャリストというか耳が聞こえない分ほかの感覚が研ぎ澄まされている人たちと一緒にもの作りをするのって、面白いなと思っているんです。
杉原:2013年に東京2020の開催が決まった後、2016年くらいから様々な人が動いていたじゃない。プロダクトを開発していこうとした人たちの中で、販売に至っているチームって実は少なくて。

本多:面白い、その視点で見たことなかったです。へえーそうなんですね!
杉原:まだまだ開発途中の人たち、あきらめてしまった人たちがいるなかで、本多さんたちのチームは、しっかりと完成に至った。あきらめず完成させることで、やっと世の中に新たな価値を届けることができる最初のフェーズに立てるわけです。
本多:行里さんにそう言われるのはめちゃくちゃ嬉しいです!
杉原:ここからは、本多さんたちにしか見えない、売らなきゃいけない、より魅力を伝えなくてはならないフェーズに入っていくと思うのですが。
本多:そうなんですよ。最近よく思うのは、マインドセットを変えていかないといけないなと思っていて。今までは作りたいものを届けると言っていたのですが、ここからはどう継続して届けるか、より多くの人たちに届けられるかっていうのを考えないといけなくて、フラストレーションがあります。僕はデザイナーなのに…っていう。(笑)

杉原:僕もありました! よく言われるのは、「元、デザイナーじゃない?」っていうこと。それもあながち間違っていないんだけど、それを言われるたびに、日本って絵を描く人がデザイナーだっていうのが染みついているんだなと。僕たちはストーリーをデザインするコンダクター(指揮者)みたいな感覚だと思っています。コンダクターは、ありとあらゆる楽器の音だったりを感度高く見ていかないとオーケストラの演奏はできないじゃないですか。そうなると、めちゃ勉強しないといけない。そういう意味では、海外で言われているデザイナーに近づいた気がしますね。だから販売するってすごいと思いますよ。
本多:なるほど、指揮者か…確かに。マインドセットをどう切り替えるかっていうのはまさに悩んでいる最中で、これからまた売り上げのことも考えなければいけないなかで、じゃあどういう方向性で行こうかって、イラレとかフォトショもほとんど触ってないし、自分はもうデザイナーじゃないんじゃないかな、とか思っていたのですが、さっきの言葉を聞いて嬉しくなりました。
杉原:これからも応援しています!

本多達也(ほんだ・たつや)
1990年 香川県生まれ。大学時代は手話通訳のボランティアや手話サークルの立ち上げ、NPOの設立などを経験。人間の身体や感覚の拡張をテーマに、ろう者と協働して新しい音知覚装置の研究を行う。2014年度未踏スーパークリエータ。第21回AMD Award 新人賞。2016年度グッドデザイン賞特別賞。Forbes 30 Under 30 Asia 2017。Design Intelligence Award 2017 Excellcence賞。Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2019 特別賞。2019年度キッズデザイン賞 特別賞。2019年度グッドデザイン賞金賞。現在は、富士通株式会社にてOntennaプロジェクトリーダーを務めている。