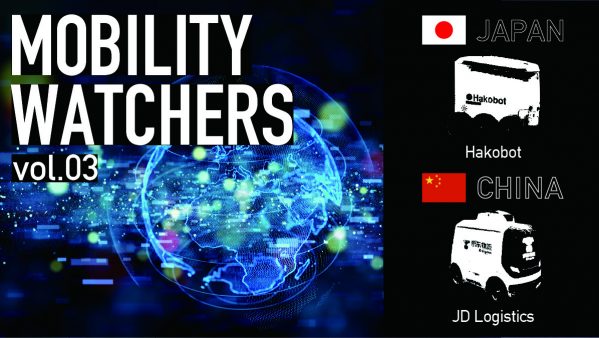研究者・メディアアーティストの落合陽一を代表として他の3人の研究者・デザイナーが手を組み、個性を活かせる新たな社会を生み出そうとしている。プロジェクト名は、X DIVERSITY(クロスダイバーシティ)。それは一体どんなものなのか、なにをしようとしているのか。2018年3月、日本科学未来館にて開催されたシンポジウムから、その全貌に迫る。
X DIVERSITYの使命と実現したい社会

東京・お台場にある日本科学未来館。当日はあいにくの雨にも関わらず、200人以上の来場者が集まった。登壇者は落合さんのほかに、大阪大学准教授の菅野裕介さん、HERO Xにも登場いただいた富士通UIデザイナーの本多達也さんとSONY CSL兼Xiborgの遠藤謙さん。会場では手話通訳者として和田夏実さんのほかに、聴覚障がい向けの情報保障として富士通のLive Talkも採用された。

「生まれながらにして視聴覚・身体能力に障がいのある方はいらっしゃいますが、高齢化社会では何らかの障がいをもつ人も増え、様々なダイバーシティが生まれます。できないこととできることを考えたときに、できないことをなるべく小さくして、できることをより拡張する。そうすれば、本当に個性が活かせる社会になるのではないか、ということを我々は考えています」
シンポジウムは、落合さんによるプロジェクト概要についての講演からスタート。X DIVERSITY始動の背景として、科学技術振興機構(略称JST)のCRESTに採択されたプロジェクトであることも冒頭でふれられた。

「少子高齢化によって我々の社会を維持する介護・福祉における労働力は限られており、(移民などの抜本的な人口維持策がなければ)何らかの工学的な解決が必要です。我々は人や環境の違いとAIをクロスして、多くの人々が問題解決に近づく仕組みを考えています。ダイバーシティと言っていますが、要はインクルージョン(包摂)可能な社会。多様性のある人たちがインクルーシブになっている社会を生み出すことが我々の使命です」
その課題解決のために集められた選ばれし仲間たち。ジェネラリストの落合さんを筆頭に、3人のスペシャリストがチームを支える。

「僕の中でこの X DIVERSITYは、『チーム作り』が命だと思っているプロジェクトのひとつ。横に分けると僕と菅野さんがアカデミックな仕事で、本多さんと遠藤さんは産業界の人。縦に分けると僕と遠藤さんはスタートアップをやっていて、菅野さんと本多さんは大組織に属しています。さらに、僕と遠藤さんと菅野さんはPh.D(Doctor of Philosophy)持ち。それぞれの技術的専門性と連携して社会的にアプローチしていきたいと考えています」
気鋭の若手研究者が描き出す未来

X DIVERSITYの取り組み事例として、髪で音を感じる新しいユーザインターフェイス〈Ontenna〉の紹介が本多さんより行われた。OntennaについてはHERO Xのシリーズ連載(http://hero-x.jp/movie/2692/)で取り上げさせていただいたので、ここでは割愛する。
その後のパネルトークでは、未来社会デザインに向けて社会課題にどうやって技術で取り組んでいくのかということをいくつかのキーワードをもとに議論された。

落合:僕と遠藤さんがよく話しているなかで、一番重要なのは【マーケットサイズ】の話。
遠藤:義足もOntennaも、ものを売るだけでは成り立たないところがありますよね。義足は足のない人しかマーケットがないのですが、Ontennaは健常者も障がい者も関係なく楽しめるという側面がある。それが市場を広げる工夫なのかなと思います。

落合:ロボット義手が玩具というカテゴリで販売していたりするじゃないですか。要は品質保障しないと医療器具としては扱えないわけで。
本多:Ontennaを医療器具にはしたくないですね。そうしてしまうと届けるのに時間もかかるし、価格もすごく高くなってしまう。マーケットの話もありますが、障がい者のためのものだけになるとデザインもよくなくなってしまう。むしろ誰もがつけたくなるようなカッコいいものを作りたいという想いがありました。

落合:遠藤さんと【スキーム】の話もよくしています。我々はバーチャルラインをもっているので、問題を抽出して、データセットして、統合化することはできるけれど、ネットプールを使ってライセンス管理するところまでは難しい。データのプラットフォームをきちんと作らないとこの国でうまく生きていくことはできないし、攻撃性の高いことをやらないといけないと思っています。
遠藤:一方で安全面をしっかり考えないといけないので、Ontennaでも義足でも同じような問題が発生したときに共通化してみんなに伝えられるような組織体があったら嬉しいですね。そうすれば、みんなが幸せになれるようなものをどんどんテクノロジーで生んでいけると思います。

落合:あとは【当事者感】がすごく重要だなと思っています。実際に聞いてみないとその人たちが抱えている問題はわからない。
本多:Ontennaで言えば、振動で伝えてくれて感動したという声もある一方で、僕は生まれてから耳が聞こえないのに、こんな振動もらったってしょうがないよ、みたいな話もある。
落合:ここらで【菅野ぶち込み】してもらいましょうか(笑)。

菅野:僕は当事者ハッカソン的なものにすごく可能性を感じています。大学にいる人間だから教育の価値を信じているところがあるんですね。人も機会学習をするとなったときにうまく設計ができていて、当事者であるユーザが自分なりの機会学習をすることができれば、将来的に多様な社会につながると思います。すごく【hackable】なOntennaだったら誰もが使うと思うんですよね。
落合:まさしくそうで、【hackable】なツールを本人が本人の理解の上で動かす分にはそれは医療器具じゃないしウェアラブルな自作電化製品になるはず。ドライバーを使って電池交換するぐらいは誰でもできるわけで、そのくらいの感覚でOntennaが調整できたらいい。僕も教育の可能性に期待しています。
遠藤:【プロトの話】とありますが、今の流れでいうと、早くプロトタイプを作って、買い手を見つけてどんどんサイクルを回し、最終的にやりたいところに辿り着くみたいなシステムでやっていますが、大企業だと辿り着くまでに死んでしまうプロジェクトがいっぱいある。一方でベンチャーでは、辿り着くまでのサイクルが回せない。

落合:ちょっと作ってみた、というものがポンポン出せるようになればいいのですが、その反面品証の面で爆発しちゃったらまずいわけで。電子工作好きが自分でつくったものがショートして火を吹いたのならすぐ対応にできると思いますが、買ってきた携帯電話が爆発したら全く対処法がわからない。
菅野:独断でデザインしてしまうと100%の性能を期待してしまうけれど、使う側がハックして作っていくというところだと、そこそこの性能で使えるというのはあると思います。
落合:僕が思っている本多さんと遠藤さんのおもしろいところは、普通友達に耳が聞こえない人や片足がなくなってしまった人がいたら、そういうボランティア団体とかをつくるじゃないですか。それなのにふたりはモーターとアクチュエータの性能で解決しようと考えるところが【hackable】な精神だなと。問題を根本から解決する方法を探すほうがアプローチとしては困難ですが、その困難なことができたら問題は完全に解決する。それって実はすごく大切なことだと思います。

個性が活かせる新たな社会に向けて走り出したX DIVERSITY。代表である落合さんは最後にこう話す。そこにプロジェクトの真髄を見た気がする。
「我々の定義している障がいは障がい者じゃない。つまり障がいそれ自体はなんらかのできないことがあるというだけで、それをもっている人間が能力的に劣っているということではない。トータルの能力の話とパラメータの偏りは別。人格と個別の機能を切り離して考えるというのがX DIVERSITYのストーリー。障がいが付随する人間をネガティブなイメージで捉えることは、今すぐ社会から捨てなければならないと僕は思っています」