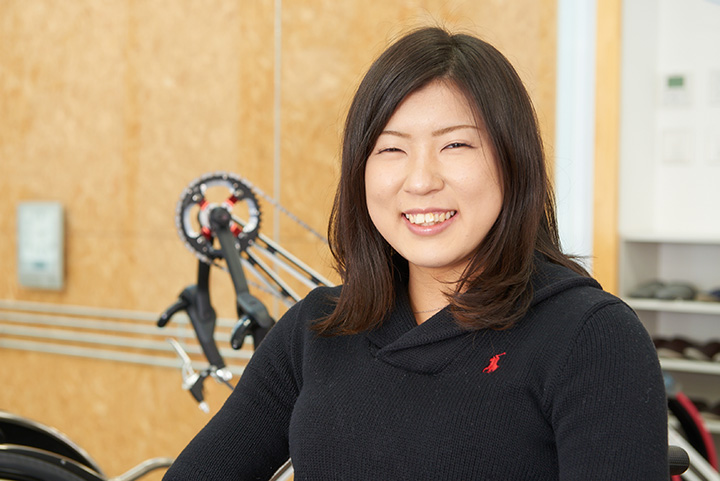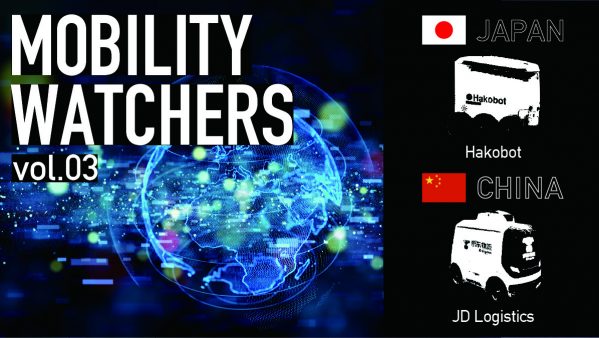健常者、障がい者を問わず、スポーツを通して様々なことにチャレンジする人をサポートする団体・「TEAM POSITIVE」。今回、その代表を務める鈴木隆太さん(以下、鈴木さん)と、HERO X編集長・杉原行里(以下、杉原)との対談が実現。“楽しむ”ということに重きをおく2人に科学反応は生まれるのか!?
新しい何かが始まる予感!
鈴木さんが不慮のバイク事故により左下腿を失ったのは、血気盛んであった17歳の時。一度は失意のどん底に落ちたものの、強い気持ちで前向きに生きることを決意。そこからその時の経験を活かし、TEAM POSITIVEの立ち上げに至ったわけだ。
これまでの人生や展望について語っていただいた第1弾のインタビュー(http://hero-x.jp/article/6015/)。前回のインタビューからHERO Xと何か一緒にできることは無いものかという話が上がり、今回の対談が実現した。

杉原:第1弾として、今年の初めに取材させていただきましたね。その節はありがとうございました!その時に、「TEAM POSITIVE」発足の経緯や、義足になった理由などはお話いただいたので、今回は、我々がもし何かを一緒にできるのならば、どのような可能性があるのかをお話できたらといいなと思い、楽しみにしていました。
鈴木さん:こちらこそ宜しくお願いします!
杉原:急に、何か一緒にできる可能性って言われてもって感じですよね(笑)。でも現実的に考えると、まず一番は、私自身がプロデューサーを務めるエクストリームスポーツとストリートと音楽のイベント「CHIMERA GAMES」などのイベントへの参加が一番近道なのかなと思います。
鈴木:そうかもしれませんね。僕自身もバックカントリーやバイクに乗る時などのアクティブなことをする時に使用する、BIO DAPTというアメリカ製の義足の展示はマッチすると思います。なぜなら、社長のMike Schultz自身もモトクロスやスノーモービルを乗っているので、義足でのデモンストレーションを行なってもらうなどはいいかもしれません。また、海外のパラリンピアンを招集したり、実際に私たちの使っている道具や義足、今まで行なってきたスポーツトレーニングの紹介なども現実的なのかなと。
杉原:確かにそれは、イベント自体のコンセプトにもはまってそうですし、取っ掛かりとしてはいいかもですね。その中で、鈴木さんが今まで積み重ねてきた経験を次世代へ伝えるためのトークショーなどがあったら、より深みが出るかも。
鈴木:僕自身、足を失ってから初めて感じられたことはたくさんありますからね。人と比べるのではなく自分自身と向き合うことの重要性。そして、やれない、出来ない事に理由を探すのではなく、やれる事を探す。そこから目標を持ち、諦めず、挑戦し続け楽しむ。そういった場で、本当の意味の心のバリアフリーを伝えられたら僕自身も嬉しいし、もっと言うと、これが伝われば世の中が変わると信じているので、ぜひ機会があればと常々考えています。
強く想い続けることの重要性

杉原:様々なエンターテイメントやスポーツが入り混じっている中に、当たり前のように、HERO Xのような存在がある。今までこのようなイベントってなかったのかなと、僕自身感じていますし。決して悪いことではないのですが、ほとんどの場合はそのカルチャーや競技に特化したイベントになってしまっている現状を打破したいという気持ちが強いんです。
どんなことでもそうだと思うのですが、今まで通りに進めているだけではいつか行き詰まってしまう時が来る。そうならないためにも、様々な方向から先手を打っておくことって大切じゃないですか。
鈴木:出来ることを無理のない範囲で日常から行っておく。例えば、ステッカーを配るくらいのことから始めてもいいと思うんです。お互いを拡散しあい様々な人に認知してもらう。もちろん大々的にお金を掛けたプロモーションも大切だとは思うのですが、それとは別にそういった草の根的な活動も、テクノロジーが発達した現代だからこそ意味を成してくるのではないかな。
HERO Xと直接何か出来たらいいな、というのも考えていまして(笑)。例えばTEAM POSITIVEで引率できるイベントを開催し、HERO Xに窓口的な事をしてもらう。私の得意分野であるスノーボードや山登り、カヌーなど。そして、新たなチャレンジを行いたいとHERO Xに連絡が来たら、こちらの持っている情報でサポートを行うなど。実は今、義足の冒険家としても活動していまして。その活動を都度発信してもらうなど協力し合えたら、僕的にもすごく嬉しいなって思っているんです。
杉原:義足の冒険家とは、具体的にどんなことをしているのですか?
鈴木:今のところは、バックカントリーを中心に動いています。バックカントリーというのは、レジャー用に整備された区域ではなく、手付かずの自然が残っているエリアに入っていってスノーボードで下山すること。ちゃんとした知識としっかりとした装備を整えないで山に入ると、確実に命の危険に晒されるので、軽い気持ちでは絶対にできないんです。今後は海外にも出向き、様々なことにチャレンジしたいと思っているので、TEAM POSITIVEだけではなく、僕個人の活動にも是非注目していただけたらなと思っています。
杉原:それは面白いですね。そういった活動をすることで全ての人に勇気を与えられたらすごく素敵なことだと思います。でも絶対に無理はしないでくださいね(笑)。

杉原:話をしてみると色々と出てくるもんですね。もちろん何かを実現するためには、しっかりと話を詰めていかなくてはいけない。その第一歩として今回のような対談は、大きな前進だと僕自身も思っています。引き続き何ができるかを模索していきましょう!
自分の置かれた状況を楽しむことを大切にする二人が直接話すことで、一緒に出来ることと、出来ないことがある程度見えてきた今回の対談。新しい何かの実現に向けたTEAM POSITIVEと HERO Xの動向に、今後も注目していただきたい。
オフィシャルサイト:https://www.teampositive.biz/













 杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?
杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?