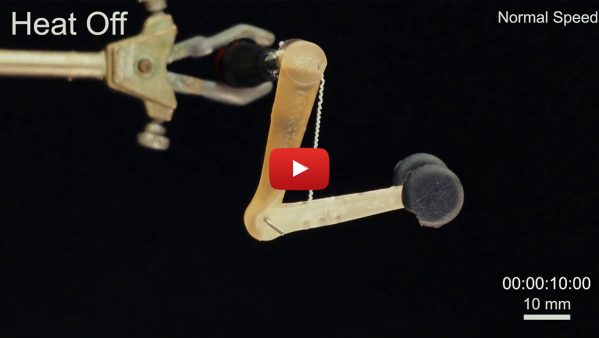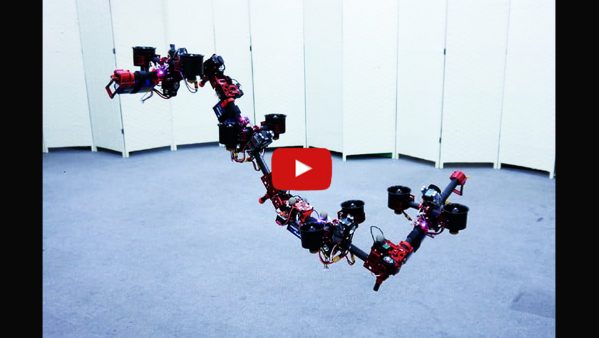周囲に広がるのは畑。前方にいる人が屈んで野菜を収穫し、こちらに投げる。受け取るために手を前に伸ばす——。これは株式会社mediVRが現在開発しているVR(仮想現実)プログラムの中のひとコマだ。ゲームのようだが、主目的は楽しむことではなく運動リハビリテーションにある。開発の背景には、どんな課題があったのだろうか。代表取締役の原正彦氏に話を伺った。
上半身の体幹バランスを鍛えるプログラム
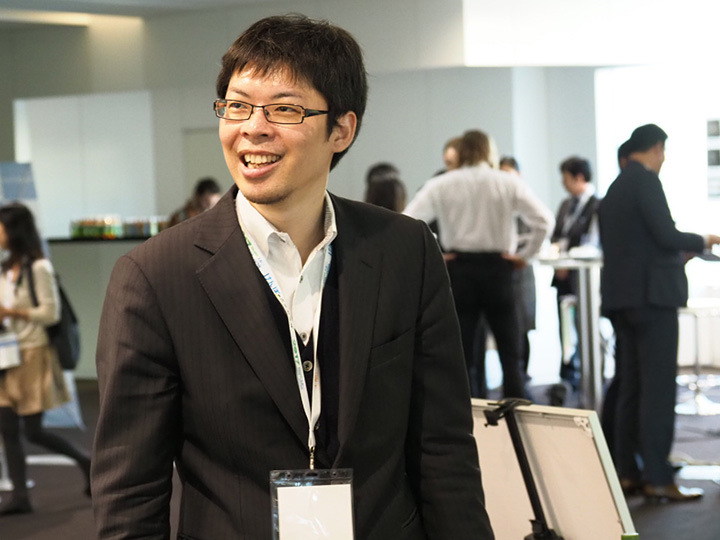
まずは、このVRプログラムについてもう少し詳しく紹介しよう。メインターゲットとして想定しているのは、歩行機能に何らかの問題を抱えている脳梗塞患者やパーキンソン病患者、高齢者だ。歩行には、下肢の筋力と上半身のバランスが必要とされる。mediVRが開発を進めるのは後者の領域、上半身の体幹バランスを鍛えるためのリハビリテーションプログラムだ。現役の医師でもある原氏は、その狙いをこう説明する。
「健常者にとって、手を前や横に伸ばす動作は難なくできるものですよね。しかし、脳梗塞後の患者にはそのコントロールが難しく、少し体を傾けるだけでバランスを崩してしまいがちです。そして、上半身がスムーズに動かないと、バランスを保持するために足が硬直してしまい歩行に障害が出ます。
止まっているエスカレーターを歩くと、不思議な感覚に陥るでしょう。あれは、小脳が覚えているバランスと視覚情報がミスマッチを起こすからなんです。脳梗塞後の患者にも同じことが起きています。今までの感覚で同じ動作ができないため、強烈な違和感を覚えて歩けなくなってしまうのです。
この状態を打開するには、自転車に乗る練習のように、何度も同じ刺激を与えて体幹バランスを小脳に記憶させないといけません。“これくらい前に手を伸ばすと体幹がどれだけ崩れるか”といったことを体と脳に覚えさせるのです」

ヘッドマウントディスプレイを装着すると、VR空間上に座標が現れる。コントローラーを持ち、その座標まで手を伸ばす。こうすることで、手を伸ばす距離や方向を定量的に指示することが可能になるのだ。
「これまでリハビリの現場では、医師や理学療法士が定量的に指示を出すことができないという課題がありました。“手を30センチ上げてください”と言われても、患者さんは“30センチってどの位?”と戸惑いますよね。そのため指示が曖昧になりやすく、負荷する刺激の強度が毎回バラバラになりがちでした。これでは医療者側も患者側もフラストレーションが溜まりますし、定量的な評価を下すことができません。リハビリで大事なのは、その人ができる最大のことを繰り返し練習すること。そのためには、定量的な指示と評価が欠かせません」
リハビリ領域においても、「神の手」と呼ばれる医師や理学療法士は存在する。患者の小さな変化に気づき、PDCAサイクルを回していける医療者が担当すると、治療効果は目に見えて変わるという。定量指示・定量評価が可能となるVRプログラムは、一部の優秀な医療者の「感覚」を、より多くの医療者に与えるものだ。それは、リハビリの質が全体的に底上げされることを意味する。
定量指示・定量評価はこのVRプログラムの大きな特徴だが、もうひとつ見逃せない特徴がある。それは、運動機能と認知機能を同時に訓練できるデュアルタスク型のリハビリという点だ。
「自転車に乗った高齢者が狭い道で人とすれ違うとき、自転車から一旦おりる場面を見たことがありませんか? “自転車を漕ぐ”“危険を回避する”というタスクを同時に行うと混乱するので、直感的にタスクを削ってシングルタスクに落とし込んでいるのです。でも、認知機能が低下するとそれもできなくなります。歩いているときに話しかけられただけで転んでしまう。“stop walking when talking”と言って、医学の世界では有名な現象です。
こうした転倒を予防するために重要なのは、軽い認知刺激と運動を組み合わせたトレーニングです。たとえば、“猿が木を揺らすとリンゴが落ち、それを受け取る”といったVRプログラムでは、“猿が奥の木に移ったから、次はあのあたりにリンゴが落ちるはずだ”と頭の中で計算し、手を伸ばすでしょう。これが自然と、デュアルタスクを処理する訓練になるのです」
「遊んでいたらいつの間にか歩けるようになっていた」を目指す

2018年5月現在、システム自体は既に完成し、安全性試験も終えているという。CTOの榛葉喬亮氏は、「いまはコンテンツとしての面白さや見せ方を追求している段階」と話す。
「手を座標まで伸ばすという基本的な仕組みは同じでも、見せ方はいくつも考えられます。たとえば、目の前に現れる悪役に対して印籠をつきつけるといった水戸黄門風の演出にすると、高齢者の方には馴染みやすいのではないでしょうか。海外で販売するなら、ドラキュラと十字架に置き換えられますね。畑で野菜を収穫するという見せ方も受け入れやすいと思います。どうすれば“リハビリ”ではなく“ゲーム”として取り組んでもらえるだろうかと考えています」
脳梗塞後、患者の3割がリハビリに苦痛を感じやめてしまうという研究報告もあるという。そこで大事にしているのが、「entertainment with hidden healthcare curriculum」という考え方だ。これは、エンターテインメントの中にヘルスケアの要素が隠れていて、「遊んでいたらいつの間にか歩けるようになっていた」状態を目指すというもの。実際に、安全性試験でプログラムを体験した高齢者は大いに熱中し、「次はうまくできるからもっとやりたい」と、決められた回数以上プレイしたがったという。また、体験者同士で「ここはこうするんだよ」と教え合う場面もあったようだ。

「お孫さんとの協力プレイができる仕組みも実装予定です。コミュニケーションが生まれる工夫を散りばめたいですね。子どもの頃、友達と“あのゲームどこまで進んだ?”と話す時間が好きでした。同じように、患者さんたちが“ここまでできるようになった”と、楽しみながらリハビリに取り組む光景をつくりだせたらと思っています」
運動機能や認知機能を高めると謳うゲームは存在するが、同社によるとエビデンスに基づいたものは少なく、医療機器よりも玩具に近いものが大半だという。
エビデンスベースでパラメータを設定したVRゲームプログラムはこれまでに例がなく、医療機関や専門家から期待が寄せられている。今年1月には、経済産業省が主催する「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018」でグランプリを受賞した。
脳梗塞患者や高齢者が自分の足で歩ける社会へ

リリース時期は年内を予定しており、HTC Vive、パソコン、プログラムをセットにした医療機器として販売する。名称はまだ決まっていないが、BtoBで想定している販売先は、病院、介護施設、フィットネスクラブなど。価格は200〜300万円となる見込みだ。
「これまでは、患者がリハビリに取り組む間、理学療法士はつきっきりで見ていなければいけませんでした。それを機械が代替することで、理学療法士は人間にしかできないことに集中することができます。また、一度に見られる患者の数も増えるでしょう。これは、良質な医療を受けられる患者が増えるということです」(原氏)
また、個人への販売も行う予定で、その場合の価格は120万円前後で考えているという。
「リハビリをくり返すことで神経回路ができ、脳と体に記憶として定着します。しかし、慢性期の患者さんが自費で通院する場合、たとえば1回1万5千円程かかり仮に週2で通うとすると、年間約160万円ほどの負担となる計算です。そして、バランス感覚を脳と体に記憶させるには、週2では足りません。
自宅で毎日リハビリをできるようになれば、“これ以上は治らない”と言われている患者も治せる可能性があるのではないかと期待しています」
再び自分の足で自由に歩きたい——。病や老いによって歩けなくなった人の夢が現実になる日も、そう遠くないかもしれない。
株式会社mediVR
2016年6月設立。VR等の映像化技術を応用した医療機器、医療システムの企画、開発及び販売を行う。現在、特許6200615技術を用いたVRリハビリテーションプログラムを開発中。