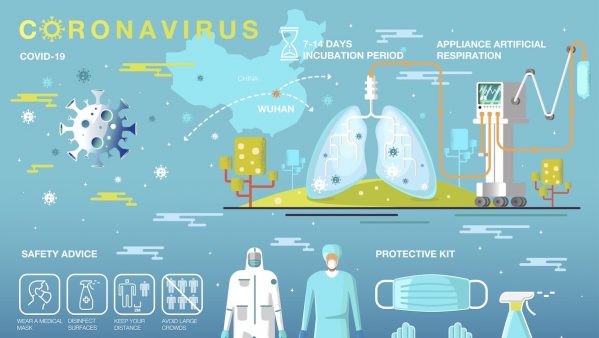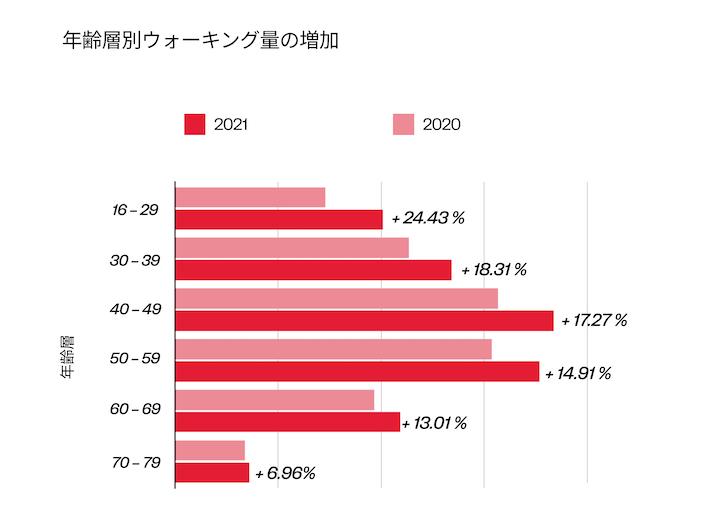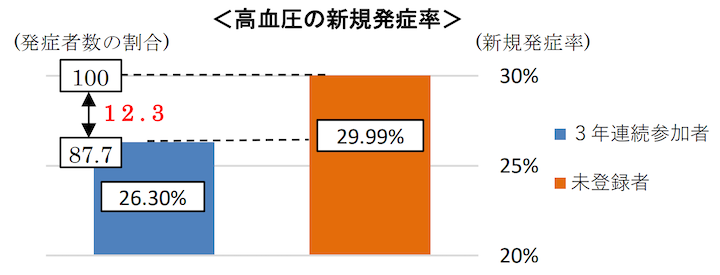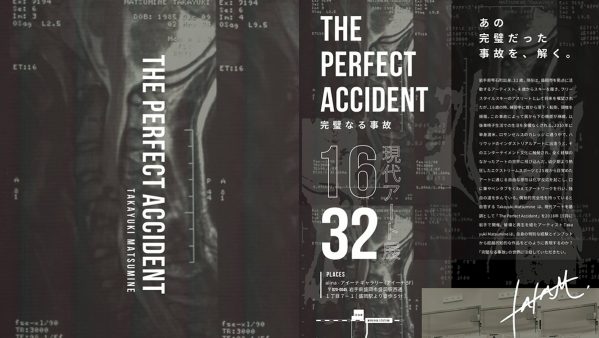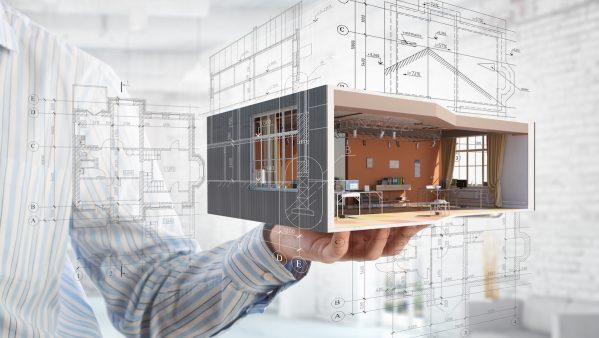株式会社三菱総合研究所と株式会社Moffの提携により開発された、ウェアラブル端末によるモーションキャプチャー技術を使用した、IoT身体機能計測サービス「モフ測」。その特徴は、ずばり「ビジュアルと数値で、リハビリによる改善を見える化できる」ということ。今回は、このモフ測の開発に携わった、株式会社三菱総合研究所の研究員鈴木智之氏と主席研究員吉池由美子氏に、モフ測が生まれた背景や今後の動向を伺った。
医療現場で見つけた「見える化」というヒント

今年3月にサービスを開始した「モフ測」。この一大プロジェクトを動かす原動力となったのが、あらゆる可能性を秘めた「モフバンド」の存在だ。
株式会社Moff(以下モフ)がクラウドファンディングをきっかけに、2014年に商品化した「モフバンド」。当初は3Dモーション認識技術を用いたスマートトイデバイスとして展開し、「モフバンド」と連動した教育向けアプリやゲームアプリなどを次々に展開してきた。これまでにないIoTデバイスとして世界的にも注目を集めてきた「モフバンド」だったが、ヘルスケア分野からのアプローチで関心を持ったのが株式会社三菱総合研究所(以下三菱総研)だった。

このプロジェクトをゼロから立ち上げた鈴木氏はこう振り返る。
「当社がベンチャー企業への提案や出資だけでなく、プロダクトづくりも含めた協業を推進し始めていた頃に出会ったのがモフでした。当時、モフの社内でもモフバンドで蓄積できるデータをヘルスケア分野で活かしたいと考え、介護施設と連携して高齢者の身体データに関する研究が始まっていました。そこで、ヘルスケア分野で専門的なバックグラウンドのある当社のノウハウも活かした形でのタッグが実現しました。まずは、モフバンドがリハビリの現場でどう活用できるのか、専門とする大学教授の方々やリハビリ現場でヒアリングすることから始めました」
リハビリといっても外科手術を行う病院やその後のリハビリを中心とした病院、介護施設もデイサービスや入所施設など、その現場やユーザーによってリハビリの内容やニーズはそれぞれ異なる。様々な施設の見学やヒアリングを重ねる中で、「ユーザーのモチベーションを引き出すリハビリの見える化」という医療リハビリ向けの新たなサービスのコンセプトが固まっていった。
求められるのは、手軽かつ精密さ

「最初に驚いたのは病院で行われるリハビリ時間の短さです。例えば骨折で入院した患者さんは手術後3週間程度入院しますが、リハビリの実施は1日20~40分程度。リハビリ専門の病院に移っても、一日に行われるリハビリは2時間程度のところが多く、特に介助の必要な高齢の患者さんになるとそれ以外の多くの時間をベッドで過ごすことになってしまいます。また、リハビリ中に行われる腕や脚の上げ下げの計測は、ゴニオメーターという分度器のようなもので行われています。測る人によっては誤差も出ますし、正確な計測は難しい。モフバンドは装着した体の角度や動きを精密に計測するセンサー機能を持っていたので、これを活用して短時間で目に見える記録を提供したいと考えました」
モフ測の開発で重視したのは、手軽さと精度。ボタン一つ押せば10秒程度でセットアップが完了するため、短いリハビリ時間でも手間をとらない。モフバンドを装着した部位の動きを1度単位で自動記録し、体の動きはリアルタイムでグラフやマーカー、3D画像で分かりやすく画面に表示される。さらに日々の成果を比較して確認できるため、ユーザー自身に分かりやすくフィードバックすることもでき、マンネリ化しがちなリハビリのモチベーションを高めてくれるのだ。

「こうした見せ方、直感的な分かりやすさで患者とのインタラクションを柔らかく作れた背景には、子供向けアプリを開発してきたモフならではの感性が生かされています。センサーを使用してデータ計測する製品は以前からありますが、いずれも研究用途の大掛かりなものばかりでした。また、それらは海外製品が多いため、日本の医療現場のニーズを汲み取って汎用されることは難しい。私たちはIoTをリハビリに取り入れていく中で、現場の先生たちと一緒に考えながらブラッシュアップしていくサービスにしていきたいと考えています」
モフバンドにみる未来のヘルスケア

今年3月に本格的にサービスを開始したばかりのモフ測だが、すでに医療や介護の現場からは嬉しい声が届いているという。
「リハビリの初期段階からモチベーションを引き出すことができ、患者さんたちも喜んでくれているという先生たちの声が多いですね。また、昨年には義足で走ることにチャレンジするというイベントにも参加させて頂き、義足にモフバンドを付けて走行運動を計測する試みも行いました。義足が実際の足のように動いているデータを見て、自分の体と一体になっている感覚が嬉しいと参加者の方々に喜んでいただけました。こうした取り組みも新たな可能性を生み出すきっかけにしていきたいです。現在はユーザーへのフィードバックを軸に展開していますが、今後2~3年のうちに様々なデータをもとにエビデンスを構築していきたいと考えています。精度検証はもちろん、モフ測の効果だけでなく、従来のリハビリ治療の効果やモチベーションの改善効果、治療期間、治療後の状態など、あらゆる角度からデータを収集し、今後の医療やヘルスケアに役立てていきたいです」

三菱総研でヘルスケア分野を専門とする吉池氏は、今後の展望をこう語る。
「現在モフ測は医療施設用に展開していますが、介護予防を目的としているモフトレと合体して、より有意義なアプリケーションにしていきたいと考えています。週に2回程度のデイサービスで行う運動だけでなく、自宅で運動したデータを施設と共有してコミュニケーションできたら、在宅時の運動不足が解消され、介護予防にもつながります。さらに、BtoBだけでなく、モフバンドを個人で持っていただけるようなBtoCが実現すれば、いつでもどこでも運動計測や遠隔診療での活用などの可能性も広がっています」
医療や介護といった分野で、新たな可能性を見出し続けているモフバンド。
子どもからお年寄りまで、1人1モフバンドという時代の到来も夢ではないかもしれない。