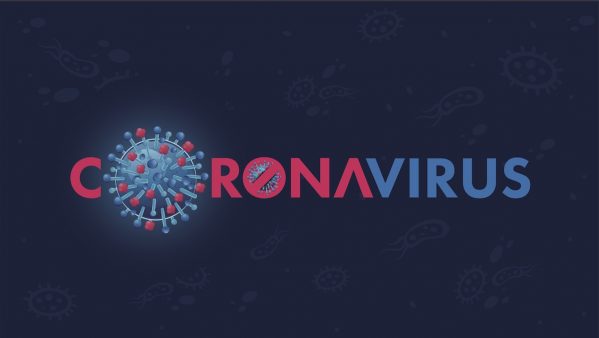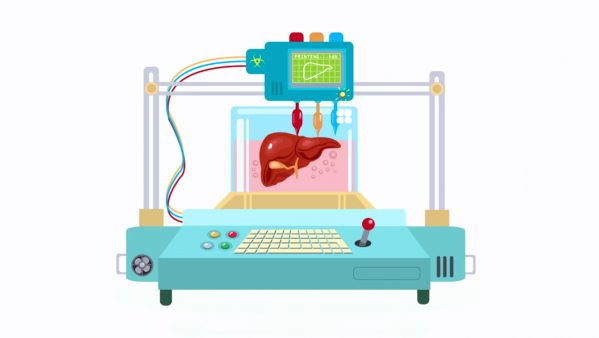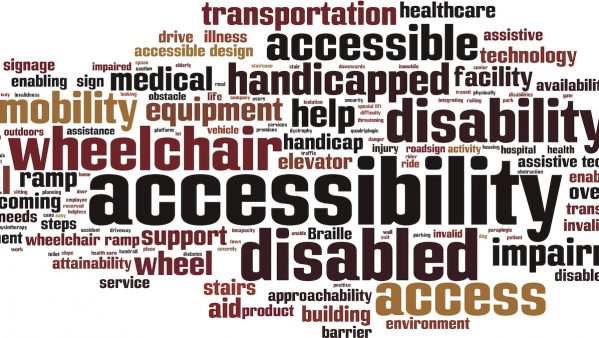VRを使った運動リハビリテーションプログラムを考案し、今年1月、経済産業省主催の「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018」でグランプリを受賞した株式会社mediVR代表取締役の原正彦氏。現役医師でありながら、医療分野において会社を5社立ち上げた起業家でもある。医学会の風雲児ともいえる原氏だが、活動の原点にあるのは、「患者に良い医療を提供したい」というシンプルな動機だという。
優秀なドクターが報われる世の中に

原氏は2005年に島根大学医学部医学科を卒業。循環器医としてキャリアを積む傍ら、臨床研究や医療統計に取り組み、世界的権威である米国心臓協会(AHA)で若手研究員奨励賞を3度受賞した。そんな原氏がビジネスの世界に乗り出したのはなぜだったのだろうか。
「より良い医療を患者さんに届けたいという想いから、アメリカで論文を発表してきました。世界の若手研究者トップ5に選ばれ、アカデミアの世界では他に追随を許さないレベルの業績を積み上げてきました。これで医療に革新を起こせると思いましたが、実際には医療の現場は全く変わらなかったんです。研究やアイデアをただ発表するだけでは、医療現場には普及しないということがわかりました。
ではどうすればいいか。世の中は資本主義で回っています。研究成果やアイデアをプロダクトという形にして、企業が儲かる仕組みをつくれば患者さんまで届けられると考えました。それがアカデミアの世界からビジネスの世界へと舵を切ったきっかけです」

2016年に日本臨床研究学会を立ち上げ、若手ドクターの研究をサポートする活動も行う原氏。そこに集まってくるアイデアをビジネスに落とし込み、会社を立ち上げている。
「優秀な人、頑張っている人が報われる世の中にしたいんです。逆に言えば、いまはそうなっていないということです。アカデミアの世界は完全に年功序列で、どんなに優秀であっても階段を一段ずつしか上がれません。給与も低いまま。熱意のあるドクターほどフラストレーションを抱えています。
彼らに論文を書かせて世界で発表させ、まずはアカデミアで評価されることをサポートします。そして、その研究成果をプロダクトにして会社をつくる。発案したドクターには株を持ってもらい、キャピタルゲインという形で思いきり還元します。
たとえばmediVRのアイデアを出したドクターには、株を10%持ってもらいました。100万円から開始したので10万円ですね。現在mediVRのバリューは10億円。2年後のM&Aを目指していますが、そのときには50億円から100億円になるでしょう。彼の取り分は5億円から10億円になる計算です。努力したドクターがその分だけアカデミックに受け入れられ、経済的に楽になり、治療に集中できる状態にしたいのです」
原氏が担うのはゼロイチの部分。ある程度形が整い、「世の中に浸透していくだろう」と確信を得られる段階まで来たら、大企業に買収してもらったほうがより多くの人に届けられるという考えだ。そしてまた別のドクターのアイデアを製品化していく。

ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018の授賞式
「患者さんのことを真剣に考えて努力してきたドクターが成功すれば、ほかのドクターも夢を持てますよね。“俺もやってやる”というドクターが増えたら、アイデアがどんどん形になり、良い医療が患者さんに届きはじめる。そんなエコシステムをつくりたいのです。僕ひとりで取り組むより、優秀な人をサポートしたほうが世の中に与えるインパクトは大きくなりますから」
技術は日夜進歩していくが、それだけでは社会は変わらない。必要なのは、自身の専門領域に技術を応用する仕組みを考え、意識改革も同時に進めていく、原氏のような存在ではないだろうか。
原正彦氏
2005年島根大学医学部医学科卒業。神戸赤十字病院、大阪労災病院で研修を受け、大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学で学位取得。循環器内科専門医、日本臨床研究学会代表理事、国立大学法人島根大学客員准教授、経営者と複数の肩書きを持つ。著書に「臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意」(金芳堂)