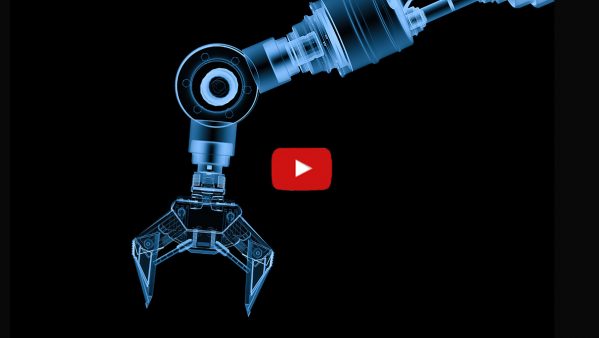2020年8月に、日本政策投資銀行等から39億円の資金調達を受けたことを発表した株式会社SkyDrive。産業用のカーゴドローンと並び、人を乗せて飛べる大型ドローン「空飛ぶクルマ」(SD-03)の開発で大きく注目されている。同機はこの夏、すでに有人実証実験も成功させた。エアモビリティ社会の実現を誰よりも待ち望む編集長・杉原行里が、SkyDrive代表の福澤知浩氏に「空飛ぶクルマ」の未来図を聞く。
「空飛ぶクルマ」にこだわるワケ
杉原:はじめに、人を乗せて飛ぶドローンについて伺いたいです。僕は福澤さんが描いているような未来を待ち望むひとりなのですが、一般への浸透具合としてはまだまだ「ドローンに人を乗せて飛べるの?」「ヘリコプターと何が違うの?」という方も多いので、初歩的なところからお聞かせいただけますか。
福澤:まず初めの質問、ドローンに人を乗せて飛べるか?というところでは、飛べます。通常、ドローンは5kgくらいですが、我々がいま開発しているカーゴドローンは、30~40kg程度運べます。プロペラの面積に比例して推力がほぼ決まるので、プロペラが大きいほど重いものが運べます。我々の製品は結構大きくて、人が乗っても問題ない推力になります。ですから、技術的な面から言えば、飛べるという答えとなります。

SkyDrive社の空飛ぶクルマ「SD-03」。2020年8月に、愛知県豊田市の豊田テストフィールドにて有人飛行試験が行われた。
©SkyDrive/CARTIVATOR 2020
ただ、やはり安全性が一番の懸念ですので、まずは、どんなシステムトラブルがあったとしても、飛び続けられるということを目指しています。その安全性レベルをボーイング、エアバスレベルに上げていくと、航空機とみなされて、一般の方を乗せて飛べるようになる。当社は2023年度にそこまで到達することを目指しています。
2つ目の質問、ヘリコプターとの違いをお伝えするために、まずヘリコプターが優れている点を挙げると、遠くまで行ける、重いものを運べるという点ですね。それに対し、空飛ぶクルマの利点は、電動なのでエンジンがなくて静か、着陸スペースが少なくて済むこと。ヘリコプターは斜めに降りたりしますが、空飛ぶクルマは完全に垂直に降りるので、離発着のスペースが確保しやすい。また、ヘリコプターはホバリングがかなり難しいのですが、空飛ぶクルマはホバリングが自動ですから、行きたい方向だけ操作すればいい。ヘリコプターのラジコンよりもドローンを操縦できる人が圧倒的に多いというのと同様に、空飛ぶクルマの操縦は簡単で自動化もしやすい。そのあたりが強みですね。
杉原:「エアモビリティ」「共生社会」などの表現もありますが、御社が空飛ぶクルマという表現にこだわっている理由はありますか?
福澤:理由は2つあります。飛行機はハレの日に使うモビリティで、それに対して、車は日常的に使えるモビリティですよね。車のように使えるということで、「クルマ」と名付けています。もう1つは、今は飛ぶだけの機体を作っているのですが、サイズがコンパクトなので、実は地上も走れるんです。地上も走って空も飛べる、現在の車の延長線上という位置づけです。
杉原:今、一気に世界各国でエアモビリティ競争が始まっています。その中で御社が掲げた「2023年度に人を乗せる」という目標は、市場調査などを見たなかではかなり早い方だと思いますが、それは可能なんでしょうか?
福澤:そうですね。可能だと思っていて、僕たち以外にもいくつかのプレイヤーがそれを目指しています。モーターやバッテリーを中心とする部品の成熟度と、それの組み合わせが要素だと思うのですが、ここ3~5年くらいで急激に部品の成熟度が上がってきて、さらに、スマホの普及で精度の高いセンサーの価格が100分の1とか10000分の1とかに落ちている。
杉原:今の質問は意地悪な意味ではなくて、僕は必ずエアモビリティ社会は起きると信じているんです。世界的には同じような競合他社がすでにサービスを展開したりしているんですか?

福澤:人を乗せている会社は、今はないです。ただ、我々が認識している限り、2020、23年あたりにスタートすると宣言している会社が2、3社あります。といいつつも、この手の開発分野のものはだいたい遅れるのですが(笑)。
杉原:宇宙開発と一緒で、遅れますよね。
福澤:はい。それで、みんなが同じようにスタートするとしたら、僕たちもトップ集団にはいるかなと。最初は運航の環境を限定して、安心・安全をキープしながらデータを蓄積しつつ改善し、アップデートしていくのが早いのではないかと思います。100%の機体を作る、そのぶん遅くなっても仕方ないという考え方もありますが、やはりベンチャーなので早めに出して回しながら圧倒的に拡げていくほうが当然よいと考えています。

杉原:それはそうですよね。だって大企業ができないことをやらないと意味がないですよね。大企業はエビデンスがないことに対して投資できない、稟議を通せない。でも、稟議なんて、我々のような規模の会社だったら福澤さんや僕だけじゃないですか。
福澤:そうだと思います。
ドクターヘリの代替にもなり得る
杉原:例えば電気自動車が流行ってきた理由に、電源供給のポートがどんどん増えてきたことがあると思うのですが、日本のエアモビリティ社会でのポートはヘリコプターと共有ですか。それとも遊休地を使っていくのでしょうか。
福澤:僕らが最初に飛ばすことを考えているのは、大阪の海上飛行ルートなんですね。大阪湾周辺にはポートとして活用できるスペースと場所がいくつかあって、そこを転用しようと思っています。ある意味、遊休地ですね。川や海の上の方が非常時に着陸しやすく、住んでいる人たちの理解も得やすいという観点で選んでいます。それ以外はヘリポートだったらどこでも止まれますし、あとはヘリ―ポートほどの面積が不要なので屋上が余っているところなどを使えるのではないかと。
杉原:面白いですね。日本はヘリコプターを導入している実績が世界ランキングのトップ5、トップ10レベルだと思います。ですから、上空を飛ぶことに対する理解はあると思うのですが、さきほどおっしゃった周辺に住んでいる人たちの理解度という話でいえば、倫理観とかと戦っていかなきゃいけないと思います。そのへんは、どれくらいの早さで受け入れてもらえると思いますか。
福澤:2023年度に大阪で飛ばすことに関しては積極的に官民の関係者と協議を進めているので、実現可能にかなり近いと考えております。ただ、見上げたらたくさん飛んでいる状態になった時に「落ちてこないの?」「空が汚くなっちゃうね」「うるさいんじゃない?」という懸念が出てきますが、そこはなかなかコントロ―ルできません。「空飛ぶクルマ」という単語を使うのは、その観点でも利用者側のイメージが湧きやすく、新しい移動モビリティだけどなじみやすいと考えています。
杉原:僕は緊急性を有している所にイノベーションが起こりやすいと思っているのですが、御社は災害に対するアプローチはされていますか。
福澤:ドクターヘリの代替はあり得ると思っています。ドクターヘリは運航費だけで年間約2億円かかるのですが、空飛ぶクルマは1台あたり約3千万円程度を想定していて、買ってしまえば終わりです。俄然コストパフォーマンスがいいので、そういう観点ではアリですよね。
杉原:どんどん普及していけば価格が落ちて、その時に車と一緒で、軽自動車を買って、ハイブリッドを買って、スポーツカーを買って、みたいになると思うのですが、狙うところはどのへんですか?
福澤:やはり小型乗用車のトヨタ・ヴィッツ系ですね。誰でも簡単に乗れる手軽なものです。主婦のかたや子どもでも興味を持つようにしたいと思っていて、デザインも、クールなフォルムでありながら、日常になじみやすい感じをだすようにしています。
杉原:ということは、フェラーリやポルシェのようなものが出てくると、より比較がしやすくなりますよね。
福澤:そうなります。僕たちのゴールは、日常的に空を自由に使えるようになるということ。コンパクトで誰もが使いやすくて、買いやすいモビリティであり、サービスがいいなと思います。
杉原:今後もうひとつ必ず出てくるのが、ライセンスだと思います。ライセンスは、航空機を運転するときに付帯するラインセンスになるのか、それとも新しくライセンスを発行していくのか。
福澤:現時点では、ライセンスは不要にしたいと考えています。自動運転だからそもそもライセンスはいらない、という方向にしていきたい。逆に操縦者は誰かというと、遠隔のパイロットか、完全にAIか自動運転という感じになるだろうと。ただ、最初の数年間は安全性担保のためにパイロットライセンスを持った人が万が一のために操縦できるようにしたいと考えているので、新しいライセンス基準を作っていきたいと考えていますが、基本的にはドローンの操縦スキルと危険・緊急時の回避ができるスキルというふうにできると思うので、結構ライトなものになると思います。
誰もが気軽に
空を飛べる社会をめざして
杉原:2030年度くらいには多くのエアモビリティが地方や海上を中心に制空権をとりながら、2040年度くらいには当たり前の文化になっているとされています。結構遠いですね。もう少し早められませんか(笑)。
福澤:スマホと一緒でスマホが登場したのはもう10年以上前で、今は誰でも持っているじゃないですか。アーリーアダプターな人は購入も早かったと思うんです。ですが、そうでない方たちはこれでいうと「いまだに空飛ぶクルマっていう単語すら聞いたこともない」という人たちだと思うので、その方々が使うまでが2030年度と考えています。
杉原:最後に、御社のめざす未来というのをお聞かせください。
福澤:みんなが気軽に、安全に安心して空を飛べるという時代をもってくることですね。
杉原:ぜひ、早くお願いします!(笑)
福澤:はい。ぜひ2023年度に大阪で乗って頂けたら嬉しいです。

<プロフィール>福澤知浩(ふかざわ・ともひろ)
株式会社SkyDrive代表取締役。東京大学工学部卒業。トヨタ自動車にて自動車部品のグローバル調達に従事。同時に多くの現場でトヨタ生産方式を用いた改善をし、原価改善賞受賞。2014年にCARTIVTORに参画、共同代表に。2017年に独立、製造業の経営コンサルティング会社を設立後、20社以上の経営改善を実施。2018年にSkyDrive創業、代表取締役に就任。