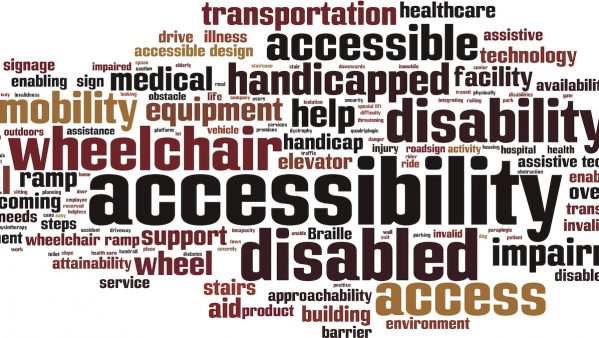運動音痴でも気軽に楽しめるスポーツの創造。この挑戦を続けるのが一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会。こたつの上で湯呑を使ってデジタルみかんを弾き飛ばしゴールを決め合う「こたつホッケー」や、ばらばらになった靴下からペアを見つけて籠に入れる「くつし玉入れ」など、くすっと笑えて誰もが楽しめる斬新なスポーツをいくつも生み出している。自らをスポーツクリエーター・福祉クリエーターと呼ぶのが同協会で代表理事を務める澤田氏だ。澤田氏はスポーツを通して何をなそうとしているのだろうか。『HERO X』編集長の杉原行里が澤田氏が見る未来について伺った。
スポーツをリノベーションする

杉原:前編に引き続きお話を伺いたいのですが、新しいスポーツの創造により、澤田さんは何をしたいと思っているのでしょうか。
澤田:一番わかりやすいのはスポーツの再定義です。これについてはゼロから何かをつくるのではなくて、リノベーションでいいと僕は思っているんです。明治維新以降に入ってきた近代スポーツって、日本の場合、過去の悲しい歴史色が入ってしまい過ぎなところがある気がしているのですが、その後についても経済成長と共に歩んで来てしまったためか、スポーツの定義がすごく狭いなと。前編でもご紹介いただいたトントンボイス相撲は、スポーツを薬に見立てているんです。発声をすることによって心肺機能の強化につながる。遊んでいたらリハビリもできちゃったみたいな状態を生み出せるので、高齢者にスポーツを処方するみたいな。そう考えると、僕らは色んな風に健康に寄与できるスポーツをつくっているわけです。
“ゆる”が飛び越えられる壁
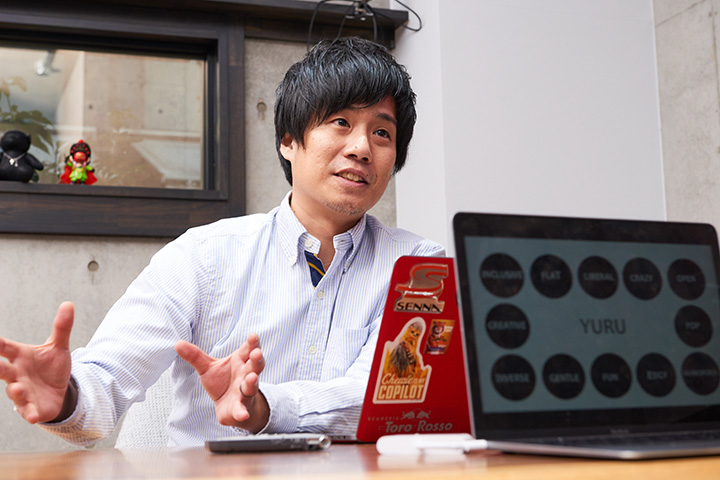
杉原:そうなると、狭かった定義が広がりますね。
澤田:そうなんですよね。せっかく2020東京があるのですから、これを活かせたらおもしろいなとも思います。何か日本は面白いスポーツの解釈をし始めたぞというのが世界に少しでも認知されたら十分かなと思っています。

デジタル技術との融合でこたつがホッケー台に変身
澤田:そんなわけで、「ゆるスポーツ」は今年から海外にも出して行っているんです。
杉原:なんか「カワイイ」と同じ感じで「ゆるスポーツ」が日本発の言葉として定着したら面白そうですね。
澤田:そうなんです。ゆるって言葉が実はポイントで、ダイバーシティやバリアフリーとかも言葉は入って来ていましたけれど、日本人がそれを腹落ちするレベルで理解するには時間が掛かったじゃないですか。イノベーションって言葉も認知はしたけれど、ちゃんと理解されてない感じもしますよね。僕は日本人だったら日本語ワンワードで勝負すべきだと提唱していて、直訳できない日本語に価値があると思うんです。

澤田:ゆるって言葉をアメリカ人とかに説明する時、ゆるっていうのは、リベラル、オープンでクレイジーで多様性があって創設的でみたいな。これはもう僕の解釈ですね(笑)。だけどゆるってコンセプトはやはり英語圏にはないんです。ゆるって言葉のすごくいいのが、みんなばかにするわけですよね。そこががすごいよくて。
杉原:なるほどね。たしかに英語にはできない表現ですね “ゆる” は。
澤田:人間の営みって放っておくと敷居が高くなって硬直してくるのですよね。組織も人の体もそうだし。それを人工的にもう1回ほぐすということが、“ゆる” だと僕は思っています。
杉原:狭い捉え方しかできていなかったスポーツの捉え方をほぐしてくれるということですか?
澤田:そうですね。人間、カッコいいものが好きな人もいるけれど、カッコいいアレルギーみたいなところがある人もいて、クスッとできる “ゆる” の要素は意外と万能だと思うんです。だから今、手掛けている視覚障がい者用に作っている肩に乗せて道案内とかをしてくれるロボットも、ちょっとかわいい忍者風にしていて、これ、多言語化して外国人観光客が使っても面白いと思うんですよ。スポーツも、どこかカッコいいばかりじゃなくて、遊び心がある “ゆる” が入ることでアプローチできる人が増えると思っています。

澤田智洋
1981年生まれ。幼少期をパリ、シカゴ、ロンドンで過ごした後17歳の時に帰国。2004年広告代理店入社。映画「ダークナイト・ライジング」の『伝説が、壮絶に、終わる。』等のコピーを手掛けながら、多岐に渡るビジネスをプロデュースしている。
誰もが楽しめる新しいスポーツを開発する「世界ゆるスポーツ」協会代表理事。一人を起点にプロダクトを開発する「041」プロデューサー。視覚障がい者アテンドロボット「NIN_NIN」プロデューサー。義足女性のファッションショー「切断ヴィーナスショー」プロデューサー。高知県の「高知家」コンセプター。








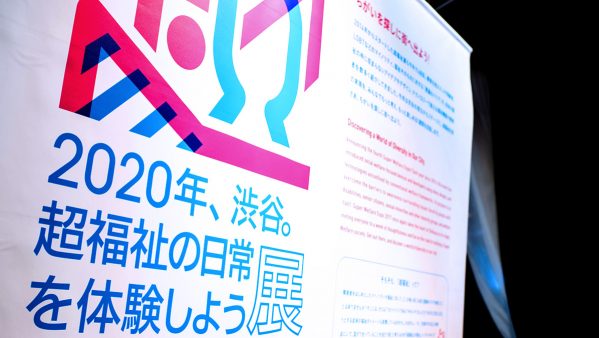


 それは、CHIMERA GAMESが始まったきっかけとはまた違うロジカルで進行している企画でして。今の子供達が置かれている環境って、遊び道具一つとってもクリエイティブ能力が必要ない物ばかりじゃないですか。ゲームにしても、ルールとパターンの中で進んでいくから、与えられた情報をどれだけ飲み込むかってだけなんですよ。
それは、CHIMERA GAMESが始まったきっかけとはまた違うロジカルで進行している企画でして。今の子供達が置かれている環境って、遊び道具一つとってもクリエイティブ能力が必要ない物ばかりじゃないですか。ゲームにしても、ルールとパターンの中で進んでいくから、与えられた情報をどれだけ飲み込むかってだけなんですよ。