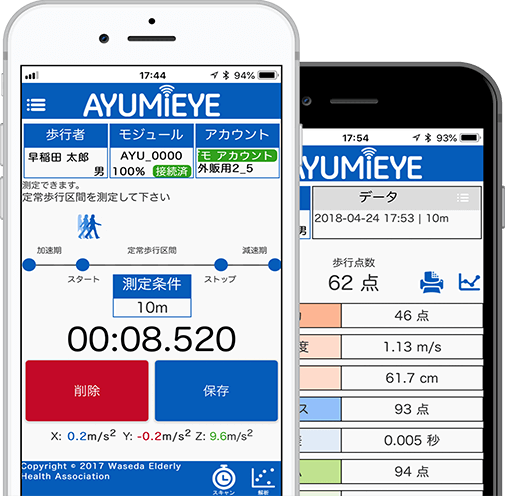目次
従来の枠に収まらない新たな発想から生まれた“カッコいい、カワイイ”プロダクトや“ヤバい”テクノロジーを備えた福祉機器を数多く紹介し、国内外から注目を浴びている渋谷発の「超福祉展」。仕掛け人であるNPO法人ピープルデザイン研究所代表理事・須藤シンジ氏の活動は、同展をはじめとする“コトづくり”のみならず、モノづくり、仕事づくり、人づくりなど、領域には多岐に及ぶ。その根底に流れるは、人々の意識をデザインするという形なき思想、「ピープルデザイン」。この生みの親も、また須藤氏である。ピープルデザインが目指す世界とは? 今後、超福祉展はどのように発展していくのか? 須藤氏に、HERO X編集長の杉原行里(あんり)が話を伺った。
モノづくり、コトづくり、仕事づくり、ヒトづくり。
打てば響くのは、次世代を担う若者たち

杉原行里(以下、杉原):世界に先駆け、超高齢化社会に突入している日本ですが、マイノリティや社会的に弱い立場に置かれている人たちと混ざり合う社会づくりにおいて、他の先進国のほうが、より進んでいるような印象を受けることもしばしばあります。その点については、どのようにお考えでしょうか?
須藤シンジ氏(以下、須藤):非常に難しい質問ですが、ひと言で言うなら、もともと遅れている、ということになるかと思います。1996年に母体保護法が制定・公布され、その後、障がい者自立支援法が2005年に制定され、2006年に施行されましたが、それ以前のこの国の障がい者は、いわば、法律的には人として認められているとは言い難い現実があったわけです。先進国比較でいくと、社会福祉などの面では、およそ50年は遅れているのではないでしょうか。
遅れというのは、すなわち、不都合な現実。だからこそ、キレイな言葉を並べるより、その不都合な現実を直視して、掘り下げていき、埋めるべき穴は埋め、捨てるべき部分は捨て、作り直す部分は作ることが、必要だと思います。その一方、この戦後70余年の間に築き上げられてきたやり方では、おそらくこの先、永続性が担保できないだろうし、新たな選択肢が必要になってくるだろうというのが、個人的な意見です。それゆえ、ここ6年間ほどは、「モノづくり」、超福祉展をはじめとする「コトづくり」、障がい者のための「仕事づくり」、そして、次世代の作り手や送り手を育んでいく「ヒトづくり」の4つの領域をベースとした活動を通して、さまざまな提案を投げかけることに力を注いできました。

杉原:周囲の反応はいかがですか?
須藤:圧倒的に言えるのは、学生さんなど、次世代の反応が極めて高いということですね。打てば響くという実感があります。学生に関係する活動をいくつかご紹介させてください。まず、この「JOYFUL」は、昨年の春から、都立高校と県立高校で使用されている英語の教科書です。「A Cool Way to Live Together」という見出しと共に、ピープルデザインのモノづくりやイベントなどをご紹介いただいています。僕たちの活動をピックアップしてくださったのも、非常に若い研究者たちが集っている教科書づくりのメーカーさんです。

国際、大学、自治体。
多彩な連携体制で実現した認知症プロジェクト
須藤:もうひとつは、この2年間に渡って、国内外の大学生と共に行ってきた認知症の共同開発プロジェクト「People with Dementia Project」。これは、オランダのデルフト工科大学との国際連携、慶應義塾大学大学院 博士課程教育リーディングプログラムPLGS、青山学院大学 法学部 法務研究科、教育人間科学部、専修大学 ネットワーク情報学部 ネットワーク情報学科との大学連携、認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ(DFJI)との団体連携など、多様な連携によりスタートしたプロジェクトです。学生たちは、現場に入り、各自がピックアップした問題点に対する解決策を提案します。それらを単なるアイデアに留まらせるのではなく、渋谷区や川崎市との自治体連携によって、社会で実装・実験していくというものでした。
今日ちょうど、ここに来る前に、この認知症プロジェクトの最終報告会を行っていたのですが、例えば、認知症の当事者の状況が体験できるVRの開発や、祖父母が元気な時から、孫が聞き手となって、さまざまな想い出を書き留めていき、もし、認知症になった時は、家族との間での会話を促進させていくためにそれらを使うというものなど、学生たちからは、さまざまな提案が上がりました。
また、認知症の進行によって、時間と場所の認知能力が低下することを踏まえて考案された、朝夕の歯みがきの時に、灯りが点く歯ブラシフォルダーや、外出中に自分の居場所が分からなくなるなど、困りごとがあった時に握ることで、家族にSOSを知らせることができるアクセサリー的なものなど、デルフト工科大学の学生からは、今あるテクノロジーを使い方ひとつで実装できる提案などがありました。なかには、ケーススタディとして研究成果を掲げているものもあり、仕入れ値から販売場所に至るまで、社会実装を踏まえたディテールが微細に渡って考慮されていました。

杉原:海外の大学や大学生の学生たちは、社会に繋がるチャンスが多いですよね。国は異なりますが、僕もイギリスの大学でプロダクトデザインを学びました。大学内で行う課題のプレゼンテーションなどは、企業の方などが普通に見に来られたりしますし、そこで披露した提案や研究内容が魅力的であれば、「一緒にやりませんか?」と、ダイレクトに声が掛かります。言うなれば、プロの世界に直結しているからこそ、真剣度が違う。
須藤:その通りだと思います。企業や投資家が、有能な学生本人にアプローチした一例として、2014年当時、デフルト工科大学大学院の1年生だったAlec Momont君の動画プレゼンテーション「Ambulance Drone」をご紹介したいと思います。
須藤:毎年、ヨーロッパで心停止に陥る人は100万人にも上るが、従来の応急手当では、対応に極めて時間を要することから、ほんの8%の人しか助からない。そこで、目的地に1分以内で到着できる、時速100kmで飛行するAED搭載アンビュランス・ドローンを設計。これによって、生存する確率を80%に上げることを可能にした――。この新しいドローンの開発と、通報からわずか1分足らずで迅速に対応できるという方法論の提案は、非常に高く評価され、Alec君は、ある有名企業のシニアマネージャーに大抜擢されました。特筆すべき点は、この動画が発表から4年ほどで、約946万アクセスに達していること。すごいですよね。
同大学の人間工学博士のリチャード・グーセンス教授は、教え子であるAlec君の開発内容を、第1回目の超福祉展で登壇した際に話してくださいました。また、ピープルデザインは、同大学最先端研究所のコンセプトのひとつにもなっています。
杉原:素晴らしい展開です。
須藤:高齢者が増加の一途を辿る中、そこにあるさまざまな課題解決の過程を可視化していくことは、超福祉展のタイド(潮流)のひとつでもあります。

超福祉展、ピープルデザインがもっと面白くなる
二つの“種まき”
杉原行里:超福祉展では、WHILLをはじめ、スズキセニアカーやヤマハ発動機株式会社さんの電動三輪コミューターなど、毎年さまざまなパーソナルモビリティが披露されています。今後は、どのような展開を予定しているのですか?
須藤:世界的には、2015年9月の国連サミットで採択され、2016年1月1日に正式に発効された17の「持続可能な開発目標(SDGs)」を実現するために、2030年に向けて、各国での準備が着々と進められていますし、日本では、超高齢社会に突入するとされる2025年がやがてやって来ます。より広い視点で見ると、大切なのは2020年の先だったりしますが、皆さんと同じで、超福祉展も、2020年をひとつのメルクマールとして捉えています。
モビリティも、さまざまな困りごとを解決するために生まれたプロダクトやサービスなどについても、今後、2018年、2019年、2020年の3回の開催において、ホップ・ステップ・ジャンプの段階を踏みながら、未だ見ぬ将来の芽吹く時期に向かって、それぞれの針路をきちっと見せていきたいと考えています。プロトタイプが本格的に社会実装されていくその過程において、「こういうものがあるんですけど、どうですか?」と提案を投げかけながら、世に顕在化させていくことは、イノベーションを起こす人たちが“種まき”する姿も可視化させていくということですね。
2016年下期より、デフルト工科大学のリサーチフェローに就任させていただき、最近では、オセアニアの大学でも、教鞭をとらせていただいていますが、前編でもお話したように、僕たちの活動領域のひとつである「ヒトづくり」においても、より一層、種まきに精を出して、次世代を育てていきたいと思います。

須藤シンジ(Shinji Sudo)
1963年、東京都生まれ。有限会社フジヤマストア/ネクスタイド・エヴォリューション代表、NPO法人ピープルデザイン研究所代表理事。デルフト工科大学/Design United/リサーチフェロー。大学卒業後、大手流通系企業に入社。販売、債権回収、バイヤー、宣伝、副店長など、さまざまな職務を経験する。次男が脳性まひで出生したことにより、37歳の時、14年間勤務した同社を退職し、自身が能動的に起こせる活動の切り口を模索し始める。2000年に独立し、マーケティングのコンサルティングを主な業務とする有限会社フジヤマストアを設立。2002年、ファッションを通して、障がい者と健常者が自然と混ざり合う社会の実現を目指し、ソーシャル・プロジェクト「NEXTIDEVOLUTION(ネクスタイド ・エヴォリューション)」を開始し、現在に渡り、「意識のバリアフリー」をメッセージする活動を展開中。その後、「ピープルデザイン」という新たな概念を立ち上げ、障がいの有無を問わずハイセンスに着こなせるアイテムや、各種イベントをプロデュース。2012年には、ダイバーシティの実現を目指すNPOピープルデザイン研究所を創設し、代表理事に就任。2015年より、従来の枠に収まらないアイデアから生まれたクールな福祉機器やテクノロジーを紹介する「超福祉展」を主催している。2016年下期より、デルフト工科大学/Design United/リサーチフェローに就任。
NPO 法人ピープルデザイン研究所
http://www.peopledesign.or.jp/