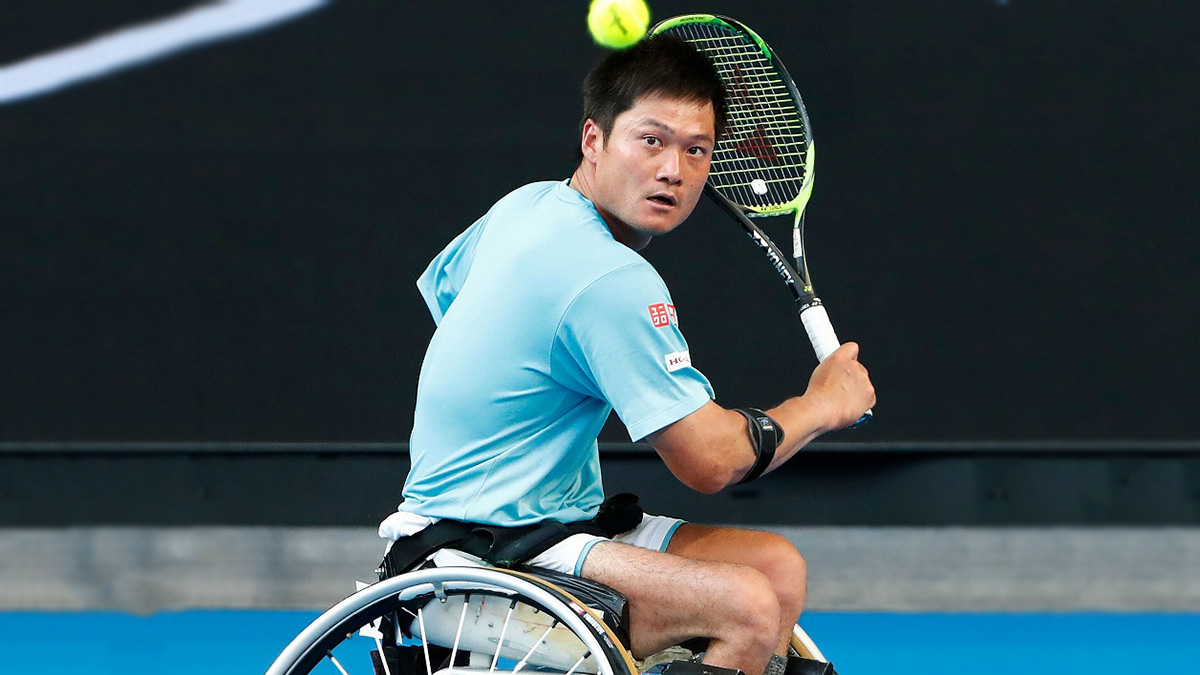2017年7月にロンドンで開催された世界パラ陸上競技選手権の男子走り高跳び(切断などT44)決勝で、同クラスのアジア記録、日本記録を更新する2m01の跳躍を遂げ、銅メダルを獲得した“日本初の義足ジャンパー”、鈴木徹選手。2016年リオパラリンピックのプレ大会「IPCグランプリ・リオデジャネイロ大会」では、それを超える自己新記録の2m02を樹立するも、同年に行われた本大会では4位入賞に留まり、メダル獲得を逃したが、その雪辱をみごとに果たす結果となった。しかし、ここからが本番。5大会連続出場のパラリンピックでは、6位、5位、4位と順位を上げてきたが、悲願のメダルはまだ手にしていない。活躍が期待される東京2020に向けて、どんな日々を過ごしているのか。“義足アスリートのパイオニア”が自身に掲げる使命とは――。競技用義足やトレーニングのこだわりに至るまで、鈴木選手に話を伺った。
経験を伝えることは、必ず誰かのためになる

2000年、20歳の時、右下腿を失ってからわずか1年ほどで、走り高跳び日本代表選手として、シドニーパラリンピックへの出場を果たした鈴木選手。その頃から山梨県の母校などで講演活動を始め、現在に渡って、全国各地の小中学校や高校などで、累計1000回に及ぶ講演を行ってきた。インタビューの日も、都内のある小学校で講演会を終えたあと、その足で約束の場所に駆けつけてくれた。
「僕たちは、オリンピック選手に比べて、メディアに出る機会はそう多くはないですし、その意味では敵わないと思いますが、ほとんどのパラ選手が、病気やケガなどで、一度スポーツを離れるなど、それぞれにつらい経験をしていて、それを乗り越えた選手もいれば、今も病気やケガと戦いながら競技に立ち向かっている選手もいます。その経験を伝える役目って、絶対にあると思うんですね。想いの部分を伝えることで、何かに悩んで、落ち込んでいる人が、『また、頑張ろう!』と奮起するきっかけになるかもしれないし、この国の未来を担う子どもたちが、本当の意味で、多様性社会を理解するための機会にもなるかもしれない。もちろん、走り高跳び選手としての自分があってのことですが、自身の経験を言葉にして伝えることは、ずっとこだわってやってきました」
相当な場数を踏んできたが、今でも、“伝わるように伝える”ことには、たいへん苦心するという。例えば、走り高跳び選手が、バーを超える時の空中姿勢のことを「クリアランス」というが、それを初めて聞く人にとっては何のことだか分からない。だからこそ、競技にまつわる専門用語など、当事者にしか分からないことを伝える時、鈴木選手は、努めて平易な言葉で説明することを心がけている。
「ちゃんと伝わっているかどうかは、小学生の反応を見たら、一番良く分かりますね。そこで得たことが、メディアの方の取材やインタビューの時に、活きることが多々あります。競技や僕自身のことを知らずに来られる方もいらっしゃるので、そういう方たちに対しても、きちんと伝えられるよう、常日頃から意識しています」
18年間、同じ義足に徹する理由

競技用、生活用共に、鈴木選手が使用するのは、アイスランドに本社を置く世界的義肢パーツメーカー、オズール社の義足。数あるメーカーの中から、なぜ、オズールを選んだのだろうか。
「ブライアン・フレージャーという米国の義足の男子陸上選手の存在がきっかけでした。事故で右下腿を失った年の夏、テレビのある番組で、来日中の彼を見かけた時、どちらの足が義足か分からないくらい、すたすたと歩いていることに衝撃を受けました。義足でも、こんなにキレイに歩けるようになるんだと。彼に憧れて、彼と同じオズール製の生活用義足を使い始めたのですが、重いし、扱いが難しく、最初は、なかなか思うようにはいきませんでした。それでも、フレージャー選手を知ったおかげで、彼のようにキレイに歩けるようになりたい、自信がついたら、ハーフパンツで街を歩きたいという目標ができましたね」
一方、アスリートの体の一部となる競技用義足の板バネも、2000年に初出場したシドニーパラリンピック以来、フレージャー選手と同じオズール製のものを愛用し続けている。しかも、今なお使用しているのは、18年前と同じ旧型モデル。義足の技術開発がめざましい進歩を遂げ、新たなイノベーションが次々と登場する中、その逆を地で行くようなこだわり。旧型モデルを使い続ける理由は、一体何なのだろうか。
「旧型モデルの板バネは、反発が小さく、コントロールしやすいからです。僕は、義足踏切ではなく、最後は、健足の左足で踏み切っていくので、最新型の板バネだと、反発が強いので弾かれてしまうし、重さもあるのでコントロールしづらい。ただ、これはあくまで僕の場合であって、選手によっても、種目や障がいによっても、さまざまに違います。選択肢が格段に増えた今、短距離走と走り幅跳びで、義足を使い分けている陸上選手もいますし、皆、自分に合うものを探して、色々と試していると思います。僕自身も、新しい義足が出てきた時に、試したことはありますが、競技では、ずっと同じ義足を使っていますね。ゆえに、この18年間、義足が理由で、記録が伸びたということはないです」
体は消耗品。トレーニングは、
本当に必要なことだけやる

競技用義足と同様に、トレーニングについても、「基本的には、わりと昔からあるようなベーシックな内容をベースにしている」と鈴木選手は話す。
「最先端のトレーニングも試したことがありますが、結局は戻ってくるというか、基本的には、コアな部分をしっかり抑えたトレーニングを行っています。ただ、記録が伸び悩んでいた9年間を振り返ると、トレーニングも含めて、同じことをやっていたんですね。続けることはもちろん大事ですが、凝り固まってしまうのは良くない。新たな視点を取り入れることも必要だと思い、3年ほど前から、海外でもトレーニングを積むようになりました」
スウェーデンやオーストラリアでのトレーニング経験からは、多くの気づきを得たという。
「筋力、走力、体幹を鍛えるトレーニングのいずれにおいても、走り高跳びにより有効なメニューが多くありました。しかも、競技に伴ったそれぞれのトレーニング内容がリンクしているので、より記録が伸びやすくなるという好循環が生まれます。実際、普段のトレーニングに、良いと思うものを取り入れてみたら、自己ベストの更新に繋げることができました。ただ、すべてが正解かといえば、そうではありません。もし、海外で受けたトレーニングを全部やり続けていたとしたら、多分つぶれていたと思います。30代後半の僕には、ハードすぎる内容だったので。だからこそ、未熟な20代の頃に行かなくて良かったと思いますね。全てを鵜呑みにして、やっていたでしょうから」
もうひとつの気づきは、
無意味なことはしないということ。
「日本のスポーツの世界では、長い時間をかけてトレーニングするほど、良しとされる風潮がありますが、海外だと、大体2時間くらいで終わるんですよね。しかも、無駄なものが削ぎ落とされているので、内容は濃密。長時間トレーニングしたとしても、だらだらとやっていたなら意味がないし、その逆に、集中してやれば、短時間で終わる練習もあるなど、トレーニングのあり方を根本的に見直す良いきっかけになりました。特に陸上競技の場合、アスリートの体は消耗品なので、なるべく無駄に使わずに記録を伸ばすのが一番。そのことが、本当の意味で、腑に落ちました。とはいえ、日本にも優れたトレーニングはあるので、それぞれの良い部分を取り入れたら、より理想的なトレーニングが出来上がるのかもしれません」

鈴木徹(Toru Suzuki)
1980年5月4日、山梨県生まれ。駿台甲府高校時代、ハンドボールで国体3位の成績を残したが、卒業前の交通事故により右下腿を切断。リハビリをきっかけに、走り高跳びを始める。その後、順調に記録を伸ばし、初めての公式大会で当時の障がい者日本記録を超える1m74を記録。日本初の義足の走り高跳び代表選手として、2000年シドニーパラリンピックに出場して以来、5大会連続入賞。2016年リオパラリンピックのプレ大会で、自己新記録の2m02を樹立し、自身のアジア記録と日本記録を更新。2017年、世界パラ陸上競技選手権大会で銅メダルを獲得。2m01の跳躍でクラスT44のアジア記録、日本記録を樹立した。自身の経験を活かし、全国各地の小中学校や大学などで講演活動も行う。SMBC日興証券株式会社所属。
[TOP動画引用元:©Paralympic Games]