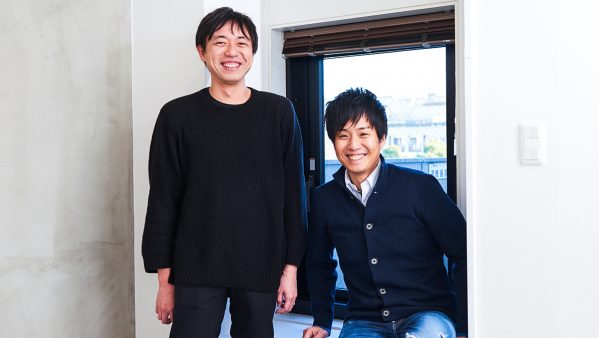目次
ピョンチャンパラリンピックが開幕し、数々のアスリートたちの活躍が注目されている。しかし多くの皆さんにとって、パラスポーツがここまでエキサイティングで面白いスポーツであることを知ったのは、ごく最近ではないだろうか? 本記事では、今日のようにパラスポーツが注目されるようになるまで、パラスポーツの魅力を伝え続けてきた人物を紹介したい。パラスポーツ専門のウェブサイト『MA SPORTS(http://masports.jp)』代表・荒木美晴さん、パラリンピックではシドニー大会から取材を続けているライターだ。HERO X編集部では、荒木さんをお招きし、ジャーナリストとしての視点から、パラスポーツの魅力と東京2020の課題についてお伺いした。
1998年の運命的な出会い。
それから20年、パラスポーツと選手の魅力を伝え続ける

時は1998年、長野パラリンピック。たまたま観戦することとなったアイススレッジホッケー(現:パラアイスホッケー)との出会いが、荒木さんの人生を変えた。氷上の格闘技とも呼ばれるスリリングなこの競技の、強い衝撃音とスピード感、想像を超えた競技の迫力に圧倒され、これまでにないゾクゾク感を覚えたという。パラスポーツに魅せられた荒木さんは、フリーのライターに転身、それ以来、書き手としてパラスポーツの魅力を伝え続けている。
そんな人生の転機もあり、今回のピョンチャン大会で2大会ぶりの出場となったパラアイスホッケー日本代表は、荒木さんにとって思い入れのあるチームだ。「日本では、キャプテンを務める北海道苫小牧市出身の須藤悟選手に期待したい」と荒木さんは目を輝かせる。
初めてのパラリンピック取材は、2000年のシドニー大会。それまでにも国内の大会等で取材は重ねてきたが、パラリンピックなどの大舞台に携わるのはこの大会が初。世界のレベルを目の当たりにし、心を躍らせた長野大会を思い出したという。このときの心境について、「アクレディテーションカード(資格認定証)を首からさげたときは誇らしい気持ちでいっぱいでした。現地ではメディアセンターで資料をもらい、会場までバスに乗り、ミックスゾーンへの動線があってと、行ってみないとわからないことがたくさんあり、周りの人に教えてもらいながら慎重に行動しました。事前の合宿取材で顔や名前を覚えてもらっていたので、ミックスゾーンで待っていたら喜んでくれた選手もいて。無我夢中でしたね。」と、荒木さんは18年前を振り返る。
ルールを知ることで、
想像を超えたパラスポーツの奥深さを知る
今や日本のパラアスリートの間では名の知られたベテランライターの荒木さんに、インタビューの際に心がけていることを聞いた。「特に意識していることはないのですが、その選手ならではの感情の出し方であったり、言葉以上のところを察知するのが記者だと思うので、そこは大事にしています。それには長く競技や選手を見ていないと難しいので、できるかぎり継続して取材活動をするよう努力しています。」荒木さんならではの細やかな心づかいが、選手との距離を縮める近道になったのだろう。

「夏季スポーツは、2004年アテネパラリンピックで、国枝慎吾選手と斎田悟司選手がダブルスで金メダルとったところから始まり、車いすテニスの取材を続けています。パラスポーツはどの競技も観るとすごく興味深く面白いのですが、競技のことを知らない人がまだまだ多いので、記事を通してもっと知ってもえるようにと、さまざまな切り口で情報発信するよう心掛けています」
車いすテニスや車いすバスケットボールは、学校の授業などでテニスやバスケットボールの実技経験が一般的であることからイメージしやすいが、パラ競技名を聞いても、全く想像のつかないものもある。
「例えばゴールボールは視覚に障がいを持つ人のためのオリジナル競技。いわば新しいスポーツなんです。選手たちはアイシェードをして、鈴入りのボールを転がし合い、相手ゴールを奪う競技なのですが、その奥深さったらありません。普段目が見えている私たちは、まず目隠しをしたら、普通に立っていることすらままならないのに、鈴の音だけを頼りにゴールを守る選手たち。『本当は見えてるんじゃ……?』と思わずにいられないほどのすさまじい集中力と投球技術は必見です。実は国内の大会は晴眼者もメンバーとして出場できるので、私もいつか挑戦してみたいと思っています」
以前、インターネットテレビに出演し、パラスポーツの競技紹介や解説をしたことがあるという荒木さん。こんなコメンテーターがいたら、パラスポーツ観戦がグッと楽しくなるに違いない。
ジャーナリストとして本当に伝えたいこと

東京2020に向けてバリアフリー化が急速に進められ、パラリンピックへの注目も集まっている現在に比べて、荒木さんが取材を始めた頃は、パラリンピックの存在すら知らない人も少なくなかったという。当時、現場で取材していたのは、フリーライターと一部の大手メディアくらいだったという。新聞に載るのは結果のみで、文化面や生活面に掲載されることも多かった時代。そこを変えたい、と荒木さんは思っていたという。「いつ事故に遭い、周りの人にどんな励ましの言葉をもらって成長できたか」といった選手のバックボーンは興味も引くし、大事な要素。でも、選手がこうして活躍する裏に、どんな工夫や努力があったかを知らないのは、もったいない。
「私は、当初からパラスポーツをきちんとスポーツの側面から伝えたいというのは一貫していました。『腕がない、足がないのに速く泳げて、走ることができてすごい』と観る人は言う。では『なぜ速いのか?』を伝えるのが、私たちの仕事。『ない部分をどう補い、アスリートとしてどう競技と向き合ってきたか』という部分も大事にしたい。近年は、様態は様々ですが、プロ選手として活動したり、競技に専念する環境を整える選手も増えてきました。スポーツである以上、結果が求められるわけですが、レースや試合の結果が伴わなければ、時に厳しく記事を書くこともあるでしょう。賛否両論あると思いますが、これからのパラスポーツに対するメディアの報道姿勢も変化の時を迎えていると感じます」
ロンドン、リオ、そして東京2020。
それぞれのパラリンピック

史上最も成功したと言われている2012年ロンドンパラリンピックで、現場取材の中にいた荒木さんが一番ゾクゾクしたのは、水泳競技会場での一幕。
「観客の声がより響く構造をした会場が、満員な上に大歓声で、私たちがビリビリ感じるくらいの熱狂ぶりでした。長野パラリンピックのときと同じ高揚感に包まれましたね。尊敬すべきなのは、イギリスの選手以外のことも応援していたこと。表彰式ではイギリスの選手が表彰台に立っていなくても、最後まで立って国歌を聞き、拍手を送り、選手が捌けるまでみんな会場に残っていた。どの国の選手にも、会場全体で敬意を表していました」会場には、パラリンピックを初めて観た人が多かったが、誰もが「本当に面白かった!」と満足気な様子だったという。

逆に、2016リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックは、様々な不安要素を抱えたままの開幕となり、たしかに会場も空席が目立つ競技が多かったが、“サンバの国”ならではのノリノリな国民性によって、会場は笑顔と声援に包まれていたという。
そして、東京2020。10大会連続でパラリンピックの前線にいる荒木さんが楽しみにする一方で、特に心配しているのは、“ボランティア” の分野。「外国からきた人たちに『来てよかった』と思ってもらえる入り口となるのがボランティアたちの対応」日本はまだ世界的な規模の大会は経験が少なく、知らない外国人とのコミュニケーションにも不慣れだ。そんな中、本当に心のこもった『おもてなし』ができるかが課題である。
「東京まで、あと2年半。今回の平昌パラリンピックをきっかけに、パラスポーツに興味を持ってもらえたら。障がいの程度に応じたルールや道具の工夫を知れば、もっと楽しいと感じるはず。パラリンピック競技以外にもたくさんのパラスポーツがあるし、観戦が無料の大会も多いので、身近なところからぜひ会場に足を運んで、生でパラスポーツの魅力に触れてほしいです」
荒木美晴
1998年長野パラリンピックでパラアイスホッケーを観戦 。その迫力とパワーに圧倒され、スポーツとしてのパラスポーツのトリコに。この世界の魅力を伝えるべく、OLからライターへ転身し、パラスポーツの現場に通う日々を送る。国内外におけるパラスポーツの認知度向上と発展を願い、障がい者スポーツ専門サイト「MA SPORTS」を設立。『Sportsnavi』『web Sportiva』などスポーツ系メディアにも寄稿している。パラリンピックは2000年のシドニー、ソルトレークシティ、アテネ、トリノ、北京、バンクーバー、ロンドン、ソチ、リオ、平昌大会を取材。
MA SPORTS
http://masports.jp