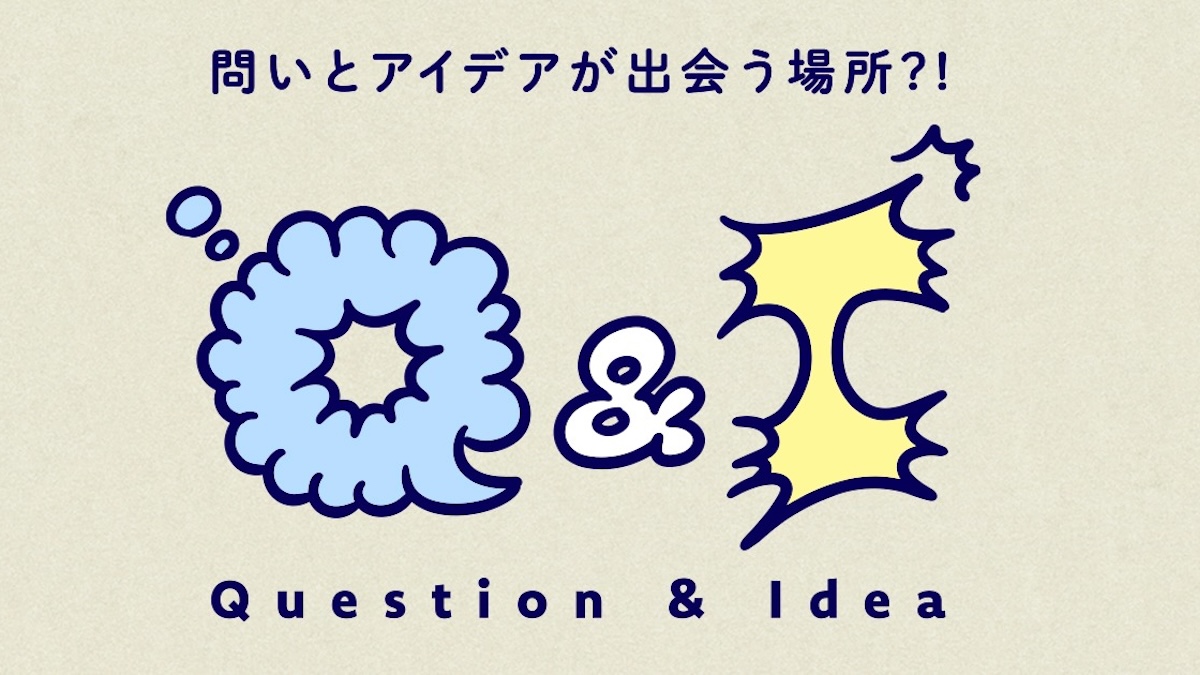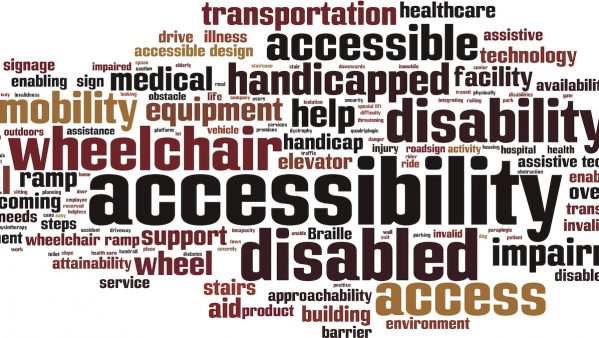目次
昨年10月、今解くべき社会の「問い」と、それに対する「アイデア」が出会う新しいプラットフォーム「Q&I」がスタートした。社会課題に対し、たったひとつの正解を出そうとする「Q&A」ではなく、まずは自由にアイデアを出してみる「Question & Idea」の姿勢を世に打ち出すプラゥットフォーム、それが「Q&I」だ。
肩肘はらない気軽るさが人々を巻き込む
「社会課題」この硬い文字面に、「いやいや自分にはそんなことを解決する才能はないから」と、多くの人が思ってしまう。ところが一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会が作り出したプラットフォームQ&Iは、社会課題の難題をポップに見せることでいろいろな立場の人を巻き込んでいる。
「もっと社会が補助犬に「ウェルカム!」になるアイデアとは?」
「重度障がいがある方が、親から離れてもHappyに暮らせる仕組みとは?」
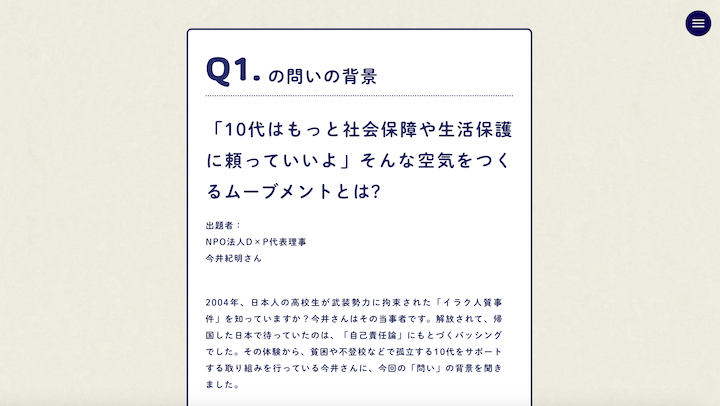
――「Q&I」に掲載されている問いは、さまざまな社会課題に取り組む団体や企業などから提供された、私たちの身近にある社会課題だ。
「Q&I」は、この問い(Q)に対して誰でもアイデアを投稿することができる。掲載されるアイデアの評価基準は、良い・悪いのジャッジをするための「Good」ではなく、問いの提供者が特に「グッと(Goot)きた」かどうかを基準に定めている。
プラットフォームの仕掛け人は、一般社団法人世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智洋氏と株式会社Amplify Asia代表取締役白石愛美氏。
学校教育では、問題に対して「正解」を見つけようとすることが多い。しかし社会課題にはそもそも正解がないことも多く、澤田氏は、社会課題に対してただ一つの正解を出そうとするQ&Aという構造に問題を感じたという。そこで、社会課題を身近に感じ、気軽にアイデアを出し合う環境として生まれたのが「Q&I」だ。
問いに対するアイデアを形にした“ゆるスポーツ”
「Q&I」の発案者である澤田氏も、問いに対するアイデアを形にした1人だ。ゆるスポーツとは、年齢・性別・運動神経に関わらず、高齢でも障害の持つ人でも誰もが楽しめる新しいスポーツジャンルで、世界ゆるスポーツ協会ではゆるスポーツの創造、普及活動を行っている。
自身は運動が苦手という澤田氏。日本人の40%以上の人が日常的にスポーツをしていないという社会課題に気付いた。健常者はもちろん、障がい者も運動不足の人が多い。そこで、「運動が苦手な人も、障がい者、高齢者でもみんなでできるスポーツを作れないか?」というアイデアから生まれたのがゆるスポーツだ。
「ゆるスポーツ」について澤田氏に取材した記事はこちら
正解のない社会課題を解くためには、ただ一つの「答え」を見つけようとするのではなく、まずは自由にアイデアを出してみる柔軟性が必要だと澤田氏。今後も「Q&I」に注目だ。
SusHi Tech Tokyo 2024
ゆるスポーツ体験やイノベーターの
「Q&I」を見られる展示も
2024年4月27日〜5月26日に行われる「SusHi Tech Tokyo 2024」のショーケースプログラムでは、今回紹介した「Q&I」や「ゆるスポーツ」を手がける澤田氏が「ゆるスポーツ@シンボルプロムナード公園」「子ども発明教室@日本科学未来館」「発明データベース@日本科学未来館」をプロデュースする。
SusHi Tech Tokyo 2024とは
“Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo”
東京発の持続可能な新しい価値の創造を見出し、推進するプロジェクトで「グローバルスタートアップ プログラム」「シティ・リーダーズ プログラム」「ショーケース プログラム」の3つのプログラムで構成されている。有明アリーナ、日本科学未来館、シンボルプロムナード公園、海の森エリアを会場とする「ショーケース プログラム」では、最先端技術を活用した体験型展示が用意され、さまざまな課題が解決された2050年の東京の姿、そして可能性に触れられる。
------------------------------------------
PODCASTプログラム #HEROQUEST はニッポン放送PODCAST STATIONで無料配信中
未来の社会をデザインするHEROを迎える【聴く冒険プログラム】。
今回からは「HEROQUEST -Sushi Tech Tokyo 2024 edition」。
4月27日・土曜日から5月26日・日曜日まで東京ベイエリアを中心に行われる
Sushi Tech Tokyo 2024ショーケースプログラム に注目。
Sushi Tech Tokyo で描かれる 2050年の東京の未来を冒険していきます。
第1弾となる今回は、
世界ゆるスポーツ協会代表理事の他、ゆるミュージック、ゆるアートなど
さまざまなプロジェクトを展開する、澤田智洋さが描く
2050年の東京の未来を冒険します!
Suhi Tech Tokyo 2024は、
4月27日・土曜日から5月26日・日曜日まで
東京ベイエリアを中心に開催されます。
詳しい情報はオフィシャルWEBサイトをチェックしてください。
https://zip-fm.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/46407779-eadd-49f1-9d5c-bbde346ddb7c/
<ゲストプロフィール>
澤田智洋
1981年生まれ。コピーライター。アミューズメントメディア総合学院、映画「ダークナイト・ライジング」、高知県などのコピーを手掛ける。2015年に「世界ゆるスポーツ協会」を設立。ほかにも「世界ゆるミュージック」「世界ゆるアート」などさまざまなプロジェクトを手がける。著書に『マイノリティデザイン』(ライツ社)、『ホメ出しの技術』(宣伝会議)、『ガチガチの世界をゆるめる』(百万年書房)がある。
-------------------------------------------