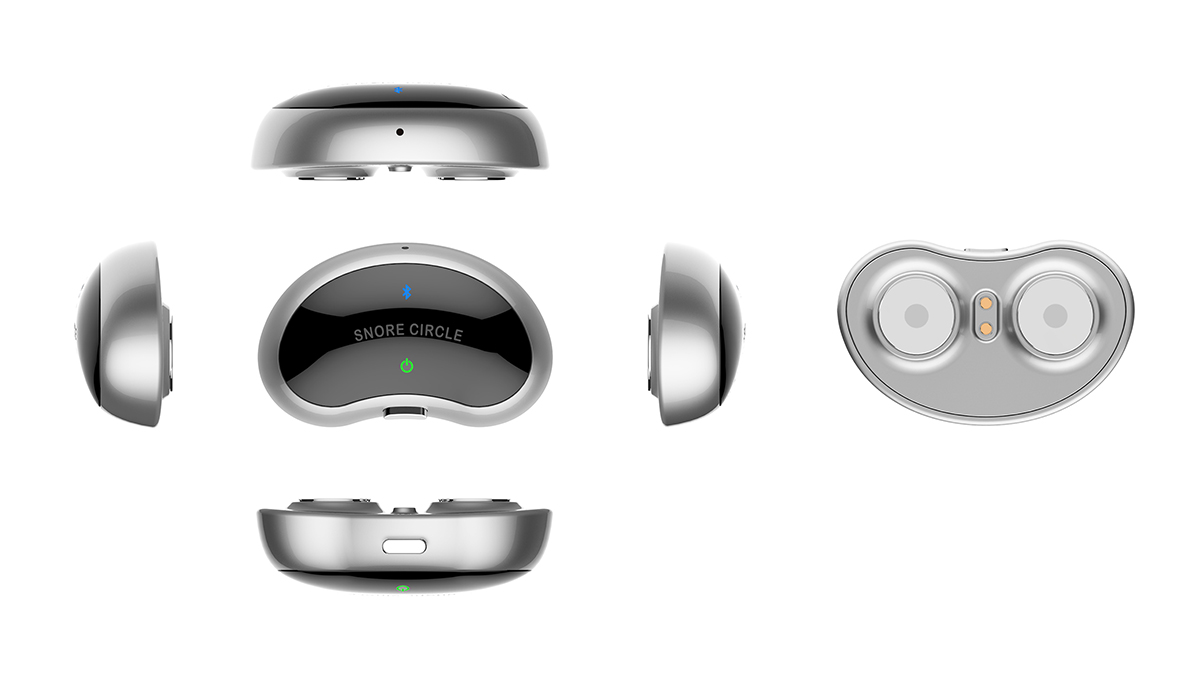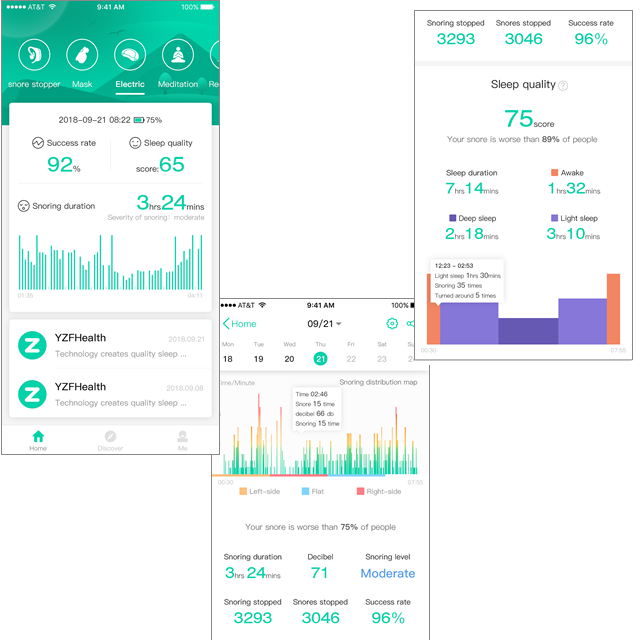車いすユーザーが車の運転をする場合、自分が運転席に座ってから、車いすを助手席や後部座席に収納する必要がある。仮にラゲッジ・スペースに収納する場合は、介護者がサポートする以外に方法はない。そんな現状を変えようと、イスラエルのエンジニアリング会社TMNで代表を務めるモシェ・オフェック氏が、車いす収納支援ロボット「Robot R11(ロボットR11)」を開発した。この画期的なプロダクトは、一般的な乗用車であれば、ほぼどんな車種でも搭載できる。取り付け作業だけで、誰もが求めていたパフォーマンスが可能になるのだ。欧州最大の福祉機器展「REHACARE(リハケア)」でも話題になった、新たなプロダクトに迫る。
ドライブ時の車いすユーザーの
ストレスを大幅に軽減
多くの車いすユーザーが抱えている課題、そのひとつが、車を運転する際、車いすを収納するために多くのエネルギーを消費するということだ。乗車の際には、運転席側のドアを開けて車いすから運転席に乗り換えたら、自力で車いすを畳み、助手席か後部座席に収納するのが一般的。座った状態でその作業を行うこと自体、かなりの労力を必要とするだけでなく、車いすを収納した場合、車のシートは、確実に1つが(収納スペースとして)埋まってしまう。
だからといって運転席に座ったままでは、ラゲッジ・スペースに車いすを収納することは物理的に不可能であり、介護者の助けも必要だった。
イスラエルのエンジニア会社、TMNで代表を務めるモシェ・オフェック氏が開発したのは、ラゲッジ・スペースの内部からアームが伸びて、運転席の横に置いた車いすをピックアップし、収納するロボット「Robot R11」だ。
長いアームは、極めてスムーズに車いすをキャッチし、無駄な軌道を描かずにラゲッジ・スペースへ納める。時間にして約40秒。まったくストレスを感じることはない。車いすを収納し、車で目的地に到着したら、今度はアームがラゲッジ・スペースから車いすを取り出し、運転席の横にそっと置いてくれる。
この画期的なアームの動きを完成させるために、オフェック氏は、「1万回以上のテストを行った」という。しかもRobot R11は、400を超えるオペレーションを記憶した高性能ロボットであるにも関わらず、非常にコンパクトで、基本的にどんなタイプの乗用車にも装着が可能だ。
最初の試作品が完成してから、「15年もかかってしまった」とオフェック氏は笑いながら語るが、多くの実験と検証を繰り返して精度を高めたこのプロダクトは、2018年、欧州で開催された著名な福祉機器展「REHACARE」でも、高評価を獲得した。
小売価格は、約1万4000ユーロ、日本円にして175万円前後。今後はアジア市場への進出も本格化する予定があるだけに、日本での発売にも期待が膨らむ。
[TOP動画引用元:https://youtu.be/yWJ3VvsLOvo]