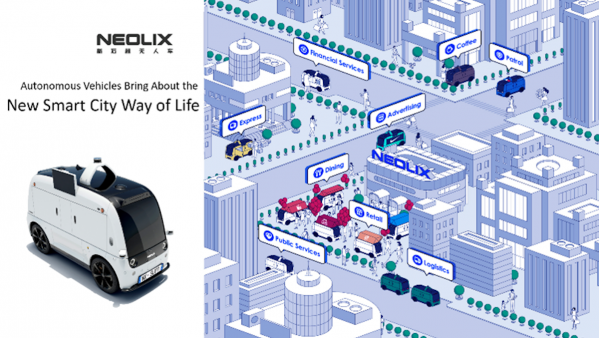昨年はイチローの引退という大きなニュースもあった野球界。今年はいったいどんな話題が持ち上がるだろうか。野球にサッカー、バスケットボールにラグビーなど、近年は日本でも様々なプロスポーツの盛り上がりが顕著だ。いずれのスポーツをするにせよ、現役で長く活躍するためには自身の健康管理はもちろん、どのようなトレーニングをするかによっても体のもちは違ってくる。そんな中、大リーグでも導入が進んでいるあるガジェットの発売が日本でも始まっている。
間もなくはじまる春の選抜高校生野球大会。球児たちの汗と涙のドラマに、つい時間を忘れて見入ってしまう方も少なくないはずだ。そんな高校野球の世界でここ数年議論が交わされてきたのが、投手の球数制限問題。過度な投球が将来的に投手の運動障害を招く可能性があるとして、有識者らにより検討が重ねられてきた。株式会社オンサイドワールドより発売された「motus BASEBALL」は、こうした背景のなか、注目を集めつつある投球解析データデバイスだ。投手のけが予防と投球パフォーマンス向上に向けて、さまざまな機能を有しており、現在はメジャーリーグの試合でも正式に着用が認められているという。
自分の限界と日々戦うアスリートにとって、自身のパフォーマンスを客観的なデータという裏付けを持って管理することはとても重要だ。経験と感覚に基づいたコンディショニング管理は、パフォーマンスの向上どころか、選手人生を縮めてしまうような故障のリスクにもつながりかねない。投手の球数制限が議論されている高校野球においても、選手のコンディショニング管理は大きなポイントとなっている。新たにルールが整備されたものの、過度な投球による投手の肩や肘の故障は、投球数や登板間隔だけが要因ではなく、投球フォームや体格、球種などの個人差にも起因すると言われている。100球未満であっても故障する選手もいれば、逆に100球以上投げても故障なく投球できる選手もいると言えるのが現状だ。
単に投球制限数未満だから故障しないという考え方ではなく、投手一人ひとりが自分自身の状態・パフォーマンスを適切に管理すること。投手が将来に亘って長くマウンドで活躍していくためには、こうした考え方が何よりも大切だ。

今回リリースされた「motus BASEBALL」は、投手がセンサーを搭載したスリーブを肘に着用し、投球することで、投球動作の数値やトレーニング量、肘のストレス値データを取得・蓄積し、客観的なデータによる判断指標を提供するウェアラブルデバイス。
専用アプリをダウンロードし、センサーと同期することで、投球解析に役立つ様々な機能を使うことができる。
注目したいのは、肘のストレス状態を数値化する機能。投球データの機械学習により、肘のストレス状態を数値化することができる。数値化という形で見える化したことで、一定以下にストレス値を抑えることでき、肘の故障リスクを大幅に軽減。故障・ケガの予防に役立てることができるという。

肘に過度な負担がかからない美しい投球フォームは、パフォーマンスの向上にもつながる。投球毎に蓄積されたデータは、フォーム改善のための客観的なデータとして使うことが可能だ。これらのデータはトレーニング設計の際にも力を発揮する。米国メジャーリーグをはじめとした一流の投手たちの投球データを元にして、ユーザーに合わせた投球トレーニングメニューを提案。トレーニング量の管理と、トレーニングの質を高めるサポートをしてくれる。さらに、デバイスに試合予定日をあらかじめ入力しておくことで、ベストコンディションを試合当日に保てるための練習量を管理することも可能だ。
適切なコンディショニング管理を欠いたばかりに、有望な選手が故障により野球をあきらめたり、それが原因でベストパフォーマンスを発揮できないことは、野球業界にとって大きな損失。選手をデータで支える名サポーター「motus BASEBALL」が、選手と野球業界の将来を明るいものにしてくれそうだ。