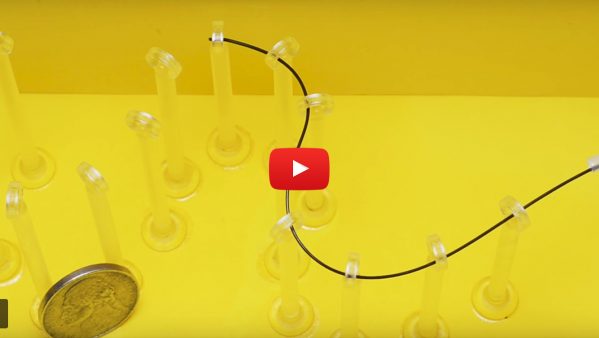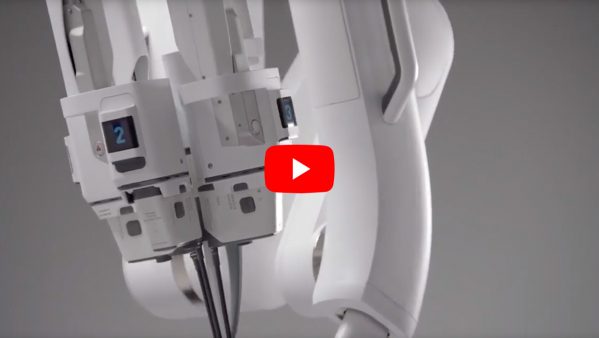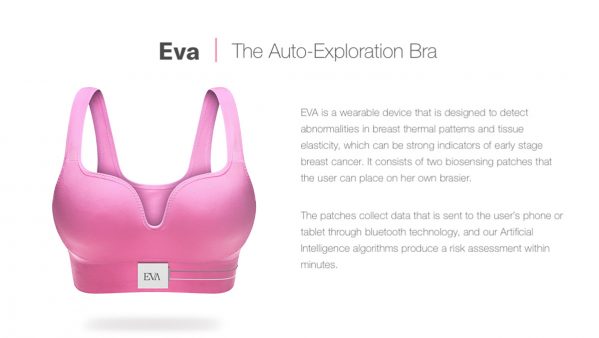「世界を変えるデザイン展」など、あたりまえにある日常について「考える」きっかけを作りだしてくれている株式会社 GRANMA 代表本村拓人氏。彼は現在、東京都が進めるパラスポーツの支援団体「TEAM BEYOND」で、プロジェクトメンバーの一人として動いている。世界中から称賛が集まったロンドンパラリンピック。果たして、東京はそこを超えることができるのか!? 共に「デザイン」というフィールドに立つHERO X 編集長 杉原行里と本村拓人氏がお互いの思いを語り合った。
「ナニモノか」という枠を超える
杉原:本村さんは「なに屋」になるのでしょうか?
本村:遊休不動産の利活用を推進するプロデューサー、地域デザインや地民大学の運営、起業人材に対するインキュベーターや社会問題を提起する展覧会やイベントのキュレーター。そして今回のようなパラスポーツの普及を手掛けるディクレション業務などを兼業していると、正直まだ自分の肩書を発明しきれていないです。骨董通りの文化作りや国連大学で毎週催されるファーマーズマーケット。表参道のコミューンや滝ヶ原など地方の活況などを同時多発的に仕掛ける元IDEE代表の黒崎輝男さんから仕事に対する姿勢やスタイルはとても影響を受けています。黒崎さんは「僕たちの仕事は様々な”状況”をつくくりだすこと」とよく言っていますが、私もその状況や文化を作り出すことに関心を寄せてこれまで国境や宗教的垣根を超えて動いていて、例えば、「世界を変えるデザイン展」で見せたようなプロダクトによって世の中を見直すこともしているし、いろいろな肩書があるのが現状です。最近では地域や組織の創造性がグッと上がる状況づくりをする機会が多く、可能な限り恒常的に想像力をかき立て続けるための仕掛けや区画(ブロック)を作ることに力を入れています。仕掛けやブロックとなるのは醸造所を改修してできたオープンキッチンやワーキングスペース、定期開催するマーケットやギャラリーであったり。それらは人が作るものなので、人自体が仕掛けや区画になることももちろんある。こうした区画や人がいくつも集まることで、特徴ある村や地域ができます。ブロックを作るのにはいろいろな要素がからんでくるので、ぼくは「○屋です」と決めることはできないですよね。

いたって真面目な話をする二人
杉原:その感覚はすごくよく分かります。僕もよく言われるんですよね。「ナニ屋ですか」と。でも、決めつけないでほしいという気持ちがあります。人間を仮に3D解析にかけたとしても、そこに出てくるデータと、解析では見えない部分が必ずあるわけで、多角的に捉えないといけないと思っています。“デザインできるよ”“車もできるよ”“医療もやってるよ”「じゃあこれ全部入れてなんていう名前ですか」と聞かれても、“知らないよ”というのが僕の答え。決めつけることで出る強さは確かにあるとは思うのですが、自分は学者タイプではないので、いろいろなことに興味を持ってやっていきたくなる。学者タイプの人は、一つのことにガッと没頭していける強さがある。しかし、僕らは学者タイプではない。初対面で失礼ですが、本村さんも学者タイプではないですよね(笑)
僕らみたいなタイプは次々と料理していくのが仕事。何か名前を付けられると居心地が悪くなる気がしませんか。
ムーブメントは創れるのか
本村:本当そうです。杉原さんのされていることは、目に見えるものとしてありますよね。松葉杖とか。僕は目には見えない人々の意志や希望などを地域づくりという説明しにくい方法で可視化しているのですが、根底はとても似ていると思っています。杉原さんの手がけられたカーボン松葉杖は、個人の体に合わせて作られるもので、松葉杖だけれどその人個人の顔が見えるプロダクトだと思います。地域づくりも同じで、顔の見える場所とか、エリアというのが、本当は一番個性が出ていると思っていますし、幸せなことになると僕は思いたいです。僕の場合は長年世界を歩いてきましたが、これが「一番」だというところにやっとたどり着いたところです。
杉原:じぁあ、肩書は「本村拓人」ですね(笑)

杉原:そんな本村さんが今回、パラスポーツを盛り上げる「TEAM BEYOND」に関わられていると伺いました。
本村:僕に課せられている役目は3つあります。一つは、世界のネットワークを引っ張ってきながら、短期的・局地的になりがちな視点を広げるという役割です。もう一つは、パラスポーツの永続的普及に対して貢献するという点です。「TEAM BEYOND」は都市開発や産業構造の中に障害者の個性を忍び込ませていくことがパラスポーツの永続的普及につながることに気が付いていて、そこへの提案をしていくのが自分の役割です。もう一つが、ムーブメントを草の根から発生させること。東京都が音頭をとって進めている「TEAM BEYOND」が本格的なシビルアクションとして日本に広がり定着させることを僕としては狙っています。
本村:これまでの取り組みで大企業の方々の参加は多く集まってきました。しかし、こうした大企業がする取り組みは一過性で終わる可能性が高い。人々にパラスポーツへの認識を根づかせるための仕掛けにはもう一工夫必要だと思っています。もっと個にアプローチしていくことです。そこで、まずは中小企業の方々を巻き込む策を練り始めているところです。冒頭にお話ししたように、個や個性が表面化することで魅力的な地域が生れるというのが僕の持論ですから、やはり、個へのアプローチを大事にしていきたいのです。
杉原:具体的にいうと、どんなことだと思いますか
本村:バリアフリーな街を考えた時、都市全体で一気にやるというのは難しいことで、例えば、ある有名ショップなどでバリアフリーの旗艦店のようなものをつくり、それが発端となり全国にそのスタイルの店舗が拡散していくようなソーシャル的なつながりを作っていくなど、小さなところから始めるのが先決だと思っています。中小企業は、大企業よりも動きが速いので、広がるスピードも加速するのではないかと。
杉原:早いですよね。自分事として動くから。
本村:そこです。2020年に向けたパラスポーツ観戦の動員数を増やすための取り組みとして、小さなところへのアプローチを仕掛けていこうと考えています。大きい事業は事業として否定はせずに、そこはそこで動かしながら、小さなブロックをいくつも投入していくのです。
杉原:本村さんの目から見て、まず第一のゴールはどこだと思われていますか
本村:まずは、パラリンピックの観客席を満席にすることです。チケットも完売で、できれば、若い子たちがそこを埋め尽くしているような状態をつくることです。これはあくまでも一過性ですが、第一のゴールとしては十分すぎる結果だと思います。
杉原:ロンドンであれだけ満席になったというのが一つのインパクトとしてあって、そこからインスパイアされているということでしょうか。
本村:そういうことです。今年はそのために、皆さんが自分事としてパラリンピック、パラスポーツを受け止められる素地を作っていきたいです。