冬季パラリンピックの競技において、世界中からひと際熱い眼差しが注がれるチェアスキー。高校3年生の時、トリノパラリンピックに初出場して以来、三大会連続の出場を果たしたチェアスキーヤー、KYB所属の鈴木猛史選手は、バンクーバーではジャイアント・スラローム(大回転)で銅メダル、ソチではダウンヒル(滑降)で銅メダル、スラローム(回転)で金メダルを獲得し、世界の頂点に立った。“回転のスペシャリスト”の異名を持つ覇者は今、2度目の頂点を目指すべく、目前に迫るピョンチャンパラリンピックに向けて着々と準備を進めている。チリ合宿から帰国したばかりの鈴木選手に話を聞いた。
KYBという心強い味方があってこそ、僕がいる
同じチェアスキーでも、海外選手の場合、合宿先やレース本番で、ショックアブソーバというサスペンションの部品が折れるなど、何らかのアクシデントが起きた場合、ほとんどはその時点で終了となる。理由は至ってシンプル、技術面でサポートできる人がいないからだ。しかし、鈴木選手をはじめ、日本の強化指定選手には、非常事態にも難なく対応できる心強い味方がいる。ショックアブゾーバの部品開発を行うエンジニアを筆頭に、卓越した腕を持つKYBの技術者たちだ。中でも、海外遠征や合宿に帯同し、選手たちからその場で聞いた要望に沿って、細かな調整を行い、直ちに仕様を変えてしまうというテクニシャンの存在について、鈴木選手はこう語る。
「その方がいてくださるだけで、安心して練習に打ち込めますし、レースにも集中できます。このような体制に恵まれているのは、現状日本だけなので、海外の選手からは、羨ましい!ってよく言われますね(笑)。本当に助けられています」
ダウンヒル(滑降)で銅メダル、スラローム(回転)で金メダルを獲得したソチから約4年。ピョンチャンに向けて、鈴木選手のマシンはどのように進化したのだろうか。
「シートやショックアブソーバについては、かなり細かく調整を行っていますが、とりわけ大きな改造はしていません。僕は自分の感覚を頼りに、“もっと、ここをこうしたい”というアイデアや意見を各技術者の方に伝えて、それらが反映されたマシンにまた乗って、体感的に確かめていくタイプ。ですので、細かいと言っても、先輩方(森井大輝選手、狩野亮選手)の緻密なこだわりに比べれば、足元にも及ばないと思います。滑りにしても、かなり感覚的な方です。“なんで、そんな滑りができるんだ?”と聞かれても、体で覚えているから、言葉でどう表せばいいのか、僕には分からない。うまく説明できるに越したことはないのですが、トークは得意な先輩方にお任せしたいなと(笑)」
失敗から学んだ自己管理の大切さ

「オンとオフはきっちり分けて、休む時はきちんと休むようにしています。休む勇気も大事ですね。それは、初めて出場したトリノパラリンピックの時に身をもって学びました。当時の僕はまだ高校3年生で、寝れば回復するだろうと思っていたのですが、やはり間違いでした。パラ大会前もレースがありましたし、休みなく練習していたことも関係していたと思います。大会の前半戦、40度近い高熱が出て、体調を崩してしまい、1レース棄権しました。失敗を経験して、自己管理の大切さに改めて気づかされました」
食事も、その時々の体調を第一に考えたメニュー構成だ。疲れている時は、無理して食べるのではなく、食べられるものを口にする。鈴木選手の胃袋を温かく満たすのは、昨年結婚したばかりの妻・響子さんの手料理だ。
「食事の面だけでなく、精神的な面でも助けられています。弱音を吐きたくなる時、優しく耳を傾けてくれる一方、諭される時もありますが(笑)、しっかり支えてもらっていることに感謝しています。もしかしたら今、自分はひとりぼっちだと思っている人がいるかもしれません。でも、人間は皆、力を合わせて、支え合いながら生きている。応援してくださる方をはじめ、僕自身、周りの人たちに助けられてきたところが大きいから、余計にそう思う気持ちが強いかもしれませんが、今後、どこかで僕の競技を観てもらえる機会があったとしたら、“ひとりじゃないよ”と全身で伝えたいです」
全員ライバル。
「でも、あの選手にだけは絶対負けたくない」
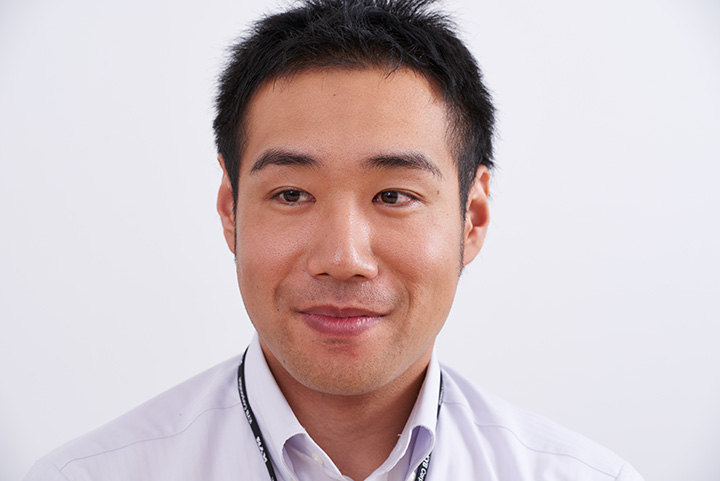
2018年ピョンチャンパラリンピックで、メダル獲得が期待されるのは、日本が誇る“チェアスキーヤー御三家”こと、森井大輝選手、狩野亮選手、そして鈴木選手。しかし、3人の背中を追って、国内外の選手たちも切磋琢磨し、近年は世界的なレベルも格段に上がっているという。
「金メダルを獲ることがずっと夢でした。でも、ソチの表彰台に立った時、この金メダルは自分が獲ったというよりも、皆さんのおかげで獲れたもの。重さはその証だと実感しました。その方たちのためにピョンチャンでも獲りに行きたいです。できれば、自慢できるようなメダルを。厳しい状況の中で競って獲得できたメダルの方が、簡単に獲れてしまうものより、ずっと面白いし、嬉しさも倍増しますよね。それは、応援してくださる方も僕も同じだと思っています」
「ライバルは全選手」と話すが、強いて特定するとしたら、誰?そう尋ねると、オランダの若干17歳のユルン・カンプシャー選手の名前が挙がった。
「僕と同じ、両足切断の選手で、昨年の世界選手権では、金メダルを3つ獲得しています。これがまた、カッコいい滑り方をするんです。同じ障がいを持つ選手ということもあって、僕が得意としているスラローム(回転)では負けたくないですね、絶対。あらゆるプレッシャーをいかに勝つための力に変えていくか。これは、自身にとっての課題のひとつです」
技術系種目のスラローム(回転)で、抜きん出た実力を世界に知らしめた人は、意外にも、自分の感覚を何より大切にしている人だった。曇り一つない、澄みきった素顔を垣間見て、期待はさらに募る。今後も、さらなる鈴木選手の活動を追っていく。
鈴木猛史(Takeshi Suzuki)
1988年生まれ。福島県猪苗代町出身のチェアスキーヤー。小学2年の時に交通事故で両脚の大腿部を切断。小学3年からチェアスキーを始め、徐々に頭角を現す。中学3年時にアルペンスキーの世界選手権に初出場し、高校3年時にトリノパラリンピックに出場。冬季パラリンピックのアルペンスキー(座位)に3大会連続出場を果たし、バンクーバーパラリンピック大回転で銅メダル、ソチパラリンピック回転で金メダル、滑降で銅メダルを獲得。2014年、春の叙勲で紫綬褒章受章、福島県民栄誉賞受賞。2015年8月よりKYB株式会社所属。














































