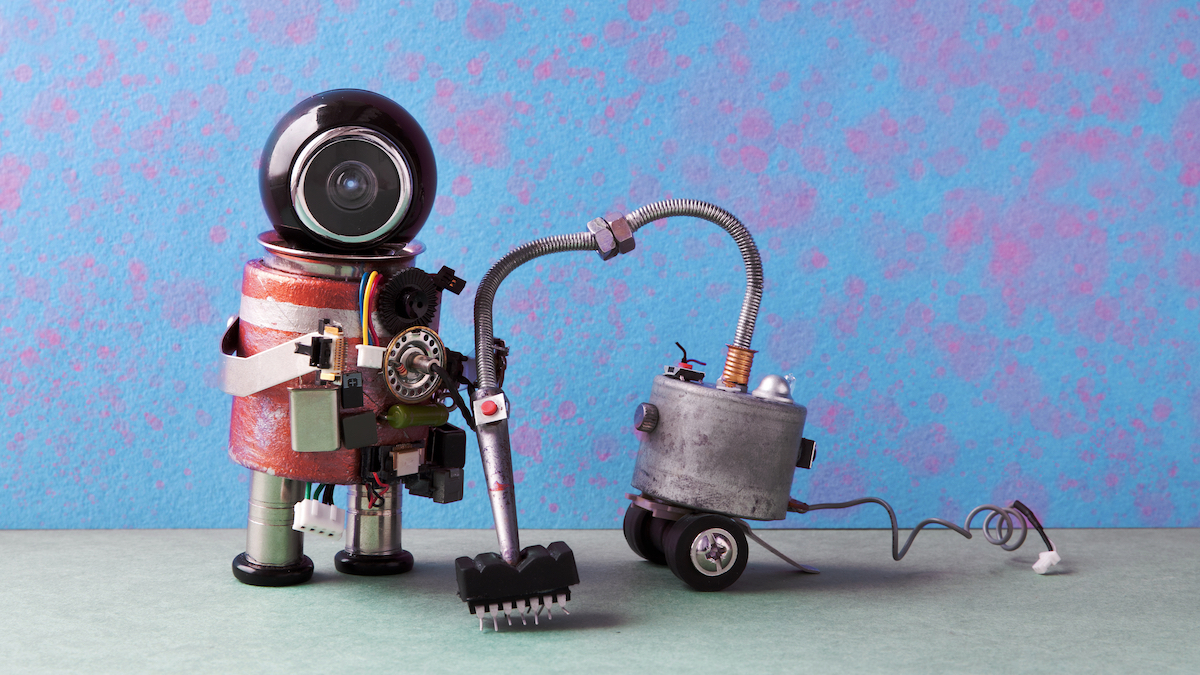チェアスキーほど、命の危険と背中合わせのパラ競技は他にない。時速100km以上の豪速スピードで、雪山の傾斜面を一目散に滑降するアグレッシブさとスリルが、アスリートを奮い立たせ、観客を熱狂させる。2014ソチパラリンピックでは、森井大輝選手がスーパーG(スーパー大回転)で銀メダル、鈴木猛史選手がスラローム(回転)で金メダル、狩野亮選手がダウンヒル(滑降)とスーパーG(スーパー大回転)の2種目で金メダルを獲得。日本のヒーローたちは、圧倒的な強さを世界に知らしめた。そんな彼らの疾走を裏舞台で支えているのが、日本トップクラスのシェアを誇る総合油圧機器メーカー、KYB株式会社(以下、KYB)のショックアブゾーバ開発者、石原亘さんだ。別名・油圧緩衝器と呼ばれるこの部品、一体どのように作られているのか?目前に迫る2018ピョンチャンパラリンピックに向けての開発は?石原さんにじっくり話を伺った。
極寒の世界で活かされる、卓越した技術
チェアスキーの大会や強化合宿が行われるのは、世界に点在する雪山。氷点下20~30度の世界で、優れたパフォーマンス力を発揮するためには、安定した性能を保持できるショックアブゾーバでなければならない。
「シリンダーの中に入れるのは、二輪車用とは異なる専用の油です。その油を密封するためのシールという部品など、寒冷仕様の部品については、長年、弊社が培ってきたスノーモービルの技術を活かしています。チェアスキーのショックアブゾーバには、さまざまな分野の技術を集結させて作っています。モトクロスやロードレースの技術も、取り込めるものは取り込んでいます」
 選手のお守り的存在
選手のお守り的存在
海外遠征には、専任のテクニシャンが同行
サポート体制も万全だ。海外各地で行われる合宿や大会には、現場でのセッティングを専門に行うテクニシャンが帯同する。KYBにテストライダーとして入社した元モトクロスライダーで、選手から聞いたコメントを元にその場で仕様を変えて仕上げてしまうのだそうだ。
「お守りじゃないですけど、いてもらえるだけで安心です。どこをどう調整すればいいのか、僕たちだけではやはり分からないところが多いので。家族のように仲良くしていただいているので、いらっしゃらない時は、ポカンと穴が空いたみたいな寂しい気持ちになります」と話すのは、鈴木猛史選手(写真、右)。
石原さんは、テクニシャンからフィードバックした情報を元に、改良を加えたり、新しい部品を作るなどして、連携体制を取りながら、設計業務に従事している。そのかたわら、国内で行われる大会や遠征には、定期的に足を運び、選手たちに会いに行く。
「現場では、選手からの評価や要望をじかに聞けますし、実際に滑りを見ることで、以前の動きとの違いを確認することもできます。選手と密なコミュニケーションを取ることで、何を求めているのか、その意図がだんだん見えてきます。具体的に“この部分をこうしたい”と言う選手もいれば、“滑りをこんな風にしたい”と抽象的に伝える選手もいます。それらをきちんと聞き分けた上で、適切な説明や提案を行うように心がけています」
 調整のキモは、感覚を翻訳するという作業
調整のキモは、感覚を翻訳するという作業
「例えば、選手が“堅い”という時、どの部品が機能した時に堅く感じるのかを見極めなくてはなりません。製品にフィードバックするためには、感覚を正しく“変換”することが極めて重要です。翻訳とも言えるこの作業は、中々難しいところもありますが、きちんと汲み取れるよう、精度を上げることに尽力しています」
ソチパラリンピック閉幕後の2014年ごろよりサポート体制を刷新し、テクニシャンやスタッフと共に、選手たちの活躍を一心に支えてきた石原さんにとって、嬉しいことがあった。
「弊社がショックアブゾーバの開発を本格的に再起してから、最も心に残るのは、狩野亮選手からいただいた言葉です。“これまでは自分の納得がいく仕様になるのに3年かかっていたのに、1年ほどで3年分の進歩ができた”と。大変喜んでくださり、感無量でした」
日本代表選手たちと作ってきたショックアブゾーバの仕様は、当然ながら、速さを目指すものだが、その進化と共に、乗りやすさも格段にレベルアップを遂げている。近年は、市販のチェアスキー用製品の提供も行っている。
「レジャーとして、チェアスキーを楽しまれている一般の方はもちろんのこと、次世代の日本代表選手を目指すような子供たちならなおさら、初期の段階から、より乗り心地の良いマシンに乗っていただく方が、成長も早いのではないかと思います」
 来春開幕のピョンチャンパラリンピックに向けて、ショックアブゾーバの改良・調整に全力投球の日々を過ごす石原さんは、技術者という生業についてこう話す。
来春開幕のピョンチャンパラリンピックに向けて、ショックアブゾーバの改良・調整に全力投球の日々を過ごす石原さんは、技術者という生業についてこう話す。
「弊社の製品は、基本的に自動車や工業製品に関わるものなので、それ単体でスポットライトを浴びる機会は少ないです。しかし、パラリンピックという世界の大舞台で戦うチェアスキーヤーのマシンの重要な一部を担う部品開発を通して、世の中に貢献できるということ。それを少しでも知ってもらえたら、技術を志す若い人たちにも夢のある仕事ではないかと思います。目指す道の選択肢のひとつとして世界が広がれば、幸いです」
選手が表舞台のヒーローなら、石原さんら技術者は、紛れもなく、裏舞台のヒーローだ。近々、テレビなどで競技の映像を目にする機会があれば、どうか想い出して欲しい。この人なしに、チェアスキーのマシンは存在しないということを。表裏一体のヒーローがタッグを組んで目指す世界の頂点は、もうすぐそこだ。
石原 亘(いしはら・わたる)
チェアスキーショックアブソーバ開発者。2009年、KYBモーターサイクルサスペンション株式会社に入社。スノーモービル、ATV用ショックアブソーバの設計を経て、2015年よりチェアスキー用ショックアブソーバの設計に携わる。また、設計開発を行う傍ら、チームの国内遠征にも同行し、現地での仕様変更などのテクニカルサポートも対応する。趣味はモトクロス、自動車ラリー競技への参加や、スキー、スノーボードなどのウィンタースポーツ。