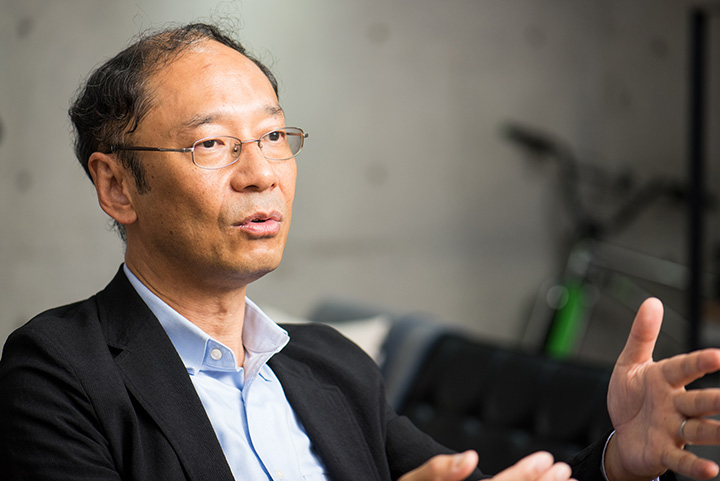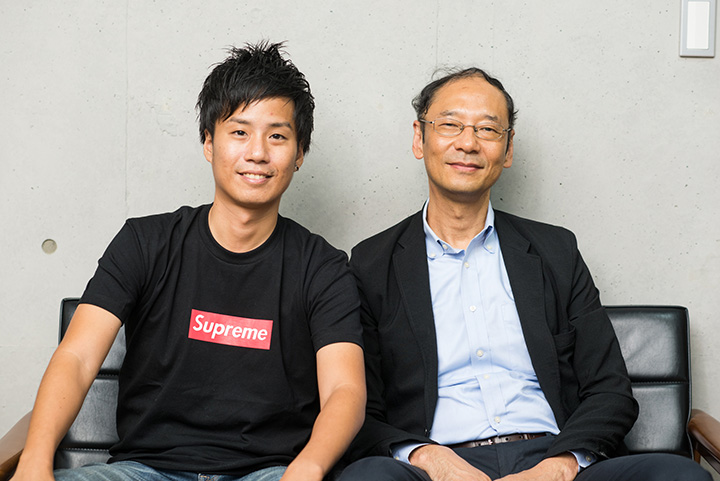VR技術のソリューション提供で最先端を走る企業、株式会社ABAL。VRライブストリーミングやVRストアなど、ビジネスにキャッチアップしたアイデアで突出している点が特徴だ。本誌編集長・杉原も昨年、同社の「ABAL:プレゼンテーションタワー(6階建てビルを仮想空間の中で体感する展示)」を体験して大興奮! VRは今後、我々に何を提供してくれるのか。代表取締役・尾小山良哉氏が提唱するキーワード「リテールテイメント」とは何か? 未来のテクノロジーを展望する2人の対話から、杉原のVRアイデアも飛び出す!?
現実空間を拡張していく
ロケーション型VR
杉原:御社の社名のABALは、アヴァロン(Avalon)から来ているんですか?
尾小山:そうです。アヴァロンの語源はケルト語で「リンゴ」なんです。もう1つにはアーサー王の眠るアヴァロン島という島の名前で、もう1つの世界、マルチバースという意味で名づけました。
杉原:VRブームの第一期といってもいい2016年に会社を立ち上げられて、この5年間は出口戦略も含めて大変だったと思います。続けられたのは、VRの時代が必ず来るという思いがあったからですか。
尾小山:そうですね。今おっしゃられた出口戦略については、今でも信じていたことが実現できたとは言えない段階です。ただ、信じられるかというと、それは信じられる。やはり最大の理由は、人間のコミュニケーションの表現には、まず文字があって、その次に映像になったけれど、結局映像のコミュニケーションは映画ができた100年前から、精度は上がっても「ビジュアルのコミュニケーションに時間軸がつきました」というところから変わっていないからです。
空間そのものをパッケージングできる体験のコミュニケーションが、僕らのこのやり方、つまりVRだと思っています。体験のコミュニケーションは文字も映像も包括していく上位コミュニケーションですから、タイミングの問題はあれども、確実にこの流れになっていくと思っています。

ABALが提供している体験共有プラットフォームは、システムとハードを組み合わせ、VR空間内での自由移動・体験共有を可能にするソリューション。設置に大がかりな工事なども必要なく、空間をVRで拡張することができる。
画像元:https://www.abal.jp/
杉原:実際にABALタワーを体験させてもらって、すごく面白かったんです。リアルと仮想現実の境界線がかなり微妙になっていて、没入度が高いなと。やはり御社にしかないシステムやテクノロジーがあるんですか。
尾小山:我々の最大の強みは空間を圧縮する技術ですね。小さなスペースの中に巨大なVR空間を作る技術に関しては、特許技術でもあります。一番わかりやすいものでいうと、あのタワーの中のエレベーターの部分はABALだけのものです。今VRは大きくクラウド系の文脈と、ロケーション系の文脈という2つがあるんですよ。クラウド系の文脈はご存じの通り、クラウドの中にゲーム空間のような大きなワールドを作っていく考え方です。一方で 僕らがメインとしているのはロケーションベースのVRで、現実の空間に対して、VRを使って空間を拡張する考え方です。この技術を使って現実空間の不動産価値を向上させるとか、場所そのものが持っている価値を飛躍的に伸ばすということをやっています。そして、今我々が最も注力している領域が店舗空間なんです。
まるで本当にショップを訪れているかのような感覚になるVR POP-UPストア。
杉原:というと、タワーの一番上ですね。
尾小山:そうです。商空間そのものをDX化するところに我々のソリューションは使えると思っていて、バーチャルのストアを作ったり、店舗内のディスプレイ空間をVRで作って、その中で買い物ができるようにしたり。それが今、我々が一番力を入れている領域です。
便利軸、代替案、可逆性でVRを考える
杉原:タワーの中に360度の巨大ドームシアターがありましたよね。このコロナ禍でイベント、エンタメ関係は多大な打撃を受けました。その中でこのシアターは非常に可能性が大きいと思いますが、やはり今後、ライブシーンやエンタメシーンがストリームとして行われていくというのは大いにありますよね。
尾小山:そこは間違いないと思います。今まで集客というのは一か所に人を膨大に集めなくてはいけなかったのですが、それ(会場)と自宅で体験するというものの間に、僕は分散集客というのがあると思っています。例えばですけど、中央区の会場で100人規模だとしても、全国10か所でやっていますというと、それだけで1000人の会場となる。それだと集中過密リスクも防げて、機会損失も少なくなる。分散で集客を小さくしていく流れを作るときに、VRは非常に可能性があります。1回のライブで3万人ドーンと集めるのではなく、全国の市町村に1個ずつとか、そういう興業の手法がこれから出てくるのではないかと思っていますね。

『ABAL:プレゼンテーションタワー』では、世界3大フェスと称される音楽フェスティバル『Tomorrowland』を、360度のドームシアターで再現した。こうしたVRを使ったライブ参加方法が浸透する日も近い。
杉原:中央集権的な流れももちろんあるのですが、情報社会で5Gが動いていくと、中央に行かなくて済むという流れが必ず出てきますよね。
尾小山:加えて、コロナ禍を経て、オンラインコミュニケーションが悪だったり、違和感だったりの時代にはもう戻らないと思います。可逆性のない変化が起きていて、それはマインドステートとして相当大きいですね。
杉原:エンタメの中でも旅行はどうでしょうか?
尾小山:旅行そのものの代替案としてのVRは厳しいと思います。便利軸と代替案というものと、可逆と不可逆というものがあって、バーチャルライブなどは代替で始まったけれども、別の面白さが出てきて、ここは生き残る領域だと思っています。一方で非対面コミュニケーションなどは、便利軸で動いてしまって可逆性はゼロ。これがもう一番戻らない軸だろうと。
そういう意味では、バーチャルツアーは代替案で、便利でもないので、可逆性がすごく強くて、コロナが終わったら戻るだろうという感じです。
杉原:例えばですけど、バーチャルツアーで「今、イギリスに行ってきたよ」みたいにはならないと僕も思います。でも1つだけ、バーチャルツアーが出たら絶対やりたいと思うのは、宇宙ですね。
尾小山:そこはそうですね! 結局、旅行の一番可逆性が大きいところは、行こうと思ったら行けるということ。でも宇宙は、そう簡単には行けない場所だから、バーチャルツアーは流行ると思います。国際宇宙ステーションに360度のカメラがあって、そこに行けるというだけでも、相当アガると思います。
杉原:しかもそこに無重力空間的な雰囲気を出す装置があれば、「宇宙に行った」と言っていいですもんね。だからやっぱりこのVRというものは人間の感覚値を、ある意味すごく拡張していくものだと思うので、拡張領域って人間の欲深い考え方でいくと、限りないですよね。

ABALがめざすものは“リテールテイメント”
杉原:ABALの事業の中で、街中で開かれる展覧会のようなこともされているとか。
尾小山:百貨店で開かれたあるアミューズメントパークの展覧会を手伝わせていただいています。このパークは僕がCMをやっていた頃にも携わったことのある所だったので、今回ABALとして関われることになったときは感慨深いものがありました。パークのキャラクターにバーチャルで会えたり、物語の世界の中をバーチャル空間を使って散策できたりといったことをやらせていただきました。
杉原:すごいですね。かなり時代の潮流を抑えていますよね。
尾小山:ABALで色々なモノ作りをしてきましたけど、今回の展覧会は僕としては、かなり完成形に近いです。前半では、キャラクターが住む世界をバーチャル空間に再現しています。それで、最後がお店になっていて買い物ができる。僕らが思い描いている“リテールテイメント”、つまりエンターテイメント+リテール空間が全部統合されていて、1つの世界観の中で、規模感のあるコンセプトツアーみたいなものが実現しています。
僕らが考えるリテールテイメントの最終形ってこうしたアミューズメントパークそのものなんですね。世界的に有名なアミューズメントパークがいくつかありますが、どこのパークもパーク部分が大きく見えるけれど、反対側にはそのパークのキャラクターグッズなど、物販エリアが必ずあります。この部分は売り場そのものなので、ひとつの大きなリテールテイメント空間ととらえることもできると思って。僕らの最大の強みは、あのエンターテイメント空間とリテール空間の比率を自在に変えることができることです。3坪くらいの中でアミューズメントパークのような空間を構築するというのが僕らの一番やりたいことかなと思うので、今回の展覧会の企画を一緒にやれたのはすごくうれしいですね。

ディレクタースキルの
マネタイズの手段が起業だった
杉原:HERO Xはエンジニアやデザイナー、企業など、色々な人が見てくれているのですが、その中で起業をこれからめざす人達もいらっしゃいます。ひとことアドバイスをいただけますか?
尾小山:やってみる、ですよね。結局、僕っていくつ会社を作って、いくつ潰したかわからないみたいな感じのところがあるんです。僕自身はディレクターでモノ作りをしていて、自分の持っている技術をどうにかマネタイズしなければいけなくて、起業に至ったんです。逆に孫(正義)さんとかは起業家なので、色々なビジネスプランの中で一番いけるやつを選ぶ感じですけど、あれって色々なことができる人に与えられた選択肢だなと僕はすごく思うんです。僕はそうではなかったけれど、起業するというゴールを持ってやりたいことをいっぱい出すことができる環境にある人ならば、それもいいのではないかなと思います。
杉原:今日は面白い話をありがとうございました。今、我々は医療の身体データをセンシングする事業をやっているのですが、出口としてVRというのは間違いなく必要になってくるところだと思います。ぜひ、またお話させてください。
尾小山:はい。体感というものを表現する箱というか空間としては、我々の空間はすごく使いやすいと思いますので。
尾小山良哉 (おこやま・よしや)
株式会社ABAL代表取締役。1996 年金沢美術工芸大学卒業後、太陽企画株式会社(企画演出部) に入社、24 歳から TV-CM の演出を開始し、同年、毎日広告デザイン賞第 1 部優秀賞 受賞。その後、あらゆる映像表現のディレクター として頭角を現し、2004 年に有限会社ディスバウンドディメンショ ン、2008 年に株式会社ドロイズ、2014 年株式会社 wise を設立。 TV-CM、VP、MV、遊技機、ゲーム等幅広いジャンルでの映像制作に携わる。 2016 年 1 月に設立されたジョイントベンチャー企業「株式会社 ABAL」を設立。
関連記事を読む