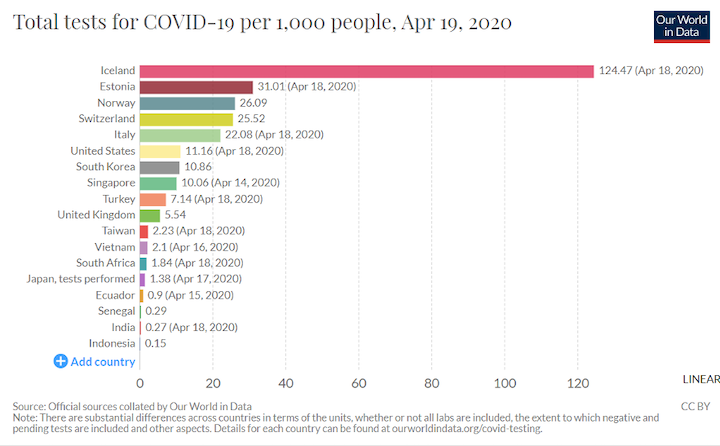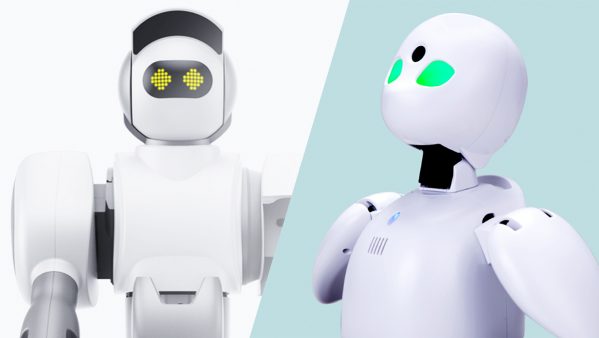見た目の美しさだけでなく、虫歯や歯周病のリスクが低減する、かみ合わせが良くなるなど、整った歯並びが健康面に及ぼす影響は大きい。しかしながら、定期的な通院が必要かつ費用が高額なことから、歯列矯正に踏み切るには覚悟してという声もよく耳にする。 米国で今年の9月にNasdaqに上場した「Smile Direct Club」は、これまでハードルが高かった歯列矯正のニュースタンダードとなるかもしれない。
 「Smile Direct Club」の共同創設者であるAlex Fenkell氏とJordan Katzman氏の出会いは、13歳の時のサマーキャンプに遡る。キャンプの参加者ほぼ全員がびっしりと矯正のワイヤーを装着していたこと、またAlex氏自身も矯正器具を着けて青春時代を過ごしていたことを振り返り、2人は手頃でより良い歯列矯正の手法を作ろうと決意した。2014年の設立時より、投資グループCamelot Venture Groupの協力を得ながら、顧客が在宅で医師とやり取りできるビジネスモデルの実現に成功している。
「Smile Direct Club」の共同創設者であるAlex Fenkell氏とJordan Katzman氏の出会いは、13歳の時のサマーキャンプに遡る。キャンプの参加者ほぼ全員がびっしりと矯正のワイヤーを装着していたこと、またAlex氏自身も矯正器具を着けて青春時代を過ごしていたことを振り返り、2人は手頃でより良い歯列矯正の手法を作ろうと決意した。2014年の設立時より、投資グループCamelot Venture Groupの協力を得ながら、顧客が在宅で医師とやり取りできるビジネスモデルの実現に成功している。
「Smile Direct Club」の具体的なサービスは「イメージ作り」「マウスピースでの治療」「アフターケア」の3ステップで構成されている。実店舗でスキャンを行うか、もしくは自宅に送ってもらう専用キットで取った歯型のデータを元に、歯科医がレビューを行い、治療プランを策定して、3Dプリンターでマウスピースを作成する。
顧客はどのように笑顔が変化していくかプレビューで確認したのちに、日々、オーダーメイドのマウスピースを装着して理想の歯並びに向けて治療する。治療が完了した後は、就寝時に装着するリテーナーを別途購入して、矯正した歯並びが後戻りしないようキープすることもできるし、90日ごとに医師がオンライン上で状況をモニターしてもらうこともできる。
気になる価格は、月々85ドル×24ヶ月プラス初回のデポジット250ドルでトータル2290ドルか、1895ドル一括払いの2パターン。米国内での平均費用6000~8000ドルと比較するとかなり手頃で、定期的な通院が不要という手軽さから、すでに75万人以上の笑顔に貢献した実績を誇る。国外展開を含め、市場規模がどれくらい拡大するかも要注目だ。
[TOP動画引用元:https://vimeo.com/336377978]