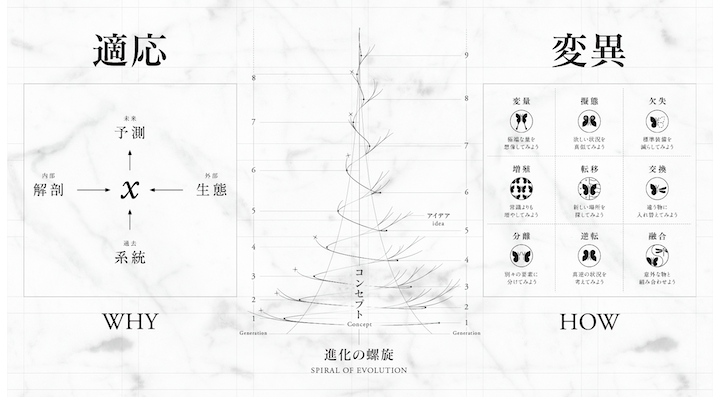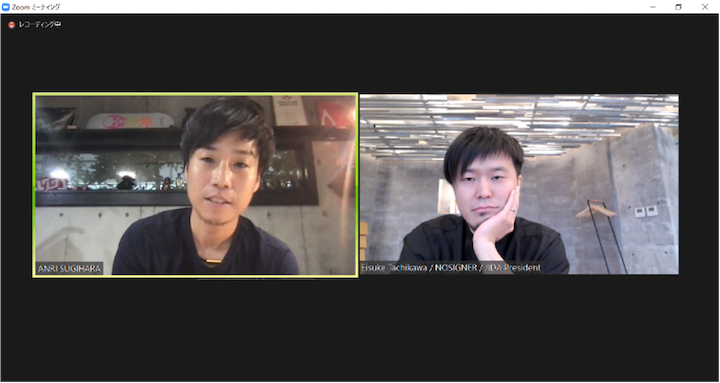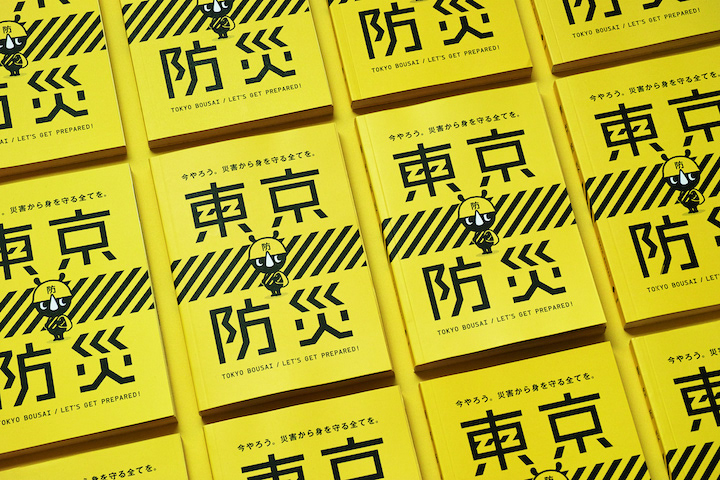大手家電メーカー勤務という安定の職を手放し、起業の道を選んだプロダクトデザイナー小西哲哉氏。前編では波乱の起業についてお話を伺った。現在は編集長杉原行里が代表を務めるRDSでもデザイナーとして活躍するが、デザインとはいったいなんなのか、後編ではデザイナーの先輩(⁉︎)でもある杉原が小西氏と共に、プロダクトにおけるデザインの価値について対談していく。
当たり前とはなにか
変化を受け入れる準備

杉原:福祉プロダクトに関わるようになり、福祉業界の今までは…という切り口をよく耳にするようになりました。大抵の場合は「福祉用具でもカッコイイものを」などという声なのですが、僕は少し違うのではないかと考えています。福祉用具を特別視する視点自体がもう古くなる。むしろ、皆さんが変わる準備はできていますか?という時代が来ているなと。小西くんは義手の製作に関わられるようになって、そのあたり、思うところはなかったですか?
小西:健常者が欲しいと思えるものがあってもいいのではないかと思っていました。企業に勤めていた頃は家電製品のデザインを担当していたのですが、「欲しい」という欲求を起こさせることは結構大事なことだと思っていて、福祉分野でも機能性だけでなく、そういう「欲しい」と思う、欲求を満たすものがあってもいいはずですよね。
杉原:所有欲を駆り立てられるものですよね。
小西:カッコイイと純粋に思えるものがあってもいいんじゃないって。でも実は、義手でそれをやろうと思った時、はじめは少し躊躇もあったんです。『義手でそんなことしちゃうなんて、何を考えているんだ』的なことを言われるのではないかと。でも、実際に出してみたら、皆さん意外と温厚な反応でした。健常者と障がい者と分けて考えてしまいがちなのだけれど、みんな同じ人間ですし、「カッコイイ」と思うことに健常者と障がい者の隔たりはないのだなぁと。
杉原:僕もそう思います。今僕らが考えているプロダクトは多分、将来的には当たり前になるものだと思うんです。例えば、こんなにメガネ人口が増えるとは誰も予想していなかったと思います。そこから派生して、目の中に直接レンズを入れてしまうコンタクトレンズが生まれましたけれど、当然、開発した当初は『直接目に入れるなんて』という意見もあったでしょう。でも、今はもう当たり前になっています。福祉プロダクトにおいてもそれが起こっていくと思います。受け入れる側がその変化についていけるかどうかではないのかなと。日本は2025年には人口の30% 以上が高齢者になるのですから、モビリティーという枠組みは絶対に不可欠になる。今は車いすユーザーがそれほどマジョリティーではありませんが、高齢化が進めば利用者は増えるでしょう。ただ、車いすという枠組みだけで考えていたのでは広がりを見出せない。ならば、車いすを飛び越えて、モビリティーとしてカッコイイと思えるものを作り、一石を投じたい、僕の場合はそんな気持ちが沸き起こりました。
小西:単純に、時代が変わってきているという感覚はありますよね。
デザインがもたらす選択肢

杉原:小西くんがやってこられた家電で例えると、炊飯器は米が炊ければいいという機能面だけでなく、キッチンに置いた時に許せる存在、デザインかどうかも購買者は選ぶポイントにしているはずです。つまり、皆がデザイン性を気にするようになってきた。多くの人にとって炊飯器は自分自身が使うものだから、自分ごととして考えられるため、カッコイイに越したことはないと。技術が進み、炊飯器の炊き上がり具合に大差が見られなくなると、人々が選ぶ指標として考えるひとつに、必ずデザインがあるはずです。でも、福祉業界の用具にはまだまだその選択肢が少ない。
小西:なんでないのか?というところですよね。RDSのメンバーの方々と車いすの開発に携わらせていただくようになり、はじめて車いすのデザインを手伝っていますが、RDSの皆さんと一致しているのは「自分でも乗りたいと思うものを作る」ということだと思います。
杉原:ここが一致していないと、なかなか一緒には作れません。
小西:ところが、これが非常に難しい。それぞれに良いものを作るぞという気持ちを深く持っているだけに、お互いの「これだ!」が噛み合わさるまでの道のりが一番大変だった気がします。
杉原:「乗りたい」と思えるものの感覚は各々で違うからでしょうね。また、世の中にまだ無いものを作り出そうとしているからってこともある。カッコイイと思えるかどうかは、感覚的なものだから、難しい部分はあります。
小西:「WF01」の原型ができたあたりから、やっと「これだ!」という方向が見えてきた。こうやったら面白そうだとか、もっとこうしたらいいなど、意見も出るようになっていきました。そうなるともう、高齢者とか体が不自由な方に向けてというよりも、自分が乗りたいものはどれだという感覚に近づき始めました。
杉原:それがすごく大事なことだと思っています。ボーダレスな製品を作るには、いかに自分ごと化できるかだし、そこがなければ目指すものは出来上がらない。今年も一緒に境界線を突破していきましょう!
小西 哲哉
千葉工業大学大学院修士課程修了。パナソニックデザイン部門にてビデオカメラ、ウェアラブルデバイスのデザインを担当。退職後、2014年にexiiiを共同創業。iF Design Gold Award、Good Design Award金賞等受賞。2018年に独立しexiii designを設立。現在ウェアラブル、ロボット、福祉機器など幅広いカテゴリーのプロダクトデザインを中心に、さまざまな領域のプロジェクトに取り組んでいる。