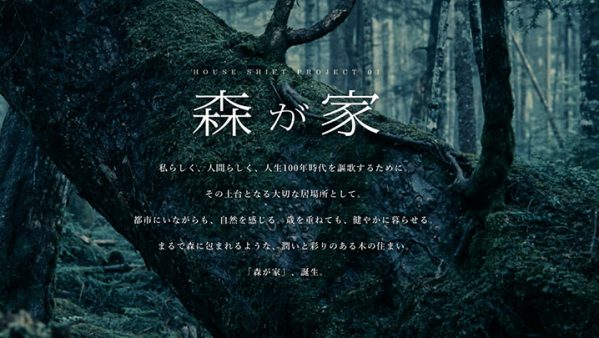目次
eスポーツという言葉が先行しつつも、その実態はよくわからないという人が大半なのではないだろうか? 一般的にはテレビゲーム大会と同義に捉えられることが多いが、eスポーツの黎明期からさまざまな角度で関わってきた、運楽家である犬飼博士氏のヴィジョンは壮大だ。RDSの代表であり本誌編集長の杉原と、ゲーム遊び・ゲーム作りに没頭してスポーツにたどり着いた犬飼氏が、未来について語り尽くす。
テレビを使って遊ぶようになった
最初の世代
杉原:犬飼さんは、映画監督を経てゲーム監督(開発)の道に進まれ、その後はeスポーツのプロデューサーとしても活躍されていました。そこでお聞きしたいのですが、一般的にeスポーツ=テレビゲームというイメージだと思うんです。しかし、犬飼さんが現在やられていのは実際に身体を動かすものが多いですよね? そこが面白いと思うのですが、犬飼さんは「eスポーツ」というのをどう捉えられているのでしょうか。
犬飼:「ゲームはスポーツだ」ということは、すでに1994年くらいから言っていたんです。自分は1970年生まれなので、カラーテレビがすでに普及していた世代。小学校低学年でアタリ社のテレビゲームが出てきて、高学年になって任天堂のファミコンが発売され、中学くらいでゲーム業界がいろいろ盛り上がってきた。つまり、テレビという装置を見るだけでなく、使って遊ぶようになった最初の世代なんですよ。
もっと言うと、1920~30年代にモータースポーツが生まれるわけですけど。工業社会が成熟してコモディティ化し、車が社会の中に浸透したことで、仕事や遊びに使われ、モータースポーツが生まれるわけです。経済成長をした日本でも1970年代後半にスーパーカーブームがおこりますよね。そういう風に、時代の流れとともに世間へ浸透していく。ファミコンが誕生したとき僕は13歳でしたが、同時に『キャプテン翼』の影響でサッカー人気もおこった。子どもにとっては、どちらも「面白い」というだけで境目はないんです。カウンタックが走っていればカッコイイと思ったし。何も考えず、区別もなく受け入れていた。その感覚はいまでも変わらないんです。

犬飼:小学校の頃にはパソコンも普及してきて、テレビゲームも作っていましたから。
杉原:えっ、作られていたんですか?
犬飼:今ならみんな作るでしょ? 猫を右から左に動かすとか、プログラミング教室でやるのと似たようなものですよ。僕が小学生の頃からできる環境はあったんです。ポケットコンピューターみたいのが、1万円で買えましたから。MSXというパソコンも3~4万円。なので、僕らはグラウンド(校庭)だけでなく、テレビのなかでも遊び始めた世代なんです。そこにはルールがなかったから何をやってもよかった。
杉原:そんな昔から、プログラムの環境が整っていたとは知らなかったです。
犬飼:サッカーもテレビゲームも区別なくゲームに熱中してきたので、「テレビゲームのゲームもスポーツと呼んでもいいでしょ?」というのが僕のeスポーツ感。
2035年には、たくさんの人が
eスポーツの恩恵を受けるようになる
杉原:eスポーツって犬飼さんが提唱したんでしょうか?
犬飼:いや、最初は人から聞きました。1999年頃、『Quake(クエイク)』というゲームをやるイギリスのチームがあって、彼らのチーム名に「eスポーツ」という単語が入っていたんです。それを見て、「eスポーツって表現はいいね」と僕らの周りが言い始めた。当時は、部活のようにテレビゲームをやるニュアンスで使っていたんですけどね。その後、2000年に韓国で『World Cyber Games』という大会が始まって、そこが「eスポーツ」という単語を大々的に使った。そのへんから、eスポーツというものの認識や状況が変わってきたんです。
杉原:へぇ~、ハンゲームが流行った頃ですよね?
犬飼:厳密に言うと、ハンゲームが流行る2~3年前ですね。

杉原:僕は2010年くらいに「eスポーツ」という言葉を聞くようになって。そこから急激に盛り上がって、市民権を得た印象です。
犬飼:う~ん、市民権を得たとまでは言えないかな…。2000年頃、eスポーツ事業を始めるにあたって35年計画を作ったんですよ。そのタイミングで僕はゲームの開発をやめたんです。というのも、作るだけではなくプレイすることもちゃんと伝えたかった。それで、2000年から数えて35年後には、おそらくたくさんの人がeスポーツの恩恵を受けると思ったんです。
杉原:それはどういう意味でしょうか? 詳しく教えてください。
犬飼:スポーツって、スポーツが大嫌いな人にも恩恵を与えていますよね? というか、溶けている。国の政策など、何らかのカタチでスポーツは生活に入り込んでいるという意味。eスポーツもそうなります。
杉原:今年の茨城国体では、文化プログラムとしてeスポーツ選手権がおこなわれますしね。
犬飼:多分これから10~20年くらいで、そういうものが積み重なって、みんなにとって普通なことになる。ひょっとしたら、eスポーツという言葉もなくなっているかもしれない。
杉原:「ただのスポーツじゃないか!」、みたいなことですか?
犬飼:そうそう。スポーツという言葉に反発する人もいるから、スポーツという名称すらなくなるかもしれない。
杉原:それは「ゲーム」という言葉にも当てはまりそうですね。
犬飼:いや、そもそも「ゲーム」という言葉が当てはまらないから「スポーツ」に言い換えた経緯があるんです。ゲームという言葉は誤解が多いんです。現代社会においては、多くのことがゲームと呼ばれるようになっている。IT社会、情報社会になって、人間の行動をゲームとして扱えるようになってしまったから。このように、あまりにも広範囲にゲームという言葉を使っているので、「ゲーム文化」と言ったときに何を示すのか不明瞭になってしまいました。というわけで、議論が成り立たないので、ゲームという言葉は使いたくないんですよ。
杉原:そこで「eスポーツ」という言葉に置き換えられていったということですね。
身体情報をすべて測定するのが
当たり前の時代になる

犬飼:よくする例え話ですが、「音楽」はもともとアコースティックなものでしたよね。その後、電気が普及することでエレクトリックギターやシンセサイザーなどが出てきて、「エレクトリック音楽」が生まれる。言い換えば「eミュージック」なんです。そういう感じで、「スポーツ」も「eスポーツ」になるだけ。メールもそうでしょ? いま郵送の手紙を指すとは思われていない。
杉原:昔は、「eメール」って呼んでいましたもんね。
犬飼:そう、「eスポーツ」も「スポーツ」の中に溶けていく。
杉原:つまり、今後はもっと大きなものになっていくわけですか?
犬飼:普通になっていく。コモディティ化していきます。
杉原:そう考えると、犬飼さんが2013年に『スポーツタイムマシーン』を発表された理由がよくわかりますね。
犬飼:そうなんです。情報化はあらゆるところで起こっていて、僕たちは身体情報をすべて測定するという意味での「情報化」をやっている。それが当たり前になる社会を目指しています。まだ珍しいことなんで早めにやったほうがいいですよ。
杉原:もっと早く知っていたら、10年前の自分と100m走で戦いたかったですよ。でも、あの映像を見ると、みんなすごく楽しそうですよね。
犬飼:人間ってくだらないから、走るだけで大喜びする(笑)。走っているときは、背景に映し出されている対戦相手の映像も見えないんですけどね。
杉原:それってリアルなスポーツと似ていますよね。サッカーをやっている人と、観ている人は乖離している。
犬飼:そういうことです。
eスポーツに関する
プラットフォームを作っていきたい
杉原:『スポーツタイムマシーン』はどこかに常設されているんですか?
犬飼:まだないです。『スポーツタイムマシーン』を作る前、2010年頃には『eスポーツグラウンド』という、4×6mくらいの設備を作って売っていたんです。床面にプロジェクターを当てて、キネクトで各種データを取って、デジタル空間で遊べるというもの。簡単に言えば、床に大きいiPadがあって、指の代わりに人間が動いて遊ぶような感じ。アプリは誰もが開発できるようにして、eスポーツのグラウンドとして使いたかった。
iPhoneもまだ完全には普及していなかった時代なので、当時は理解してくれる人が少なかった。いまは、それよりもサイズを大きくした『IT体育館』を目指しています。
杉原:それはすごいですね。人間の各種計測データが遊びに変化する。
犬飼:でも、昔からなかなか資金調達ができないんですよ。未来は必ずそうなる、そうならざるを得ないことを描いているのに。
杉原:稲見昌彦(東京大学先端科学技術研究センター教授)さんとやられていることも、そのひとつですか?
犬飼:そうですね。稲見さんは『超人スポーツ』という名前で研究をしているということです。
杉原:計測データを使って遊ぶという意味では、ワントゥーテンさんがやっている『サイバーボッチャ』とも似ていますよね。
犬飼:そうそう、彼らは『サイバーボッチャ』という単体の遊びを提供していますけど、僕らはプラットフォームを提案している。それくらいの差ですよね。
杉原:今後、iTunesストアみたいにeスポーツに関するプラットフォームを作っていくわけですね。将来的には、情報化させた身体情報をどう活用していくのでしょう。
犬飼:データ(身体情報)をリアルタイムで取って、クラウドに貯めて、過去の情報をほしいときに引っ張れるようにしたいと思っています。
犬飼博士
1970年、愛知県一宮市生まれ。運楽家/遊物体アソビウム/ゲーム監督。映画監督山本政志に師事後、ゲーム業界にて『TOY FIGHTER(アーケードゲーム)』、『UFC(ドリームキャスト)』、『WWF RAW(Xbox)』といった作品を制作。2002年より、スポーツとゲームを融合する「eスポーツ」の事業を開始。『World Cyber Games』、『Cyberathlete Professional League』、『Electronic Sports World Cup』といった国際eスポーツ大会の日本予選をオーガナイズ。2007年度文化庁メディア芸術祭にて、ゲームソフト『Mr.SPLASH!』が審査員会推薦作品に選出。2012年には、日本科学未来館で常設されている『アナグラのうた 消えた博士と残された装置』に参加。2013年には、YCAM公募企画『LIFE by MEDIA』国際コンペティションや、文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞などを受賞した『スポーツタイムマシーン』を発表。