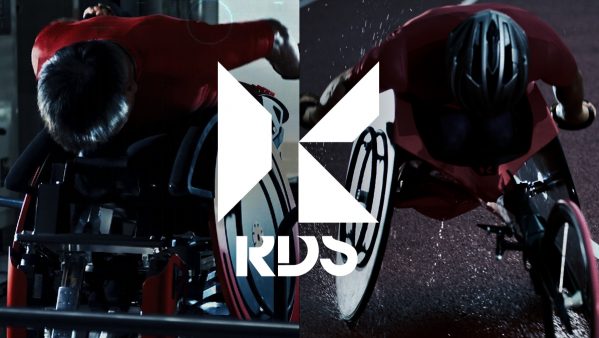東京2020大会の公式文化プログラム、日本文化を世界に発信する「東京2020 NIPPONフェスティバル」で、パラリンピック開幕直前に実施されるプログラムのクリエイティブディレクターに就任した小橋賢児氏。テーマ「共生社会の実現」に向けた小橋氏の想いと、日本人が本当のアイデンティティを見つけるためにしていくべきこととは。イベントプロデューサーとして活躍する小橋氏と『HERO X』編集長の杉原行里が語り合う。
杉原:まずは、小橋さんがクリエイティブディレクターに就任された「東京2020 NIPPONフェスティバル」についてお話を聞かせてください。
小橋:オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典であるとともに文化の祭典でもあるんですよね。「東京2020 NIPPONフェスティバル」は来年の4月~9月にかけて実施される東京2020オリパラの公式文化プログラムです。世界中からたくさんの人が集まる機会に日本の文化を世界に発信していこうというもので、大きく4つの取り組みを行なう予定で進められています。1つ目がプログラムのキックオフともなる「大会に向けた祝祭感」をテーマとした歌舞伎とオペラによる舞台芸術、2つ目が「東北復興」をテーマにしたプログラム、3つ目が、オリンピック開幕直前に開催される「参加と交流」のプログラム、そして4つ目が、私がクリエイティブディレクターとして関わっているパラリンピック開幕直前に開催する「共生社会の実現」に向けた “きっかけづくり” のプログラムです。
伝統・文化は変わっていく

杉原:「HERO Ⅹ RADIO」(2019.01.25放送分)にゲスト出演いただいた際の「文化というものはその時代によって変わって成長していく」という小橋さんのお話が大変印象に残っているのですが、今回の “きっかけ” というのはそこに通じるところがあるんですか?
小橋:もちろんあります。21世紀に入り情報革命が起きて世界中と繋がったことにより、みんなの中で多様な文化とか、多様な考え方というのが当たり前になってきています。しかしその一方で、目の前にある社会はあまり大きく変わっていない。そこのジレンマに多くの人が苦しんでいる気がしています。
日本人が持っている民族的な文化の “和の心”、僕はこの “和” は、調和の “和” だと思っているんです。日本人は様々なものを取り入れて調和していく力があって、元々ものすごく多様性のある文化を持っている民族のはずなのに、今は真逆に走っていて、“感じる力” や “空気を読む力” が強くなっているように感じています。さらに言うと、同調圧力が強いからか、“気にする” になってしまって、本当の自分を見い出せずにいる人が多い。自分のアイデンティティすら分からない自分が、他者を認めるのはなかなか難しいわけで、これが今の日本の姿だと思うんです。
そんな日本において、東京2020のタイミングで、日本から調和という “和” が始まっていくきっかけづくりができることは、ものすごく意味があることだなと思うんです。全てを変えられなくても、イベントがきっかけで人々が変わっていくとうことは大いにあり得ると。
杉原:特にパラリンピックの文脈は変わりましたよね。
小橋:2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックが突破口を開いたなと思うのは、“アンリミテッド” という部分。オリンピックが終わって人々の機運が下がってきたときに、障がい者とアーティストがコラボレーションして、いろんなところでパフォーマンスやアート、演劇をやったんですよね。それまでの、障がい者をそんな風に扱ってはいけないんじゃないかっていう世の中の意識が変わって、それがパラリンピックに繋がっていった。街中で、これまで体験したことのない多様なライフスタイルや文化を感じていろんなマイノリティーを知ることで、自分もある種のマイノリティーなんだと知ることができる。そうなって初めて理解できると思うんです。
本当にそうなのか?と価値観を疑うこと

杉原:僕は、小橋さんが総合プロデュースされた「STAR ISLAND」で花火を観るまでは、花火というものがある程度の自分の想像を超えることはなかった。でも、「STAR ISLAND」で花火を観た瞬間、僕のそれを超えてしまった。これが文化の継承という新しいスタイルなんだと思ったら期待が高まりますよね。小橋さんは東京2020のオリパラを機に、自分たちの時代において何を変化させていきたいですか?
小橋: 一見、ネガティブに思われていることに対する価値観を、本当にそうなのかな?と一度疑うことで、変えていきたいですね。ネガティブに思われていることも、「誰から見るか」というだけの話ではないかと。それらはよく考えてみると特徴や個性で、もっと上手く使い合えたらいいなって思うんです。例えば、障がいを持っている人に対して、「助けてあげる」だと、完全に弱者を見る視点になってしまっていますよね。そうじゃなくて、その人が持っているものの良さを引き出せるような社会になった方がいい。
杉原:海外では、男性女性関係なく、重そうな荷物を持っている人やベビーカーの人を見かけたら、躊躇なく声をかけて手伝ったりする文化がありますよね。でも日本では、知らない人に声をかけるとなんか変な空気感になってしまうことがあるから声をかけたくてもかけられない。“調和” と、“空気を読む” が混在してしまった結果ですよね。
小橋:結局、感じてしまうが故に、先に想像して行動するのをやめてしまう。多様な生き方や文化を一気に知ることができる東京2020は、きっと二度とないチャンスですよね。世界中から否応なく人がいっぱい来て、ものすごい数のイベントが一気に開催される。こういった、ある意味での “カオス感” って必要だなと思んです。普段触れ合えない人たちと触れ合うことによって、自分の概念やリミッターが外れる。そうなって初めて理解できることがあると思います。例えば音楽フェスって、みんな既知のアーティストを目的に行くんですけど、気づいたら全然知らなかったアーティストに出会って、そこから価値観が変わっていくことがある。そんな風になったらいいなって思うんです。
小橋賢児(Kenji Kohashi)
LeaR株式会社 代表取締役/クリエイティブディレクター 1979年東京都生まれ。88年に俳優としてデビューし、NHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』など数多くの人気ドラマに出演。2007年に芸能活動を休止。世界中を旅しながらインスパイアを受け映画やイベント製作を始める。12年、長編映画「DON’T STOP!」で映画監督デビュー。同映画がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にてSKIPシティ アワードとSKIPシティDシネマプロジェクトをW受賞。また『ULTRA JAPAN』のクリエイティブディレクターや『STAR ISLAND』の総合プロデューサーを歴任。 『STAR ISLAND』はシンガポール政府観光局後援のもと、シンガポールの国を代表するカウントダウンイベントとなった。 また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会主催の東京2020 NIPPONフェスティバルのクリエイティブディレクターにも就任したり、キッズパークPuChuをプロデュースするなど世界規模のイベントや都市開発などの企画運営にも携わる。
Born August 19th, 1979 and raised in Tokyo. At the age of 8, he started his career as an actor and had played roles in various dramas, films and stages. He quitted his acting career in 2007 and travelled the world. Experiences through the journey inspired him and eventually started making films and organizing events. In 2012, he made his first film, DON’T STOP, which was awarded two prizes at SKIP CITY INTERNATIONAL D-Cinema FESTIVAL. In the event career as creative director, He has acted as Creative director at ULTRA JAPAN and General Producer at STAR ISLAND. Not only the worldwide scale events, he produces PR events and urban development