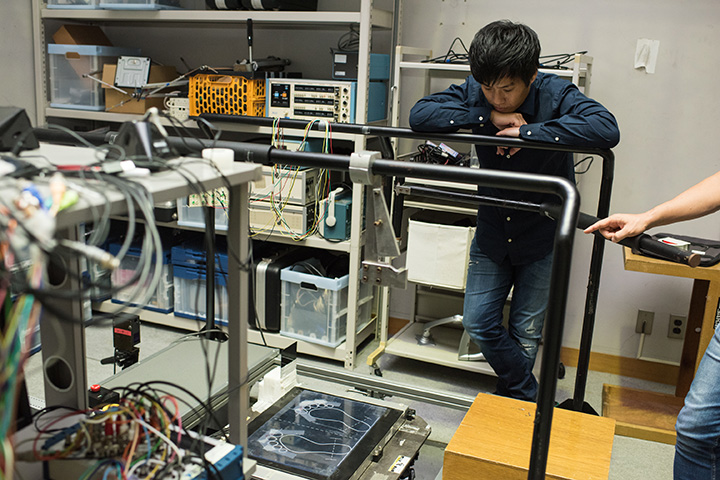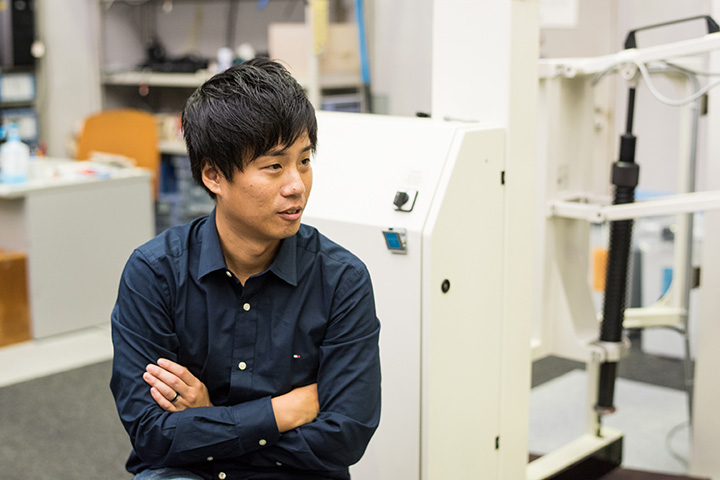近年、大きな社会問題になっている数々のハラスメント。とりわけスポーツ界では、監督やコーチと選手間の異常な主従関係や、暴力的な行為が問題視されることが多い。度々メディアでも報じられるこうした歪みの裏側には、記録やパフォーマンスの向上を目指す指導者側の感情的な空回りや、埃をかぶった根性論などが横たわっている。スポーツ科学とセンシングテクノロジーは、それをポジティブなコミュニケーションへと変える。第一人者である長谷川 裕氏をお招きし、編集長・杉原と最新のスポーツ指導の在り方、そして未来について語り尽くしていただいた。
スポーツに直接役立つ科学技術の追求

杉原「まず、スポーツ科学、そしてセンシングというものは、大きく言うとどういうものなのか、簡単にお聞きしたいのですが」
長谷川「スポーツ科学と一口に言っても、細かくはスポーツサイエンスとエクササイズサイエンスという2つがあります。例えば、マラソンランナーがランニングマシンの上で走っている時に呼気を計測しているとしたら、スポーツサイエンティストとエクササイズサイエンティストは、各々違うことをやっているんですよ」
杉原「なかなか違いが難しいですね(笑)」
長谷川「簡単にいうと、スポーツのためにトレーニング技術を開発したり、選手の問題点を発見したり、怪我しない方法を考えたり……、パフォーマンスを向上するための方法を見つけるために、科学的な手法や基礎科学を使っていくのがスポーツサイエンス。そのために筋力や心拍数のみならず、事細かなデータを計測するのがセンシングという技術です。逆にスポーツを使って、身体運動や健康に繋がるような人間のなんらかのしくみを発見するとか、メカニズムがどうなっているのかを調べるのが運動科学、すなわちエクササイズサイエンス。僕自身は、スポーツサイエンティストでありたいと思っています」
杉原「なるほど、長谷川さんは、スポーツに直接役立つ科学的な技術やしくみを研究されているということですね。世間一般が対象ではなく、スポーツに特化した世界がフィールドであると」
長谷川「そうです。でもスポーツに特化した研究というのは、ごく一部のエリート選手のためのものではないか? とよく言われるのですが、私がやっている研究は、一般の方の健康にも役立つんですよ」
杉原「世間一般にも役立つか否かで、正直、大学の研究費も変わってきそうですよね(笑)」
長谷川「確かにそれはあります。かつてアメリカでは、シューズでもギアでも、開発するとなれば、大きな企業から巨額の研究費が調達できたのですが、各々の企業は自分たちで研究所を持つようになりましたから、大学の研究所には、お金が回らなくなってしまいました。製薬会社や医療機関は、今でも肥満対策や高齢者の転倒防止、安全な子供の食事、そういうものに対しては研究費を出してくれますが、それではスポーツの研究はできませんよね」
杉原「そうなると厳しいですね」
日本にスポーツサイエンスは根付いていない?

長谷川「でもヨーロッパのスポーツ科学は、そうではありません。いかにこのチームを勝たせるか? 端的にそういう研究をしています。プロスポーツのチームには研究所があるのが普通です。サッカーでいえば、マンチェスター・ユナイテッドも、チェルシーも、バルサも、研究所では10人以上の専門職がスポーツサイエンスを研究しています。アメリカには、それがないんですよ」
杉原「それはイギリスが中心ですか? それともヨーロッパ全体?」
長谷川「ヨーロッパの国々は、どこもそういう環境が整っていますよ。あとはオセアニアですかね」
杉原「ちなみに日本はどうなんですか?」
長谷川「日本は、そういうことをしているプロスポーツのチームはありません。自分がアドバイザーとして携わったJリーグの(名古屋)グランパスは、2004〜2008年頃にスポーツサイエンスを選手育成に導入しようとしていました。でも残念ながらそのプランは、すぐに変更されましたね」
杉原「そうなんですね。確かにヨーロッパと日本では、スポーツ文化の根付き方も違いますし、スポーツ自体の熱狂度も違います。科学を積極的に使っていこうという動きは、まだ日本には根付きにくいのかもしれません」
長谷川「そうだと思います。これはヨーロッパだけに限らないのですが、スポーツサイエンスが進んでいる地域では、サッカーの試合全体を、スタジアムに設置した8台ぐらいのカメラでカバーして、どのプレーも必ず2台以上のカメラで記録するプロゾーンというシステムがあります。それで計測したデータは、俯瞰で見たアニメーションにして、選手の能力を約4000項目も分析できるんです。自分はそのシステムに魅せられて、イギリスのリーズまで行って交渉して、日本で会社を作って広めようとしました」
杉原「それは画期的なシステムですね」
長谷川「それでサッカーの日本代表にも提案をしました。でも、当時の監督には、“こんなものに頼っている指導者はダメだ”とはっきり言われましたよ。そこで自分も“では、なぜプレミアリーグの全チームがこれを導入しているのですか?” と応戦したのですが、“向こうの選手はこういうものがないと、いうことを聞かないからだろ”と、突き返されました(笑)」
杉原「もう、それは論点が違いますね」
長谷川「そうなんです。日本では、まだまだ監督の存在は絶対で、選手は監督にモノをいうのはおかしいという風潮が根深い。でも、ヨーロッパでもアメリカでも、選手は監督にいろいろと聞いてきます。そういうコミュニケーションを取るときに、感覚論で曖昧な答えをしても選手は納得しませんから、いろいろなセンシングのデータを見せる必要があるんです」
感覚を可視化すれば
すべてがわかりやすくなる

杉原「自分もレース用車いすの開発をしていますが、やはり感覚で話しをされると同じ土俵で話すのが大変。感覚とは、毎日違うものだから難しい。だから感覚を出来る限り可視化して開発していく必要があるといつも感じています」
長谷川「可視化したデータを重視するというのは、スポーツサイエンスと一緒ですね」
杉原「例えば、一緒に開発をしているアスリートが、座っている車いすの“ここが硬い”、“ここがやりにくい”と言ったら、まずスタッフはそれを反映させようとする。でも自分は止めるんです。なぜなら、それって感覚だから。感覚ほど曖昧なものはない。だから計測をして、硬いと感じる原因を探る必要があるんです」
長谷川「確かにそうですよね。本来、データで判断すべきものってことですね」
杉原「はい。そこで僕たちは、モーションキャプチャーや加速度センサー、触覚センサーなどいろいろ使って計測して、アスリートの違和感を可視化するんです。そうすると、“結局、あなたが言ってたのは、このことか!”と、初めてみんなで納得できるようになる」

車いすの開発も、センシングと同様に、計測と可視化がカギを握る。
長谷川「そうそう、そういうことです。それだと選手に問題点がちゃんと伝わりますよね。データを解析して、ノウハウにしていくことも大切ですし。トレーニングも感覚でやっていくと、わかったつもり、できたつもりになる。それが一番よくないです」
杉原「海外のサッカーだと、コーチやマネージャーが、サッカー経験者じゃないケースも多々ありますよね。日本ではまだ少ない気がします。経験の有無だけじゃなくて、指導者は解析がどれだけできるか、それを利用してどれだけいい戦略が練れるのか、そういうところも評価されるべきだと思うんです」
長谷川「ある競技のコーチやスタッフが、その競技の経験者ではない場合、その人が選手から信頼されたり慕われたりすると、その畑で育った指導者は、ものすごく毛嫌いしますよね」
杉原「そうですよね。あとセンシングで選手の状態を常にデータ化しておけば、怪我をしたときにも、壊した身体の状態を過去のデータと照らし合わせられますよね。カルテ共有ができれば、対処も早くなるはずです」
長谷川「確かにそうです。プレミアリーグでも、選手が移籍をしたら、それまでどんなトレーニングをしていたのか、怪我や筋力の状況、スプリントやパワーなどのデータを受け継ぐのが普通です。そうやって選手個々の健康を守って、リーグ全体のレベルを引き上げているわけですよ」
杉原「プレミア全体のレベルが上がったのは、センシングやデータ解析などの技術が反映しているからかもしれないですね。ただ、僕が好きなアーセナルは、いつも怪我人が多いですが、スポーツサイエンスのレベルが低いんですかね(笑)」
長谷川「いやいや、アーセナルの研究レベルは、かなり高いはずですよ(笑)」
長谷川 裕(はせがわ・ひろし)
1956年京都府生まれ。龍谷大学経営学部教授(スポーツサイエンスコース担当)。日本トレーニング指導者協会(JATI)理事。スポーツパフォーマンス分析協会代表理事。エスアンドシー株式会社代表。筑波大学体育専門学群卒業、広島大学大学院教育学研究科博士課程前期終了。龍谷大学サッカー部部長・監督、ペンシルバニア州立大学客員研究員兼男子サッカーチームコンディションコーチ、名古屋グランパスエイトコンディショニングアドバイザー等を経て、スポーツセンシング技術等を利用した科学的トレーニング理論の実践的研究を続ける。著者は『アスリートとして知っておきたいスポーツ動作と体のしくみ』、『サッカー選手として知っておきたい身体の仕組み・動作・トレーニング』ほか多数。