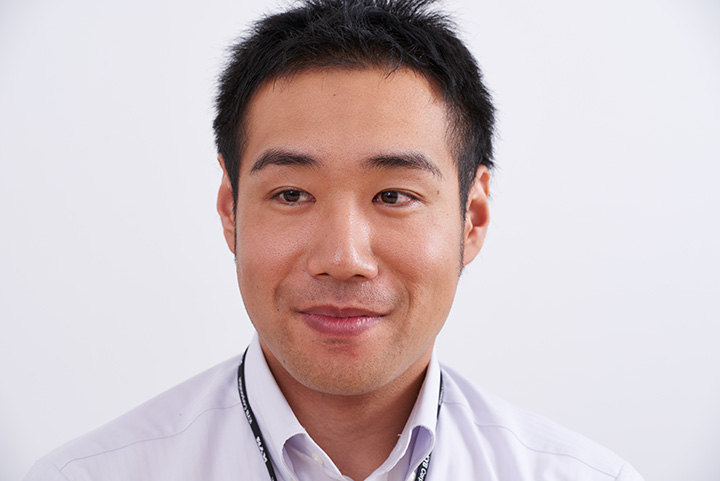昨年3月、卓越した身体能力とチャレンジ精神を武器に、ピョンチャンパラリンピック・スノーボードで2つのメダル(バンクドスラローム:金/スノーボードクロス:銅)を獲得した姿は記憶に新しい。成田緑夢選手(以下:成田選手)にとって、昨シーズンは最高の形で幕を閉じた。次なる目標に舵を切った彼は、ピョンチャンの余韻冷めやらぬなか、冬季パラ競技からの引退を宣言。さまざまな競技体験を経て、2018年11月に東京2020をパラ陸上走り高跳びで目指すことを発表した。2020年まで1年半。夏冬のオリンピック・パラリンピック出場を目標とする成田選手の競技に取り組む姿勢に迫った。
方針決定。第一歩は“5千回”

ピョンチャンパラリンピック後の冬季パラ競技引退を機に、スポンサー契約を見直した成田選手は現在はフリーとなっており、コーチを付けず独立独歩でトレーニングを行っている。2018年にはカヌー、ボート、射撃、馬術、陸上などを経験しながら、東京2020に向けてフォーカスする種目を吟味した。
最終的に走り高跳びを選択したのは、自身の能力と経験を鑑みてのものだ。成田選手は、以前からスノーボードと平行して、東京2020を念頭におき、陸上にも取り組んでいた。その種目のひとつが走り高跳びだった。公式記録を有していることから、東京2020へ出場する最短距離と判断し、選択したというわけだ。
12月下旬の取材当日、都内某所のトレーニング場に姿を現した成田選手は、走り高跳び用のマットを引っ張り出し、バーを設置すると、おもむろに2回跳躍した。
「“5千回”の成果はこれですね。1回目の跳躍が以前の跳躍で、2回目が今の跳躍。後者の方が下半身がしっかり浮いているのがわかると思います」

成田選手は11月下旬、ひとつの目標を宣言していた。
「高跳びのバーを5千回乗り越える」
目標達成の期限は2018年12月16日。成田選手は以前から、自身の目標を期限付きで設定し、『誓約書』を書くという作業を繰り返してきた。達成した目標は、誓約書にして数百枚。その際、「達成できなければ、丸坊主になる」という条件を自らに課す。なぜ5千回なのか、という問いには、「なんとなくですね」と笑う。この日の成田選手は、無論、丸坊主ではなかった。
目標宣言から約20日間。毎日のように、体力の限界までバーを跳び続けていたという。とはいえ、闇雲に跳んでいるわけではない。
「僕は“無駄な一手”は打ちたくないんです。考えた時間に比例して、人は進歩する。だから、5千回意味のある跳躍をしなくてはいけません。今回に関して言えば、(跳躍して)空中にいる時のエネルギー研究がテーマでした。跳び続ける中で、目線、手や頭部の位置を変えてもなかなか納得のいく跳躍ができませんでしたが、最終的に腹部の重心移動に意識を向けるスタイルに落ち着きました」

幼い頃からスポーツにおいて父親の英才教育を受けてきた成田選手は、2013年、フリースタイルスキーのハーフパイプで世界ジュニア選手権の頂点に立ち、五輪出場をうかがっていた矢先、トランポリンのトレーニング中の事故で左足腓骨神経麻痺を負った。
左足膝下の感覚がない、いわゆる『機能障がい』という状態のため、パラリンピックを制したスノーボードでは、左足に硬い材質のブーツを履き、ターン時には左膝をウェアの上から握りながら、微妙な力の加減で身体のバランスをコントロールする工夫を施してきた。陸上では、左足首をテーピングで固定し競技に臨んでいる。ただ、走り高跳びにおいては、左足の状態を加味した跳躍の工夫は現段階では考えていないという。
「今までは助走や跳躍ではなく、空中姿勢を意識してきました。要するに“詰め”の部分ですね。僕はトランポリンなどの経験から、空中での身体感覚には自信があるんです」
将棋を通じて学んだもの

成田選手の強みは、“越境する力”とも言える。一見して関連性がなさそうに見えても、本質的に目標達成に必要な物事を見極め、積極的に取り入れるという姿勢だ。「無駄な一手」や「詰め」といった言葉にもあるように、成田選手はここ最近、「先読みの質」や「選択の質」の向上のために将棋をたしなむようになった。一時は東京・千駄ヶ谷にある将棋会館にも通っていたほどだ。「目の前の一歩に全力で」というのは、しばしば成田選手が口にする自身のポリシーだが、メディアの取材に対しても「“一歩”の選択肢が広がった」と将棋による影響を語っている。
将棋における終盤の力を磨くためのトレーニングとして始まり、今ではひとつのゲームとして確立している『詰将棋』というものがあるが、成田選手にいわせれば、走り高跳びで現在取り組んでいる領域が、まさに詰将棋にあたるという。
「将棋には序盤、中盤、寄せ(終盤)とあって、いずれも大事ですが、最終的には詰将棋ができなかったら勝てないわけです。だから今はガンガン詰将棋をやっているような感覚。5千回もやれば、詰め方のパターンも自ずと分かってくるんです。高跳びに置き換えると、次のステップとしては、助走(序盤)や跳躍(中盤)の動作をそれぞれ反復することを考えています」
他方で、最近では「読みすぎることのデメリットも感じるようになった」ともいう。
「将棋から一手の大切さを学びながらも、思考の深さと行動の速さのバランスをとる必要性に気づいたんです。今までは目の前の選択肢が生まれた瞬間に一手指していました。将棋を始めてから、他の選択肢を思考できるようにはなったのですが、考えすぎて逆にスピード感が落ちてしまったように感じていて。選択肢を複数浮かべて、最善の判断を素早くすることが大切だと感じています」
自発的挑戦が生み出す強さ

「一手を大切にする姿勢は、そのまま人生にもつながる」と成田選手は語る。
「課題を乗り越えるためには、目の前の一歩を無駄にはできないんですよ。自分の場合は、人生とリンクしているものとしてスポーツがありますが、スポーツの場合は自ら課題を設定してそれを乗り越えていくわけです。それに対して人生における壁は突発的に現れる。スポーツを通して普段から課題を乗り越えるトレーニングをしておけば、壁にぶつかっても怯むことはありません」
冬季パラリンピックを優勝という形で終えたものの、「夏冬オリンピック・パラリンピック出場」という規格外の目標を踏まえると、今はまだ道半ばだ。彼にとってのキーワードは「挑戦」。挑戦の中から工夫が生まれる。しかしそのマインドは、受傷する前はあまり持っていなかったという。

「怪我をしてスポーツを一度やめた後、自ら再開しました。以前は、父親というコーチの元で義務感を感じながら練習をしている感覚もありましたが、今では自分で考えて取り組むことができている。要は、プロセスを楽しむことが重要なんですよね。課題に挑戦している自分を見るとワクワクします」
現時点での走り高跳びの自己記録は1m80cm。パラリンピックで活躍するレベルまで到達するには約20cmの開きがあり、乗り越えるべき課題は多い。「高跳びは練習しても記録が伴わない場合もある」と競技特性上の難しさも心得ている。
とはいえ、成田選手にとっては、過程にハードルが多いほど楽しむことができるのかもしれない。誓約書にしたためた目標に向けて、境界を越えた試行錯誤を重ねた先に、軽々とバーを飛び越える姿を見ることができるはずだ。
一手一手を吟味し、迅速にアクションに転じる。2020年までの1年半を、成田緑夢は盤上の駒を動かすように過ごしていく。

成田緑夢 (なりたぐりむ)
大阪府大阪市出身、1994年2月1日生まれのプロアスリート。フリースタイルスキー、スノーボード、トランポリン、陸上選手。小学校時代からスノーボードの国際大会に出場。16歳で高難易度の技を決める技術を持ち、トランポリン競技でも功績を納める。18歳からフリースタイルスキー (ハーフパイプ) を始め、世界選手権の日本代表に選出される。19歳の時にトランポリンの練習中の事故により左足の腓骨神経麻痺の重傷を負うが、障がいを克服してハーフパイプ競技に復帰。2018年3月の平昌パラリンピックでは、スノーボードクロスで銅メダル、スノーボードバンクドスラロームにおいて金メダルを獲得した。その後、スノーボード競技からの引退を発表。東京2020大会では、陸上の走り高跳びでの出場を目指している。