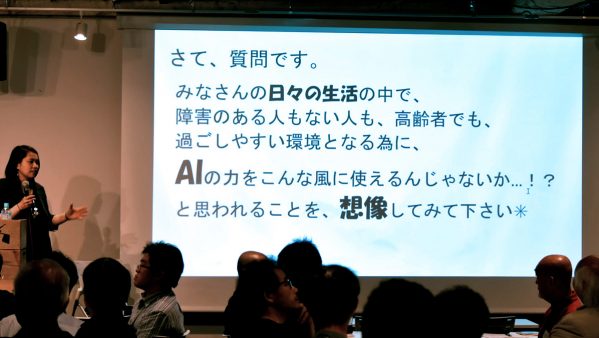今回、HERO X連載企画【パラリンピックのヒーローを発掘】にご登場いただいたのは、中京大学陸上部に所属し、400メートル部門の日本記録保持者・池田樹生選手。2016年に開催された“ジャパンパラ陸上競技大会”にて、自己ベストを2秒近く縮める「57秒40」の日本記録を叩き出し、一気にトップアスリートの仲間入りを果たした池田選手に迫るべく、様々な角度からお話を伺った。
日本記録を出した今、
池田選手が目指す場所とは?

記録を塗り替えるということは、同時に背負うものが増えるということ。だからこそ得るものも大きく、そこから来るプレッシャーに勝つためのフィジカルやメンタルの強さが要求されるのだ。そのきっかけとなった「57秒40」の世界に初めて足を踏み入れた時の感覚は、どのように感じていたのだろうか。
「この時は、他のクラスの方も一緒に走るレースだったので、1位でゴールしたのは僕ではなく、すぐにはタイムが分からなかったんです。自分の中では、自己ベストは出ただろうという手応えは持っていましたが、まさか57秒台で走っていたのには驚きました。ただ、レースプランとして、はじめから突っ込んでいこうということだけは決めていたので集中力は高かったんだと思います。
そして、日本記録保持者になったことで、今までには持ち得なかった感覚のプライドが生まれ、もっと世界で勝負がしたいという気持ちがその瞬間に芽生えたのを覚えています。もう一つは、レース用の義足を使って走る技術が向上したのも確実に感じたので、そこも自信になりました」
たったひとつの勝利が、その人を今までとは違う人間に一瞬で変えてしまう。我々には決して理解することが出来ないであろう、研ぎ澄まされた世界がそこにはあるのだ。

池田選手にとっての日本記録は、一つの通過点であるのは間違いない。ならば、さらに早く走るためにはどのような意識変革が必要だと考えているのだろうか。
「僕の場合は、右半身に障がいが偏っているので、意識して強化していかないとかなりもったいない走り方になってしまうんですね。だから、トレーニングも右を集中的に鍛えられるよう組んでいます」
コンマ何秒で競い合う厳しい世界で戦うために、日常生活の中でも心掛けなくてはいけないことが多々あるはず。
「僕は普段、中京大で健常の方々と同じ陸上部に所属しながら練習をしているんですね。そこで僕がやることは、たとえばスタートダッシュなどでも、海外の選手と走っているイメージを持って練習することが可能なのです。そう言った意味では、かなりレベルの高い練習を、少し意識を変えただけで出来たりするんです」
自らが置かれている状況や環境を俯瞰することで、今やるべきことを合理的に見出す池田選手。確かに、質の高いイメージを持った練習は、高い費用をかけて海外遠征に行くよりも、確実に身になることは想像に難しくない。様々な苦労を乗り越えてきたらこそ、たどり着いた境地なのかもしれない。
義足の開発に関わり、成し遂げた進化

自分の足の代わりをこなす義足。ましてやレース用ともなると、細かなインプレッションや感触などがとても重要になってくるのは間違いないだろう。1/100秒を争う世界なら尚更だ。
「以前は、基本的に市販で売られている義足のアライメント(角度)などを調整して使用していました。しかし今回は、自分で履く義足の開発に関わらせていただけるということでしたので、走った時に感じた違和感や、もっとこうしたいという自分の意見をしっかりと持って伝えていかないなくてはと考え方が変わりました。
現在使用しているジェネシスの義足ももちろん気に入ってはいるのですが、開発に関わるという事はもっと僕自身も義足について知らなくてはいけないので、とにかく色々な種類の義足を履き、経験値を上げたいです」

「それに今は、100mのレースも400mのレースも同じ義足で勝負しているのですが、僕自身が義足に対しての知識をしっかりと持っていれば、将来的にはレースごとに義足を履き替えるというのも夢ではないと思います。特に去年のレースで失敗してしまった経験があるので」
確かにそうだ。選択肢が増えるという事は、レースごとに変わる環境に細かく対応出来るようになる。そうする事で、ポテンシャルを最大限に引き出す一つの要素として弱点を詰められるようになるのは、記録の更新やメダルに近づくための大きな役割となっていくのは明確である。
高い壁でもある、憧れのアスリートは?

「僕が勝手に意識しているだけですけど、佐藤圭太選手です。国内トップの座をずっと守り続けている人なので、やっぱり倒さなくてはいけないと思っています。もし、僕が圭太さんを抜かすような時が来たら、お互いの刺激にもなりますし、さらに二人が切磋琢磨することで、国内のレベルを上げることができたらいいなと思っています。
やはり、義足を使って走るという経験は、絶対的に圭太さんの方が上だと思っているので、まずそこの差を埋めなくてはいけませんね。ただ健足は僕の方が優れているとデータが出ているので、競技用の義足をつけたことで、それを無駄にしないように練習を進め、結果を残していきたいです。
それと先日、アメリカのジャリッド・ウォレス選手と一緒に練習する機会がありまして、その時に “もっと一歩目から義足を蹴っていけ” とありがたいアドバイスをいただきました。陸上のスタートっていうのは、レースの中でももの凄く集中力を要す大事な場面なので、そのアドバイスを完璧に自分の物に出来るまで突き詰めていき、佐藤選手に勝ちたいです!」
最後に、我々を含め陸上競技ファンが最も気になっている「9秒台は狙っているのか」と質問をぶつけてみた。
「もちろん出してみたいです!でも、それだけではなく、パラリンピックに出場している他の選手が9秒台で走るところも見てみたいし、もっと言えば、そのレースで一緒に走っていたいなというのはありますね。世界的なレベルの上がり方を見ていても、それはもう遠い未来の話ではないと感じています」
その誠実な笑顔の奥に、アスリートの証である熱い魂を確かに感じることができた今回のインタビュー。東京2020までとは言わず、池田選手にはその先まで全力で駆け抜け続けてもらいたい。