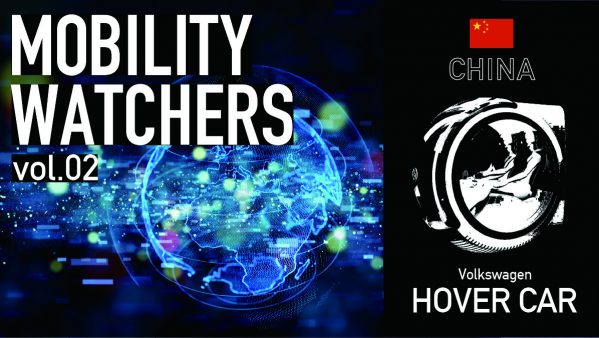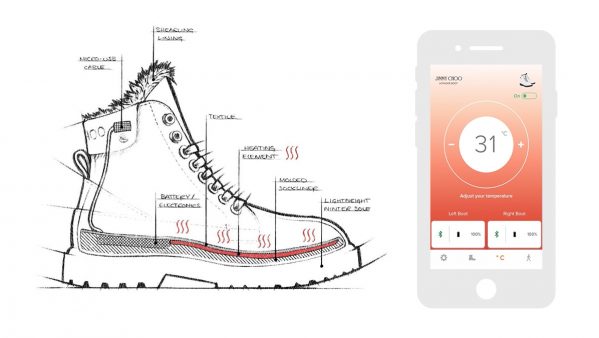2014年からスタートした最も新しい世界選手権シリーズのフォーミュラEはシーズン7 に突入している。カーボンニュートラル、脱炭素社会を目指すために世界各国が電気自動車(EV)の普及に躍起になっている。EVの普及が本当にカーボンニュートラルのベストソリューションかどうかは別として、EVの存在は、モータースポーツに新風を吹き込んだことは確かである。
スペインの実業家、アレハンドロ・アガグ氏が中心となり、国際自動車連盟とともにスタートさせたのがフォーミュラEである。既存のモータースポーツのイメージを一新させるアイデアを盛り込んで、世界中を転戦、開催地は首都や世界的に有名な観光地とした。2020年からはグローバルに広がったコロナ禍によって、そのコンセプトが必ずしも踏襲されてはいないが、それはモータースポーツに限らず、あらゆるイベントが規制されるという如何ともし難い状況なのである。モータースポーツ、特にサーキットモータースポーツは、専用のパーマネントサーキットで競技が行われる。広大な敷地に造られたサーキットは、人里離れていることが多い。しかし、フォーミュラEは、街中の公道を一時的に閉鎖、または、公園内の道路を使用した特設サーキットを利用する。観光地では海岸やハーバー近くの幹線道路を閉鎖することはあるけれど、各国の首都開催の場合は、ど真ん中で行うことは叶わず、ロンドンで開催された時には、テムズ川の河畔公園を利用した。ローマ開催もやや郊外だが、イタリアの古都ローマの雰囲気を感じられるサーキットを設定した。

市街地、それも首都で開催できるのはなぜか? その最大の理由は、排気音がしないからである。以前にも記したことがあるがEVはとてもシンプルなコンポーネンツで構成されている。モータースポーツの魅力でもある排気音(エキゾウストノート)がEVのフォーミュラEにはない。フォーミュラEは内燃機関のエンジンを持っていない。エンジンは、化石燃料を主体とした燃料をエンジンシリンダー内で燃焼させて動力を発生させる。しかし、フォーミュラEは、電気でモーターを回してそれを動力としているので、エンジンの燃焼時に発生する爆裂音が無いのである。“音”という魅力を削がれているが、市街地や観光地の目抜き通りでモータースポーツという非日常的なイベントが行われるという新たな魅力を生み出したのがフォーミュラEなのである。

フォーミュラEのマシンは、最高速度こそ280km/hに達するが、最大出力は270馬力(レース中)であり、レースの形態はタイムレースで45分+1周である。F1のように1,000馬力以上の怪物マシンが走り回るわけではないのだ。フォーミュラEはマシンのシャシーはワンメイク、統一されており、他のコンポーネンツがシンプルであるが故にハードウェアの差は少なく、車両にいたっては差がほとんどないと言って良い。またコースの幅員はモータースポーツ専用のパーマネントサーキットに比べて狭く、1周の距離も最大で3.5キロ程度なので接戦が演じられるという面白さがある。フォーミュラEのマシンパフォーマンスの現状とオーガニゼーションの思惑がマッチしているから特設サーキットで十分楽しめるイベントとして成立しているのだろう。
レーシングカーが公道に出たら即逮捕!?
日本と海外とのギャップ
市街地特設のサーキットをどう設営するかは、当然ながら国レベル、開催地の自治体レベルの理解と協力がなければ実現はできない。世界的な観光地における開催は、アトラクティブなイベントが加わるというメリットがあることは容易に理解できる。首都のような大都市での開催はどうだろう。一般社会へのEV促進のキャンペーンの思惑を持って参加している自動車メーカーの場合、系列のチームや中国系の新興EVメーカーの宣伝としては格好のイベントである。

さて、ここからはモータースポーツの文化と伝統には国によって格差があるという話になってしまう。動力は別として自動車が発明されたのはヨーロッパで、その自動車を使って競走したのは都市間レースが初めだった。サーキットが存在しなかったので当然公道でレースが開催されたのである。このような素養がヨーロッパにはあるから、公道レースに対するアレルギーみたいな拒否感は無いのであろう。ところが、日本は極端に異なる。
筆者は、都内、お台場で何年にもわたってモータースポーツイベントを開催したNPO法人の理事を務めている。そして、できることなら周辺の公道でレーシングカーを走らせたいと考えて、関係各所に折衝した。最後には、公道を使用する許可と、安全性を確保するために公安、警察とのやりとりが大変であることが身に染みた。所轄の警察署の担当者が了解してくれても本庁が許可してくれなくては走行が実現できない。われわれのNPOのイベントではなかったけれど、F1の日本グランプリの事前プロモーションとして、あるチームのスポンサーが東京浅草の目貫通りを走行するイベントを企画したが、警察からの許可が出なかった。スポンサーと企画会社は、山車にF1車両を乗せて仲店をお練りし、浅草寺の境内で走行することとした。その際に警察から通達されたことは、「一瞬でもF1車両が公道に下ろされたら、責任者を逮捕する」だったのである。

日本の公安関係は、前例が無いことに対する拒否反応が強い。モータースポーツに対する理解と歴史、伝統が理解してもらえていないのは残念である。日本のモータースポーツを統轄する省庁は、4輪レースが警察庁と国土交通省、2輪レースは文部科学省である。何故官庁が異なるのかは筆者も知らない。そして、両官庁共にモータースポーツは、“スポーツではなく、興行である”と認識していると知った。現在スポーツ庁が縦の組織に横串を入れ、そのスポーツ性を伝えてくれそうなので少しは安心し始めたところである。
物理的に開催できるかどうかではなく、精神的に、公道でレースを行うというコンセプトに対し賛成か反対かという点では欧米では賛成に挙手してくれる数は多いだろう。あとは、物理的にどうかである。

まず、コースの設定とともに付帯する施設を設けるだけの敷地の広さがあるかどうかだ。そして、国際自動車連盟の自動車レースの安全規則に則ったコース設定が必要である。公道の両脇、内周と外周にコンクリートバリアを設置。3キロのコースを作るのであれば、それだけのコンクリートブロックを用意しなければならないということが分かるだろう。さらにバリアの上には金網のキャッチフェンスが設備される。万が一マシン同士が接触して跳ね上がった場合にも、コース外に飛び出さないようにするためだ。主催者は少なくともこのような仮設施設を造ることができるだけの資力がなければ、開催へ漕ぎ着けることはできない。そして開催地の政府、自治体との連携は不可欠である。公道を閉鎖するわけであるから、交通規制を敷くために公安、警察の協力はどうしても仰がなければならない。また、フォーミュラEのイベントは短期間である。予選と決勝は、ワンデー。よって、設営と撤収も短期間に終えなければならない。それが実施できる機動力、大規模なイベントをコントロールできるだけのオーガニゼーションがベースになければ開催は不可能なのである。しかし、だからこそ、開催できる都市においてはメリットもある。開催できる都市が少ないということは、世界からの注目を集めるチャンスにもなる。果たして日本の都市はこれをどう捉えるか。モータースポーツを愛する者としては開催できる都市の出現に期待したい。
関連記事を読む