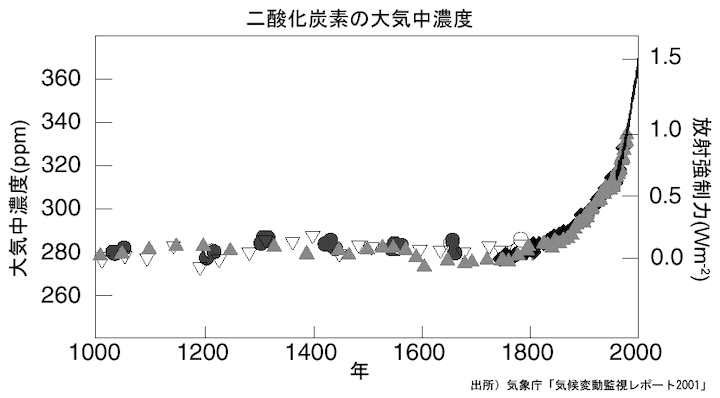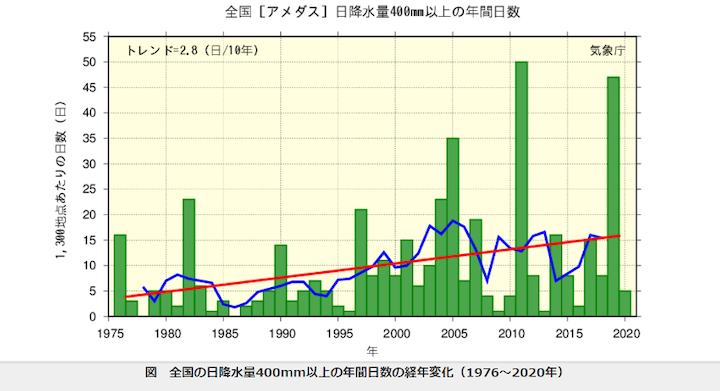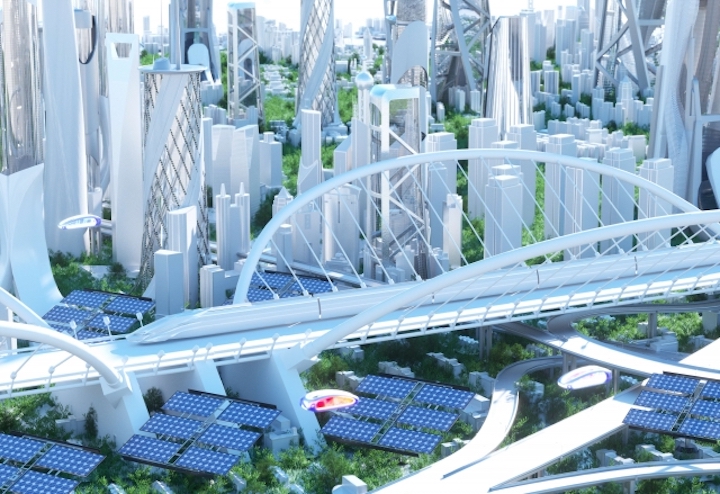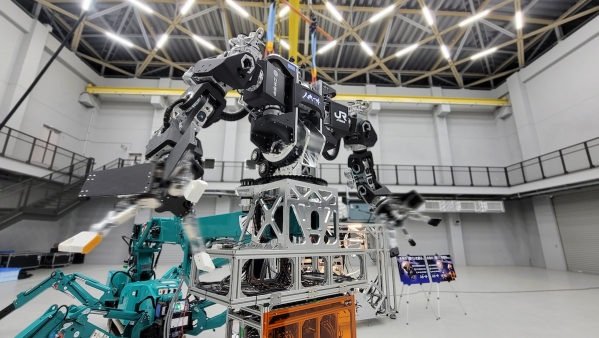コロナの影響で開催が危ぶまれる東京オリンピック。一流選手を間近で見られるというチャンスと共に、経済効果も注目を集めていた。オリンピックの中止は経済に対する打撃もあるため、安全か経済かという議論が沸き起こるのは当然だろう。実は、各国にもたらす経済効果としての視点で見ると、モータースポーツも同じことが言えるのではないか。今回は、そんな経済とスポーツ興行の関係性をモータースポーツジャーナリストの高橋二朗氏が解説する。
どれだけ知ってる?
モータースポーツ
誰もが知るF1を筆頭とする華やかなレースで人々を魅了するモータースポーツだが、その裏で繰り広げられる経済活動についてはあまり知られていないかもしれない。今回はそんなモータースポーツの裏側を紹介しよう。
まずはモータースポーツの説明から。ひとくちにモータースポーツといっても、いろいろなカテゴリーが存在する。モータースポーツのために造られたコースで行われるのがサーキットモータースポーツ。レースがその代表で、その最高峰が世界フォーミュラ・ワン選手権(F1)となっている。一方、専用に造られたコースだけでなく、公道と一部の特設コースを使って行われるのがラリーだ。こちらのトップレースが世界ラリー選手権(WRC)だ。そして、サーキットで距離の長い競技を行うのが世界耐久レース選手権(WEC)、有名どころだけでも三種類があるわけだ。
各々シリーズによって参加できる車両の規則が異なり、各シリーズは年間に複数の大会を催してそのトータルポイント(または有効ポイント制)で年間のチャンピオンを決定している。ワールドステイタスのシリーズ(世界選手権)では、グローバルに転戦、日本も開催地のひとつである。今年はF1の日本グランプリ(鈴鹿サーキット)、WECの日本大会 FUJI 6時間レース(富士スピードウエイ)、WRCの日本大会 Rally Japan(愛知県・岐阜県内)が予定されている。世界的なコロナ禍でも予定通りのイベントが行われることを祈るばかりだ。また、日本国内だけで完結する国内選手権もある。レースでは全日本SUPER FORMULA選手権、SUPER GT選手権。ラリーでは、全日本ラリー選手権をトップカテゴリーとしてこちらは日本各地で競技が行われている。F1は、グランプリ=GPという、その国でのトップイベントである名称が与えられている。各国名に「GP」が付けられるトップステイタスのレースは格式が高く、華やかで、煌びやかで他のシリーズとはグレードが違う扱いとなる。

当然、F1GPに参戦する車両も一流のものが集まる。モータースポーツの最高のテクノロジーを結集した車両は、参加チーム独自で製作したものでなくてはならないというルールがあるため、独自のファクトリーで製作されたシャシー(自動車の基本骨格)に、エンジンメーカーから供給されるエンジンを搭載しているという組み合わせでマシンは作り出されている。今シーズン7年ぶりに参戦する日本人ドライバー角田裕毅選手がハンドルを握るのは、イタリアに本拠を置くアルファタウリチームのマシンだ。シャシーには、日本のホンダエンジンが搭載されている。
ところで、一体このマシンはいくらくらいするのだろうか? 最高水準のレーシングマシン製作技術によって製作するマシンは金額で換算することが難しいと言われているのだが、F1に参戦しているチームの年間予算はトップチームで約600億円、下位チームでも約100億円を下らないと報じられる。これはチームの運営全体の予算額で、マシンの開発・製作費も当然この中に含まれている。とにかく膨大な軍資金がいることに違いはない。
ここで登場するのがスポンサーだ。各チームはこうした経費を賄うためにマシンのボディーにスポンサーのロゴを大きく露出させている。このため、F1マシンは“走る広告塔”とも言われるのだ。あまり知られていないことだが、スポンサーの中には金銭的なサポートと共に技術パートナーとして参画する企業もある。チームの年間予算が莫大であることや、スポンサー料、ドライバーの報酬など、やはりF1GPにうごめくお金は、他のシリーズとは桁が違う。
意外と知らないF1と経済の関係性

F1GPの運営は現在、『F1グループ』が行っていて、権利関係のマネジメントの全てを司っている。F1グループは、各国の主催者(日本は鈴鹿サーキット)から興行開催権料を支払ってもらい、F1GPシリーズの運営をし、各チーム・ドライバーへ利益分配を行なっている。
当然F1GP開催地への経済効果は大きなものとなる。全日本選手権レベルの大会の例を見ても、SUPER GTは、一大会で約1,000人の関係者が開催地に移動。その関係者の移動費、宿泊費、飲食費など地元に投下される金額、それに伴う税収入は、数日という短期間でも一つの産業並みとなる。つまり、モータースポーツは、転戦する産業という一面を持っているのだ。
サーキットは、観客の入場収入と大会のタイトルスポンサー、サブタイトルスポンサーからスポンサー料金を得ている。その対価としてスポンサーは、看板でのスポンサー名の露出、中継TVでの露出、その他の方法でスポンサーの存在を周知させる。関係者だけでなく、サーキットへの観客の移動費、宿泊費、飲食費などが発生するわけで、それが地元の税収入になるのだから、サーキットのみならず、その自治体も大規模なイベントの誘致を望むわけだ。F1GPがヨーロッパ大陸で転戦する場合には、自国の観客だけでなく隣接する国から国境を超えて観戦に来ることも期待できる。
そして長年モータースポーツの取材を続ける筆者も、モータースポーツの経済効果を痛感する出来事があった。2004年、日本初のWRCが北海道の帯広市を中心にして開催された(以後、2007年まで毎年開催)。筆者ももちろん取材で参加していた。開催から数年経て帯広を訪れた際に、WRC主催者からメディアに配布されたイベントのロゴ入りのバッグを肩にかけて駅前の駐車場に立ち寄ると、料金所の老人に声をかけられた。
「あなたは、ラリーの人か? もう一回ラリーを呼んでもらいたい。ラリーは帯広の商店、飲食店、うちみたいな駐車場を儲からせてくれた。もう一度お願いしたい」地元の方からの声は、モータースポーツがもたらす開催地への経済効果を証明していた。
短・長二つの経済効果とは
モータースポーツが開催されるサーキットのグランドスタンドの裏で展開される公式グッズ販売は、チームやドライバーの人気度によって売り上げが大きく左右される。ファンはご贔屓チーム・ドライバーのグッズを求めるのは当然だ。F1GP開催日のトータル売り上げは1店舗で数百万円を記録したということを聞いたが、その金額の数十倍、数百倍という規模で長期的な効果も生み出している。エンジン供給メーカー、ホンダは、創業間もなく、そのモータースポーツ活動によってホンダファンを生み出し、4輪・2輪のホンダオーナーを生み出している。この状況もいち自動車メーカーの利益だけでなく、開催国、開催地への利益供与と捉えても良いだろう。
近年、世界的な観光地がF1GPの開催誘致に積極的なのだが、先日2022年アメリカ・マイアミでの開催が発表された。原則として一国内の開催はひとつのGPだけ(1国1GP)だったのだが、イタリアのようにモンツァサーキットで行われるイタリアGPに加えて、サンマリノGPの名称でイモラサーキットにおいて開催される例もあった。今シーズンは第2戦としてエミリア・ロマーニャGPを同イモラサーキットで開催する。多額のF1GP開催権料をF1グループに支払っても利益が見込める故に、開催に名乗りを上げたのだ。F1GPの開催は、地元への経済効果を望むだけではなく、その国の経済発展、経済力を世界に示す役目も持っている。
1950年からスタートして現在に至るF1GPは、伝統的に開催をしてきた国々に新たな開催国を加えて、今シーズンは23戦を予定している。新たに加わった東欧の国はその存在感を世界に示し、また中近東の国々は、その経済力をアピールするためにF1GPを開催しているともいえる。小国ながら世界のセレブの憧れの地、モナコは、公道を一時的に閉鎖してレースを開催している。近代的なサーキットに比べて安全性は決して高いとは言えないモナコGPだが、これは伝統を重んじる一面をF1グループが継承しているがゆえだろう。アジアの小国、シンガポールでも海側の埋め立て地に広がる新市街の公道を用いて、ナイトレースを開催している。世界に放映されるテレビ中継の時間帯としても欧米に有利な時間帯で生中継できるナイトレースは、観光立国のシンガポールとして、経済効果でもダブルのメリットが期待できる。最終戦、第23戦の地、アブダビGPもナイトレースで開催される。こちらのダブルメリットはテレビの放映時間帯と夜間に気温が下がるという点だ。
オランダGPが今年復活する。1985年以来開催されていなかった同GPは2020年に行われる予定だったが、コロナ禍で延期を余儀なくされ、今シーズンの第13戦でカレンダーに組み込まれた。その裏には、世界チャンピオン最有力候補であるレッドブルチームのオランダ人ドライバー、マックス・フェルスタッペン選手の存在が大きい。オランダGPが開催されていなかった時には多くのオランダ人ファンがベルギーGPや、他のヨーロッパ大陸のサーキットへ詰めかけた。ホンダのエンジンを駆るレッドブルはホンダの供給最終年にオランダ人初のF1チャンピオンの可能性が高くなり、経済効果だけではなく、モータースポーツ好きの国民の高揚を狙っている。お国柄、日本とはその度合いは異なるが、角田選手とホンダの活躍による国内の経済効果は明確な数字には表れないが、有形無形の経済的な効果を生み出しているのは事実だ。
関連記事を読む
- F1ガスリー初優勝!アルファタウリ・ホンダ スポンサーキーアカウントマネージャーが話すスポーツビジネスの裏側
- 最速技術とモビリティの未来に向けてGO
- 空飛ぶタクシーも夢じゃない 官民一体となって進む「空飛ぶクルマ」の移動革命
- モビリティが本当に必要なのは誰? パーソナライズ化の鍵は汎用性にある