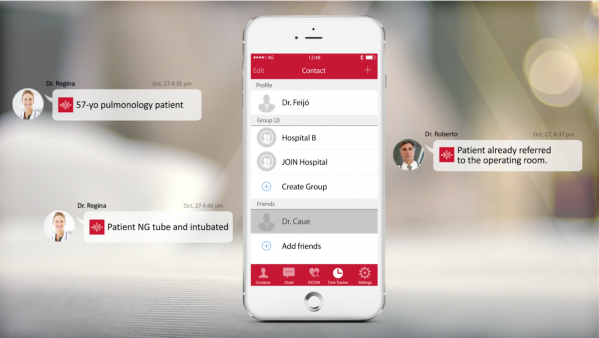最先端技術の結集とも言える車いすレーサーはパラスポーツフリーク、カーマニアからテック好き、更にはSFファンにとっても刺激的でわくわくする存在かもしれない。 国内企業が開発に挑んだ車いすレーサーの舞台裏に迫る記事を2本続けてお送りしよう。
翼のようなフレームでフィールドを駆け抜ける!
ホンダの新型車いすレーサー「翔」が誕生

【元記事URL】:http://hero-x.jp/article/6996/
軽量かつ高剛性のカーボンモノコックフレーム構造を世界で初めて採用したことで、パラスポーツ界に新しい風を巻き起こした車いすレーサー「極(きわみ)」のアップグレード版、その名も『翔(かける)』。
乗り心地や走行の安定性を向上、ステアリング周辺パーツがフレーム内部に埋め込まれるなど、レーサー本体のバージョンアップはもちろんのこと、車いすレーサーを漕ぐ力の見える化で、アスリートへのフィードバックを提供したり、非破壊検査をレース現場で実施したりと、ホンダが多角的なアプローチで車いす陸上競技に注力していることがうかがい知れる。
車いすアスリートのレジェンドが惚れ込んだ、
最速マシン開発チーム【八千代工業:未来創造メーカー】

「極(きわみ)」2018年取材当時のモデル
【元記事URL】:http://hero-x.jp/article/3046/
ホンダ太陽株式会社、株式会社本田技術研究所とともに車いすレーサーを開発する八千代工業。
「極(きわみ)」の超軽量カーボンホイールを実現するにあたって、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)という素材に目をつけた狙いや開発の過程を具体的に追う。
車いすマラソン女子の第一人者でもある土田和歌子選手が成し遂げた偉業に始まり、米国やスイス、南アフリカなど、“最速” を求める海外選手からの支持も熱い。
部品事業では海外を中心とした事業拡大の推進に尽力するかたわら、ものづくりへのこだわりには矜持が感じられる。
次世代モデルは一体どのような変化、進化を遂げるのだろうか? まだまだ目が離せない存在だ。