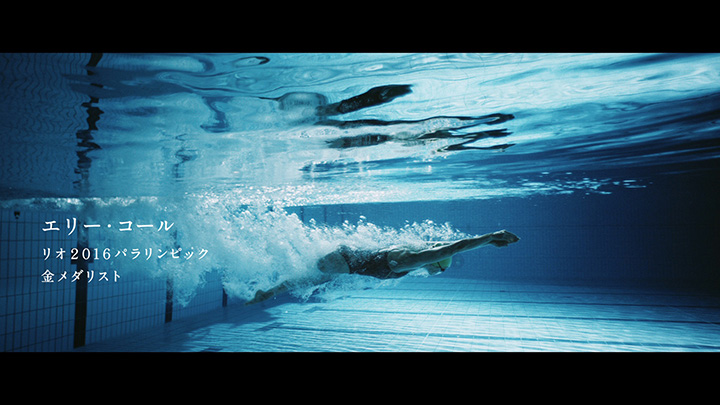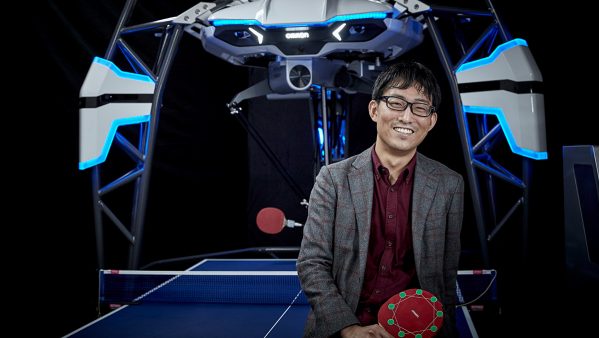昨年、桐生祥秀選手が叩き出した日本人初の9秒台や、つい先日アジアパラ大会男子陸上100mでアジア新記録をマークした井谷俊介選手など、何かと盛り上がりを見せている男子陸上であるが、女子陸上界にも虎視眈々と自らに課せた使命を果たすべく、東京2020で表彰台を狙うひとりのパラアスリートが髙桑早生選手 (以下、髙桑選手) である。
記録よりも、表彰台に上がることに重きを置く練習
 ロンドンパラリンピック陸上100m、200m入賞。パラアスリート2014年アジアパラリンピック陸上100mでは銅メダルと輝かしい記録を残し、現在、NTT東日本シンボルチーム個別認定選手として活躍する髙桑選手。高校2年の時から二人三脚で歩んできている高野大樹コーチ(慶應義塾大学体育会競走部短距離コーチ)とともに、フィジカルとマインドを含めた勝つためのトレーニングを常に突き詰めている。
ロンドンパラリンピック陸上100m、200m入賞。パラアスリート2014年アジアパラリンピック陸上100mでは銅メダルと輝かしい記録を残し、現在、NTT東日本シンボルチーム個別認定選手として活躍する髙桑選手。高校2年の時から二人三脚で歩んできている高野大樹コーチ(慶應義塾大学体育会競走部短距離コーチ)とともに、フィジカルとマインドを含めた勝つためのトレーニングを常に突き詰めている。
そして今回、髙桑選手のホームグラウンドである慶應義塾大学日吉キャンパスの陸上競技場に足を運び、練習の様子を拝見させていただいた。なかでも気になったのは、スターティングブロックから中間疾走にかけての局面を抽出したトレーニング。
「スターティングブロック蹴ってから最初に接地する足が義足の方なので、すごく不安があるんですね。競技用の義足の接地面って、ほんと点くらいしかないので、いい意味で力を抜き、加速できるような動きを得るためにブロックをしっかりと蹴ることが必要となってきます。そこでいかに勢いよくスタートを切り、かついいポジションに義足を着けるかが、レースの出来を左右するスタートには重要なんです」
短距離走ではスタート、すなわちはじめの一歩が勝敗を分ける大きな要素となる。その一歩目を点で捉えていくということは、精神的にも落ち着きが必要なはず。
「その必要があるからこそ、鳴ってから一歩目を出す感覚に関しては、自分の中に刷り込ませて自動的に出てくるものにしなくてはなりません。いかにそこで次の一歩に繋げられるかが大事になってくるので」


高野大樹コーチと、一本走るごとに丁寧なセッションが交わされている。
100m、200mだけではなく走り幅飛びの選手としても好成績を残し続けている髙桑選手が行っているであろう、特殊なトレーニングも気になるところ。
「義足がたわむ感覚が分からなくなった時とかに、縄跳びやけんけんをやります。特殊かと言われるとそうでもないかもしれませんが、義足を扱うという事をすごく重要視して、トレーニングに組み込むことは多いですね。

走り幅跳びの練習中に、黙々と義足の感覚をけんけんで確認する髙桑選手。
「それに私は、パラリンピックでメダルを獲る選手達と比べると、体格や筋力的にもまだまだ足りてないと自分では思っていて、実は勝つために強く出来ることだらけなんです(笑)。ですから通常のトレーニングでも、かなり吸収していけるのではないかと。とはいえ、それなりにキャリアを重ねてきて、昔ほど疲労に対しての回復力が良くなかったりするので、今まではあまり得意でなかった食事制限なども心掛けています」

アスリートとして、長所を伸ばし弱点を克服するためには、時に自らを俯瞰視することも必要となってくる。髙桑選手は自身のアスリートとしての特徴をどのように捉えているのだろうか。
「まず自分で思う長所は、よくも悪くも楽観的なことです。たとえば、なんだか今日は調子良くないなと思ったら、けっこう練習を抜いたりできるタイプなんです。いまここで無理に走り、悩んだり考えすぎてもしょうがないなと思った時には、手を抜いて練習したりします。それは、サボるとは違うぞって信じています(笑)。
逆に短所は、練習に弱いところですかね(笑)。本番に強いって言われがちだし、自分でもそれなりに結果を出してきたんですけど、練習だといまいち力が出せなかったりするんです。おそらく気持ちの面だと思うんですが」
本番が近づいてきた時に、練習でうまくいっていなかったことが不安要素となり、気持ちが揺れたりはしないのだろうか。
「それはなります。でも、そこで楽観的スイッチが入り、なんとかなるんじゃないかって思考が働きます」
なるほど。世界で戦うレベルのメンタルの強さをも持ち合わせているということなのだろう。緊張感をパフォーマンスに変えるのも、選手である以上それも技術といえる。そして、その緊張感は誰にでも味わえるものでもはないものだと、髙桑選手は話してくれた。東京2020に向けての目標はいかに。
「出場するからには表彰台を目指し、メダル獲得です。記録っていつ出してもいいものだと思っていて。でも東京2020のメダルは、地元開催の上、全く同じ条件下での一番なんですよ。そこにすごく価値を感じていますし、特別な大会ほど記録より順位にこだわります」
そんな強い意志を持つ髙桑選手も、一人の女性であるのは間違いない。普段見せることのない彼女の日常も垣間見てみたいと思った。
スポーツにも共通する刹那的な時間が魅力

「劇場に舞台を観に行くのが大好きなんです。とくにミュージカル! 舞台ってスポーツと一緒で、その一回しかないものだと思っていて、同じ演目の同じセリフであっても、全く同じものって絶対にないというか無理。その儚さにすごく惹かれてしまうんです。それと、あの空間に入った瞬間、非現実的な世界に行ける不思議な感じも魅力です。しかも基本ひとりで行くんです(笑)。演劇や映画はひとりで十分じゃないですか。でも食事くらいは誰かと食べに行ってもいいのかな…」
一瞬にかける世界で勝負をしているゆえに感じる繊細な刻の感覚。その研ぎ澄まされた神経を癒すのに、女性としてもうひとつ趣味としているものがあるという。
「ここ数年はスキンケアも趣味なんです。もともと肌は強い方なんですけど、そこに少しだけ手を掛けてあげるとどんどん良くなっていく感じにはまりました(笑)。特に陸上競技は外で行うスポーツなので、どうしても陽に当たっている時間が長いから、いかに肌を回復させるかというところで日々頑張っています」

そして最後に東京2020で注目している選手を尋ねてみた。
「オリンピックに関しては、同級生でもある陸上短距離選手の山縣亮太選手です。ずっと同じ環境でトレーニングをしてきたんですけど、今も順調に伸びていますし、これから男子陸上の短距離界を担う存在として、どこまで彼が行くのかすごく楽しみです。
あとは、東京2020から新種目となるサーフィンの大村奈央選手。私も陸上競技が大好きですけど、彼女ほど、海が好き、波に乗るのが好きという純粋な気持ちで競技をやっている人はそういないかなって思っています。私自身、海に対して別世界というか、憧れを抱いている感覚があるので、そこでスポーツをやっているのがすごく遠い世界で楽しんでいる感じがして(笑)。彼女も同い年なので、ぜひ表彰台に立って、笑顔でいるところを見たいと思っています。
パラリンピックでは、選手というよりか、男女ともにトップ選手として活躍している車いすテニスのアベック優勝に期待しています!」
しっかりと見据えている東京2020では、必ずや表彰台の一番高いところから、選ばれた者しか目にすることのできない景色を見ているはず。「髙桑早生」その時までこの名前を忘れないでほしい。

髙桑早生(NTT東日本)
陸上競技【T64(下肢切断)クラス】選手
1992年5月26日生、埼玉県出身26歳
中学生の時に骨肉腫で左下腿を切断。義足となり、高校から本格的に陸上競技を始める。2012年ロンドンパラリンピック100m7位入賞、200m7位入賞。2016年リオデジャネイロパラリンピック100m8位入賞、200m7位入賞、走幅跳5位入賞。3大会目となる東京2020パラリンピックではメダル獲得を狙う。片下腿義足クラス(2017年までT44)女子100m日本記録&アジア記録保持者(13″43)、女子200mアジア記録保持者(28″77)