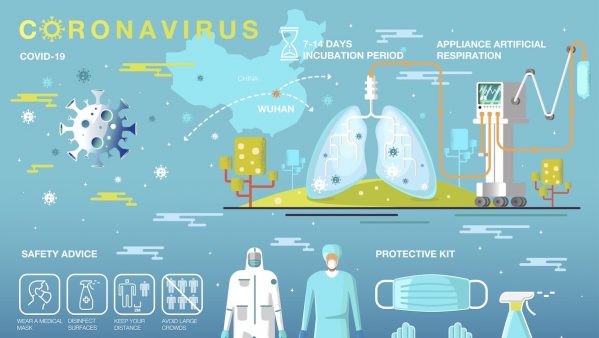セサミンEXをはじめとするさまざま健康食品を開発してきたサントリーウエルネス株式会社。健康寿命やQOL(Quality of Life)向上が叫ばれて久しい日本だが、健康やQOL向上は、目には見えない感覚的なものも多いだろう。こうした感覚的なものの可視化は健康、QOLの向上に繋がりうるのか。高齢化社会を迎えた日本で、人々の健康に基軸をおいてきたサントリーウエルネス代表取締役社長の沖中直人氏にDXというキーワードで編集長・杉原行里が迫る。
「老化を科学する」ことに着目
杉原:サプリメントなどさまざまな健康食品を開発されているサントリーウエルネスさんの設立の経緯をお聞かせください。
沖中:サントリーは自然の恵みを、我々の加工技術を使って豊かでおいしい飲み物に変換し、お客さまの生活文化を創造していくというところから始まった会社です。創業者の鳥井信治郎が最初につくったヒット商品「赤玉ポートワイン」は、当時の医学博士から薬洋酒いうことで推奨してもらいました。創業当初から美味健康という文脈の流れがあり、1973年には新しい社是「人間の生命の輝きをめざし 若者の勇気に満ちて 価値のフロンティアに挑戦しよう 日日あらたな心 グローバルな探索 積極果敢な行動」が生まれました。
杉原:素敵な社是ですね。
沖中:はい。同じ年に中央研究所というものをつくり、自然の恵みをサイエンスして、人々の健康に役立つ素材や成分の研究が始まっています。その成果としていろいろな素材が生まれ、90年代の終わりには健康商品事業をスタートさせました。そのときからセサミンもありましたが、なかなか軌道に乗らず、思い切って、ダイレクトマーケティングに切り替えようということで、いまから20年くらい前にサントリーウエルネスが設立されました。

杉原:これまでの研究開発のなかで生まれてきた素材や成分を生かして、とくに健康寿命といったものを考えたビジネスにしているのですね。
沖中:そうです。「老化を科学する」という着眼点と、「自然由来の素材や成分で健康維持をサポートする商品を提供する」という2つの概念がユニークだったのだと思います。
杉原:僕、非常に思うのは、寿命と健康寿命というものが乖離しているということです。寝たきりの10年や、歩けなくなってからの10年というのは、本当の意味で健康であるのかないのかという議論が世界中で行われていると思います。そんななか御社は、セサミンEXをはじめとする商品を提供し、健康寿命を延ばしていくという企業なのでしょうか。
沖中:そうですね。「老化を科学する」ということが象徴するように、健康寿命を延ばしていこうというのがそもそもの出発点です。ただ、これから10年くらいの間に、日本は認知症が大きな社会問題になってくるのではないかと危惧しています。
杉原:間違いないと思います。
老化を科学し、一人ひとりの人生に
寄り添う商品やサービス開発を進める
沖中:体がすべて健康と言えなくても、人間は、最後はこころがアクティブで豊かな状態であれば幸福感を感じることができるのではないかと思います。ですから、体の健康ばかりでなく、こころの健康を含めて、「人生100年時代に最後まで寄り添っていくような会社になっていく」というのが、私の挑戦です。
杉原:そうすると、未病がキーになりますか。
沖中:サプリメントに関してはそうですね。私たちが飲料や酒類の酸化を抑える成分の代表格であるポリフェノール研究をしている中で、「品質維持に作用するなら、人間の健康維持にも効果があるのでは?」と、そのような視点から「老化を科学する」研究が始まりました。
杉原:老化というのは、どのへんを指されるのですか。脳、あるいはこころですか。
沖中:体ですね。40代になると30代までのような無理が効かなくなる。これはもう老化のあらわれではないかと思います。
杉原:老化は数字として可視化されていないじゃないですか。僕はいま38歳ですが、よく40代から変わってくると言われて、何が変わるのかを自分で人体実験しようかなと思っているんです。そのときに何を計測して、何が指標になっていくのかなということに興味があります。老化を科学していくなかで、老化は可視化されるものなのでしょうか。
沖中:いろんなものが可視化されていくでしょうね。私たちは可視化されたデータも活用し、様々な商品やサービスを開発し生涯にわたってお客さま一人ひとりの元気を応援する伴走者になりたいと思っています。

杉原:認知症に関してですが、いま僕らは追尾型のロボットや最適な座位をコーチングするロボットSS01(http://hero-x.jp/article/7870/)をつくっていて、僕は超高齢者社会が価値に変わっていくと考えています。2025年には先進国で初めて人口の30.3%が65歳以上になる。そういう最大の実証フィールドを手に入れられるので、そこから生まれるプロダクトやサービスは輸出していけると思います。
サントリーウエルネスさんは、今後はお客さまの解像度を上げていくとのことですが、具体的に解像度を上げるとは、どういうことを指されているのですか。
DXはあくまでも手段
ゴールを見つけることこそが重要
沖中:これはシンプルで、お客さまのこころのなかにある不安とか不便とか不満を、ちゃんと理解することですね。私たちは、シニアのお客さまのお困り事というものを観察して、洞察して、そこに寄り添いながらサービスを提供していきたいと考えています。
例えばですが、シンプルに言って、杉原さんは75歳以上の方のこころの悩みってわかりますか。
杉原:想像はしますが、難しいですね、まだ経験していませんので(笑)。
沖中:そうですよね。私は先日行われたイノベーションガーデンのイベントで、慶應義塾大学の宮田裕章氏と話したなかでも「DXは手段」ということを言い続けていたのですが、ゴールさえわかれば、手段はそこに結びつければいいと考えています。
杉原:そこはまさにそのとおりだと思います。
沖中:私から見ると、世の中のDXを叫んでいる人の多くは、手段から入っているのではないかと感じます。もしくは、自分のまわりの不都合なことがわかっているから、それをDXで解決しようとする。でもDXが全てを解決してくれるわけではない。私たちのサービスでは、顧客から直接話しを聞くコールセンターがありますが、今回のパンデミックで多くの声が寄せられました。そこで改めてシニアの方のこころの動きがわかったのです。
そこがわかれば手段は後から考えればいいと思うんです。解像度を高めずして手段に走るなかれということです。
DXは未来を変えられるのか?
杉原:それでは、サントリーウエルネスさんが考えているゴールというのは、こころに抱えている問題を、デジタルではなくて、人間として理解していくコミュニティを再形成していくことですか。
沖中:コミュニティがつくれるかどうかはまた別の話で、まず、こんなに多くの人が長く生きるということは、ホモサピエンス史上初めてだと思います。そして、人間のこころがおざなりになっている現実がある。そこを1回飲み込んで、消化して、そのうえで自分たちにできることをしていこうと。そのときにはサプリメントというもので信頼関係を築いたら、やっぱり最後はこころなのではないか。サントリー2代目社長の佐治敬三は、公害問題がたくさん起きていて、オイルショックもあった1973年に、「これからはこころの時代が来る」と言っているんです。すごい先見の明だと思います。

杉原:なるほど、理解しました。
それではDXというか手段については、御社の独自の開発でいくのか、あるいはさまざまな企業が開発していくなかでプラットフォームになる可能性もあるということですか。
沖中:いろんな人が遠くから見たときに、結果としてそのように見えるようになるかもしれない。でも、プラットフォーマーを目指すとか目指さないとかではなくて、私たちで出来ることはやり、手の届かない部分は誰かと協力し合ってやるということです。
個人的な価値観の違いだと思ったのですが、すべてのものをデータにする、「世の中で起きていることを因数分解して数学的に解釈していくということ」、それは人間が科学というものを見つけて以来、突き進んできた道だと思います。しかし、私はそこまですべて数学的に解析しなくてもいいのでは、と思うことがあるんです。無駄があってもいいと思っています。データの解析で突き進んでいった先に、本当に幸せがあるのだろうかと思います。
杉原:哲学的ですね。
沖中:すべてが計算され尽くした人生よりも余白のある人生の方が面白いと思います。
杉原:それはまったく同感です。
沖中:データとかDXというものは、どれくらいの余白のバランスでやるかということが大切なようにも思います。
杉原:僕らがいちばんクリアしていかなければいけない問題はテクノロジーだけではないんですよ。人の心を理解することだと思ってます。僕らが今研究を進めている歩行解析ロボットなんて、仮にロボットが「あなた、転びますよ」なんて言われても、そのコミュニケーションは成立しにくい。僕らが大事にしなければいけないのは、その人の背景を理解して、どのようにコミュニケーションをとればいいのかということなのです。
沖中:私は、人は自分が生きて経験した以上のことは、なかなかわからないのではないか?と思っていて、だからこそいろいろな経験をすることが重要になってきます。見て感じることが大事で、その意味では高齢者のことを理解することはものすごく難しい。だからそれをやり続けていかないと、わかった気になっているだけでお客さまに喜んでもらうことはできないのではないかと思います。DXによってシニアはみんなキラキラしたアクティブシニアになれるように言う人がいたら「それホントか?」と、いい意味で疑問を持ち、それを徹底的に掘り上げて考えていくことが、DXの1丁目1番地なのではないでしょうか。
沖中直人(おきなか・なおと)
1991年 慶應義塾大学法学部政治学科卒業、サントリー(株)(※現サントリーホールディングス(株))入社、資材部へと配属となり主に包装容器の調達を担当。1996年食品事業部へ異動し清涼飲料事業、商品開発・ブランドマネジメント業務に従事。「伊右衛門」の開発でチームリーダーを務め、大ヒット&ロングセラー化実現の立役者となる。2010年サントリー食品インターナショナル(株)食品事業部部長を経て、2015年執行役員 ブランド開発第一事業部長に、2019年常務執行役員 ジャパン事業本部戦略企画本部長、ジャパン事業本部コミュニケーション本部長に就任。無糖茶カテゴリー(伊右衛門・サントリー烏龍茶)、水カテゴリー(サントリー天然水、輸入水ブランド)、機能性カテゴリー(グリーンダカラ、ビタミンウォーター)、トクホカテゴリー(黒烏龍茶、胡麻麦茶)、SBF国内の商品開発企画業務に携わった。
2020年1月、サントリーウエルネス(株)代表取締役社長へ就任、現職。
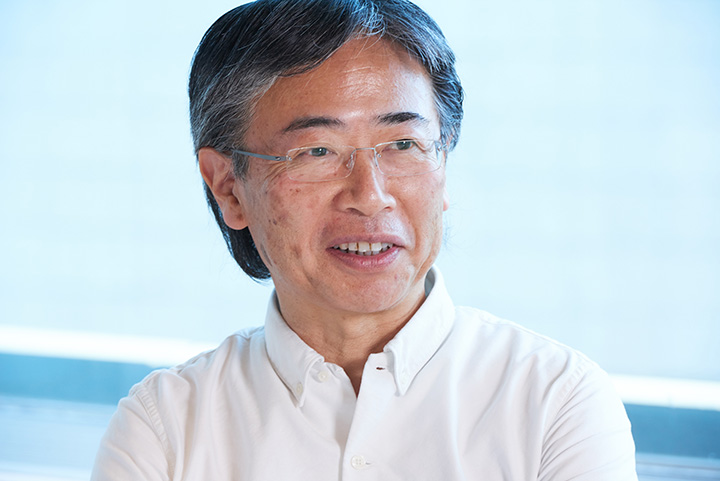 杉原行里(以下、杉原):僕が中邑教授のやられている「ROCKET」というプロジェクトに興味を持ったきっかけは、昨年開催されたサイバスロン(http://hero-x.jp/article/1224/)の会場でメディアに追っかけられている子どもたちが目に止まり、あの子たちなんだろうって気になったのが始まりなんです。
杉原行里(以下、杉原):僕が中邑教授のやられている「ROCKET」というプロジェクトに興味を持ったきっかけは、昨年開催されたサイバスロン(http://hero-x.jp/article/1224/)の会場でメディアに追っかけられている子どもたちが目に止まり、あの子たちなんだろうって気になったのが始まりなんです。 公平や平均が良しとされる世の中に一石を投じる
公平や平均が良しとされる世の中に一石を投じる