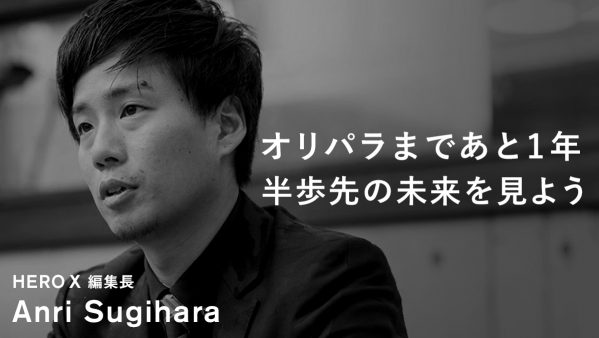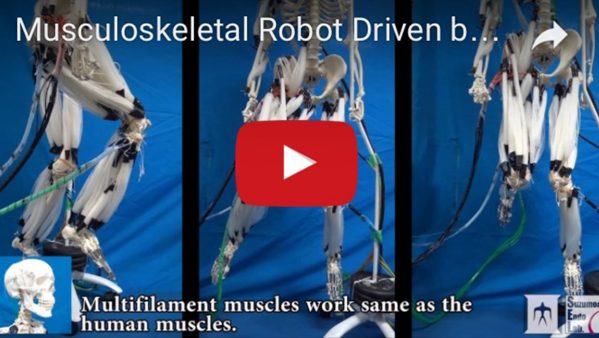世界のCare Design Classificationsランキングが発表になった。1位を受賞したのはJulien Codet氏。車いすのデザインが評価されてのランクインとなったのだ。2位には、光栄なことに、私の名前が書かれている。ケアデザイン部門には、様々なプロダクトがある中で、車いすが1位、2位を獲ったことを興味深く感じる。
Julienが所属するのは、アメリカにあるインバケア社。車いすメーカーとして、世界的に有名な会社だ。そんなインバケアに籍を置く彼が作り上げたのは、肥満の人向けの車いすだった。2019年、アメリカのハーバード公衆衛生大学院の研究チームは、このままいけば、10年後には国民の50%が「肥満」と判定されると警告を出している。肥満はただ太っているというだけではなく、糖尿病など、様々な疾病に繋がるリスクがあるため、肥満の解消について、アメリカでは各分野の専門家による研究も進められている。そんな中、開発されたのが、この車いすだった。
体重が増えすぎた体は、自重に耐えられず、歩くことすらできなくなることもある。しかし、動かないことが悪循環になるということは、誰でも想像がつくことだろう。Julienが考えたのは、外出が難しくなってしまった肥満の人が車いすに乗ることで、外出の機会を増やそうというものだった。自宅のベッドで寝たきりの生活を送るよりも、リハビリのために外へと出る。肥満解消の第一歩を、そこからはじめてもらおうという気持ちだったのだろう。説明には「太り過ぎた人たちの自信と自尊心を取り戻す」と書かれていた。
対肥満患者を対象としたこの車いすは、耐荷重なんと300キログラム。これだけの重さに耐えられる車いすにするためには、相当の努力がいる。耐荷重を重くするためには普通、支えるものの重量も重くせざるをえない。ところが、このインバケアの車いすは、300キログラムの耐荷重を実現しつつも、車体を軽くする工夫が凝らされているのだ。加えて、折りたたみ方にも特徴がある。従来、横折りになるものがほとんどのところ、まるでパイプ椅子のように、縦方向に折りたたむことができるのだ。
利用者の心を動かす優れたデザイン性と利便性、そして、対象とするユーザーを絞り込んでいるという点が、実に面白い。私が手がけている車いすも、対象とするユーザーを絞っている。車いすユーザーと一括りにされがちだが、ユーザーの状況は千差万別だからだ。今、私の率いる会社RDSがターゲットとして考えるのは、アクティブなユーザーだ。
仕事も遊びも健常者と変わらずに行える人々。僕の考えでは、車いすは、洋服と変わらない、外出する時には必ず身につけるものなのだが、これまでファッション性を追求したものはあまり見当たらなかった。
車いすユーザーがそれほど多くないということも、デザイン性の高い車いすが発展しなかった要因だろうが、これからの日本は違う。超高齢化社会を迎えている日本では、車いすユーザーは増えると予測されている。今は健常である自分も、いつなん時、車いすのお世話になるか分からない。自分事化して考える時、はたして、既存の車いすで自分は満足するだろうか。私の答えはNO。だからこそ、ファッション・デザイン性の高い車いすを目指して開発をしている。
日本の保険は素晴らしくて、私たちはいつでも医療を受けられるという恩恵を受けている。だが、平等という名のもとに、押し殺している心もある。車いすの購入には補助金が出る制度などがあるため、なんとかその範囲内で収めたいという人もいるだろう。しかし、考えてみてほしい。もしも、車だったらどうだろうか。車を選ぶ時、「動けばなんでもいい」と考える人は少ないだろう。同じデザインの車しか走っていない、そんな街をあなたは想像できるだろうか。かっこいいスポーツカーもあれば、小回り重視のコンパクトカーもある。デザイン、性能などいろいろ吟味して、自分が乗りたいと思う車を人は手に入れるはずだ。たとえ、レンタカーだとしても、どんな車に乗りたいかで選ぶのではなかろうか。足にハンディを負った人にとって、車いすとはモビリティである。日常に欠かせない乗り物であり、自分を自由に移動させてくれる相棒のような存在だ。そこで、考えてみよう。「カッコイイ車いすに乗りたい」 そんな色気を出すことは、果たして贅沢なのか。
そしていつの日か、誰もが乗りたいと思うモビリティー化する未来が待ち遠しい。
「ここまでだ」と諦めずにすむ世の中を、読者と共に作っていきたい。
(トップ画像引用元:https://competition.adesignaward.com/gooddesign.php?ID=76707)
関連記事を読む