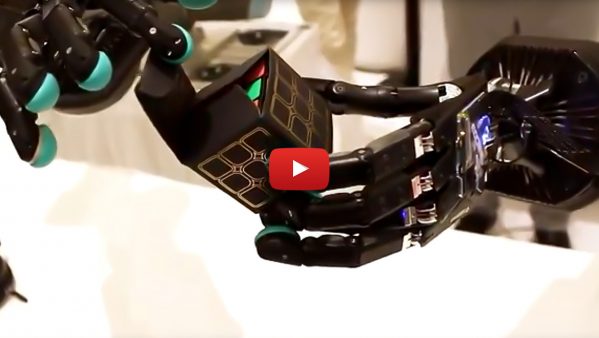先日お台場特設会場にて行われた CHIMERA GAMES Vo.7。その前夜祭イベントとして、米カリフォルニア州の MEGABOTS (メガボッツ)社の巨大ロボット、アイアン・グローリーがお披露目された。今回は日本にメガボッツをもたらした張本人、三笠製作所代表の石田繁樹氏と本誌編集長であり RDS代表の杉原行里との対談をお届けする。
―おふたりの出会いは、どのようなものだったのでしょう?
石田「初めて出会ったのはドイツのシュトゥットガルトでした。私の会社では制御盤を取り扱っていて、ドイツに支社があるのです。お互い製造業だから、話が合うだろうと、共通の知人を通じて会食したことがきっかけでしたね」
杉原「当時まだ僕は30歳になる前で、石田さんは先輩ですが、共通の趣味であるサッカーの話で盛り上がり、それ以来長い付き合いになります。いつかロボットの分野で何か一緒にやりたいですね、という話をしていましたが、ようやく今回それが現実のものとなりました。日本人にとってロボットは、アニメで慣れ親しんできた身近な存在。実際に操縦できる巨大ロボットを、多くの人に間近で見て、触れてもらえる機会を作ってみようと」
石田「パズルの足りないピースが埋まっていったというか、点と点が線になって、メガボッツの事業が共同出資という形で実現したのです。今回は1年間という期限付きのプロジェクトなのですが、単にロボットを持ってきて “どうだ!” というだけではなく、ロボットに触れた人たちがどんな反応をするのか、実地マーケティングの意味合いもあります」

石田繁樹
1972年、愛知県生まれ。名古屋の本社を含めた国内の支社と海外支社を持つ、制御盤の会社である三笠製作所の代表取締役。堀江貴文氏と共同開発した自動配達ロボット Hakobot や、ドバイ警察で導入されている移動式交番の開発と納入、eスポーツ選手の支援や普及のための事業団チーム KYANOS(キュアノス)の活動でも知られる。
―メガボッツ社が行ったロボットファイト(DUEL=デュエルと呼ばれる)の動画が、SNS を通じて多くのロボットファンの間で話題になっていましたね。
杉原「もちろん、デュエルはロボットを使ったエンターテイメントのひとつとしてアリだと思います。でも、戦うロボットにはどうしても軍事利用というイメージがつきまとってしまう。だからこそ、そうしたネガティブな面を一切出さずに、新しい切り口を見出したいのです。例えば、ボクシングのように、ルールがあるスポーツに置き換えてみたら面白いかもしれないと」
石田「ロボットが殴り合う姿を見るのは、確かにエキサイティングですよね。その反面、ボロボロになっていく姿を見るのは、生みの親である開発者としては悲しいですけどね(笑)」

ブースからキャタピラーで移動して、その動作を披露したアイアン・グローリー。往年のアニメファンの男性からは、サブングルやボトムズの名が挙がった。予想以上に、多くの女性がこの巨大ロボットに興味を持って、近づいていたのも印象的だった。
―日本初披露の舞台が CHIMERA GAMES だったのは、そういう理由があったのですね。
石田「テクノロジー系の展示会にこのロボットを持ってきたとしても、反応は薄いと思うのです。CHIMERA GAMES という、アーバンスポーツの祭典にロボットを持ってきたことに意味があるのです。もちろん、日本でも巨大ロボットは、これまでにいくつか作られています。でも、ロボットを作ること自体がゴールになってしまっていて、その先がない。だからこそ、自分たちが “ロボットを使ってこういうことができるのでは” という仮説を立て、それが正しかったかどうかを実証したいのです」
杉原「今後はロボット・パイロットという、子どもたちが憧れる新しい職業が生まれるでしょうね。メガボッツをきっかけにして、アジア中にいるロボット好きとつながって、新しい取り組みが始められるかもしれません。現時点で僕らが思い描いているひとつの試みは、ロボットによるスポーツ競技や遠隔操作による eスポーツですが、もちろん違ったアイデアがあってもいい。むしろ自分たちよりも若い世代や、これからの大人になる子ども達がロボットについて考えるきっかけになればいいなと思います」
―例えば、ロボットに仕事を奪われるのではないか……。そんな不安を持つ方も少なくないのではないでしょうか?
石田「だからこそ、ロボットが共存する未来が楽しいものだということを、我々が提示しなければならない。ロボットがあることで、新しいレクリエーションや新しいマーケットが生まれるはずだし、そこで得たものからさらなるイノベーションが生まれる可能性だってあります」
杉原「今回アイアン・グローリーを日本に持ってきた目的は大きく分けて2つあります。ひとつ目が、先ほどから話しているきっかけ作りであり、人々の反応を見てみたかったこと。ふたつ目は、エンジニアリングの面から見て、人のために役立つロボットとして何ができるのかを探ることです」

記者発表会時に乾杯の音頭を取る、MEGABOTS社代表のマット氏と杉原。会場には多くのマスコミや関係者が訪れ、注目度の高さをうかがわせた。この頃、短時間ではあるがパネルディスカッションも行われ、各人それぞれのロボットがある未来について話が及んだ。
石田「皆が嫌がるような仕事を、ロボットを使ったエンターテイメントにすることができるかもしれません。例えば、炎天下の草刈りは誰にとっても辛いものですが、遠隔操作したロボットで誰が一番早くきれいに草刈りできるか、というゲームにする。給与ではなく賞金を付ければ、エントリーする人がたくさん出てくるはず。そうなれば、安い人件費を求めて海外実習生を呼び寄せるということも少なくなり、結果として社会問題の解決にロボットが寄与できるかもしれません」
杉原「確かに石田さんのおっしゃる通りですね。そんな風に、物事を違う角度から見ることで、楽しいものにもなるし、辛いものにもなる。だからこそ、ロボットは大きな可能性があるコンテンツなんです。“このロボットはこういう使い方をするのです” と限定するのではなく、何に使うのかわからない余白の部分にこそ、人をワクワクさせる新しい技術があるはず」
今回のお披露目と試乗体験を皮切りに、いくつかのイベントも控えているそう。このアイアン・グローリーと直に触れる機会が、あなたの住む街にやってくるかもしれない。スポーツかエンターテイメントか、まだはっきりとした用途が提示されたわけではないが、この2人が考えるロボットの未来は、子どもからお年寄りまでもワクワクさせるものに違いない。

会場に遊びに来ていたお子さんとアイアン・グローリーのワンショット。誰もがコックピットに乗れるということもあり、子どもからお年寄りまで多くの人が展示ブースに集まった。抽選によって選ばれたラッキーな人たちは、操縦まで体験することができ、終始盛り上がっていた。