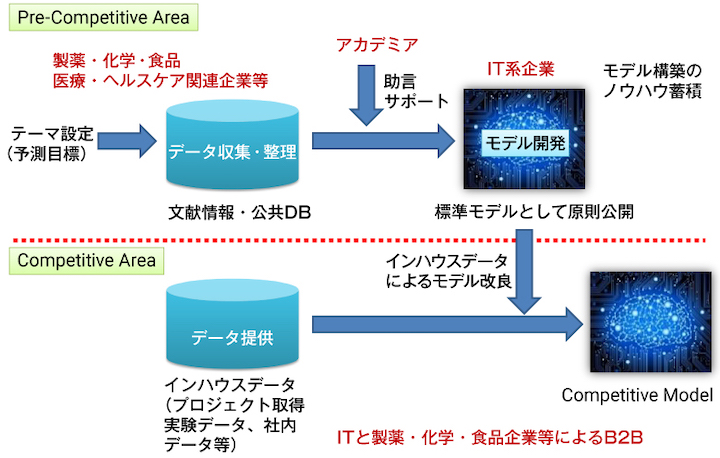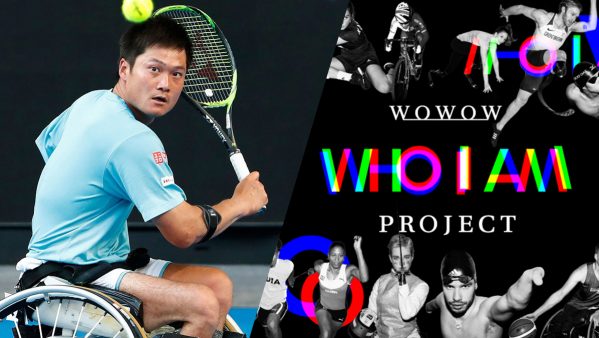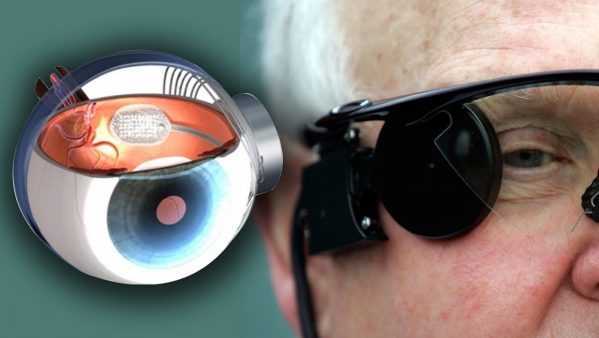総人口の25%、4人に1人が65歳以上という超高齢化社会が進むなかで、アクティブシニアと呼ばれる活動的な高齢者も増加傾向にあり、高齢者がいかに健やかな生活を送れるかが、これからの課題のひとつとなっている。ハイパーネットワーク社会研究所、九州工業大学、オートバックスセブン、富士通九州システムズが共同開発した「IoT杖」は、その一助となるかもしれないアイテムだ。
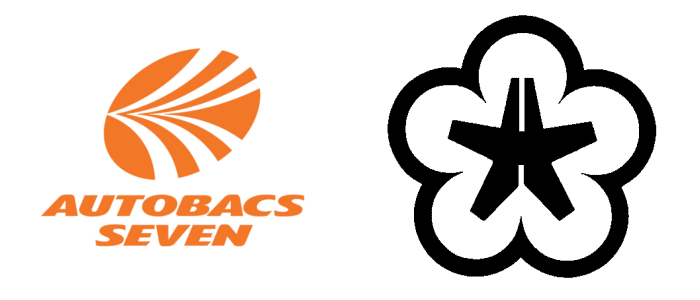 本製品は、高齢者や視覚障がい者が使用する杖や白杖を使い、見守りサービスを可能としたもの。GPS と加速度センサー、通信モジュール内蔵の IoT 機器を市販の杖に取り付け、オートバックスセブンが開発したクラウドサービスに連携することで、外出をした際の位置や移動情報、また転倒情報まで、家族や介護者が確認できる。見守りサービスとして提供される予定で、2019年の実用化を目指している。
本製品は、高齢者や視覚障がい者が使用する杖や白杖を使い、見守りサービスを可能としたもの。GPS と加速度センサー、通信モジュール内蔵の IoT 機器を市販の杖に取り付け、オートバックスセブンが開発したクラウドサービスに連携することで、外出をした際の位置や移動情報、また転倒情報まで、家族や介護者が確認できる。見守りサービスとして提供される予定で、2019年の実用化を目指している。
IoT 機器に装備される緊急ボタンを押下することにより、コールセンターから緊急連絡先に連絡するサービスの連携も検討されている。
また、高齢者や視覚障がい者にとって、ストレスフリーに活動できることも重要。普段持ち歩くような物と同等になるよう、製品の重量は30グラムを切ることを目標とするなど、実用化に向け様々な改良を進めている。デバイスの価格も1万円以下、サービス利用料は月額500円前後を想定しており、手頃で身近なサービスとして浸透する可能性も高い。
このほか、視覚障がい者向けには、専用のスマートフォンとヘッドセットを利用し、音声で目的地まで道案内する移動支援サービスを提案するなど、多方面での事業拡大に期待が集まっている。
インフラからだけでなく、ソフト面やマインドからもバリアフリーやインクルーシブな社会を実現できる先進的な事例となっていきそうだ。
[画像引用元:株式会社オートバックスセブン(https://www.atpress.ne.jp/news/140368)]