目次
日本における第5世代移動通信システム5Gのサービス開始がいよいよ目前に迫っている。高速大容量、低遅延、多端末接続の実現により、よりバラエティ豊かなサービスをより快適に楽しめるようになると推測されている。KDDIとKDDI総合研究所、株式会社アクロディアはスポーツ行動認識AIとセンサー内蔵型ボールからスマートフォンで取得したデータを活用し、選手の技術向上に役立てることができるアスリート育成支援システムを2019年10月に発表、スポーツテックサービス分野へ本格的に乗り出した。AI×IoTという最先端技術を駆使したサービス『アスリーティックラボ』の詳細や、提供するにあたっての課題点や今後の展望について、KDDI総合研究所にて話を伺った。
全身65か所の骨格点から身体の基本動作を認識して、
リアルタイムでアドバイスを返す

KDDIとKDDI総合研究所は2018年に、単眼カメラの映像からスクワットやランジなど31種類のトレーニング動作や姿勢を認識する「宅内行動認識AI」を開発。
コーチや指導者がつきっきりでなくても、深度センサーや専用デバイス、高度な技術を用いずとも、スマートフォンのカメラで撮影した映像から行動を認識し、各トレーニングのカウントや姿勢、テンポをリアルタイムでチェックできるようになった。
そこから発展したのが今回取材したアスリート育成支援システム『アスリーティックラボ』に使用されている「スポーツ行動認識AI」である。「スポーツ行動認識AI」では、同じくスマートフォンで撮影した競技者の映像から、全身65か所の骨格点を抽出して、指先を含む骨格などの動きや、ボールを捉えパスやキャッチなどを行う基本動作を認識、フォームから身体の使い方までをリアルタイムに解析することが可能となった。
このシステムは2019年8月に開催されたスピードクライミングの国際大会でも、出場選手の競技記録やリプレイ動画を世界記録と比較しながら会場のディスプレイに表示する “トライアル” で使用されており、競技者のみならず観戦者に向けた新しい体験を提供する施策として高く評価された。
KDDI総合研究所 スポーツ行動認識AI
このAIを用いたシステムに、アクロディアが開発した3次元モーションセンサーを搭載したボール型IoTデバイス「TECHNICAL PITCH (テクニカルピッチ)」を組み合わせたものが、今回の最先端技術を駆使したスポーツテックサービス『アスリーティックラボ』である。このボール型IoTデバイスとの掛け合わせをすることで、「スポーツ行動認識AI」の画像解析だけでは分からない部分までをも補うことができるとKDDI総合研究所 メディア認識グループの田坂和之氏は語る。
「スマートフォンのカメラではまだ、競技している様子をスローモーションで捉えることまではできません。そこでボールの中にセンサーを入れることで、ボールがどれくらい加速しているのか、回転しているかが分かり、競技者のフォームとボールの関係性を知ることができるようになりました。今回のサービスを用いれば、それらをおさえた上で選手に、それも即座にアドバイスすることが可能となったというわけです」
マイナースポーツや学生チームでも
スマートフォンさえあれば、
高度な指導を受けられるように
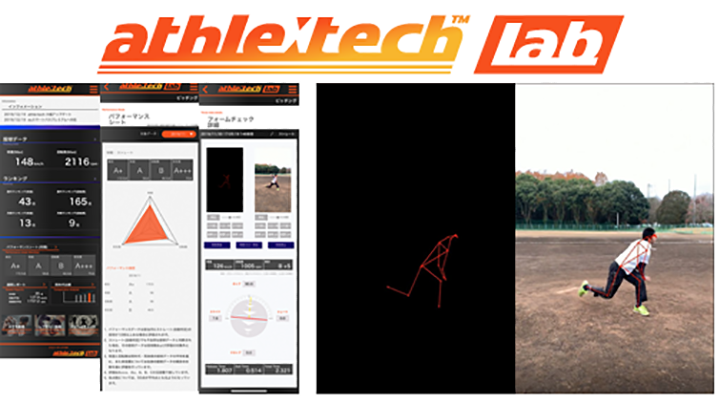
『アスリーティックラボ』
「TECHNICAL PITCH」は、野球ボールとスマホさえあれば手軽に投球の分析ができるというサービス。2017年に販売が開始してから登録ユーザー数はすでに2万件を超え、100万球の投球データをクラウド上に蓄積している。重さや硬さなど、硬式野球ボールの規格に準拠しているが、2019年12月には軟式野球ボールの販売もスタート。今後サッカーやバレーボール、ゴルフなど他の競技にも順次対応していく予定だという。
ボールとスマートフォンを Bluetooth でペアリングを行い、ボールに搭載したセンサーから送付されるデータが専用アプリで解析される。回転数、回転軸、球速、球種、変化量 、腕の振りの強さ、時間(構えてからリリースするまでの時間とリリースされてからキャッチャーが捕球するまでの時間)、動画(計測時にスマートフォンのカメラで動画を撮影し計測結果と同期)を記録することができるという。

「マイナースポーツや学生チームのように活動資金に余裕がなくても、スマートフォンさえあれば映像をチェックしながら戦略を立てていくことができますし、自宅でのトレーニング時や1人で練習する際にも指導が受けられます」(田坂氏)
近年、スポーツ指導におけるデータやエビデンスの重要性が叫ばれ始めるようになったものの、現場ではいまだにコーチの感覚や経験に左右されることも多い。そんななか、今回のサービスの検証に協力してくれる大学の運動部に対しては、AIを活用したコーチングと強調するのではなく、競技者の「今」の状態をチェックすることができるものとしてアプローチを進めていった。
「過去の映像と並べて比較すると、動きが少し固くなっているな、など自分自身で体の変化を確かめられるので、ケガの予兆検知などにも繋げていくことができます」と、自己研鑽も含めアスリートの全般的なサポートが実現しそうだ。
認識できる点数が増えれば必然的に処理が重くなる。
速さと精度を保つことが決め手
開発の肝となったのは、画像認識の速さと正確さであったと、田坂氏は語る。
「実際使ってみるとよく分かるのですが、自分の動きを撮影して、フィードバックが即時で表示されるか、1〜2分後に表示されるかでは前者の方がユーザーも理解しやすいし、実際に、上達のスピードもアップします。開発の初期は、体の大まかな骨格、目や鼻など、17か所のみでしたが、両手両足の指関節、かかとなど認識できる点を段階的に増やしていき、1年半ほどかけて65点まで到達したので、スピードクライミングのトライアルでもどのようにホールドをつかんでいるかまで、より正確に表示できるようになりました。
しかし点数が増えた分だけ当然処理は重くなり、速度と精度が落ちてしまいますから、いかに精度を保ったまま、速く認識できようにするかは技術面での苦労でもありました」
スポーツでの利用であれば現段階の65点で大体網羅できるが、顔のパーツひとつひとつや、体の輪郭まで認識できれば適用先が広がる余地は十分にある。
現状、技術的に不可能ではないものの、4G、LTEといった通信方式では高画質の画像やフレームレートの大きい動画をサーバーにアップするのに時間がかかってしまうが、5Gの実用化が始まればより解析がスムーズになり、たとえばゴルフクラブのヘッドなど細かい動きもぶれることなく表示できるなど、ユーザビリティの向上も見込めそうだ。
アスリートの支援だけではなく、
日常的なレクリエーションにも。
誰でも使えるエンジンに成長させたい

KDDI総合研究所 メディア認識グループ 田坂和之氏
今後、解消していきたい技術的な課題は、人の接触が多い部分の画像解析だという。
「1人でプレイする競技や団体でも離れているか、組まれていない場合なら問題ないのですが、人が密集するところ、柔道やレスリングのように組み合うことが多い競技だと、画像だけではどちらの手であるとか、どちらの顔であるかがまだ識別しきれていないところがあります。ラグビーのスクラムを想像すると分かりやすいと思いますが、肉眼で見ても分からないものは、やはり画像で見てもなかなか分かりづらい。少しずつ技術は改善されていっているので組み合うスポーツにもどんどん適用していけるのが理想ですね」
IoTボールの活用を組み合わせたサービスのため、アスリート育成に特化したスペシャルなプログラムという印象も受けるが、あくまでも目指すのは、誰でも手に取れるエンジンとしての成長だ。
「サッカーでも逆上がりでもいいんですけど親子で公園に行ったときに、親の主観でアドバイスするんじゃなくて、データで示してあげる方が子どもも主体的になるのではないかと思うんです。何で伝わらないんだ!って親がもどかしくなってしまうせいで、イヤになってしまうお子さんもいますから、人それぞれのアドバイスができる存在として、日常的なレクリエーションに取り入れてもらえると嬉しいですね」と田坂氏は笑顔で語る。
5G開始、そして東京オリパラ開催と、スポーツテックのメモリアルイヤーとなること間違いなしのこの1年、大きな発展に期待したい。








































