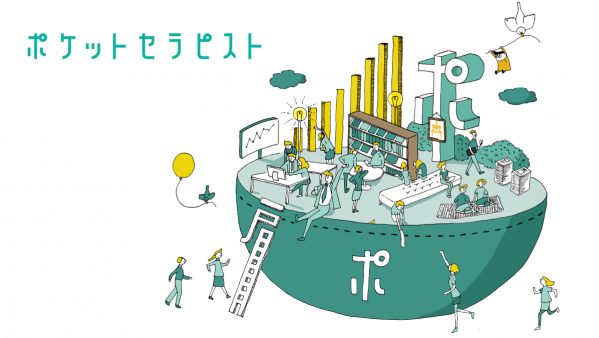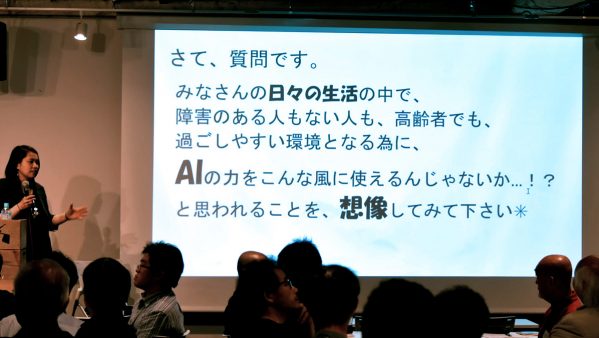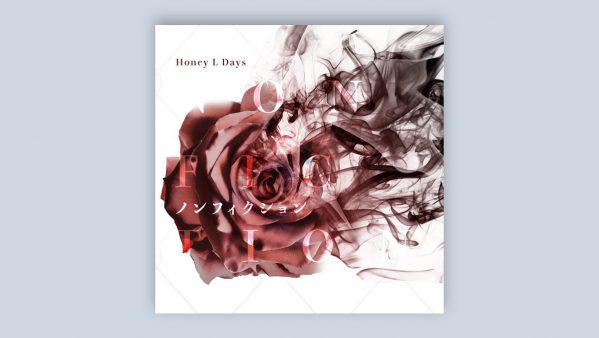先日公開されたVol.1では、主に「ROCKET」がどのような活動をするプロジェクトなのかをご紹介しましたが、このVol.2では、気になる授業内容についてもう少し深掘りしてみたいと思います。彼らのような才能の塊を、どのように開花させ、社会で力を発揮させるのかを紐解いていきましょう。
リアリティを追求する意味
まさにスマホ世代のど真ん中のROCKETの子どもたち。それは、テクノロジーの進化によって、合理的かつ時間を短縮して答えにたどり着ける利便性の反面、学ぶことの上でも重要な、体験し自ら学ぶ経験を奪い取ってしまっていることにもなるわけです。しかしROCKETでは、「解剖して食す」という授業を設けています。たとえば、硬い甲羅を持ったエビやカニを自ら考えながら捌き、料理を完成させるのですが、そこには教科書やインターネットには載っていない、リアルな感覚がプロセスの中に存在するからです。
とくに彼らのような存在には、そのリアリティこそが、多様な視点、表現力、アート的感性などを育む大きなきっかけとなるのでしょう。

トップランナーからのメッセージ
ROCKETに参加する子供の多くは、人と一緒に歩むことが苦手で、教室の中でも浮いてしまう特徴があります。しかし様々な分野で、トップを走り続ける人たちも、同じような孤独を体験しているかもしれないですよね。そんな彼らの発するリアルな言葉は、間違いなく生徒たちに突き刺さる強烈なメッセージのはずなのです。
今までにも、実業家の堀江貴文氏、宇宙飛行士の山崎直子氏、400mハードル日本記録保持者の為末大氏など、様々な分野で活躍するトップランナーの方々が講義を行ってきました。彼らの共通点は“好きなことを突き詰めている人たち”。その真意は、すべてを無難にこなすより、一点突破の強みを持つということ。我々からすれば意外と勇気のいることですが、彼らのような子たちはそうすることで、いい部分だけをとことん伸ばすことに集中できるのです。

自由と責任が伴う課外授業
この課外授業では、国内だけにはとどまらず、時には海外にも飛び出すことがあるようです。ナチス独裁下で大量虐殺の象徴として名を残す負の遺産“アウシュビッツ収容所”での課外授業を実施。また国内では、北海道の雄大な大地で炭焼き窯を再生し、最高の炭を作る授業や、最果ての地にある現代にないものを探しに行くなど様々内容が用意されています。
しかし、これらの課外授業のねらいは、決して目的を達成することだけではないのです。その過程で起こりうることのすべてが学びであると、ROCKETは考えているのです。普段ならイライラしてしまうような場面でも、何かを見出す努力をしてみたり、何かを製作する過程での自らのこだわりには妥協してはいけないなど、自由の中から人生に必要な要素を自然と身に付けさせることが目的なのです。

マインクラフトを題材にした公開授業を見学して
先日、マインクラフトワークショップと題した、公開授業に見学に行ってきました。その授業風景は、講師の話を前提に進んでいくのはもちろんなのですが、とにかく発言が自由!ルールは、まず先生のことを先生と呼ばないことと、発言時は手を挙げるというこのたった二つのみ。20名の生徒の中には、もちろん様々なタイプなの子たちいますが、通常の学校では友達ができにくい子たちのはずが、ここではみんな仲良くやっているのには正直驚きました。
ところでマインクラフトとは、ブロックを地面や空中に配置し、自由な形の建造物等を作っていくサンドボックスゲームのこと。このゲームを使いグループに分かれ、文化財を再生するのが今回の授業の目的でした。何より驚いたのが、議論を始めてから答えを導きだすまでのそのスピード。大人の会議などでは、2時間ほど話しあっても正直きちんとした結果をその会議内では出せないことが多々ありますが、彼らはそのまるで逆。現に、大人の私でも彼らが議論を始めるとすぐに話しに着いていけなくなくなったほどですから。

このような様々な授業を通して、才能を導きだすROCKET。実際、私にも彼らのようなユニークな感覚を持つ中三の甥がいます。彼がこの世に誕生してから今まで、学校側にそのような子どもを受け入れる体制ができていないと、正直ずっと感じてきました。病院などに行っても、頼るところもなく、同じ悩みを抱えている保護者の方を嫌ってほど見てきました。この問題は社会全体、もっと言えば国策として真剣に取り組まないといけない事案だと私は思っています。発達障害に理解ある環境や、その家族を守る社会が一刻も早く実現するために、この「ROCKET」のようなプロジェクトは、もっと増えなくてはいけないのです。
オフィシャルサイト
https://rocket.tokyo/