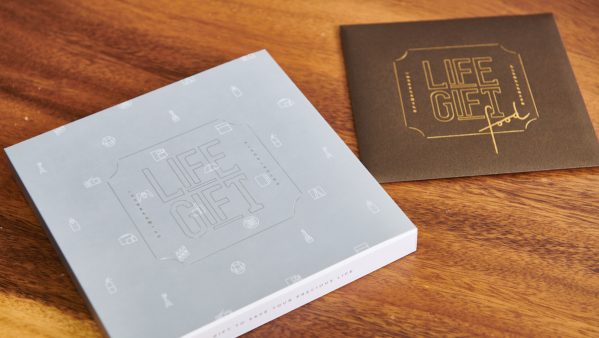目次
すさまじい山の急斜面をマウンテンバイクでひたすら下り、タイムを競う“ダウンヒル”という競技がある。日本ではまだまだ認知度は低いが、欧州をはじめとした世界では、かなりの盛り上がりを見せている競技なのだ。そんなダウンヒルのトッププロとして活躍する永田隼也選手は、4年前よりオークリーでアスリートを担当するスポーツマーケティング部で働くようになり、選手と社員を両立させている。
マウンテンバイク・ダウンヒルの選手として
覚悟を決めた理由

3歳の頃から大好きな三輪車に乗り、家の前の坂道をトップスピードで攻めていた永田選手。そして小4の時にマウンテンバイクと出会い、小学校の卒業アルバムにはすでにプロになる意思を綴っていたという。
「最初は一定の周回コースでゴール順を競うクロスカントリーという競技から始めたのですが、『なんかこれじゃないんだよなあ』と感じていたんです。そしてある日コースに行った時にダウンヒルをやっている人を初めて目の当たりにし、フルフェイスのヘルメットのかっこよさや滑走している姿に衝撃を受けたのが、ダウンヒルとの出会いでした。
ただ、当時の10歳という年齢では出場できる大会がなく、しばらくはレースには出られませんでした。小学校6年の時にようやく年齢制限のない大会に初めて大人に混ざって出場し、上位に入ることができたんです。その結果を見て、大会を主催していたメーカーの方がスポンサーをしてくれるという話になりまして。そこからですね、道が開けたのは」
プロになり初めての試練と向き合う

Riding photo : Hiroyuki Nakagawa
小学6年生ながら、大人に混じって結果を出すという才能の片鱗をすでに見せていた永田選手。そして高校生の時、ホンダのHRCマウンテンバイクチームとの契約で本格的なプロ人生が始まったわけだが、プロになったことでの意識の変化はあったのだろうか。
「その当時は、プロになる前と同じくレースに勝つことだけをひたすら考えてやっていました。そういう意味では、大きな意識の変化はなかったかもしれません。変化があったのは、大学を卒業した学生から選手一本になった時。プロとしてこれからどう活動していくか意識し始めました。勝つということだけではなく、活動費の捻出が必要になってくるからです。
周りが就職をしていく中、もっと自分も稼がなくてはいけない。すなわち選手として勝つだけではなく、お金を生まなくてはいけないわけです。マウンテンバイクのダウンヒルはまだまだマイナースポーツなので、食べていくのは難しい。そこも真剣に考えないな…と」
環境の変化が自らを成長させた

「HRCのヨーロッパチームに所属させてもらい、ワールドカップを転戦していた時は、選手としての環境がすべて整っているわけです。本当に人間だけ行けばいいみたいな恵まれた環境で。だたそのチームが一年で解散になってしまい…。
そうなると翌年からは、自力で行かなくてはいけないですよね。その時に初めて、お金がすごくかかっていたことに気付くんです。飛行機代、ご飯代、宿代と普通にかかりますから。そりゃ悩みますよね(笑)。でも自分が勝負したい場所は海外であると明確だったので、稼いで収入を得ようというよりかは、いかに海外のレースを転戦できるかを考えるようになりました」
恵まれていた環境から離れ、たった一人で活動し始めたことで資金繰りという大きな仕事が増えた永田選手。トレーニング時間の減少などの歪みを解消するために、シーズンオフの冬の間にスポンサー集めをし、シーズン(5月~11月)が始まったらそのスポンサーフィーでレースを回るという動きに辿り着いたのだ。
リズムが重要なダウンヒルという競技

Riding photo : Hiroyuki Nakagawa
一度でもこの競技を見れば、“急斜面×スピード=恐怖”という公式が頭に浮かぶはず。集中力がものをいうだけに、レース中の思考はどのようになっているかも気になるところ。
「レース中はコースのことしか考えていません。スタート前から自分のイメージしたゴールのタイミングと本番のゴールタイミングを同じに持っていけるくらいまで反復しますね。自分のイメージ通りの走りができた時はタイムが出ています。実際にはその逆が多いのですが(笑)。
また、ちょっと思考とは違うのですが、レースの組み立て方は自分流を持っています。何人もの選手が走っていれば、やっぱりコースが荒れてきますよね。その辺を予測したラインを考えるようにしていて、このラインは本線ではなくなるだろうなと思ったら、はじめからそれ以外のラインでレース展開を考えるようにしています。ですので、はめようと思った轍ががなくなった!みたいな焦り方はないです。僕が雨のレースが強いのは、その考え方がもろに出ている結果だと思います」
 今回インタビューをさせていただいたのは、オークリーのスポーツマーケティング部に所属する企業の一員というもう一つの理由がある。選手としての視点も持つ永田選手は、具体的にはどのような活動をしているのだろうか。
今回インタビューをさせていただいたのは、オークリーのスポーツマーケティング部に所属する企業の一員というもう一つの理由がある。選手としての視点も持つ永田選手は、具体的にはどのような活動をしているのだろうか。
「スケートボード、サーフィン、BMX、モトクロスなどのアクションスポーツ選手の契約からはじまり、選手を起用したマーケティングやサポートなどを主に担当しています。昨年からは、国内のトッププロと次世代が一緒に競えるオークリー主催のサーフィン大会を、オリンピック会場となる千葉県の釣ヶ崎海岸(志田下)で開催していて、それもすべてオーガナイズさせていただいています。自分にとってサーフィンというのは未知の領域でもあったので、かなり勉強させていただきました。
実はオークリーに入社した年に初めて全日本のタイトルを獲ることができたんですが、この仕事で他競技の選手のメンタルの強さなどから刺激をもらえたこと、そして社員と選手の両立のためのタイムマネージメントをしっかりできたことは、二足のわらじを履いている僕にとってのメリットなのかもしれないと、その時に感じました」
選手として、そして企業の一員として今後の目標
「選手として結果を出すことはもちろんですが、やっぱりマイナースポーツであるマウンテンバイクをもっと多くの人に広めていきたいという気持ちは大です。またオークリーの社員としては、もともとアクションスポーツが大好きでオークリーに入社しているので、オークリーが絡むアクションスポーツを、東京2020もあるので最大限に盛り上げていければなと思っています」
最後に永田選手は、ダウンヒルの魅力をこう語ってくれた。
「自分がダウンヒルを始めた理由が“かっこいい!”だったので、やはりそこが一つ。それと、道無き道をあの速度で滑走する競技って他にないじゃないですか。忘れられないその衝動や永遠に難しいのがもう一つの魅力です」

Riding photo : Hiroyuki Nakagawa
永田隼也
幼少のころよりマウンテンバイクに親しみ、16歳でダウンヒル国内シリーズ戦Jシリーズの最高峰であるエリートクラスに当時最年少で昇格。
2006年には海外チームに在籍し、W杯を転戦した経験を持つ。
2010年に全日本選手権で準優勝を飾り、2015年に全日本選手権で悲願の初タイトル獲得。
2016年にはRed Bull Holy Rideでも初タイトルを獲得。現在は欧米で人気急上昇中のエンデューロにも力を入れて、国内トップ選手としてライディングを続ける。
<戦績>
2008年 アジア選手権 準優勝
2010年 全日本マウンテンバイク選手権 ダウンヒル準優勝
2011年 アジア選手権 3位入賞
2015年 全日本マウンテンバイク選手権 ダウンヒル優勝
2016年 Red Bull Holy Ride 優勝
2017年2018年 マウンテンバイクアジア選手権日本代表
http://first-track.co.jp/athlete/junya-nagata/
https://www.instagram.com/juunnya/











 −早速ですが、大会前の体調はいかがでしょうか?
−早速ですが、大会前の体調はいかがでしょうか?