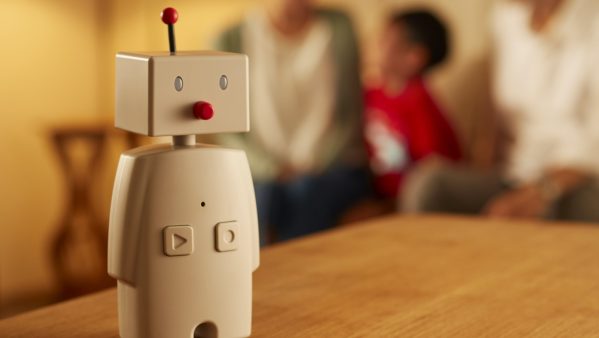目次
現在、一般的な義足は30万円、あるいはそれ以上と高価だ。そのため、途上国では義足を必要とするのに持てない人が多くいる。日本では補助金が出るため、1本目は約3万円だが、QOL向上のために2本目を購入しようとすれば、一般には30万円以上の負担となる。そうした状況のなか、3Dプリンタを用いることで、1本約3〜5万円という大きなプライスダウンを実現しようとしているのがインスタリム株式会社だ。本格的な事業スタートを来春に控えるC.E.O.の德島泰氏にお話をうかがった。
青年海外協力隊の赴任先、フィリピンで
3Dプリンタによる義足を試作

大手医療機器メーカーに勤務していた2012年、德島泰氏はJICAが派遣する青年海外協力隊の一員としてフィリピンへ赴任する。その経験がなければ、「必要とするすべての人が、義肢装具を手に入れられる世界をつくる」をビジョンとするインスタリム株式会社を起業し、C.E.O.となることはなかっただろう。
「もともと途上国に対する支援に興味があり、途上国の人たちの役に立ちたい、本当に困っている人に対する医療を提供したいという気持ちがありました。会社に籍を置いたまま、フィリピンに行ったのです」
青年海外協力隊は、途上国の産業振興の役割も担う。大手医療機器メーカーではデザインセンターに所属していた德島氏は、デザイン職のプロフェッショナルとして、デザインによって現地の産業を元気にするミッションを与えられたのだ。
「当時は3Dプリンタ自体がめずらしかったのですが、そんな最新機器を田舎の町にインストールしたりしました。ハイテク機器を使って田舎のエリアの町おこしをするのは興味深いということで、(ベニグノ・アキノ3世)大統領が視察に来たこともありました。そのような状況のなかで、3Dプリンタを使って義足が作れないかという話を、現地の人からたびたび聞くようになったのです。JICA事務所からも同じような話がありました。フィリピンではそれほど義足の需要があるのかと、現地で聞いて回ったりすると、義足をつくるところが全然ないと言うのです。そして、町には足がなくて、物乞いをしている人がたくさんいることに気づいたのです」
フィリピンには、義足を必要としているのに、義足を持っていない人がたくさんいる。それは、大きな理由が2つあるからだ。
「理由の1つは値段が高いこと。もう1つは、つくるための施設がないことです。首都のマニラでも公立の施設が2つあるだけで、田舎にはほとんどありません。それなら3Dプリンタでつくってみようかと試してみると、プロトタイプができたのです。あれ? これはできるんじゃないか? そう思ったのが、インスタリムの原点です。現地の廃材や竹で義足をつくれないかと考えたこともありましたが、3Dプリンタのプラスティックは安い素材なので、安い義足ができるに決まっています。その点でも、3Dプリンタの義足には可能性を感じました」
AIとオリジナルCADを関連させることで
義足の製作工程を簡略化できる

義足のフィット感を決定するのがソケットで、その形状はオリジナルCADによってつくられる
2年間のフィリピン赴任を終え、2014年12月に帰国すると、德島氏は勤めていた医療機器メーカーを退社した。しかし、ただちに起業はしていない。
「ビジネスベースで考えると、3Dプリンタはスペシャルなものが必要です。また、CADソフトウェアもオリジナルなものが必要だと思ったので、それを開発するために慶應義塾大学にマスターとして入りました。奨学金で食いつなぎながら開発を続け、2017年に合同会社をつくり、今年(2018年)の4月に株式会社としました」
類例のない3Dプリンタによる義足をつくるのだから、開発は試行錯誤の連続だった。
「プラスティックの義足は折れる危険があるため、十分な強度のある素材を開発するのに苦労しました。また、3Dプリンタを使って義足をつくるとき、層と層の継ぎ目で折れやすくなるなどの特有の問題も数多くあります。そこで、力のかかる方向に対して、強度が増すようなプリントの仕方を考えるなど、多くの工夫を行いました。そのため、3Dプリンタも専用の大型のものが必要となりました」
インスタリムの義足づくりは、AIを用いる点も特徴的だ。

義足装着時に大きな力がかかる方向に対しての強度を高めるため、強度が増すようなプリントの仕方を考えるなど、多くの工夫を行った
「私たちの義足づくりは、まず、義足を必要としている患者さんに来ていただいて、患者さんの断端を3Dスキャンします。これを私たちのオリジナルCADにインポートし、それをもとに、形状をつくり、ソケット(断端に触れる部分)をつくります。義足を装着したときに、触れて痛い部分が出てくるため、それを義肢装具士が修正する必要があります。義肢装具士がヒートガンなどを使って形状を修正し、患者さんにフィットさせることにより、まったく痛くない形状で、歩きやすい義足を製作できるのです。ここでポイントとなるのは、患者さんの足のそのままのデータと、まったく痛くない形状には違いがあることです。患者さんの元データをインポートしたら、結果的にはこういう形状の義足が出てきたということをAIに学ばせると、最終的には、出来上がりまでの工程も減らせます」
インスタリムは2019年春に、フィリピンで本格的に事業をスタートさせる計画がある。実質的なスタート地点をフィリピンとしたのは、安価な義足に対する需要が大きく見込まれるのに加えて、もう1つの大きな理由もある。
「私たちの事業はAIを使っているので、データをいかに集めるかということがポイントなのですが、日本、アメリカ、ヨーロッパなどでは、いろいろと越えていかなければいけない規制の壁があります。フィリピンの場合は、義肢装具に関する法律がまったくないので、規制の壁なしに事業を始めることができるのです」
事業拠点としては、多数の3Dプリンタを備える工場を、メトロ・マニラに設ける。
「スキャンした患者さんのデータはEメールで受け取れるようにしているため、地方にいる患者さんの義足も、メトロ・マニラの工場でつくって、提供できるというビジネスモデルを考えています。売値は3~5万円です。日本では30万円くらいしますから、10分の1くらいに抑えることになります」
QOLを向上させるための義足市場は
日本に手つかずのまま残っている

現在、インスタリム本社は、世田谷区が廃校となった中学校の校舎を利用した「世田谷ものづくり学校」内にある
日本での事業展開は、視野に入れているのだろうか?
「もちろん、考えています。たとえば、中学2年生でバレーボールをやっている義足の女の子がいたのですが、義足の足首が固定されているため、スニーカーしか履いたことがない、おしゃれができないと言うのです。日本では補助金が出て、どれほど高価な義足でも3万円程度で買うことができるのですが、それは1人1本までなのです。おしゃれのために、もう1本、義足を買うとなれば、30万円の負担ということになります。しかし、私たちが3万円で提供できるとなると、彼女はおしゃれをするために義足を買うことができるのです」
ウエディングの市場もあると考えている。
「義足の女性には、ウエディングドレスが着られないという悩みをお持ちの方も多いのです。なぜなら、ハイヒールが履けないからです。義足のタイプによっては、和装もできません。そうした理由で、結局、結婚式をやらないという方も大勢いるようです」
婚礼用の義足が手軽に手に入るようになれば、多くの人が、大きな幸せを感じることになるだろう。
「金属パーツのある一般的な義足だと、温泉に行けないとか、海に行けないとか、生活の不便があるようなのです。しかし、3Dプリンタでつくるプラスティック製の、水に浸かっても大丈夫な義足があれば、それも改善できます。2本目、3本目の、QOLを上げる義足があれば、生活そのものが変わるのです。生活を豊かにするための義足の市場は、日本にあると考えています」
医療機器メーカーで、3DプリンタやCADの扱いに慣れていた德島氏が、義足不足が顕著なフィリピンに行ったことがきっかけで、インスタリムの事業はスタートした。それは偶然の産物とも言える。しかし、偶然によって、すばらしい未来がつくられることもあるのだ。
德島 泰(Yutaka Tokushima)
1978年、京都府生まれ。コンピュータ部品のベンチャー企業に勤務した後、大手医療機器メーカーで働く。2012年から青年海外協力隊でのフィリピン赴任を経て、2014年、大手医療機器メーカーを退社。2017年、合同会社インスタリムを立ち上げ、2018年4月、株式会社として、現在、C.E.O.。「自分たちだけが幸せになるのではなく、製品を使っている人も、つくっている人も、素材に関わる人も、みんながフェアになる仕事をする」のがモットー。