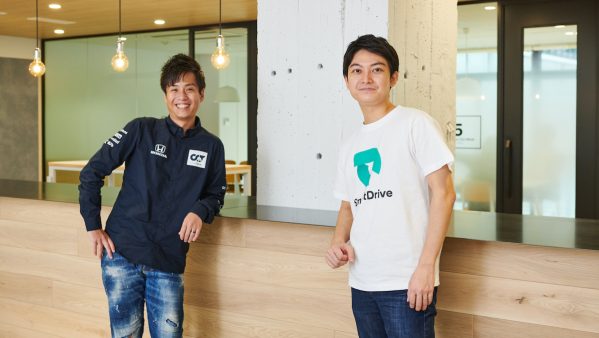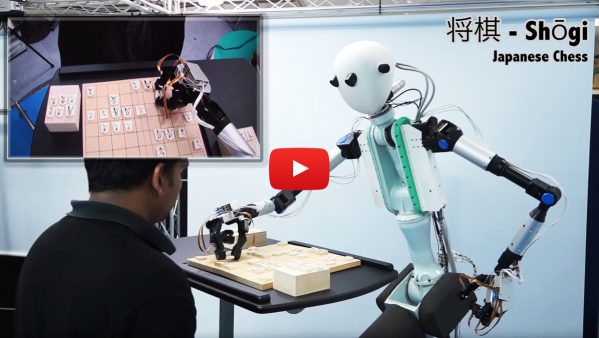2000年シドニーパラリンピック男子車いすバスケットボール日本代表チームのキャプテンを務めるなど、トップアスリートとして活躍したのち、パラスポーツを主軸とするスポーツの面白さや楽しさを伝播するために、全国各地の小・中・高や、イギリス、ブラジルの学校など、計2,600校にも及ぶ学校を訪れ、のべ80万人の子どもたちに向けて、講演活動や体験会を行ってきた根木慎志氏。現在、プロジェクトディレクターとして携わる日本財団パラリンピックサポートセンター推進戦略部「あすチャレ!」での活動をはじめ、四半世紀以上に渡り、力を注いできたパラスポーツの普及活動の先にどんな未来を見つめているのか。根木氏と出会ったその日から、“あ・うんの呼吸”で意気投合し、親交を深めてきたHERO X編集長の杉原行里(あんり)が話を伺った。
子どもたちの「カッコいい!」が、僕の原動力

根木慎志氏(以下、根木):今でこそ、離島にまで出掛けたりして、日本全国の学校で講演会を開かせていただいていますが、正直に言うと、23歳の時の初めての講演は、なかなか、気が進まなかったんです。「障がい者として生きる大変さや困難さを伝えて欲しい」と母校中学の恩師に依頼されたけど、それを生徒たちに話したいとは思えず、一度はお断りしました。でも、恩師の熱意に負けて、やったんです。緊張した空気の中、生徒たちからは、「根木さん、かわいそう」、「大変な根木さんに対して、僕らは何ができるのかな」という、どちらかと言うと、マイナスな反応があったんですね。
ところが、その後の講演会で、僕のちょっとした思いつきから、車いすバスケを披露してみたら、生徒たちからは、今までと180度違う反応が返ってきたんです。「根木さん、カッコいい!」、「根木さん、すげぇ、カッコええ~!」って言ってくれて。上手い先輩のプレーを見て、「カッコええなぁ」って、僕も憧れてたけど、その感覚と自分自身が結びついてなかったから、びっくりしました。
杉原行里(以下、杉原):“カッコいい”の前に、“根木さん”って、本当に言っていましたか?(笑)
根木:ひょっとしたら、車いすがカッコいいって、言いよったんかもしれへんけど、褒められたら素直に認める方なので(笑)。まだ車いすバスケをやり始めた頃やったし、そんなにスピードは速くなかったと思う。とはいえ、一般の車いすよりは、競技用の方が明らかにスピードは出るから、カッコよく見えたんかもしれへんよね。3回打って、やっと1回入るくらいの腕前やったのに、人前で見せようとする僕もどうかと思うけど、シュートも披露したんですね。なかなか入らんくて、手に汗握りつつ、10本近く打ったかな。今も忘れられへんけど、入った瞬間、生徒たちからは「すげぇー!」、「カッコいいー!」と再び、大歓声が上がりました。
車いすバスケを通して、人間の可能性やこのスポーツの面白さを知ったことを僕は実演して見せた。ただそれだけのことで、生徒たちの見方が、ガラリと音を立てるように変わった。その時に、子どもたちからもらった力によって、自尊心や自分を肯定する気持ちが、ゼロというよりマイナスやったところから、ポーンと引き上がったんです。その力は、今も僕の原動力になってます。
杉原:その振れ幅がすごいですよね。僕は経験したことがないから分からないけど、おそらく常に歓声を浴びている人には感じられない、ダイナミックな感じがします。今日の体験会でも、例のフレーズを言われましたか?(笑)
根木:「根木さんは?」と煽ると、子どもたちもノッてくれて、「カッコいい~!」と返してくれるんですよね。ちょっと、言わせてしまってるところもあるけど(笑)、今日もたくさんの「カッコいい」を浴びさせてもらってから、ここにやって来ました。

根木:高校生に向けた講演会では、今後の進路について悩んでいたり、これからの人生にとって大事な時期を過ごしている彼らに、僕なりに経験してきたターニングポイントでのエピソードなども織り交ぜて話します。「こうしなさい、ああしなさい」と教えるのではなく、純粋に、自分の感じてきたことを伝えるだけやけど、10年、20年経った今も、「就職しました!」、「結婚するので、披露宴に来てくれませんか?」と、嬉しい報告や誘いの連絡を受けたりして、関係が続いているんですよ。
杉原:素晴らしいですね! 根木さんが、車いすバスケの魅力を伝えたことがひとつのきっかけになって、生徒たちとの間で、人間としての繋がりが生まれているんですから。
根木:僕が影響を受けたことを伝えたことに、影響を受けてくれるなんて、これほど、やりがいを感じることはないです。
自分らしく輝く。そして、みんなで輝く。

杉原:最後に、“根木ファン”をはじめ、HERO Xをご覧くださっている皆さんにメッセージをお願いします。
根木: 誰だって、生きていれば、嬉しい日もあれば、悲しい日もあるし、エネルギーに満ちあふれてる日もあれば、めっちゃ、しんどいなぁと思う日もあるし、自分の思うようにいかない時って、多々ありますよね? でも、この世界に生きている人は皆、それぞれに違う“輝き”を持っていて、ひとりとして、同じ輝きを持つ人はいないし、輝き方だって、皆違います。みんな、輝いているんです。その違いを互いに認め合い、助け合えることができるようになれば、一人ひとりがもっと光り輝けるようになるし、もっと素敵な社会の実現に繋がるんじゃないかなと思います。
講演会で出会った生徒たちが、「今日の根木さん、眩しかった!」とかSNSで色々とコメントをくれたりするんですよ。また自画自賛してるけど(笑)、僕は僕で、自分らしく輝いていけたらいいなと思うし、できれば、みんなで輝きたい。だからこそ、これからも、親しい人と友だちになることの大切さを子どもたちや参加者の方たちに伝えて、「友だちづくり」の輪をもっと広げていきたいです。
電気でピカピカに光る服を着て、「ね、ほんまに輝いてるでしょ?」って登場したら、面白いなと思って、密かに企んでるんやけど。今、話してる時点で、秘密になってないよね。
杉原:面白いですね。でも、眩しすぎて、目を閉じたまま、講演している根木さんの姿が浮かぶのは僕だけでしょうか?(笑)。どうか、火傷には気をつけてください!

根木慎志(Shinji Negi)
1964年9月28日、岡山県生まれ。シドニーパラリンピック車いすバスケットボール元日本代表チームキャプテン。現在は、アスリートネットワーク副理事長、日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副理事長、Adapted Sports.com 代表を務める。2015年5月、2020年東京パラリンピック大会の成功とパラスポーツの振興を目的として設立された日本財団パラリンピックサポートセンターで、推進戦略部「あすチャレ!」プロジェクトディレクターに就任。小・中・高等学校などに向けて講演活動を行うなど、現役時代から四半世紀にわたり、パラスポーツの普及や理解促進に取り組んでいる。