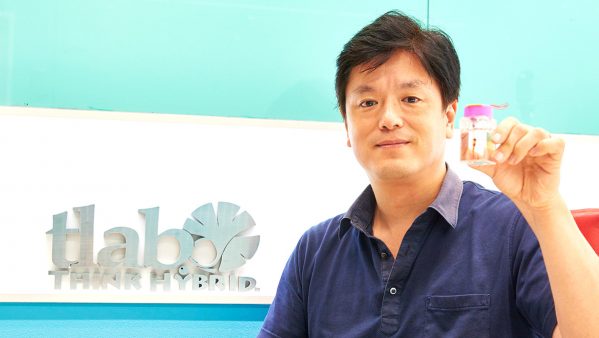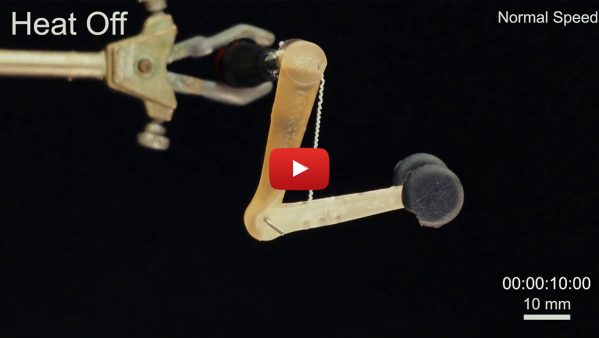パラリンピックの先駆けとなったイギリスの国際ストーク・マンデビル競技大会では、1987年の陸上競技で金メダルを獲得。2000年より始めたパラ射撃でもめきめきと頭角を現し、2002年、世界射撃選手権ライフル競技に出場を果たしたのち、2004年アテネパラリンピック日本代表に選出された鈴木ひとみ選手。その後、ピストルに転向し、射撃選手として活躍するかたわら、2年前に始めた“氷上のチェス”こと、車いすカーリングでは、東京都の強化指定選手に選ばれるなど、早くも才能を発揮し始めている。次々と新たな挑戦に挑むバイタリティの源は?パラアスリートとして33年、第一線を走り続ける鈴木選手に話を聞いた。
 車いす陸上から射撃へ
車いす陸上から射撃へ
優勝よりも、欲しかったのは生きがい
車いす陸上や射撃で、数々の栄光を掴んできた鈴木選手。それ以前は、ミス・インターナショナル準日本代表に選出されたのち、数々のファッションショーやCMを飾るモデルとして活躍していた。アスリートを目指すきっかけは、事故に遭った22歳の時、1年7ヶ月に渡る入院中のことだった。
「大部屋で、他の患者さんと一緒だったんですね。これから先のことについて、まだ自分でも分からないのに、皆さん色々と聞いて来られる。部屋から離れたくて、非常スロ―プを車いすで上ったり、降りたり、ずっと走っていました。ノートに“正”の字を書いて、数えたりしているうちに、腕が鍛えられてしまって(笑)。当時は、今よりもずっと選択肢が少なく、パラ競技といえば、車いすバスケットボールか、車いす陸上くらい。できることをやらなくては。そんな危機感から陸上競技の世界に飛び込みました」
国際ストーク・マンデビル競技大会の陸上競技で金メダルを獲得するなど、成績を着実に伸ばしていくが、2000年に転機が訪れる。
「いつしか優勝することだけが目的になっている自分がいました。もっとワクワクするような、生きがいになることはないかと模索していたんですね。水泳やチェアスキーなど、色々な競技を試してみて、一番しっくりきたのが射撃で、2000年から始めました。射撃って、面白くて、ガーッと熱く燃えたりしたらダメで、テンションは常に低飛行。というより、低く保たないと、パフォーマンス力が発揮できない競技です」
 努力より才能が問われる世界
努力より才能が問われる世界
勝つことへの熱意や集中力を研ぎ澄ませることはむろん不可欠だが、パラ射撃において、一番大事なのは才能だという。
「射撃をするためだけの感性と言い換えられると思います。それさえあれば、極論、運動神経がなくてもトップになれる競技です。逆になければ、どれだけ頑張っても伸びません。アスリートとして活躍し続ける上で、才能があるかどうかが非常に重要。この17年の経験を通してよく分かりました」
幸いにして、ライフルの感性に長けていた鈴木選手は、着実に成績を伸ばし、初めてわずか2年、2002年には世界射撃選手権に出場し、2004年アテネパラリンピックの射撃日本代表選手に選出された。
「確かにライフルは得意でしたが、ピストルの方が楽しいかなと思って、アテネの翌年に転向して今に至ります。当時の私は、41歳。もしまだ20代なら、そのままライフルを続けたかもしれません。でも、自分の人生を逆算して考えた時、得意なことより好きなことをやろうと思ったんですね。人生は有限だから」
ピストルでも日本トップクラスの腕を誇るが、「好きだけど、ライフルほどの才能はない。あらゆる努力をしてきたけれど、世界のトップと同じ土俵で戦えるかと言ったら、そういう風にはならない」と厳しい目で自分を分析する。
「私、往生際が悪いんですよ。ピストルを12年やってきて、自分の実力は十分分かっているのに、もしかしたら、もっとワクワクすることがあるかも?とつい思ってしまう。粘り強いといえば美点になるでしょうが、そんなことは全然なくて。しつこくやってしまうんですね(笑)。ピストルは練習を怠ると、あからさまにパフォーマンス力が落ちてしまうし、大会に出場するかぎりは、しっかり続けていくつもりです」
鈴木ひとみ(Hitomi SUZUKI)
1982年、ミス・インターナショナル準日本代表に選出。モデルとして、ファッションショーやCMなどで活躍する中、交通事故で頸椎を損傷し、車いす生活となる。その後、イギリスの国際ストーク・マンデビル競技大会で金メダルを獲得(陸上競技)、2004年アテネパラリンピックの射撃日本代表に選手されるなど、多彩なパラ競技において、その才能を発揮する。2005年、エアライフルから短銃に転向、射撃で活躍するかたわら、2年前より車いすカーリングを始める。2016年の日本選手権では、所属する信州チェアカーリングクラブが準優勝、東京都の強化指定選手に選出され、2022年冬季パラリンピック出場を目指す。
鈴木ひとみオフィシャルサイト
http://www.hitomi-s.jp/
マクルウ
http://macrw.com/










 命知らずのライダーが、命がけで挑んだ世界初のトリック
命知らずのライダーが、命がけで挑んだ世界初のトリック バイクに夢中の少年時代を過ごしたブルース・クックは、2005年、念願のプロライダーの道に転向し、北米全土のショーや国内の大会への参戦をスタート。“命知らずのライダー”として着実に知名度を上げていき、2012年、エクストリーム・スポーツの世界的競技大会「Xゲームズ」でデビュー。その後、ナイトロ・サーカスに初出演して以来、人気選手の一人として活躍していました。
バイクに夢中の少年時代を過ごしたブルース・クックは、2005年、念願のプロライダーの道に転向し、北米全土のショーや国内の大会への参戦をスタート。“命知らずのライダー”として着実に知名度を上げていき、2012年、エクストリーム・スポーツの世界的競技大会「Xゲームズ」でデビュー。その後、ナイトロ・サーカスに初出演して以来、人気選手の一人として活躍していました。 不屈の精神で、大事故から華麗にカムバック
不屈の精神で、大事故から華麗にカムバック 絶え間ないチャレンジと努力で、不可能を可能に変えていく
絶え間ないチャレンジと努力で、不可能を可能に変えていく 何事においても、「これくらいが自分の限界だろう」と折り合いをつけて、ピリオドを打つことは、ある意味で自分を守るためには必要な行為。しかし、それは自分の可能性を狭めることも意味します。ブルース・クックの素晴らしさは、それを決して自分に許さず、未だ見ぬ未来への希望を胸に、不可能を可能に変えていくべく、チャレンジと努力を続けていること。
何事においても、「これくらいが自分の限界だろう」と折り合いをつけて、ピリオドを打つことは、ある意味で自分を守るためには必要な行為。しかし、それは自分の可能性を狭めることも意味します。ブルース・クックの素晴らしさは、それを決して自分に許さず、未だ見ぬ未来への希望を胸に、不可能を可能に変えていくべく、チャレンジと努力を続けていること。