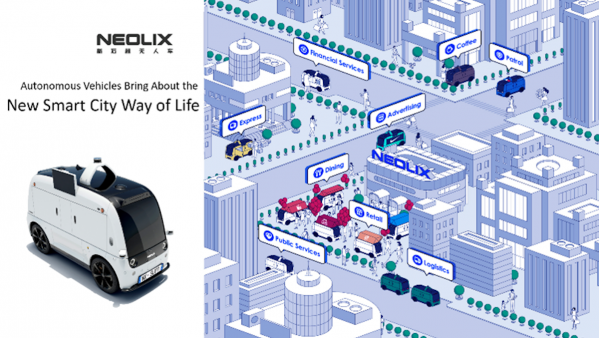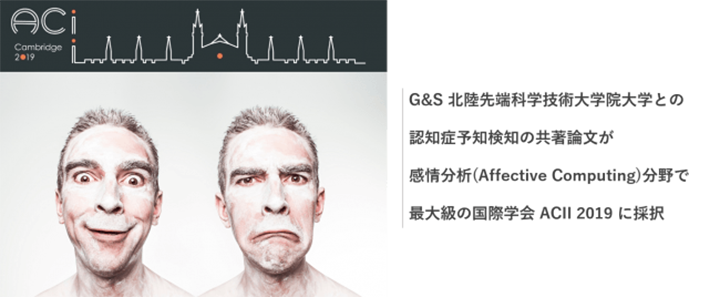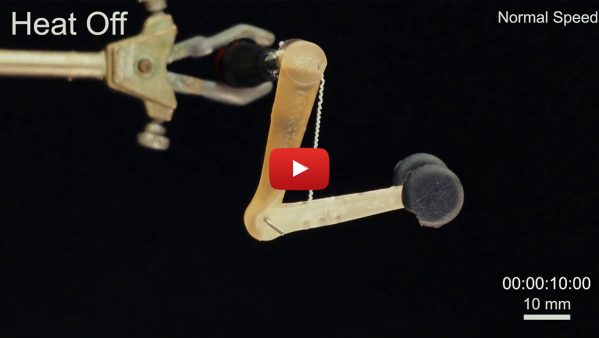残念ながら格差が見られる医療機関の充実度。コロナ前、日本の医療を受けようと、はるばる海を越えて人間ドックにやってくる海外富裕層の姿も見られたが、医療機関の充実度格差は国内でもある。特に今、人手不足が叫ばれるのが産婦人科分野。妊娠中は何かと気がかりなことも多いが、近くに産婦人科がなければ気軽に受診することもできない。また、産婦人科は乳がんや子宮がんなど女性の病気に密接に関わるが、門を叩くには勇気もいる。そんな中、気軽に相談できる場をオンラインで提供するところが現れた。株式会社Kids Publicが提供するオンライン医療相談サービス「産婦人科オンライン」代表で産婦人科医の重見大介氏に話しを伺う。
自宅で相談できる産婦人科オンライン
杉原:コロナ禍でさらに利用メリットが上がったのではないかと感じるオンラインによる相談ですが、まずは、重見さんが代表を務める「産婦人科オンライン」は、どのようなものなのでしょうか。
重見:オンライン医療相談サービスをメインにして運営しています。大きく分けて3種類のサービスを展開していて、一つは、完全予約制で10分間、1対1で利用者さんのお話しを伺うサービスです。これは、オンライン上に外来の診察室があるイメージです。LINEを使ったオンライン面談もできますし、チャットの方がいいという場合は、チャットだけでの相談も受け付けていて、リアルタイムで相談ができるものです。
2つ目が予約不要のチャット相談で、質問をチャット画面に入力いただき、いただいた質問に対して24時間以内に専門家が返信(一問一答形式)をするというサービスです。3つ目は、ちょうどこの秋にローンチの予定なのですが、予約無しで、助産師さんへ日中にリアルタイムでチャット相談(サービス提供時間内なら会話数に制限なし)ができるものです。

杉原:僕も子どもがいますが、やっぱりはじめての子の時は、分からないことも多い。親にとっては自宅からすぐに専門家と繋がれるというのは、一つの安心材料になりますよね。
重見さんはどうしてこの「産婦人科オンライン」を立ち上げようと思ったのですか?
重見:Kids Publicの代表で小児科医の橋本が、「小児科オンライン」というサービスをすでに提供していました。私は産婦人科医として学びを深めていたところで、オンラインで社会と専門家を繋ぐ必要性を感じるようになり、Kids Publicにジョインする形で「産婦人科オンライン」を立ち上げました。
すぐ聞ける、会える専門家
杉原:オンライン相談が必要だという思いにいたったのは、どういうところからだったのでしょうか?
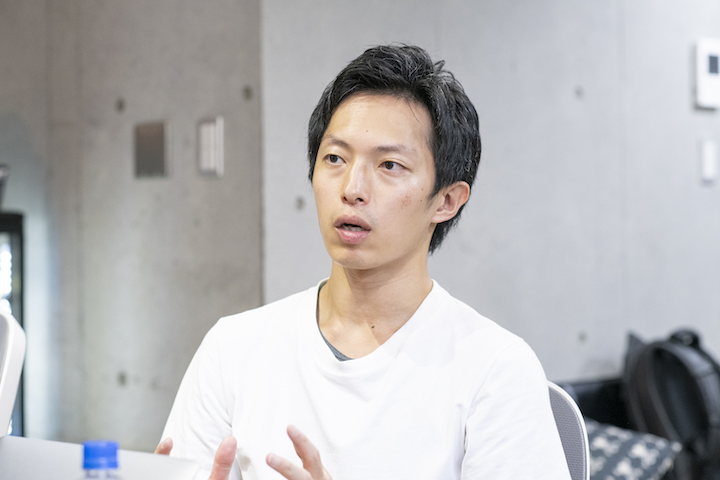
ゼロから産婦人科オンラインを立ち上げた重見大介代表
重見:はい、私は産婦人科医なのですが、公衆衛生を学びたいなと思い、一旦臨床を離れて大学院に進んだんです。その時に、普段、病院で見ている患者さんは本当に社会のごく一部でしかなくて、病院に行けずに悩んだり、困ったりしている人がもっと沢山いるのだと気が付いたのです。医師が病院で待っているというだけでは、そういう人達の声を聞き逃してしまう。病院と社会をつなぐ仕組みがないとダメなんじゃないかという思いにかられて、誰でも気軽に相談できる方法はないかと考えはじめたのがきっかけです。
杉原:それで、オンラインチャットなどを思いついた。
重見:そうなんです。妊産婦さんは20〜30代が多いので、95%以上がスマホを持っている。ならば、スマホで繋がることができる仕組みを作るのがいいのではないかと。
杉原:そんなことを考えていた時に、橋本さんの活動を知ったのですか?
重見:そうなんです。すでに立ち上げから1、2年経っていて、小児科と産婦人科で一緒にやったら出産から子育てまで切れ目なくケアできるなと。それに、(今あるシステムに)ジョインしてやる方が、社会実装が早いなと考えたんです。
杉原:サービスがリリースされた時は結構メディアにも取り上げられていましたよね。僕はそれを見ていた記憶があります。
重見:ありがとうございます。小児科オンラインは2017年度、産婦人科オンラインは2019年度のKIDS DESIGN AWARDをいただいたりしましたので、メディアにも取り上げていただきました。
ゼロから生み出した
「オンライン医療相談」の仕組み
杉原:サービスを立ち上げられた2016年の時は、ウェブ環境は整いつつあるとはいえ、医療とオンラインはまだまだ隔たりがあったというか、むしろ、隔たりを作っていたという印象があるのですが。
重見:はい。今もですが、確かに大変に感じるところはあります。一つは、個人情報の問題です。個人情報をどこまで扱うかという部分は非常に考えました。もう一つは、医療相談と診療の違いについてです。
杉原:利用者側からすると違いがあまり分からないのですが、何か法律的な問題などがあるのでしょうか?

VCからの資金調達をしないという姿勢に共感するHERO X編集長 杉原行里
重見:実は、オンライン医療相談とオンライン診療というのははっきり区別されているんです。これは、厚生労働省が指針として出しているもので、2018年に線引きの指針が公表されました。それまでははっきりとした指針がなく、従来の診療を行なっている医師の方からすると、オンラインにすると「相談」と「診療行為」の線引きが曖昧になるという懸念を持つ方もいました。それをいかに安全に、堅実に、エビデンスをしっかり出しながらやっていくというところを大事にしてサービスの開発を進めてきました。
杉原:「産婦人科オンライン」で行っていることは、医師のような専門家にお話しをうかがうのだけれども、「診療」ではないということでしょうか?
重見:そうですね。今はオンライン「相談」ということで、サービスを展開しています。
杉原:お話しを伺うに、VCとかがすぐに資金を出したくなるようなサービスだと思うのですが、資金調達はされたのですか?
重見:最初期に資金面以外でのサポートをいただいたことはあったのですが、大きな資金調達はしていませんね。
杉原:理由は何かあったのでしょうか?
重見:さきほど申し上げた、安全に堅実に開発を進めていくために、ちゃんとやりたいことをやりながら、ゆっくりと進めていきたいという思いがあったので。
杉原:それはすごくよく分かります。僕たちが関わる開発分野も似たようなことが言えるので。VCから資金を調達すると、開発速度は速くなりますが、同時に、やりたいことに制限がかかる部分もありますからね。
重見:そうなんです。なので、開発スピードとしてはゆっくりなのですが、その分、研究と平行していろいろとやってきたという経緯があります。
杉原:そして現在、すでに沢山の医療者が相談役として所属しているということですが、何人くらいいるのですか?
重見:小児科医、産婦人科医、助産師を合わせて190人くらいになっています。

杉原:絶対的に世界に必要な領域のことをされていると思うのですが、日本の場合、まだオンラインによる医療相談はそれほど認知されていませんよね。ところが、海外ではすでに普及し始めている。
重見:そうですね。中国やアメリカではすでに1日に数万件レベルのやりとりがされているとも言われています。逆にいうと、世界的にはそれくらいすでに流通しているものなので、ニーズとしてはあるはずだと思っています。ただ、日本の場合は医療機関にフリーアクセスできるというところが、海外との大きな違いだと思っています。
杉原:日本は健康保険制度が充実しているので、近くの医療機関を気軽に受診できますからね。
重見:そうなんです。患者側の費用負担も少ないので、近くに受診できる病院がある場合はオンラインを選ぶ必要がないですよね。病院が近くにないという方でも、アメリカや中国のように国土が広大というわけでもないので、車で行けば病院にたどり着ける人がほとんどですから。ですが、コロナ禍になり、少し状況が変わりました。2020年にオンライン医療相談が広がりはじめて、行政でもオンライン窓口を推進すべきだという流れになり、私たちも経済産業省から相談窓口の委託を受けました。
杉原:「産婦人科オンライン」の普及により、どんな問題が解決できるようになると思いますか?
重見:例えば10代の方などで、(病気や妊娠を)親御さんに知られたくないという理由から受診せずに症状が悪化するケースもあります。コロナになって多かったのは、妊娠したかもしれないという相談でした。あとは、私たちが特に注視しているのは妊産婦さんの産後うつです。コロナ禍で社会から孤立して、メンタルに打撃を受けている方が多くいます。産後うつをいかに減らすかということが直近の大きな課題です。そこでオンライン医療相談を妊娠中から産後まで受けた場合とそうでない場合の(メンタルの)比較をする検証(研究)をおこなったのですが、オンライン医療相談を受けた妊産婦さんの方が産後うつリスクを明確に減らせるという結果が得られました。オンライン医療相談の有効性をアピールできる材料になると思っています。
杉原:気軽に専門家に相談できる仕組みが妊産婦の心の健康もサポートするということで、ぜひ広がってほしいサービスだと感じました。今日はありがとうございました。
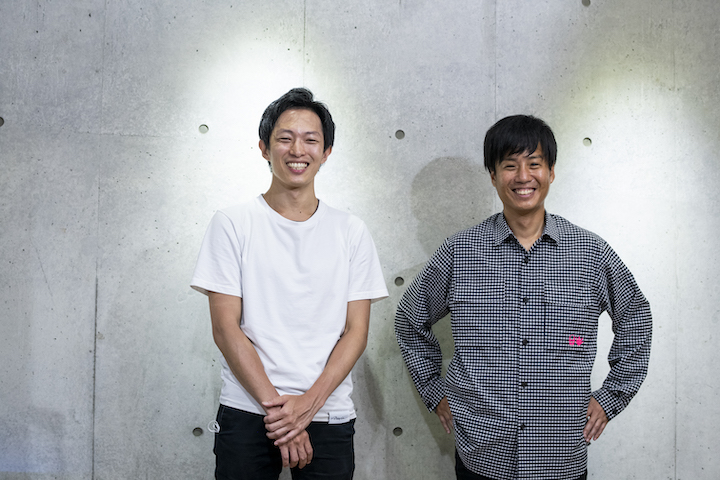
重見大介(しげみ・だいすけ)
株式会社Kids Public「産婦人科オンライン」代表。日本医科大学 卒業後、2010-2012年に日本赤十字社医療センターで初期臨床研修(産婦人科プログラム)、2012-2017年 日本医科大学付属病院 産婦人科学教室NICU(新生児集中治療室)、麻酔科を含め関連病院で産婦人科医として勤務。2018年3月 東京大学大学院公共健康医学専攻(SPH) 卒業。2022年3月 医学博士取得。現在、「産婦人科オンライン」は対法人(自治体や企業など)向けにサービス展開している。
関連記事を読む