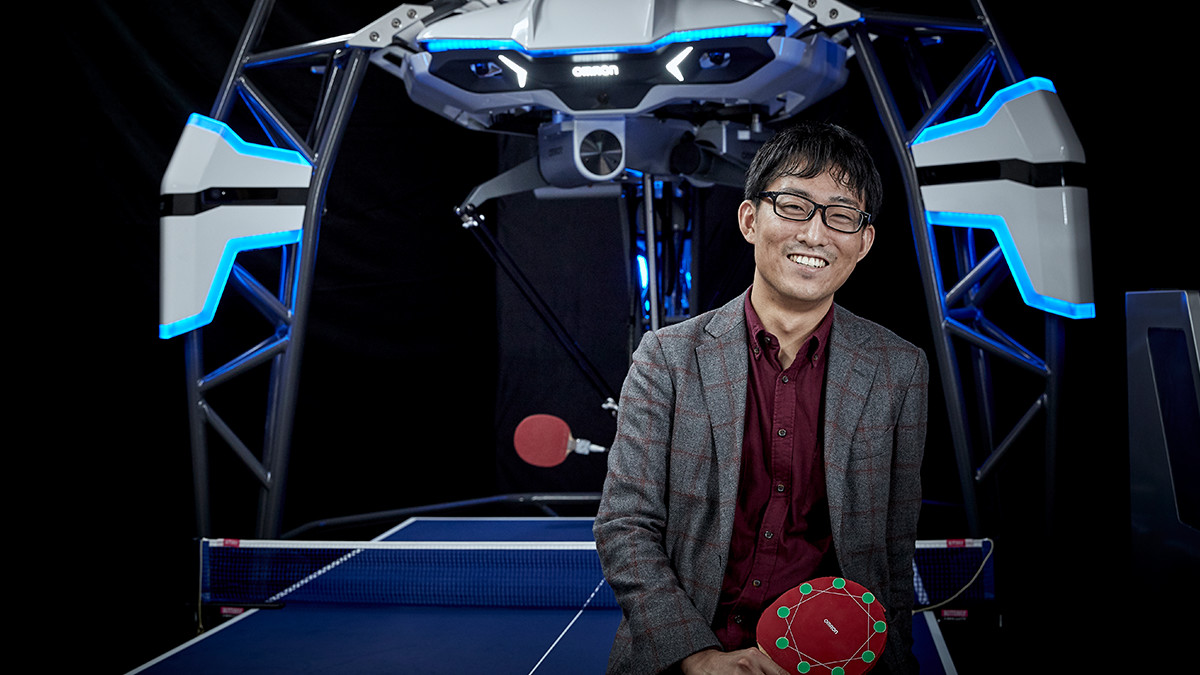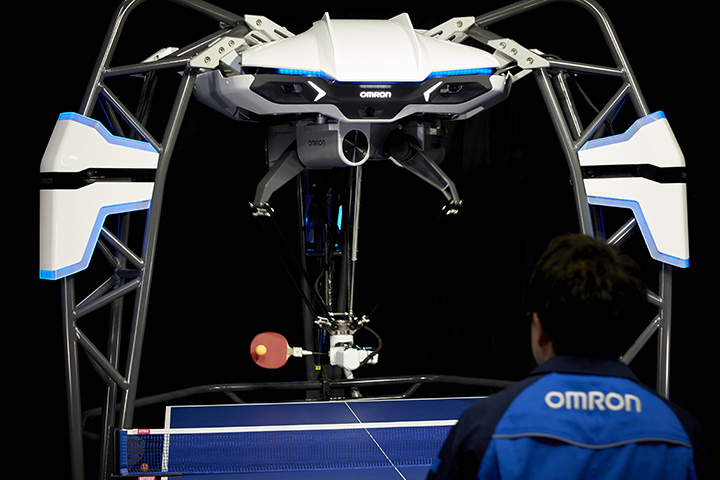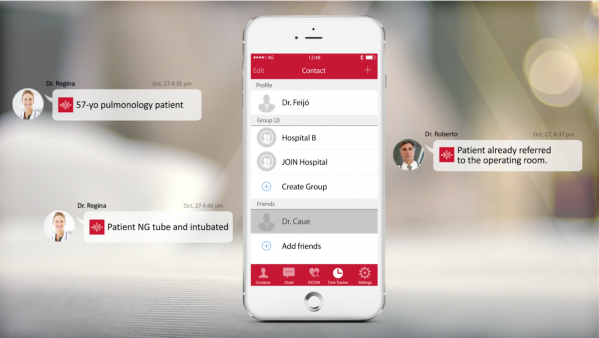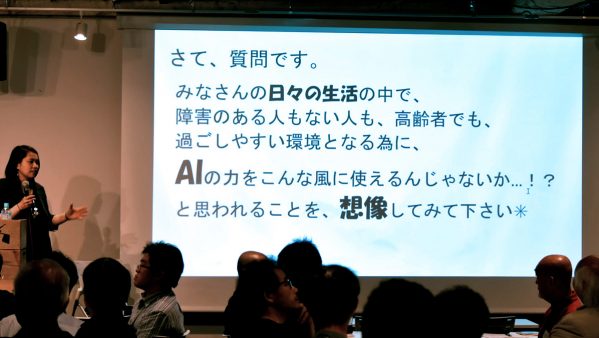フォーミュラ1(F1)の開幕に合わせて、今回はモータースポーツをテーマに特集を組んできた。モータースポーツという側面だけでなく、一般に販売する自動車に搭載する技術を試す場としての役割を果たしてきたF1、しかし今、その役割を終え、衰退へと向かっているという意見が多くある。だが果たしてそうなのだろうか。今回の特集では、F1に打って変わると言われるフォーミュラE(電気自動車のF1)との比較をはじめ、様々な角度からモータースポーツを見てきた。
2030年、新車はみんなEVになる
F1に逆風が吹き始めたと言われる要因の一つが、各国が掲げる脱炭素化の動きだろう。地球温暖化が深刻化している今、CO2の削減に国を挙げて取り組まなければ、生活を守れなくなるというのが理由だ。そんな中、悪者とされているのがガソリン自動車。車のエネルギー供給元をガソリンから電気など他のエネルギーに変えることで排気ガスを減らし、CO2削減を実現するというのが大まかな流れとなっている。そしてすでに切り替えに向けての大波が各自動車メーカーには打ち寄せている。
今年4月にはアメリカのワシントン州で2030年式以降の全乗用車を電気自動車(EV)とする目標を定めた法案が可決された。アメリカ国内では、すでにカリフォルニア州が2035年までにガソリン車の新車販売を禁止する予定を発表していたが、これよりもさらに5年早くワシントン州ではその規制が始まることになる。対象となるのは重量が1万ポンド(約4,536キログラム)以下の、車輪が3つ以上ある路上で走行する車両だ。救急搬送などに使われる緊急サービス車両は対象外となるようだが、日常使いの車の場合はたとえ他州で購入した自動車でも、同州では車両登録をさせないという。ヨーロッパ各国でもこうした動きは加速している。つまり、エコ、脱炭素化のため、ガソリン車を世の中から無くすというのが先進国が目指しているゴールの一つとして掲げられた形だ。こうした流れを受けて、自動車メーカーの中にはF1からの撤退を表明、フォーミュラEへの移行を発表する企業も出てきたのだ。F1に参戦するチーム事態が減り始めているというのもF1衰退論が叫ばれる理由だろう。ガソリン=悪という構図。しかし、この構図が生まれるとき、日本の場合、知っておかなければならないことがある。
10人に一人が関わる自動車産業
ガソリン車の衰退がもたらすもの

日本経済を支える大きな柱の一つ、自動車産業。総務省などによると、日本の就業人口は6724万人、このうちの8.1%が自動車関連の職業についているという。その多くが、ガソリン車の製造に携わってきた。これがいきなりEVや水素エンジンが主流となった場合、どうなるのか。産業に与えるインパクトは相当なものとなり、失業者の増加もシナリオとしては十分に考えられる。
各国の動きを見ても、ガソリン車廃止こそ脱炭素化の近道だという考え方が今は王道だ。しかしこれとて、100%信じられる道筋ではない。EVにはもちろん電気が必要になるのだが、脱炭素化の視点でみると優秀な成績となる原子力による発電に冷たい視線が注がれる今、再生可能エネルギーと言われる風力と水力だけで電力を賄いきれるのか。国民が手の出る価格帯で国全体の車のエネルギーを供給できるのかという問題が残っている。
また、蓄電のためのバッテリーを作るのと、エンジンを作る場合の製造工程で排出されるCO2量の違いについても考えなければならないだろう。
レース自体にかかるCO2は0.7%

F1レースの会場は独特の高揚感が得られる。エンジンの音とニオイ、人間の五感を刺激するものがそこには確かにある。パワフルでマッチョなイメージ。その爆音は排出されるCO2の多さを想起させることもあるだろう。では実際、F1レースでどのくらいのCO2が排出されるのだろうか。あるデータによると、レースにかかるCO2の推定排出量は年間25万5千トンと言われており、環境問題を考える時、批判の的になるのがこの部分だ。しかし、その内訳を見てみると、レースで排出されるCO2量はそのうちのわずか0.7%。なぜなら今、F1のマシンに使われているハイブリッドのパワーユニットは、市場に出回るどの車よりも少ない燃料で電気の供給ができる力を持っている。このため、爆音の割にCO2排出量は市中を走るどの車よりも少ないのだ。
F1を運営するにあたり、もっともCO2を排出しているのが実は運送費だ。約45%がマシンや機材を会場まで運ぶための工程で排出される。スタッフの移動にかかるCO2量を合わせると、それだけで約70%となる。F1のCEO、チェイス・キャリー氏は2019年、二酸化炭素の排出量を事実上ゼロにするというカーボンニュートラル化計画を発表、2030年を目標にCO2排出量をゼロにすると公表した。将来的には機材の輸送、スタッフの移動から各施設の運営まで、全てを再生可能エネルギーの利用で可能にすることを目指すとしている。
モータースポーツの未来はある

メルセデスベンツなど、各国の自動車メーカーが次々と参戦をはじめたフォーミュラEは、F1がガソリン車の先行開発の一翼を担ったのと同様に、EVの実験場としての役割を担っていくことは間違いない。そして、モータースポーツに新たなエンターテイメント性を持たせてくれることになるだろう。F1ファンからすると「物足りない」と評されるのは、高揚感をもたらすエンジンの爆音とニオイがないことも大きい。しかし、静かという点を逆手に取って、既に音楽エンターテイメントとの融合も起きている。もしかするとフジロックのような音楽の祭典とカーレースのコラボレーションがあるかもしれない。
そして、今後の自動車開発は電気自動車一択ということでもない。水素という選択もある中、EVとガソリン、水素それぞれがしばらくは共存することになるだろう。その中で、自動車という形にとらわれない、新しいモビリティが生まれる可能性もある。2035年、ガソリン車販売停止という話をきっかけに、F1は逆境にあるとの声も聞かれるのだが、技術が進み、水蒸気を吐き出す電子タバコが発売になっても、従来の紙タバコを愛煙する人々が消えないように、F1の爆音とニオイをこよなく愛す人たちは、必ず、消えることはないだろう。嗜好品としてのF1は今後も残り続ける。もしかすると、製造工程も含めてトータルで見た場合、ガソリン車が一番エコだということだってあり得る。未来は誰にも分からないが、技術革新のスピードが加速する今、このどんでん返しが無きにしも非ず。
ガソリンか、EVか、水素か、自動車新時代の勝者が誰になるのか、新たなレースが開幕する。
参考文献:https://www.jama.or.jp/industry/industry/industry_1g1.html
関連記事を読む
- 実はスンゴイ経済効果!各国がこぞって開催地に手を挙げるワケ
- モータースポーツは「走る実験室」だった!クルマの安全性はここから生まれた
- いまさら聞けないF1とフォーミュラEの違いとは?
- F1スポンサーの変遷にみる世の中の潮流
- 日本と世界でこれだけ違う!フォーミュラEで見るモータースポーツの捉え方