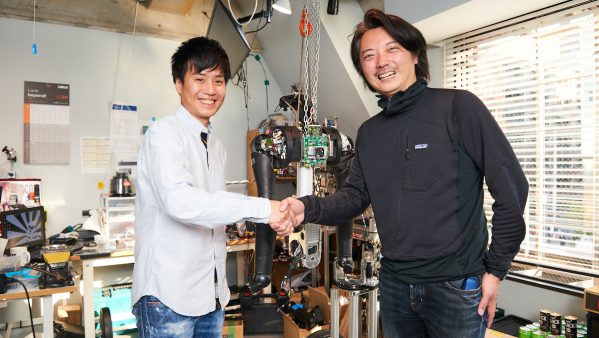2008北京パラリンピックで金メダル、2012ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得した車いすレーサーの伊藤智也選手。その後、現役引退を表明して競技から遠ざかっていたが、2017年にHERO Xにて現役復帰を宣言。57歳という年齢をもろともせず、金メダルを目指す伊藤選手の姿を追う連載である。 東京2020の出場権をかけ、11月7日から開催される「ドバイ2019世界陸上競技選手権大会」。いよいよ目前に迫った10月下旬、沖縄合宿から地元の鈴鹿に戻ってきた伊藤選手に同大会に向けた意気込みを伺った。いつも通り、饒舌な伊藤氏からは自信に裏打ちされた余裕すら感じられた。
 −早速ですが、大会前の体調はいかがでしょうか?
−早速ですが、大会前の体調はいかがでしょうか?
「正直なところ、それほどいい状態とは言えず、腕に痛みがあるんです。今日の(取材時の10月22日)の鈴鹿の気温は27℃と、えらい暑かったので、病巣を刺激してしまうのかも知れませんね。走っているときはさほど気にはならないのですが、日常生活の様々な場面で痛みが付きまといます。とは言え、この病気とずっと付き合ってきましたから、レースに影響するほどの問題ではありません。沖縄合宿から戻ってきた先週の土日はしっかり休みましたが、それからは休むことなく練習に励んでいます」
−次のレース会場であるドバイは日本よりもかなり高温ですが、暑さ対策も行なっているのですか?
「レースは夜間に行われ、平均気温は27℃です。昼間は35℃と非常に暑いそうですが、砂漠の真ん中なので朝晩は意外なほど冷え込むようです。今練習している鈴鹿とほぼ同じ気温で湿度が低く、風が吹けば体感温度はもっと下がるでしょうから、あまり気にならないです」

―RDS代表の杉原氏からの呼びかけに始まったRDSとの取り組みですが、最新マシンとの相性はいかがでしょうか?
「実に素晴らしいマシンが完成しました。日々、走りも進化しています。最新のデータ解析によって、僕のわがままなリクエストをひとつひとつクリアしてもらいましたから。故障もトラブルも何ひとつなく、本当によく走ります。ただ、データ通りの性能が発揮できるように、自分の身体が追い付いていないのが、現時点の課題です。ただ、来年の4月か5月に最高のパフォーマンスを見せられればいいので、現時点ではそれほど焦ってはいません」
―これまでのマシンと比べて、特に改善された点とは?
「一番こだわったのがセッティングです。実は、身体とマシンがぴったり合えばいいというものではないのです。横方向のセッティングは完璧だったので、あとは縦方向に少しだけ余裕が欲しかったため、そのあたりを調整しています。それから、大事なのはホールド感ですね。今回は身体を含めたモノコック(外板に必要最小限の加工を施して強度剛性を持たせる設計)構造を目指しました。乗り込んだ自分がエンジンで、ボディ(マシン)と一体化するようなイメージです。エンジンとボディをつなぐ役割もあるグローブも、データから問題点を改善した特製のものです」

―人馬一体ならぬ、人車一体とも言える、この競技で鍵になるポイントとは?
「自分自身では、空力などの細かなことまでは理解できないのですが、これまでのデータ分析によると(マシンの)ボディはしならない方が、ダイレクトに動力を伝えるということが判明しました。ですから、最新のマシンは非常に固い素材でできています」
―これまで実績のある400mと800mと違って、100m競技ではスタートダッシュが鍵になると思うのですが、伊藤さんの必勝法とは?
「まだ完璧とは言えませんが、自分なりの必勝法はあります。0〜15mまでのスタートダッシュ時のタイムは、今まで4.7秒か4.8秒だったのですが、今日の練習では4.6秒前半まで短縮できています」
―それはすごい進化ですね。新しいマシンに身体がアジャストできているのですね。
「ただ、自分のなかでのアジャストレートは20%くらい。まだフォームの模索中ですが、伸び代しか感じないです。これからはもっと早く走れるはず」

―それは心強いコメントですね。具体的にフォームの改善点とは?
「これまでのマシンは、腕と身体が同時に下に降りるときに、最大のパワーが出る設計なのですが、どうやら新しいマシンは体よりも腕が先に降りた方がいいようです。時計の針で例えると、1時から5時までの位置が一番力をかけるポイントだったのですが、新しいマシンは3時から7時までの位置が最大のトルクが出るポイントのようです」
―もっと腕を後方に回すことが、マシンの性能をさらに引き出す訳ですね。
「これが最終的な正解なのかどうかは、まだ確証がある訳ではないのですが、現時点ではそれがベストなフォームだと考えています。当然ながら、車輪に触れるときの手の角度も変わってくるし、使う腕の筋肉も違ってくるのです。それに対応すべく、自分の身体を鍛えている最中です」
―年齢からくる体力や筋力の衰えはあるのですか?
「いやぁ〜、それは本当にキツイですよ(笑)。この齢になると、筋肉量をこれ以上増やすのは難しく、維持することで精一杯です。競技メインの生活ですから、食事はもちろん大事。練習メニューによっては、炭水化物を多く摂ることもありますが、基本的には肉と野菜が中心ですね。お酒を飲み過ぎるととんでもないことになっちゃうので、そこはちゃんと自制しています(笑)」

―なるほど。練習もマシンも概ね順調に仕上がっていて、ドバイに向けた不安はないということですね。
「はい、その通りです。今までのペース通りで走れば、100mか400mか1500mのいずれかで4位以内に入れば、出場権は獲得できるので、それほど深刻には考えていません。ガッツリ走るというよりは、マシンを壊さない程度に走ればいいのかなと」
―自信たっぷりに答える伊藤選手。それは長年の競技生活による経験と、最新のデータ分析によって導かれたマシンの存在があるからということでしょうか。
「そこには自分なりの計算もあるんです。この競技で上位は日本とアメリカが独占しています。次の大会では全力を出し切るというよりも、少しセーブします。こちらの手の内を明かしてしまうと、相手に研究されてしまいますから。目標はあくまで東京2020で優勝すること。“伊藤もマシンもこの程度か”とアメリカに油断させるくらいの方がいいんですよ。とりあえず、東京2020の切符をしっかり取りに行きますのでご安心ください」
伊藤智也(Tomoya ITO)
1963年、三重県鈴鹿市生まれ。若干19歳で、人材派遣会社を設立。従業員200名を抱える経営者として活躍していたが、1998年に多発性硬化症を発症。翌年より、車いす陸上競技をはじめ、2005年プロの車いすランナーに転向。北京パラリンピックで金メダル、ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得し、車いす陸上選手として、不動の地位を確立。ロンドンパラリンピックで引退を表明するも、2017年8月、スポーツメディア「HERO X」上で、東京2020で復帰することを初めて発表した。