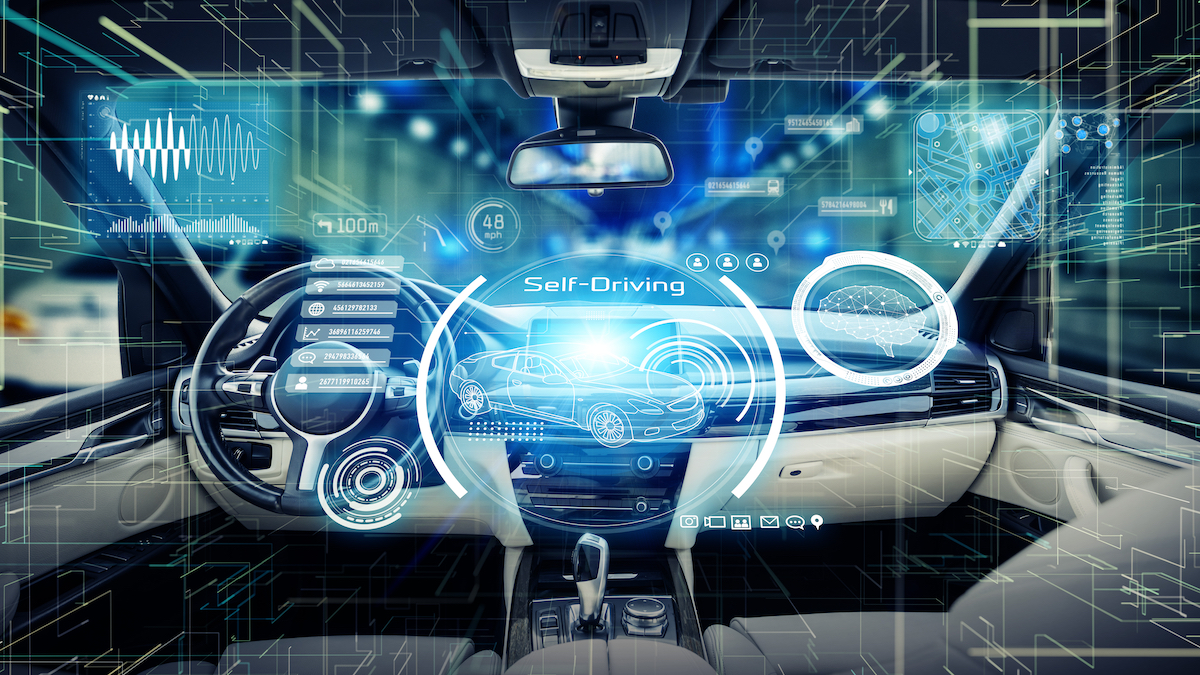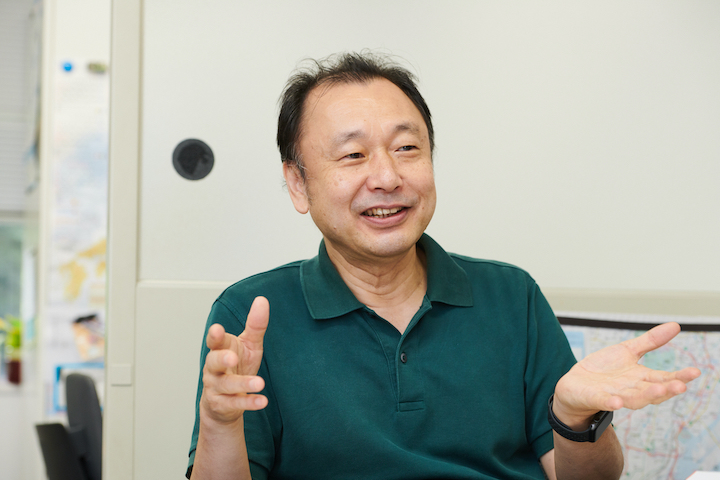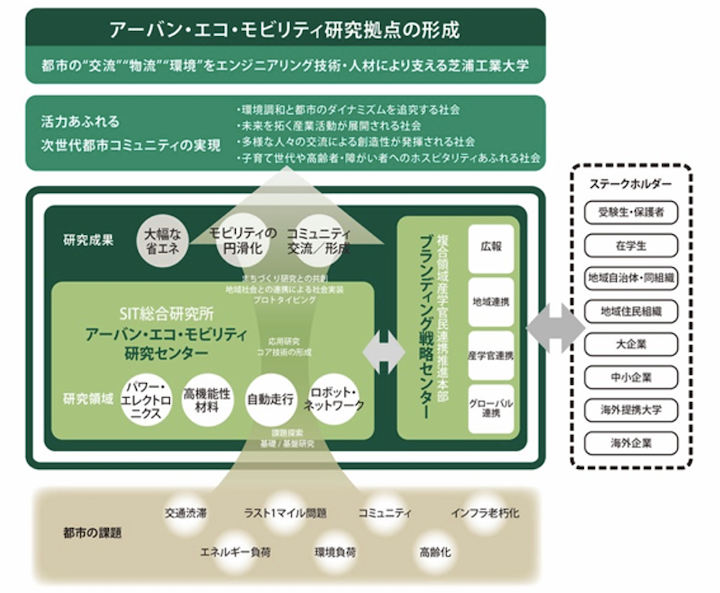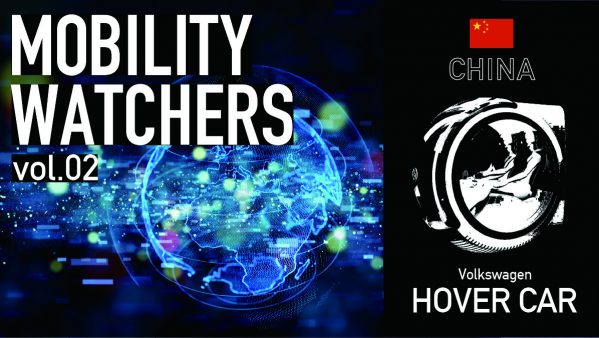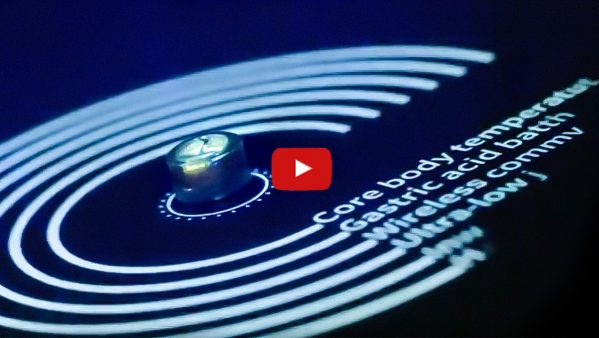サッカー審判用アプリなんて需要あるの?なんて思う方も少なくないはず。驚くなかれ、実は国内だけを見ても審判員の登録数って26万人以上もいるそう。これは、サッカーの母国であり、REFSIXが開発されたイングランドと同等の数。すなわちマーケットとしては十分なのである。さらにここ最近のサッカー人気の追い風もあり、世界的に注目のアプリとなっているのだ。
審判技術の向上は、サッカー界の底上げに繋がる

全世界の競技人口を見ても、1位のバスケットボール(4億5000万人)に次ぐ多さを誇るサッカー(2億5000万人)。日本でも人気のJリーグをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、ましてやワールドカップ開催時には、サッカーファン以外の人も巻き込み、大いに盛り上がる一大イベントとなっているほど。しかしサッカーの試合を見ていても、やはり審判の仕事はあくまでも主役ではなく、影で試合を支えること。
サッカー審判員用アプリ「REFSIX(レフシックス)」は2015年にイングランドで創設され、サッカーの審判の記録をITの力で管理することで、試合の記録や、審判の動きをデータ化し、審判技術の向上からサッカー界の底上げを目指すアプリ。


「試合日程、リーグ、試合名、レギュレーション(競技会規定)、主審、副審など、どの役割を担当するかなどの情報をスマートフォンに入力した後、スマートウォッチに同期し試合に臨むことが可能となりました。
試合中に今までは紙に記録していた、イエローカード、レッドカードの枚数、交代や得点の記録をすべてスマートウォッチで管理できるようになったことはかなりの進歩なのです」。そう語ってくれたのは、現役の大学生でもあり、自身も2級審判員として活躍するREFSIX JAPANの広報・本田大晟氏。さらにこう話しを進める。
「そこから更に派生し、心拍数や試合中に走った距離や自分がいた場所といったパフォーマンスのデータも可視化できます。それらを蓄積していくことで、自らのジャッジの傾向や動き、ウィークポイントをデータとして扱い、審判技術の向上へと繋がっていくわけです。もちろんデータをどう活かすかは個々の判断にはなりますが、REFSIXの真の意義は、そこにあると思っています」


肝心な日本での普及率はいかに?
「日本版をリリースしてからちょうど1年ほど経つのですが、最初は『何だよそれ?』『本当に大丈夫なの?』みたいな、受け入れない空気が正直強かったです。そう考えると、どう馴染んでいかせるかが最大の課題。アプリ自体がクラッシュしてしまうことはほぼないので、安心して使用してほしいと思ってはいるのですが。
『いきなり試合中に電池無くなったらどうするの?』って言われても、それはさすがに自己責任の問題じゃないですか。紙だって飛んでいったり、濡れたり、破れたりしますよね。とは言うものの、それがREFSIXに対する率直な不安なんだなと真摯に受け止めなくてはいけません。いかに不安を取り除いていくかも、普及率を上げるのに重要な点だと認識しています。それでも、リリースから1年経つと、『君も使っているんだ』みたいな会話とかも一緒に審判する人たちからも聞こえてきたりして、若い世代の審判員には徐々に広がっているなと感じています」
他国の話にはなるが、先日アメリカで開催されたダラスカップでは、大会運営側のバックアップを受け、多くの国際審判員に試してもらう機会を得ることができたという。アメリカという国柄を象徴するダイバーシティをコンセプトに、グローバリゼーションとデジタリゼーションを表す「ダラスカップエクスペリエンス」を具現化したこの大会は、今や世界でも有数の国際ユース大会に成長したいい例でもある。
このような世界的な動きがあるなか、日本の審判協会に対しても、REFSIXの普及に関しての働きかけは続いている。また、アプリの進化に対して普及率アップは欠かせない。現状でもほぼ隙がないほどの完成度の中、さらなる進化を目指すならばどのような部分があるか尋ねてみた。
「試合の部分でいうとほぼ出来上がっていると思います。今後はルールの変更にいち早くどう対応できるか。例えば、イギリスのアマチュアリーグではすでに採用されているルールなのですが、ラグビーのルールにある『シンビン(一時的退場)』が導入されたんですね。
試合時間、ロスタイムに続き、選手1人だけとは限らないシンビンという新ルールが加わると、どう時間を計測するかが大きな問題になりますよね。そこの対応が、いち早く、より簡単に出来ればREFSIXが普及できる大きなチャンスなのかなと思っています」

「REFSIXが開発されたイングランドのプレミアリーグ等のトップカテゴリーと言われるプロリーグでは、すでにリーグ毎に開発した審判用システムが実は存在しているんです。ただそれではプロのためのシステムでしかないので、審判員全体の0.1%以下にしか使われないという現実もあります。だからこそ、技術の進歩が著しいスマートフォンやスマートウォッチを使うことによって、審判界全体に浸透させることができるのではないかと考えています」
現状のサッカー審判の世界だけはなく、スポーツ界全体をみても、一般的な世界と比べるとIT化が遅れている現実がある。データの活用という面をみたら尚更。そういった意味も踏まえ、今後は他のスポーツにも対応できるようになっていくのだろうか?
「まずは、一番サッカーの審判に近いラグビーですね。すぐにリリースというよりかは、来るべき時が来たらすぐに対応できるよう、すでにプロトタイプ版はできています。フットサルやハンドボールなども考えられますが、そこでネックになるのが、スポーツがマイナーになるとそれに関わる人口も減っていくというところ。ある程度のマーケットの大きさは必要なのかなと考えています」
最後に、REFSIXが切り拓く未来をどのように捉えているか尋ねてみた。
「選手はテクノロジーを取り入れたトレーニングによって、競技スピードや競技自体のレベルが上がっていることに、審判自体がついていかなくてはならない。そこについていくために、自分が審判をした試合の情報を、正しくデータとして扱うことができるようになったということは、サッカー界の発展に繋がると信じています」
現役の大学生である一人の青年が、日本のサッカー審判会に変革を起こそうとしている。この若い力を信じ、サッカーだけはなくスポーツ全体の進展をこれからも期待したい。
REFSIX JAPAN
https://refsix.com/japan
japan@refsix.com