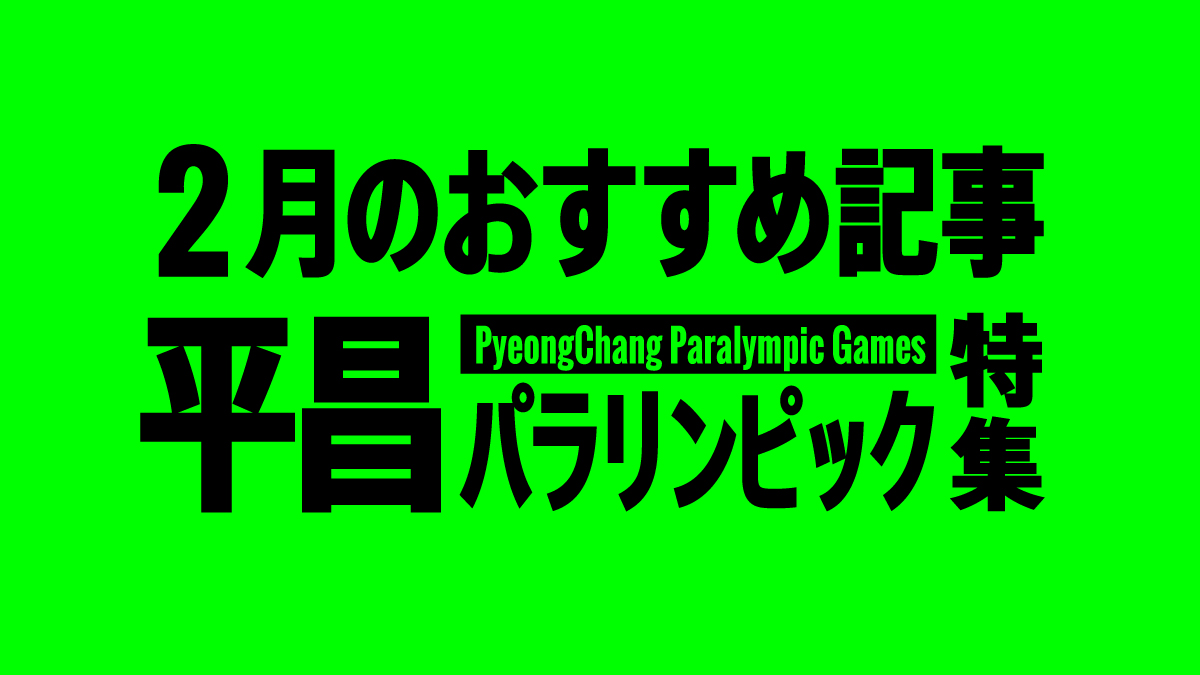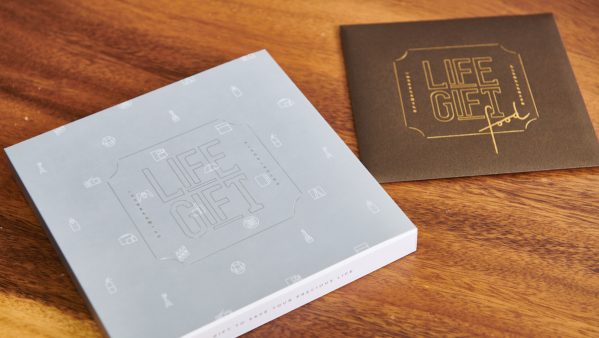3月18日に閉幕したピョンチャンパラリンピックで、最も注目を浴びた競技のひとつ、チェアスキー。W杯個人総合2連覇を達成した世界王者・森井大輝選手(=トヨタ自動車)は、狙いを定めた金メダルには、惜しくも届かなかったが、滑降で銀メダルを獲得し、4大会連続のメダル獲得を達成。鈴木猛史選手(=KYB)がスーパー大複合で4位に入賞するなど、次々と嬉しいニュースが飛び込んできた。なかでも、日本勢初の金メダルを含む5個のメダルを獲得し、出場全種目で表彰台に立った女子大生チェアスキーヤー・村岡桃佳選手(=早大)の活躍は、目覚ましい。1大会で金・銀・銅メダルを完全制覇したのは、実に、1998年長野大会の大日方(おびなた)邦子さん以来のこと。この大快挙によって、チェアスキーというスポーツが、今まで以上に多くの人に知られたことは間違いない。チェアスキーの魅力とは? 今後のスポーツの発展は、いかに? 冬季パラリンピックにおける日本人初の金メダリストであり、チェアスキー競技で、冬季大会日本選手最多記録の合計10個のメダルを獲得したチェアスキーの第一人者・大日方さんに話を伺った。
チェアスキーを普及させることは、私の夢

―近い未来、障がいの有無に関係なく、誰もが楽しめるスポーツになってくれたらいいなと思うのですが。
障がいのある人もない人も一緒に楽しめるレースができたら、面白いですよね。以前から、そう思っていて、色んな方にお伝えしていて、どなたか、そろそろ実現してくださらないかなと期待しているのですが(笑)。スキー場に行けば、スキー用具と同じ感覚で、チェアスキーをレンタルできるようになったら良いなと思います。
RDSさんでは、大輝(森井大輝選手)や桃佳(村岡桃佳選手)、夏目くん(夏目堅司選手)の体にぴったり合った精密なシートを作っていただいています。それと同じで、チェアスキーを普及させようとした時、シートのサイズを滑る人の体に、ある程度合わせていく必要が出てくると思います。
S、M、Lのサイズ展開だと、少しざっくりしているため、滑りにくいと思います。そこに、縮めたり、広げたり、微妙なサイズ感をその場で簡単にアジャストできるような工夫が加わると、理想的ですね。
―洋服でいうところのセミオーダーみたいな感じですか?
そうですね。セミオーダーのような感覚で、シートのサイズをパパッと調節できるようになれば、普及は進むと思います。あるいは、3日ほどしかもたないけれど、自分の体にぴったり合ったシートなどでも、最初はいいかもしれません。すると、「チェアスキーをやってみたい」と思った人が、障がいの有無に関係なく、誰でも気軽に試せるようになりますし、選手を目指す若手が生まれるきっかけにもなるかもしれない。スノーボードが出始めた頃、「あれ、何だろう?」って、みんなが言っていましたよね。でも、今では、普通に誰もが楽しめるスポーツになった。それと同じ感じで、チェアスキーを普及させていくことは、私の夢のひとつですね。
―今後、チェアスキーの魅力をどんな風に伝えていきたいですか?
例えば、チェアスキーの体験会を開催するとなった時、実現できたらいいなと思うアイデアが2つあります。ひとつは、ローラーを付けた試乗機。参加者の方にとって、よりイメージしやすくなるのではないかと思います。もうひとつは、アスリートの追体験ができるVRエンターテインメント。車いす型VRレーサーを開発したワン・トゥー・テンの澤邊芳明さんとは、「チェアスキー版を作りたいですね」、「できれば、ダウンヒル(滑降)の世界をぜひ体験して欲しいです」などと、お話を重ねさせていただいています。
実現するためには、色んな方の知恵や技術や力が不可欠ですので、言い続けてきました。「じゃあ、やってみましょうか」と言ってくださる方がさまざまにいて、有り難いかぎりです。数年以内に、実現するような気がするのですが、どれだけリアルに感じられるものが作れるかということが、肝になってくると思います。
チェアスキーヤーも、スノーボーダーも
どんどんカッコよくなって欲しい

―ところで、2018年ピョンチャン大会から、冬季パラリンピックの正式競技に加わったスノーボードについては、どう思いますか?
面白いスポーツだなと思います。先日、ある国内大会を観に行ったのですが、昨年よりも難易度を上げて、パラリンピックを意識したコース設定にしたというので、ちょっと滑らせてもらったんですよ。スノーボードクロスのコースに、どさくさに紛れて、チェアスキーで入っていって(笑)。すごく楽しかったですね、現場が好きなので。
その大会は、障がいがある人もない人も、一緒になって競い合うんです。スノーボーダーたちは、障がいの有無に関係なく、共に楽しんでいる風に、私には映りました。その精神を忘れずに、ぜひ開催を続けていって欲しいですね。それによって、スノーボード人口が増えて、スポーツとして広がっていくといいなと思っています。
―大事なことは、そのスポーツが好きかどうか、楽しいかどうか。一緒に楽しむ気持ちということですね。
ピョンチャンオリンピックのスノーボードの解説で、「スタイル入ってます」という表現があったじゃないですか。あれって、みんな共通で使うということが、先の大会に行って分かりました。パラスノーボードの選手たちは、義足を見せて滑るので、「寒くない?」と聞いたんです。すると、「冷たいかもしれないけど、スタイル入ってるし」って(笑)。“こっちの方が、カッコいいよね”という意味ですね。スタイルを求める姿は、大輝(森井大輝選手)などにも、共通する部分ですよね。チェアスキー日本代表の男性選手は、皆さん、すごくこだわりがあるでしょう? どんどんカッコよくなって欲しいと思います。
あらゆるスポーツを自由に楽しめる日本になれば

―この先、どんな世の中になることを望みますか?
誰もが、色んなスポーツを楽しめるようになれば良いなと思います。もちろん、ひとつの競技を突き詰めることも素敵ですが、「これからスポーツを始めよう」という人にとって、障がいの有無に関係なく、さまざまな競技を気軽に体験できるようになると、きっと楽しみも倍増しますよね。
「このスポーツをやってみたい」となった時に、「ここに行けば、できますよ」、「こんな工夫をしている人がいますよ」といった情報が、誰でもすぐに得られるような、そんな時代になるといいなと思います。
現役時代に、バンジージャンプやスカイダイビングを海外で体験したことがあります。バンジージャンプは、20年前のニュージーランドで、胴体にハーネスを取り付けて飛びました。また、スカイダイビングは、足に障がいがある人の場合、タンデム体制だと飛ぶことができるんですね。残念ながら、日本では、まだあまり知られていませんが、これらの競技も含めて、みんなが、スポーツを気軽に楽しめるような世の中になるといいですね。個人的には、今、ボルダリングにチャレンジしてみたいと思っています。なんだか、面白そうじゃないですか(笑)。
ピョンチャン大会では、日本選手団を率いる団長を務めた大日方さんいわく、「チェアスキー日本代表チームは、どんどん強くなっている」という。「98年の長野大会以来、メダルを逃したことがないんですよ。身近にメダルを獲得した選手がいると、その選手を超えようと、自分たちもさらに高みを目指して頑張ろうという次のモチベーションに繋がる。その好循環が、多分、チームの強さの秘訣なのかもしれません」。日本屈指のチェアスキーヤーたちが、さらに強く進化していく勇姿を今後も追っていく。

大日方邦子(Kuniko Obinata)
1972年東京都生まれ。3歳の時、交通事故により右足を切断、左足にも重度の障がいを負う。高校2年の時にチェアスキーと運命的に出会い、スキーヤーとして歩み始める。冬季パラリンピック日本人初の金メダルを獲得した1998年長野大会を含め、リレハンメルからバンクーバーまで、アルペンスキー競技で5大会連続出場。合計10個のメダル(金2個、銀3個、銅5個)を獲得し、冬季大会日本選手最多記録を更新。2010年9月、日本代表チームからの引退を表明。以後、電通パブリックリレーションズの社員として、公職活動に従事しつつ、スポーツを取り巻く社会環境の改善に取り組むほか、「誰もが安心して生きられる社会」を目指し、多様性を許容できる社会の普及に資する活動にも取り組んでいる。日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副会長、スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック教育に関する有識者会議委員、内閣府障害者政策委員会委員。女性のパラリンピアン、メダリストとしては夏冬通じて初となる選手団長に就任し、2018年ピョンチャン大会の日本選手団を率いる大役を務めた。