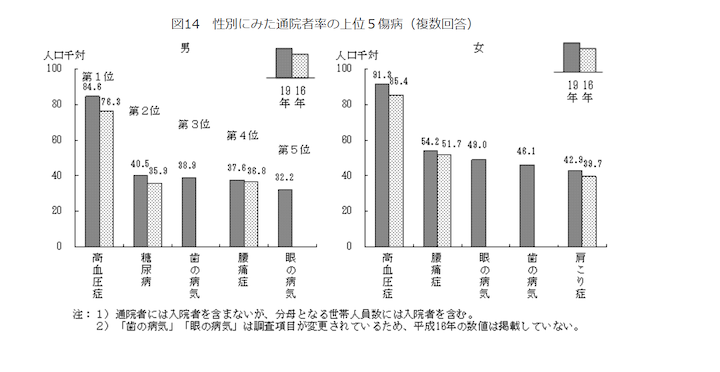トラックを颯爽と駆け抜けるパラアスリートの身体と義肢の見事な融合は、義肢装具の製作や調整を行うプロフェッショナルである義肢装具士の存在なしに実現しない。日本の義足陸上競技選手初のパラリンピック・メダリスト山本篤選手や、リオパラリンピック4×100mリレー(T44)で銅メダルを獲得した佐藤圭太選手など、名だたるトップアスリートの義肢装具を手掛ける義肢装具士の沖野敦郎さんは、「選手が、100%の力を発揮できる義肢装具を作りたい」と話す。なぜ、ジャスト100%にこだわるのか。東京都台東区・蔵前の一角にあるオキノスポーツ義肢装具(以下、オスポ)の製作所で沖野さんに話を伺った。
義手アスリートの第一人者と共に歩んで、はや10年

©吉田直人
昨今、義肢装具というと、義足の開発にスポットライトが当たることが多いが、義手もまた、トラックを全力疾走するパラ陸上アスリートの体の一部となる不可欠なツール。沖野さんは、リオパラリンピック男子4×100mリレー(T42-47)で銅メダルを獲得した多川知希選手の義手製作を、2008年北京パラリンピックイヤーから現在に渡って手掛けている。
「出会った頃の多川選手は、義手を付けずにレースに出場していました。クラウチングスタートの時の彼を見ていると、生まれつき右前腕部が短いので、右肩が下がっていて、出づらいのでは?と思ったんですね。私も、元々陸上をやっていたので、身体のバランスを左右並行にした方がパフォーマンスも上がると思い、ちょっと提案してみたのです。“義手を付けた方が、早くスタートを切れるんじゃない?”と。でも、彼にとっての私は、出会ったばかりのいち義肢装具士。その時は、“別にいいです”と言われましたが、それからしばらくして、遠征先のドイツから電話がかかってきたんです」
当時、スタートダッシュの安定性に悩んでいた多川選手は、多くの海外選手が、義手を付けているのを目の当たりにし、自分も試してみようと思い立ち、沖野さんに製作を依頼した。義手以外にも、左右のバランスを取るためには、台を置くという選択肢もあったが、走り出す時に、誤って台を蹴り飛ばすなど、他の選手の走路妨害になるようなことは避けたい、レース以外のことに気を使わず集中したいという想いもあった。

多川選手が、日本の義手アスリートの先駆者となったのは、かつて沖野さんがふと投げかけた助言が全ての始まりだ。
「今、多川選手の義手は、第4世代くらいです。義手を付ける方の腕は、筋力が弱いので、重いものが付いた状態で振るのは大変。ですので、軽量化することを最優先に製作しています。ただし、軽くすることが最良の手段であるかは、まだ分かりません。選手と対話を重ねながら、製作の方向性を決めています」
多川選手の義手開発で培った技術は、日本人のパラアスリートで唯一、義手と義足を付けている池田樹生選手の義手製作にも活かされている。その他、沖野さんが義手の製作を手掛けた選手からは、「手が伸びた感覚が得られることによって、左右のバランスが取れて、腕が振りやすくなった」という声も挙がっている。
「2020年の東京パラリンピックで使用する義肢装具は、2019年には完成していないといけません。それらを使用する選手が使いこなすために時間を要するからです。そのために時間を逆算しており、すでに動き出しています。義手について、もう一つ目指しているのが、風を切る形状にすること。頭の中に、構想は色々とあるのですが、一点ものですし、具現化するにはかなりの資金がかかります。現在は、補助金採択可否の結果待ちの状況です」
子供から大人まで、走りたい人が集う
“オスポランニング教室”

「義肢装具製作所って、料理店に似ていると思うんです。辛いのが好きな人もいれば、甘いのが好きな人もいますよね。この人には甘いものが喜ばれたから、あの人にも同じものを作るというのではなく、それぞれの好みに合わせてカスタマイズしていく意味では、すごく似ているなと。唯一違うのは、義肢装具製作所の場合、“合わなければ、他(の製作所)に変えればいい”とは、中々いかないところです。製作所の数は限られていますし、義肢装具を作るために、国や役所と契約を結んだりするので、変えるとなると、ユーザーさんは、かなり煩雑な手続きを踏まなくてはいけない。ゆえに、なんとか満足のいくものを作って欲しいという思いで皆さんいらっしゃいます」
その期待に応えるべく、奔走する日々を送るかたわら、沖野さんは、2016年12月から、新豊洲Brilliaランニングスタジアムで、月1回のオスポランニング教室を開催している。このランニング教室は、オスポで義肢を作った人だけでなく、子供から大人まで、義足で走りたいという人なら誰でも参加できる。日常用義足を使った正しい歩き方や、スポーツ用義足の板バネの使い方などについて教えながら、沖野さんも彼らと共にトラックを駆け抜ける。
「当初は、弊社にあるスポーツ用義足の部品を貸し出していました。おかげさまで、参加者の方が徐々に増えていき、板バネが足りないなと思っていたところ、昨年10月にギソクの図書館ができたので、コラボレーションじゃないですけれど、ぜひ利用させていただきたいなと思いました」
ギソクの図書館とは、スポーツ用義足を自由にレンタルできる世界初のユニークなライブラリー。その発案者である遠藤謙氏は、スタジアムに併設する義足開発ベンチャー「Xiborg(サイボーグ)」の代表も務める。
「板バネを開発する企業はこれまでに幾つもありましたが、Xiborgが他とは大きく異なるのは、遠藤さんという素晴らしい義足開発のスペシャリストがいて、義足をどう使いこなすかを教えてくれる為末大さんがいたこと。そこに、義肢装具士が携わって、取り付けや調整を行う。三位一体と呼ぶにふさわしいこのシステムは、まさに私が求めていた理想形でした」
100%に、100%で応えるモノづくりを

パラリンピックという世界の大舞台や世界選手権大会で活躍するトップアスリートたちの義肢装具について、沖野さんは揺るぎない信念をもって製作にあたっている。
「私は、選手の力を100%発揮できる義肢装具を作りたい。120%というとおかしいんですよ。なぜなら、20%は装具の力ということになるから。モータースポーツは別として、パラリンピックに限定すると、部品に動力があってはいけません。あくまで、選手主導で動かしていくものに対して、力を発揮できなければならないのです。今も昔も、選手が100%の力を加えた時に、100%跳ね返ることができる義肢装具を作ることを心がけています」
「自分の義肢装具に対して、不満を抱えて、不安な表情をして来られた方が、納品した時に、満足した表情で帰られる時、一番の喜びを感じる」と言う沖野さんに、パラスポーツから広がる可能性について尋ねてみた。
「実は、私自身、パラスポーツという言葉があまり好きではありません。パラスポーツというよりも、障がいの有無に関係なく、道具を使う“ツールスポーツ”といった新たなジャンルが生まれ、発展していけば、障がい者スポーツや健常者スポーツという区別もなくなって、車やメガネのように、義肢装具もまた、人々の動作を補助するツールとして認識されるようになるのではないかと思います。ツールスポーツに、私のような義肢装具士が携わるという形になれたら、理想的ですね」
「Liberty(自由)」、「Originality(独創)」、「Seriously(本気)」。オスポが掲げる3つのコンセプトを体現した若き義肢装具士・沖野敦郎。義肢装具の未だ見ぬ世界を拓く彼の挑戦はまだ始まったばかりだ。
沖野敦郎(Atsuo Okino)
1978年生まれ、兵庫県出身。オキノスポーツ義肢装具(オスポ)代表、義肢装具士。山梨大学機械システム工学科在学中の2000年、シドニーパラリンピックのTV中継で、義足で走るアスリートの姿を見て衝撃を受ける。大学卒業後、専門学校で義肢装具製作を学んだのち、2005年義肢装具サポートセンター入社。2016年10月1日オキノスポーツ義肢装具(オスポ)を設立。日本の義足陸上競技選手初のパラリンピック・メダリスト山本篤選手やリオパラリンピック4×100mリレー(T44)で銅メダルを獲得した佐藤圭太選手の競技用義足、リオパラリンピック男子4×100mリレー(T42-47)で銅メダルを獲得した多川知希選手の競技用義手や芦田創選手の上肢装具など、トップアスリートの義肢製作を手掛けるほか、一般向けの義肢装具の製作も行う。
オスポ オキノスポーツ義肢装具
http://ospo.jp/