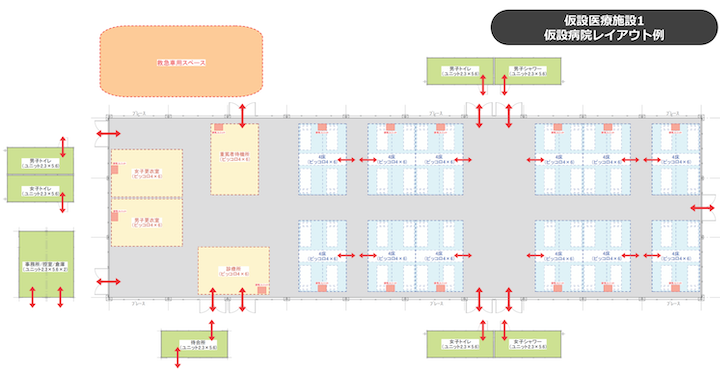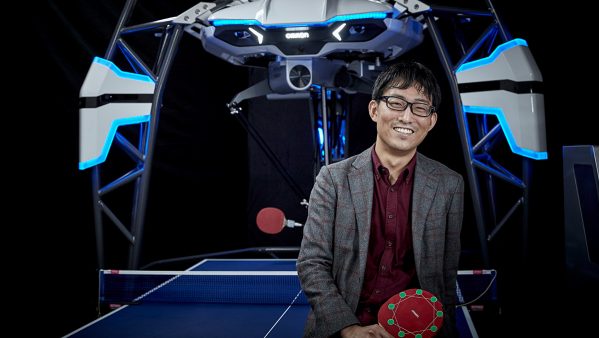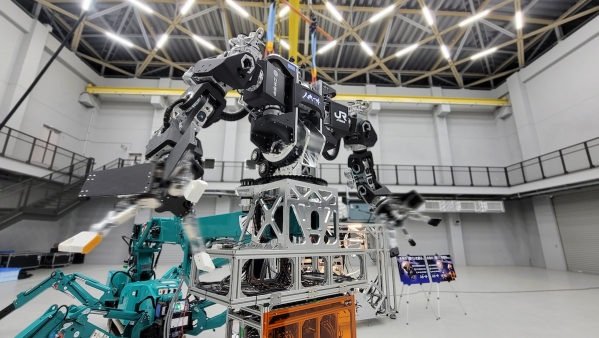今後、IoTの普及に必須となる5Gインフラ。 イギリスウェールズ州南部にあるスウォンジー大学では、この技術を使った“スマート包帯”の研究開発が着々と進められている。患者の状態をリアルタイムで経過観察できるウェアラブル医療機器の登場によって、ヘルスケアの未来はどう変化していくのだろうか。
スウォンジー大学が研究開発中のスマート包帯は、火傷や糖尿病などによる創傷を負う患者のために考案された。病院から遠い場所に住んでいたり、何らかの理由で通院できない患者など、遠隔での経過観察を実現するために、5Gをベースに、患部の状態を感知するナノセンサーを採用している。そのデータは、3Dプリント技術によって、微細に視覚化され、スマートフォンを通じて、直ちに医師側に送信される仕組みだ。
「スマートフォンを通じて、5Gインフラと創傷を繋ぐことによって、その人の居場所や健康状態を把握することも可能にします」と、同大学Institute of Life Science学部長のマーク・クレメント教授は話す。
感染症や慢性創傷を抱えている患者は、病院に再診する前に病状が悪化することもあり、最悪の場合、切断に至るケースも多々ある。リアルタイムで経過観察できるスマート包帯なら、患者の状態に応じて、その都度、必要なカスタムメイドの治療を提供できるので、不測の事態を防ぐことにも繋がる。

引用元:https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/professional-advisory-firm-pwc-moves-10801971
2017年4月、12ヶ月以内に臨床試験を開始すると発表されたスマート包帯。13億ポンド(約1859億7997万円)を費やして行われているこの研究開発が成功し、実用化が実現すれば、医師は、患者の自己申告によるデータに頼らずとも、より正確なデータを得られるようになり、効率的な病状の改善が期待できると共に、患者それぞれのライフスタイルに合ったヘルスケアの提供が可能になる。
今、メディカル・イノベーションが、健康の新たな時代を拓こうとしている。
[TOP画像引用元:https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-39590851]