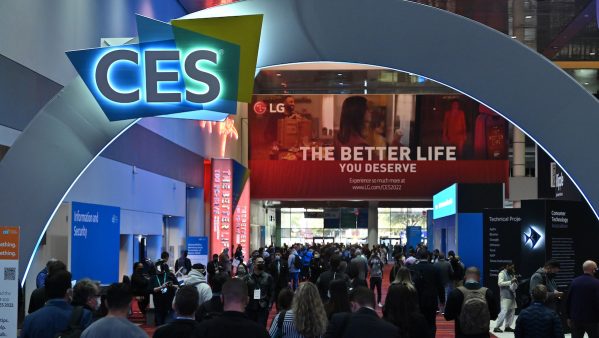ロボットと一口に言っても様々なものがある。一般に思い浮かべるのは工場や倉庫などの労働現場で稼働する産業用のロボットだろう。ごく一部のエンターテインメント系ロボットを除けば、ニュースになるのもそういった“役立つ”ロボットたちだ。そんな中、新しいロボットとのかかわりを提案しているラボが、株式会社4REだ。イベント用巨大ロボ「MEGABOTS」を擁する彼らの動きに注目!
日本でいち早くアメリカの巨大ロボ「MEGABOTS」を取得、カスタマイズして展開している4RE。制御盤のエンジニアリングメーカーであり、自動配達ロボ「HAKOBOT」なども開発する株式会社三笠製作所と株式会社RDSが新たに立ち上げた次世代型ロボットセンターだ。立ち上げにあたっての話しはHERO Xで行なった対談に詳しく掲載されている。
MEGABOTS社の巨大ロボットが、
あなたの街にもやってくるかも!?
「MEGABOTS」は、人が操縦席に座って操作する「ガンダム」のようなロボット。まるでアニメや特撮映画に出てくるような「コックピット」型の、SF感溢れる機体が魅力のロボット。高さ4.5メートルの大型ロボットで、実際に操縦できるというのは国内ではまだ珍しい。格闘家の朝倉未来のYoutubeを始め、人気Youtuberの動画などでも紹介され、また去年10月にはフジテレビの人気番組『逃走中』にも登場した。
最近はロボットというと、何に役立つのか?とすぐに考えてしまうが、4REが提案しているのは、ロボットとの新しいかかわり。前述の「MEGABOTS」はイベントなどのシーンで、ゲストが実際に試乗でき(操縦は4REのドライバーが担当)、ランチャーからTシャツなどの景品を発射することができる。エンジニア・ドライバーを派遣しての純粋なレンタルとして稼働させているのだが、主催者側のニーズに応じてカラーリングなどのカスタマイズにも対応している。
「MEGABOTS」だけではなく、4REではオリジナルロボットの製作を受注する「ロボット製作所」のプロジェクトも実施している。この取り組みのユニークなところは、単にロボットを作るというだけでなく、ロボットを使ったソリューションや広告展開、プロモーションの提案までを行なっていることだ。
同社によれば、「ロボット」を核とした、様々なビジネスの展開をパートナーと考えていくという。また、ロボットビジネスのコミュニケーションのありかたも提案したいのだとか。
小さい頃には誰もが憧れていたロボットという存在。それがいつの間にか、味気ないものになってしまってはいないだろうか。もちろん、実用ロボットの存在は今の日本の産業には欠かせない。しかし、夢を描くことで切り拓かれていくテクノロジーもあるだろう。まずは「MEGABOTS」の操縦席に座り、失われていたロボットへの夢を取り戻してみたい。
問い合わせ先
株式会社4RE:info@4re.tokyo
公式サイト:https://4re.tokyo/