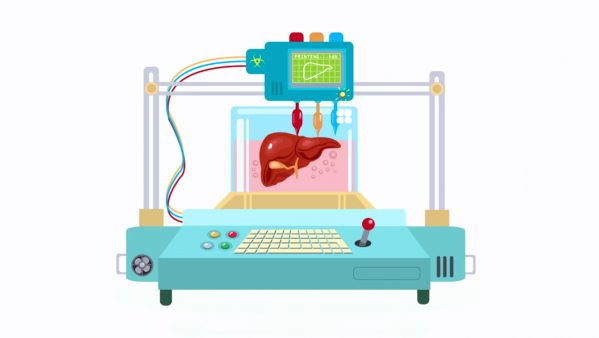F1ドライバーとして活躍、現在は社会福祉法人の理事や政治家としても活躍する山本左近氏。前編では、F1で生み出された車の技術がどのように社会へと落とし込まれていくか、また、福祉の世界に身を置くことで見えてきた「食」という課題についてHERO X編集長の杉原行里が話を聞いた。後編ではどんな話が飛び出すのだろうか。
世界と戦うためにはスピード感と判断力がカギ

杉原: 前半ではF1から社会に落とし込まれる技術や山本さんが作られた新しいスタイルの介護食の話を伺ってきましたが、世界中をめぐってきた山本さんから見て、昔と今で、変わってきたなと思われるのはどのようなことでしょうか。
山本:50年前と今で、最も変化したのはスピード感だと思います。例えばイギリスから見た世界と日本から見た世界って見てる視点が違うじゃないですか。視点が違うのは当然なんですけど、それぞれの国の歴史や発展の状況により、世の中が動いていくスピード感が違うんですよね。残念ながら過去10年ほどで世界における日本のプレゼンスは下がっていっているという印象を受けていますが…。日本が下がっているのか、諸外国が上がっているのかバランスはあるとは思うのですが、日本はやはりスピード感が失われているんじゃないかと。例えば白物家電の分野など日本が得意としていた領域においても負けてしまっている状況があり、あまりにも完璧なものを作ろうとしすぎてしまっているがゆえに、スピード感が犠牲にされている気がします。スピード感というのは、これからグローバルな社会になっていく中ではとても大事なキーワードだと思っていて、いかに応用するのかと同時に、いかにスピード感を持った判断ができるかだと思います。
杉原:F1なんて判断力がなければもう終わりですよね。
山本:そうですね。1000分の1秒ごとに判断を求められるスポーツですし、300キロで走ってたら1秒間で約80メートル進むわけですよ。1秒迷った瞬間に壁にぶつかってしまいますよね。そういう世界で常に判断を続けてきましたから、もしかすると、判断スピードの大切さについては他の方よりも敏感なのかもしれませんね。
新しい方法も恐れずに取り入れる勇気

杉原:僕が今年初めに当媒体でコラムを書いたテーマが、「自分ごと化」なんですよ。山本さんも「自分ごと化」というのをキーワード的に書かれているのを見て、おっ!と感じました。自分がそれに関係しているかということがその人にとって、自分を突き動かすうえではすごく大事なことだと思っていて、僕達の年代でいうと、親がどんどん高齢になってきていますよね。そうすると、車いすって結構自分ごと化になってくるんです。今、山本さんが掲げられているキービジョンのように、一般の人たちが少しでも自分ごと化していくには、僕らにどういうマインドがあると良いと思いますか?
山本:怖がらないことですね。人間は本質的に、自分の知らないことや、今まで無かったものに対しては恐怖心を感じると思うんですよね。構えちゃったり、関係ないと閉ざしてしまったり。でも、次なる未来を見たときにいろんな課題があるなかで、その課題解決をしていくためには、新しい方法も取り入れなきゃいけないし、今あることだけを継続していては破綻してしまう未来が見えているじゃないですか。もちろん今まで培ってきた技術や制度は素晴らしいもので、今すぐ変えなきゃいけないとは思っていないですが、未来に目を向けたときに、人口構造が変わったその時に社会システムが変わらなくていいのかなと考えると、どこかで変換していかなくてはいけないと思います。みんなが幸せになるためにイノベーションが必要なんですが、ここにつまずきがあって、イノベーションが起きるときというのは、今までの自分の生活が脅かされるんじゃないかとか、大変な生活になるんじゃないかと思いがちなんです。ですが、12、3年前に iPhone は世の中に存在してなかったじゃないですか。でも iPhone が出てきたことによってコミュニケーションの手段が変わり、コミュニティーのあり方が少し変わった。でも、人が人として生きていくうえで大切なものは昔から変化していないんですよ。なので、あんまり構えず、受け入れる幅を持つことが大切だと思いますね。
杉原:今まで様々な方々に取材をしたなかで、医療や福祉の分野で何か新しいものを導入しようと思うと、日本の場合は段階を踏まないと導入できず、時間がかかってしまう。そうすると、今、世の中に出していきたいと思った時に、スピード的に世界に負けてしまうということをよく聞きました。なかには、先に別の国で発表しておいて、日本に逆輸入のような形にしようと考える会社もでてきている。そのあたりの日本のスピード感についてはどのように考えていますか。

山本:日本で導入するのに時間がかかるのはなぜかというと、人の命に関わるものなので、100%完成されているものでなければ認められないんですよね。そこは僕も納得できます。でも、例えば画像診断ソフトの補助的運用、最終的に医師が判断するための補助的ツールという使い方であれば、それは80%の完成度でもいいと思うんです。トライ&エラーが繰り返されて100%になるので、80%の技術を100%にするという最終的な部分は、実は一番大変で時間がかかる部分なんです。そこが100%になってはじめて世の中に出るというのが今の日本の基準。しかし、直接的に人への影響が少ないであろうモノに関していえば、僕は80%でもある程度のゴーサインが出るような仕組みの方がスピード感は上がると思いますし、そうすることによって進化が加速していくと思います。
前編はこちら
山本左近
愛知県豊橋市出身。1982年7月9日生まれ。36歳。豊橋南高校卒業、南山大学入学。1994年、レーシングキャリアスタート。2002年、単身渡欧しF3参戦。2006年、当時日本人最年少F1ドライバーとしてデビュー。以降2011年まで欧州を拠点に世界中を転戦。2012年、帰国後ホームヘルパー2級を取得。医療介護福祉の世界に。医療法人・社会福祉法人 さわらびグループの統括本部長就任。 現CEO/DEO。全国老人保健施設連盟政策委員長。自由民主党愛知県参議院議員比例区第六十三支部長。