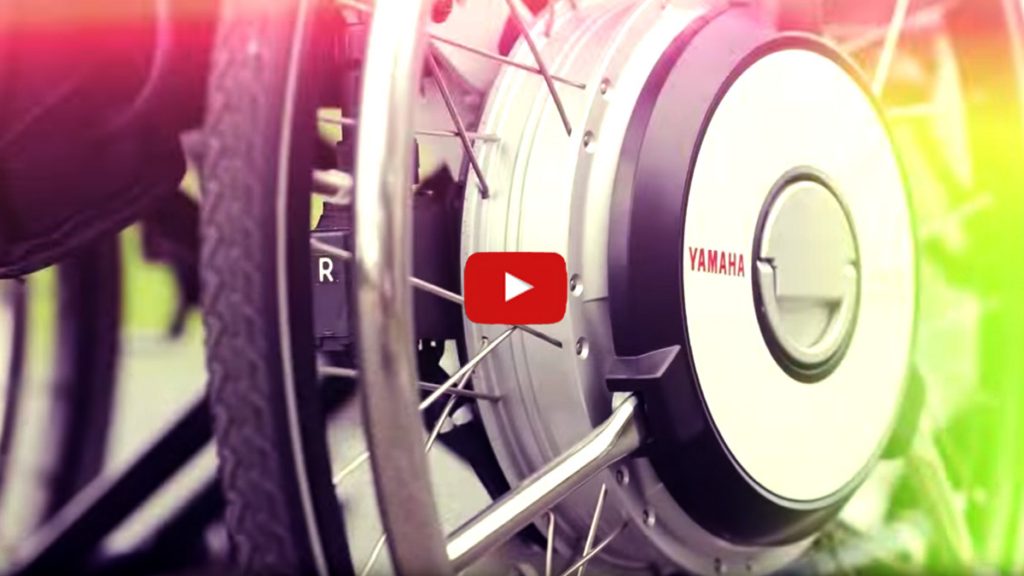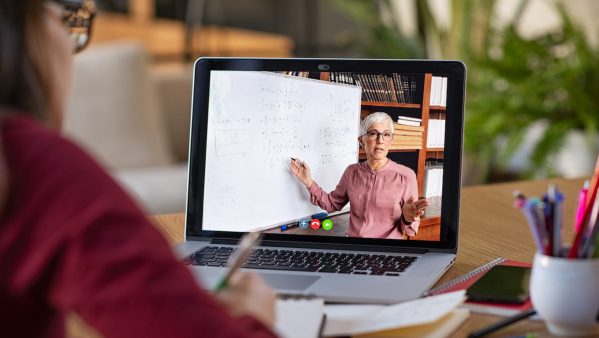日産自動車が昨2019年、スカイラインに『プロパイロット2.0』と名付けた運転支援機能を搭載し、発売した。これは、高速道路上でハンドルから手を放して走行できる機能である。クルマの運転という概念が変化していくのを実感させた。クルマの自動運転はどんな変化をもたらしていくのだろうか。世界の動きを見ていきたい。
日産自動車が発売したプロパイロット2.0は、自動運転へ向けた技術開発のなかで世界最先端のひとつといえる。たとえばドイツの自動車メーカーであるBMWやアウディは、高速道路でのハンドルからの手離し運転を実現しているが、渋滞中など限定された条件が付く。
イスラエルの自動車部品メーカーであるモービルアイは、エルサレム市街を自動運転で走るクルマの映像を公開した。市販されているわけではないが、歩行者が交差点を横断し、路線バスが停留所で停車したそれを追い越していく場面などは、我々が日本の街で見かけるのと同じような交通状況であり、一般道での自動運転を実現している。
それなのに、なぜ自動運転車がまだ市販されないのか。
技術的課題として、万一の緊急時、たとえば歩行者の車道への飛び出しや、他車が急に進路を変更したような場面で、危険回避するためのセンサー性能が不十分な状況にある。自動運転化されれば、事故の責任は自動車メーカーが負うことになるから、慎重に事を進めているところだ。
クラッキング(不正侵入や破壊)の懸念もある。自動運転の制御に外部から不法な侵入が行われないようにするとか、侵入された際の安全確保の手順などが確立されなければ、国も導入を認めにくくなるし、消費者も不安だ。
さらなる技術開発に加え、法整備や、消費者が安心して自動運転を受け入れられる不安解消の段取りが、自動運転車の市販には必要だ。
危うい自動車大国の地位
打開策はどこに
国内でも、内閣府や国土交通省などが実用化へ向けた計画を進めている。しかし消費者にとって、いまひとつ現実感のない話に見えてしまうのではないだろうか。
車両関係は国土交通省、情報通信関係は総務省、新規事業の創設など経済効果は経済産業省と、担当省庁が分かれており、内閣府などで取りまとめる動きはあるが、各省内も縦割りで担当が分かれているなど、従来の組織の枠組みのままではなかなか前進しにくい。自動運転に限らず、将来的なあらゆる生活様式や事業創出でも同じことがいえる。
組織とは別に日本の国情もある。日本は、弓なりをした国土の海岸付近に平地があるのみで、背骨のように山岳地帯があるため、国土全体を広く網羅する交通政策を行いにくい。なおかつそこに1億2000万人の国民が住み、都市への人口集中が進み、都市部と過疎地とで公共交通を含めた移動の仕方に違いがある。
大都市では、公共交通の充実によりクルマの利用がそれほど重要ではない人が多い。しかし地方都市や過疎地域では、クルマが移動の基本になる。日々の生活で必要な交通形態が地域や人口密度によって異なるため、ひとつの理想を追求した中央集権的交通問題の解決を策定しにくいのである。
欧米の場合、国土がより広かったり、平地が多かったりするため人口が偏っておらず、クルマを主体とした交通の未来像を描きやすい。自動運転や、それを利用した移動サービスなど、ひとつの模範解答があれば国や地域全体で多くの人が利用でき、事業としても採算を計算しやすい。また、具体案を策定しやすく、消費者が現実的な未来を実感したり、期待したりしやすいのだ。
それでも、世界人口の増加によって欧米の都市も住民が増え、渋滞が現実的となり、いかに効率よく人を移動させるかが課題となってきた。
もともと人口の集中により大都市化している日本の状況は、将来的に欧米の都市の肥大化の前例となっており、日本の解決策を適応できるかもしれない。
また新型コロナウイルスの影響により、混雑する電車で通勤することが敬遠されると、空間を確保できる個人の移動を充実させていく必要に迫られる。大都市においては、時差通勤を行っても、混雑は十分には解消されないからだ。
時々刻々と変化する現状を把握し、国内外の状況を検証しながら日本が将来への展望を構想してゆけば、計画はより具体性を帯び、その知見を海外へ売り込むこともできるようになるはずだ。そのためには、縦割りとなりがちな専門家集団ではなく、広い視野を持ち、俯瞰して見られる新たな創造者が必要になる。
その実現のために政府が行わなければならないことは、規制緩和だ。また、国民に理解を求める啓発や啓蒙も不可欠である。
それでも東京都という広さで考えるとまだ難しいかもしれない。ならば、区や、区の中の町といった規模でも実証を受け入れる地域に最適な自動運転を実際に実施し、住民と議論を重ねていく。失敗を恐れてはならない。失敗も、知見のひとつであり、開発の方向性をより明確にするからだ。
作られた箱庭(実証実験のテストコース)ではなく、たとえ小さな地域でも現実の町や市で行うことが肝心なのである。それには行政の支援が必要であるし、それを支える国の支援が不可欠だ。エルサレムでモービルアイ社が実験できるのも、ネタニアフ首相との太い絆があるからである。
そのうえで、自動運転がもっとも求められるのは地方都市や、過疎地域だ。なぜなら高齢化社会と、高齢者による交通事故が目立つ現状に対し、公共交通機関の成り立ちにくい地域だからである。
課題は、予算や人員の不足だ。市町村や、県単位でも、十分な施策として扱いにくいかもしれない。一案となるのが、道州制のような発想だ。県をまたいだ人員の確保や、予算の補充ができるかもしれない。その成果は、関係各地域共通の解決策とし、事業を行う企業への便宜に利用してもいいだろう。
この発想は、一次産業である農業や漁業、林業などの活性化と物流など日本の暮らし全体にも関わることであり、交通の未来像は、交通形態だけの問題ではない。衣食住+移動+仕事の未来像は、従来の行政のやり方では解決しないのである。まさに、新しい国造りの一環だ。
自動運転の車両設計においても既存の概念にとらわれず、様々な可能性を生活実態や人口増加、そして高齢化などに合わせて修正していく必要がある。
自動運転でもっとも恩恵を受けるのは、障がいを持つ人や高齢者のはずだ。それによって、生活を自立できる。目標としては、目の不自由な人が一人で初めての場所へ安心して移動できる自動運転車だ。それには真の意味でのユニバーサルデザインでなければならない。そしてクルマがはじめて健常者のものから万人のものになっていく。
動力は、モーターであるべきだ。すなわち電気自動車(EV)である。モーター制御はエンジンの1/100ほど速く、しかも数値の指示通りデジタルで行えるので、発進・加速・減速・停止を瞬時に実行できる。
当然、EVであれば排出ガスゼロなので、環境の改善に効果があり、走りは滑らかで静かなため、快適な移動を実現できるし、騒音が減れば、街は静かになる。
都市と過疎地域それぞれに目標を定めた具体的な交通計画と、それを支援する行政の在り方を新しく組織できれば、欧米へも展開できる具体案となり、なおかつ急速に経済を発展させている中国やインドへも展開できるだろう。そうなれば、日本が自動運転の先進国となれる。
そこまで壮大な未来像と計画を持てなければ、自動運転においても日本は欧米の後を追い、装置などの正確さや原価に専念する工業国で終わってしまう。そこには、中国や韓国が迫りくるはずだ。