マスク着用の必須化、外出は必要最低など、非日常が日常となりつつある日本。緊急事態宣言解除の地域も多くなり、ウイルスとの第一次決戦の出口は見え始めているとは言え、今後予想されている第2波の影響など、まだまだ油断できない状況が続く。だが、失われた日常を背景にテクノロジーへの期待は高まっている。もともと人手不足が問題となっていた介護業界、人とテクノロジーとの協同の必要性はますます高まっている。
コロナウイルスの蔓延を受け、私たちの日常は大きく変わった。人との接触を控え、外出が制限される日を、誰が予想していただろうか。だが、この映画のような状況が現実のものになっている。「With コロナ」という言葉が出てきているように、ウイルスとの共生が今後は必要になっていく。東京を省き、多くの地域で緊急事態宣言の解除となったわけだが、ウイルスとの戦いが終わったわけではない。特に高齢者のあつまる介護施設などでは、未だに面会の制限がかけられているところも多い。ゴールデンウィークには地方に住む両親の元を訪ねようとしていた人たちもいたはずなのだが、それもかなわなかった。未だ緊急事態宣言の続く都内から地方への訪問は感染リスクを伴う上に、人目も気になる。また、地方に住む両親だけではなく家族が近くに住んでいたとしても、病院では面会も制限されており、コロナというウイルスへの脅威だけでなく、孤独と戦う高齢者は多いだろう。
第2波がやってくるとのニュースも出回るなか、介護現場で働く職員は感染リスクと隣あわせの日々を過ごしている。長引くコロナの影響、接触を抑えつつ、手厚い介護をするための方法はあるのか。コロナ前に当取材班が訪れたFuture Care Lab in Japanで見た未来の介護プロダクトたちは、このコロナ禍にも活躍する素質を十分にもっていた。
厚労省の統計によると2025年時点での介護人材の需要見込みが253万人であるのに対し、介護人材の供給は215万人と、人材不足の解消を筆頭に加速する超高齢化社会における課題が山積みになっている。在宅介護から施設介護まで、フルラインの介護サービスを提供するSOMPOホールディングスが介護の現場にテクノロジーを届けるべく、IoT×介護を追求する場として立ち上げたのが未来の介護プロジェクト「Future Care Lab in Japan」だ。東京・品川の展示室には最先端の介護プロダクトが置かれている。
新しい介護のあり方として
「人間とテクノロジーの共生」を目指す
入り口にでまず出迎えてくれたのは以前HERO Xでも紹介した「LOVOT」(http://hero-x.jp/movie/8382/)。愛くるしい表情で私たちに近づいてきた。
「様々なコミュニケーションロボットがありますが、LOVOTはただ単に便利なロボットではありません。抱き上げてほしいという動作をしたり、じっと見つめ返してくれたり、『お世話したい欲』をくすぐるようで、導入している弊社の運営施設からも好評を得ています。こうしたコミュニケーションロボットにはより利便性を追求した製品もあるのですが、LOVOTは完璧ではなく人の手が必要になっています。高齢者とロボットがお互いの個性を活かしながら「共生」するという点が私たちの考え方にフィットしているので、現場で受け入れられているのかもしれません」
そう語るのはFuture Care Lab in Japanの所長を務める片岡眞一郎氏だ。
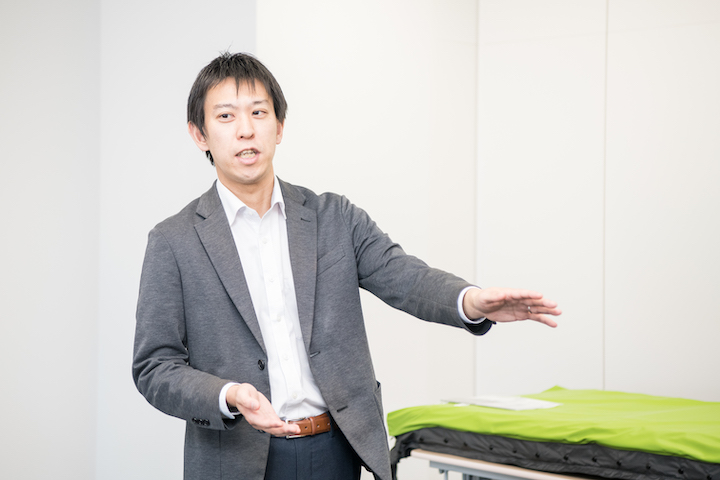
Future Care Lab in Japan所長 片岡眞一郎氏
労働人口の減少を受け、介護の質を落とすことなく、生産性を高めて運営できるサービスモデルを実現するためにはテクノロジーの力は不可欠というのは言うまでもないことだが、このコロナウイルスの出現で、テクノロジーの活用は利用者と介護者の命を守るという意味合いも持ち始めている。
実は、介護系ロボットやセンサーの製品数は著しく増加しているものの、実際に在宅介護や介護施設の現場で使ってみるとうまくいかない、効果が顕れないというケースも少なくのだという。介護事業会社であるSOMPOケアを傘下に持つSOMPOホールディングスは、2019年に「人間とテクノロジーの共生」をコンセプトにFuture Care Lab in Japanを開設。
「介護を受ける人」に対しては生活の質を維持・向上させながらと自立支援による尊厳ある暮らしを実現すること、「介護をする人」に対しては身体的・心理的負担を軽減し、働きやすい環境を構築すること、介護現場の生産性を向上し、介護職員の処遇を改善することを目指して動き始めた。
片岡氏は、元々SOMPOケアの職員。同ラボでは現場のオペレーションにおける幅広い知見と経験を活かし、ロボットをどのように使うのか、またどういう人をターゲットに使うと効果があるのかなど実証を行うほか、同業他社の見学やロボットの開発を行う企業、研究機関との共同研究からリサーチまで各種対応にあたっている。
ラボでは常時、約20~30社ほどの製品を展示し、およそ半分程度をすでに現場で導入している。SOMPOケアの施設のなかでも、フラッグシップホームと呼ばれるテクノロジーを活用した4施設で試験的に使用したのち、全国の施設での利用に移行していくという。
実証フィールドで評価を
重ねながら精度を高め、
現場での運用に繋げる
ラボを一巡してみると一口に介護・福祉関連のテクノロジーといっても、扱う製品は多岐に渡る。
排泄を匂いで知らせるセンサーや、体位変換を自動化するの自動寝返り支援ベッド、備品のストックが減ってきたら自動で発注してくれるスマートマット、画像認識で食事量を記録できるシステム、リクライニング式シャワー入浴装置など、衣食住のほぼ全てがテクノロジーで網羅できる印象を受ける。

介護版においソリューション「Swetty(スウェッティー)」

リクライニング式シャワー入浴装置「美浴(びあみ)」
「実証してみると、まだこれは実用レベルには達しない、というものも当然あるのですが、ラボでの失敗は臆せず、ここで精度を高めていけばいいと思っています。いざ現場に持っていって使えないよりは全然いいですから」(片岡氏)
製品の展示基準として、高齢者のQOL向上やADL維持、費用対効果に併せて、職員への効果も重視しているという。職員への効果はどの施設でも一様に得られるものではないため、定量的に評価することは難しい場合もあるが、超高齢社会を迎える我々にとって介護の効率化や負担の軽減は注目すべき点だろう。
その一例と言えるのがベッドに設置する睡眠センサー。呼吸と心拍を取得することができ、利用者が就寝しているのか、横にはなっているけれど起きている状態なのか、もしくは離床しているかを画面越しに確認することができる。それまで3名体制で行っていた夜勤を2名にできたという効率化だけでなく、たくさんの利用者がいるなか夜間に定期的に巡回すると、10㎞程度歩いていた距離が40%削減されたことで、介護職員の身体的な負担の軽減にも繋がったというフィードバックも得られた製品だ。また、利用者は夜間の巡回により起こされてしまうこともなく生活リズムが整いやすいという利点もある。
一方で、在宅介護向けで、非常に好評を博しているのが「HelloLight」という製品。LEDライトのON/OFFを通信で知らせることができるIoT電球だ。

IoT電球「HelloLight」
1日の間に点灯と消灯の動きがないと通知する期間検知機能を備えており、以前のように遠方に住む独居の家族を訪ねられない今、見守りができるのはありがたい。利用にあたって工事や電源、Wi-fiの設定も不要なため、届いたその日から気軽に使い始めることができる。テクノロジーの活用はあくまでも「さりげなく」やることがカギとなりそうだ。
職員のやりがいまでテクノロジーが
奪わない運用設計を意識
新たな技術を施設に導入する上で、片岡氏は職員への敬意を強く意識している。
「たとえば血圧や脈拍といったバイタル測定を自動化すると、記録の手間が省けて効率化できます。しかし、バイタル測定はただ数値を計測する作業ではありません。昨日と比べて表情が明るいな、今朝は何となく寝不足っぽいな、とか長年その人を見ているからこそ分かる観察の時間でもあります。観察という介護職員ならではの行為を残した上でバイタル測定を自動化していかないと、大事なことを失ってしまい、現場のモチベーションも下がってしまうかもしれません。新しいテクノロジーの運用を設計する際は、職員のやりがいについても細心の注意を払っています」

ラボの壁に貼られた「声の成る木」には見学に来た現場の職員からのリクエストが綴られている。
「職員からは、自動で体重を測定できるものが欲しいという声がこれまでに何度も出ているんです。体重の増減は健康管理の観点で重要な指標となるので、少なくとも月に1回程度は実施したいのですが、職員2人がかりで要介護者を起こして支えながら計測するのは非常に負荷の大きい仕事ですから、自動化したいというアイデアにはなるほど、と感じました。現場を知っている人たちだから出せる意見やアイデアを、ラボではできるだけ吸い上げていきたいですね」
コロナ禍では人間同士の接触を極力控える必要がある。しかし、要介護の人にとって、人の手を借りずに日常を過ごすことはほぼ難しいのだが、テクノロジーの力を使えば感染リスクを低くする努力をすることは可能だろう。「人間とテクノロジーの共生」が実現していく姿をこれからも見届けたい。








































